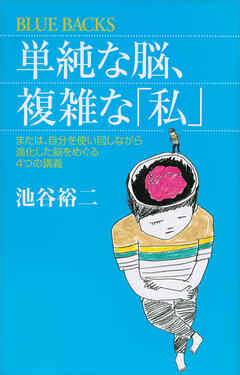あらすじ
「心」はいかにして生み出されるのか? 最先端の脳科学を読み解くスリリングな講義。脳科学の深海へ一気にダイブ!
ベストセラー『進化しすぎた脳』の著者が、母校で行った連続講義。私たちがふだん抱く「心」のイメージが、最新の研究によって次々と覆されていく──。「一番思い入れがあって、一番好きな本」と著者自らが語る知的興奮に満ちた一冊。
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
因果とは脳の錯覚である
他人は自分の右半分の顔しか見てない
記憶は積極的に再構築される
感情は行動に整合するように変化する
人の考えているほとんどは作話
自由は過去に向かって感じる
自由意志はない自由否定がある
ニューロンは水漏れした鹿威しの仕組み
脳科学はリカージョンの矛盾から逃れられない
凄まじく面白すぎる
Posted by ブクログ
心や自由意志について脳科学の観点か見つめ直すことができる。ページをめくるたび新たな発見がありおもしろかった。
特に印象に残ったのは無意識のほうが意識より正確、(意識的な)記憶は歪められる、意識が無意識にあとから理由をつける、好き嫌いの理由は案外単純な理由かも、など。
Posted by ブクログ
脳科学者・池谷裕二さんによる、
トピックとそれらを読み解く内容が盛りだくさんの、
講義録形式の本です。
実際に、池谷さんの母校の生徒9人が彼から受けた講義が
この本になっています。
460ページくらいのなかなかのボリュームの本ですが、
その物理的な「なかなかな量」を超えるくらいの内容の濃さです。
そして面白いのです。最新の脳科学の知見が披露されますが、
柔らかい言葉でもってなされるその解説、詳説にうーんと唸らせられる。
自由意志とはなにか、
無意識の作用について、
脳の神経はどういう成り立ちをしているか、などなど、
哲学や心理学や生物学などの領域にまでまたがるような、
横断的な学問としての脳科学というものがわかり、
そのひとつひとつに自分のアタマのいろいろな領域を刺激されて、
フル回転で読むようなことになります。
といっても、興味深い読みものなので、
時間の余裕があってゆっくり読めるのならば、苦痛も感じないはずです。
(ところどころ調べないといけない言葉も、
人によってはあるかもしれないですが)
とくに心に残ったところは、まず、
同じ労働をしても、報酬の金額が少ない人のほうが
その労働に対して「楽しかった」という感想を持つそうだというところ。
ボランティアでの満足感へのヒントだとも思いました。
一方で、高給取りなんかが傲慢だったりするイメージがありますが、
仕事に楽しさを感じてないからなんでしょうか。
「金のためだししょうがねー」と。
仕事は金のためなのはもちろん(だと僕は思う)。
でも、楽しいにこしたことはない。
そのあたりのちょうどいい賃金の金額ってあるんだろうけど、
個人差があるだろうなぁと思いました。
格差の下の人たちが、少ない賃金でも楽しさを感じてしまったら、
それは豊かな社会なのだろうか、それとも、かわいそうな社会なのだろうか。
また、ブラック企業で働く人がそこを離れないのにも、
このような脳の習性・心理が働いているのだろうかと思えました。
それは間違った脳科学・心理学の活用の仕方だと思う。
それと、脳はゆらいでいるということ。
入力+ゆらぎ=出力になるから、
同じことをしようとしても結果は微妙に異なったりする
(いつもゴルフのパッティングが決まるとは限らないのがその例)。
きっとルーティンってものが、
その脳の揺らぎを一時的に抑えられるんじゃないだろうか。
そうやって、出力のばらつきを抑えている気がする。
実際、アルファ波がでているときは失敗すると書いていました。
アルファ波が出ていないとき、弱い時には、
ゴルフのパッティングもうまくいく。
そして、アルファ波は脳波測定器をみながらならば、
自分で出したり弱めたり調節できるようになるものなんですって。
そうやって、アルファ波を弱める術を覚えたら、
ボウリングなんかはすごくいいスコアが出せるだろうなぁ。
運動音痴の人も、もしかするとアルファ波が強いせいでそうだ、
っていう可能性もありますよね。
野球なんかで玉を投げるのにもコントロールが悪かったりっていうのは、
アルファ波のせいかもしれない。
逆に、アルファ波って優れた芸術家には欠かせないみたいに言われた時期って
あったと思いますが、そうい芸術家が運動に優れていないのが、
このメカニズムのせいかもしれない。
あと、このあいだ『弓と禅』のレビューで書きましたが、
そこに出てくる名人の弓道の師範はどんな脳波なんだろうなって
気になりますよね。そこまでの域に達していたら、
逆にアルファ波がでていて、それまでの常識が覆るような
奥が深い結果が出そうにも思えたり。
まぁそれは僕の勝手な想像ですけども。
非常に面白く、濃い内容と量に圧倒されながら読み終えました。
うまくいえないのですが、読み通すと、何か、
「この世の仕組み」みたいなのすら見えてくるような本です。
良書でした。
Posted by ブクログ
以下気になったことのまとめ
1章
自分の行動や思考の多くは無意識的な振る舞い
なので自分が想像してるほど自分のことはわからない
理系は人差しが短い。
これは、単に男の人のほうが人差し指が短く、男の人のほうが理解に進みやすいということ。
人差し指が短い理由は、お腹の中にいるときな、男性ホルモンにさらされると男性になるが、男性ホルモンにさ細胞を殺す作用があり、人差し指が短くなる
と言われている
天然パーマはIQが低いのも同じような理屈。
アフリカには天然パーマの方が多く、アフリカの一部地域では教育が届いておらず、そういう統計になっているだけ
こうしたデータは因果関係ではなく相関関係があるといえる。
因果関係があることは証明できない。統計的に相関の強さを見て、因果関係があるとしているだけ。
解熱剤を飲まなくても熱は下がるかもしれない、など。
脳の活動こそが事実、つまり感覚世界の全てであって、実際の世界である「真実」については脳は知り得ない
人の顔は、左側だけでほとんど判断している
言語は左脳で判断して、イメージは右脳が司る。左側の視野で見たのもは、右脳が判断するので、左側
この歌はなんで好き?という理由でメロディーや歌声ではなく、実は楽しい時に聞いた曲を聴くといい曲と錯覚してしまう
視線を動かして見た場合と、視線をそのままにして新しいものを見た場合だと、視線を動かしたときの方が魅力的に錯覚しやすい
脳が視線を動かしてみる必要があるもの、と錯覚するから
恋愛は麻薬のように快楽作用がある。
快楽は盲目にさせる。ネズミが快楽のボタンを押すと、そればかり押して食事もしなくなり気付いたら餓死してしまうなど。
子孫を残す際は、よりよいパートナーを選ぶ脳がある。しかし全世界の人からベストは探せない。そのとき、恋愛で盲目になって、目の前の人がベストパートナーと錯覚できるよように、恋愛がある
ひらめきは思いついた後に理由を説明できるが、直感は理由を説明できない
大脳基底核が直感を扱う。大脳基底核は、自転車の乗り方や箸の持ち方など体を動かすことに関連したプログラムを保存している。
そしてこれは、非常に正確。箸の持ち方を間違えたなどがらないように、正確。
大脳基底核は、1回やっただけでは記憶しない。繰り返しによって記憶される
女性はノンヴァーバルコミュニケーションに長けていて、ちょっとした仕草や態度や表情に敏感。男性はこれが苦手なので、言葉を重視する
例えば女性はプレゼントの際にも、どんなシール貼ろうかやリボンなど細部に気を配る。それが女性には伝わるから
人の痛みを見ると、自分も痛いと脳が感じてしまう。それは仲間外れにされた、など社会的な心の痛みも、脳は「痛み」と感じてしまう。
進化の過程で動物は他者の存在を意識できるようになった。次に他者を観察することで、その行動の理由を推測できるようにらなった。
他者を観察して得たことを自分にも適用すれば、自分の観察にもなる。
そういった手順で自分に心があると理解する
3章
脳は常に頭蓋骨の中にあるので、外界の情報を知るには手や足や目など身体を使わないと情報を得れない
味覚は塩味、甘味、旨味、酸味、苦味の5種類
皮膚の感覚も温覚、冷覚、圧覚、痛覚など数種類
嗅覚は、400種類くらい嗅ぎ分ける。ネズミなら1000種類。嗅覚だけ異常に多い。
それは、食べ物を探すため。睡眠中でも嗅覚は活動している。嗅覚以外も感じ取れていたら、睡眠が妨げられる
身体を動かそうと思ったとき、その直前には脳はすでに身体を動かす準備を始めて完了している。その後、身体を動かそうと思い、動かすという流れ。
子供は体は動く準備できたらすぐに行動しちゃう。大人になるとそれを拒否できるようになる
よって、ぼくらは自由意志ではなく、体が思ったことを「やらない」という選択肢、つまり自由否定ができるだけの存在
4章
アリの行列。アリはフェロモンを出しながら歩き、フェロモンを辿って帰る。
そのフェロモンは揮発性で時間が経てば消える
時間が経てば消えることで、今残ってるフェロモンに時間という概念が加わる。昔のフェロモンが消えることで、帰り道がわかるようになる
でもたまにフェロモンを辿っていかないアリがある。それはノイズだが、そういうアリが最短ルートを見つかるかもしれないし、もっと大きな餌を取るかもしれない。だから必要
アリのフェロモンは揮発性なので、濃いフェロモンを辿っていけばノイズには騙されない仕組みにもなっている
Posted by ブクログ
本書の終わりに、著者は、アウトリーチ活動について述べていた。アウトリーチ活動とは、研究者が、専門家ではない一般の人たちとの対話の場を持ったり、一般書を著したり、易しい講演を行ったりと、その労力をいわゆる社会活動についやすことである。
本書は、著者の出身高校の現役学生に対し、全校講演を行った内容と、その内容に特に興味を示した9名に対し、その後行われた3日間に渡る特別講義の内容を収めたものである。すなわち、後輩学生たちへのアウトリーチ活動の記録である。
アウトリーチ活動については、賛否あり、「一般向けにかみ砕く行為は真実の歪曲」などという否定意見もあるそうだが、本書を読む限り、科学的なテーマについて、実際に検証を行いながら真実を確認するやり方で行う講演であり歪曲に値するとは感じなかったし、さらに未来の科学者に対し、科学的課題究明のプロセスを体験してもらえるという教育的側面でもとても有効な取り組みであると感じた。
「ロウソクの科学」でファラデー氏が、子どもたち相手に実験を交えながら講演した光景とダブルものがあった。
本講義は、脳科学に関する講演であると思う。第一章では、「脳は本当はバカなのだ」というような話が、実例とともにたくさん紹介されていた。「ゲシュタルト群化原理」という脳の早とちりの話、能動的に視線を動かせば好きでないものも好きになるという「錯誤帰属」の話、長く接することで好きになってしまうという「単純接触現象」の話、というように専門的な内容を卑近な事例で紹介してくれる。
本書の中では、脳の不思議を体験できるような実験がふんだんに盛り込まれている。サブリミナル効果が無意識に働きかけているという事実が、データから証明される。まるで手品でも見ているかのように不思議でかつ、興味深い。
手首を動かす実験では、「手首を動かそう」と意識する前に、すでに脳が準備しているということが分かった。脳が「動かせ」という指令を発する前に、すでに実際に「動いている」という実験データであった。意識する前から脳が準備しているとはどういうことか?脳が指令を出す前にすでにアクションが起きているということはどういうことか?意識は、何者かに支配されているのか?
この実験結果は、受講した高校生にも非常に印象が強かった。自分としては、意識の前に無意識が脳をスタンバイさせたり、意識の司令前に無意識の指令があったのではと考えてみたくなった。
そのほか、講義の内容は多岐にわたり、初めて知ったことが満載である。例えば次のようなこと。
・「遺伝多型」というものが個性を生み出している事実(血液型の違いや、赤色を感じる受容体の違い、うまみを感じる受容体の違い、嗅覚の違いなど)
・生物進化の過程には、機能の「使い回し」があるという事実(今まで別の機能として役立っていたものを、全く異なる方向に転用し、新しい使い方を発見して、能力を開発していくこと)
・脳の働きには「ゆらぎ」があること。ゴルフクラブを握る握力は、脳のゆらぎによって異なり、それによってショットの成否が決まる。この「ゆらぎ」の仕組みの把握により、コントロールできる可能性があるということ。
・脳の可塑性について。これがあるから、遺伝子で決定されたデフォルトの状態から、さらに変化できる。学習や訓練によって能力を固めていけるのは、脳にこの可塑性というものがあるからだそうだ。
・脳のゆらぎ(ノイズともいわれる)には、3つの役割(①最適解への接近、②確率共振、③創発のためのエネルギー源)があるということ
・その③創発とは、数少ない単純なルールに従って、同じプロセスを何度も繰り返すことで、本来は想定していなかったような新しい性質を獲得すること。
本書のタイトル通り、脳はシナプスとニューロンの単純な働きによって機能している。ニューロンがやっていることは、シナプスを経由の入力を足し算し、その結果を次のニューロンへ出力するという単純なものだそうである。しかし、そのシナプス入力に「ゆらぎ」が発生し、創発が起こる。
最後にリカージョン(入れ子構造)ということについての講義があった。これが我々が心の不思議を感じる要素のようである。「複雑な私」とは、ここから来ているようだ。
脳の構造や働きについて、高校生と共に学んだが、まだまだなんとなく消化不良感がある。高校生たちの事後の感想にもまだ完全に理解しきれていない様子は感じられたものの、彼らの視点は鋭く、著者にドキッとさせる質問が飛び交い、科学の世界へののめり込みかたは、将来への頼もしさが感じられた。。
それと同時に、自らが脳の保有者であり、使い手でありながら、その機能について知らないこと(知らなかったこと)が多いということ、またその機能の不思議さに対する驚きがあったということも事実である。