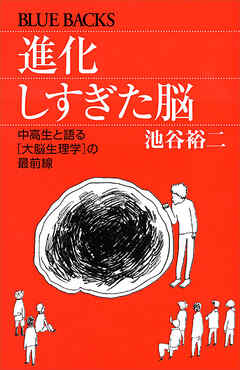あらすじ
『しびれるくらいに面白い!』
最新の脳科学の研究成果を紹介する追加講義を新たに収録!
あなたの人生も変わるかもしれない?
『記憶力を強くする』で鮮烈デビューした著者が大脳生理学の最先端の知識を駆使して、記憶のメカニズムから、意識の問題まで中高生を相手に縦横無尽に語り尽くす。
「私自身が高校生の頃にこんな講義を受けていたら、きっと人生が変わっていたのではないか?」と、著者自らが語る珠玉の名講義。
メディアから絶賛の声が続々と!
『何度も感嘆の声を上げた。これほど深い専門的な内容を、これほど平易に説いた本は珍しい』――(朝日新聞、書評)
『高校生のストレートな質問とサポーティブな池谷氏の対話が、読者の頭にも快い知的な興奮をもたらす』――(毎日新聞、書評)
『講義らしい親しみやすい語り口はもちろん、興味をひく話題選びのうまさが光る』――(日本経済新聞、書評)
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
普通のひとは「自分も中高生の時にこんな授業を受けたかった!」と仰るんでしょうけども私の中高生時代は夜ヒットや紅白で後ろに座ってる歌手が何をしてるのかを凝視するのに忙しかったので今でちょうど良かったです。
5章構成ですが2章「人間は脳の解釈から逃れられない」3章「人間はあいまいな記憶しかもてない」5章「僕たちはなぜ脳科学を研究するのか」が特に良かったですね。(1章の脳機能説明、4章のアルツハイマー薬を中心としたものもいいですけどね。でも4章はちと難しかったです。私には。)
特に特に気に入ったフレーズを3つ。
P127「目ができたから世界ができた」
P171 「自由意志は潜在意識の奴隷に過ぎない」
P192「下等な動物ほど記憶が正確で融通がきかない」
人間の脳の曖昧さを自覚した上で何かを信じたりこだわったりするならば、世界は格段に穏やかになるんでしょうけどねぇ。
楽しい楽しい本でした。当然星5。
Posted by ブクログ
・一回通読。はじめて知った面白い話が多すぎて、メモなしで思い出しながら感想書くのは難しい。
・大脳皮質の表面積を部位ごとに表現したホムンクルス。人間は舌と人差し指、ネズミは前歯と髭など。びっくりするけど腹落ちするね。
・脳はダイナミックに構築されていく。水頭症で部分的にしか使えなくても、生活を通じて一般人と遜色無い生活能力を発揮。つまり、脳は余剰が多く、進化しすぎている。ニューラル・プロスティクスの話とかロマンありすぎて念力の能力拡張したくなる。
・ネズミの実験から見る報酬系の強烈さ。これに抗うことは人間にできるのか?という話は、カントの傾向性と自由の話に通ずる。扁桃体と本能の話を見ても、自由意志の存在に自信がなくなる
・人は言葉の奴隷という話。言語が違えば、概念の有無や連想の仕方も変わってくるとなると、異文化理解の難しさも納得。
・記憶や学習の仕組み。神経細胞、シナプス、ヘブの法則、NMDA受容体、複雑系。順を追った説明により、美しいほどシンプルな面と、数式化が困難な複雑な面をそれぞれ理解できる。
Posted by ブクログ
面白いので、読んで欲しい本。脳と身体がいかに密接に関連しているのかの良くわかります。SFで脳だけの人間が存在するような描写を見たことがありますが、余り現実的ではないことが分かります。
Posted by ブクログ
高校生との対話形式のため、わかりやすく脳科学の専門的な内容が理解できる。いわゆるサイエンス的な内容だけでなく、心とはなにか意識とは何かといった捉えどころのない領域にもエビデンスベースで独自の解釈を加えながら、説得力のある説明をしているため、かなり腹落ちのする内容だった。2007年に出版とのことだが、内容はまったく色褪せないもので、この本を起点に少し情報をアップデートさせるので十分なほどクオリティが高かった。
Posted by ブクログ
”中高生と語る”とあるように、中高生向けの少人数講座の講義録のような形でまとめられており、すごくわかり易く、また興味を持ちつつ読み進めることができる。わかり易いものの、書かれている内容は大脳生理学の一部とはいえ本質で最先端だと思う。
こういう書籍が、新しい分野に関心を持つきっかけになると感じた。あらゆる分野で、このような位置づけの書籍なり、講義録なりが揃うと嬉しいし、酔いたいと思う。
Posted by ブクログ
じゃんけんの手など、一見ランダムと思われる選択をするとき、ニューロンに作用するナトリウムイオンの一時的な量が決定を左右している話が面白かった。意識とは何か
Posted by ブクログ
脳科学の一般書で最も有名といっても過言ではない本にも関わらず、なかなか読めていなかったので読んでみました。全体的に色々なジャンルで脳の面白さを研究の紹介も交えて伝えられており、とても楽しめました。
脳が身体の制約を受けて、能力をフル活用できていないというのは興味深かったです。その点でコンピュータに意識が芽生えた場合にも身体の違いから同じような意識ではないという推測も納得感がありました。
環境に適応できない個体が子孫を残せないのが本来の進化の原理なら、現在の医療技術は環境を変化させることで個体を生存させている"逆進化"とも言えるかも知れないというのも考えたことのない発想で面白かったです。
また、視覚情報処理の初期段階での網膜→視床(外側膝状体)→1次視覚野の流れの中で、網膜から上がってくる情報は単純計算で3%ほどしかないというのは、脳での再帰的な活動が占める割合の大きさを示す面白い例えだなと思いました。
終盤の意識や心を科学的に解明できるのかといった内容では話がとっちらかっている印象がありましたが、結論のない話なので仕方がないかなとも思いました。脳は自発発火による活動の影響が大きく、再現性がないため再現性を重視する現代の科学と根本的に合わないのでは?という視点は興味深かったです。ただ、意識や心の話は哲学書の方が定義をきちんとしてから議論をしてくれる気がします。
Posted by ブクログ
意識も脳という物理的モジュールが生み出す現象に過ぎないと思ったので、私の悲しみや苦しみもいずれ解体して単純な反応の関数と化することに希望が持てた
Posted by ブクログ
慶應義塾ニューヨーク学院高等部の8名に向けて行われた脳科学講義4回の記録と、東大薬品作用学教室のメンバーとの追加講義
大脳生理学の2007年の最前線の内容が非常に優しく説明されていて、興味深い内容のものばかり。
四章の終わりで4回の講義をまとめられているが、こんな盛り沢山の濃い内容をしっかり振り返れる講義力も相当に驚かされる。
脳の機能は、体があって生まれる
心は咽頭がつくった
見るとはものを歪める行為、一種の偏見
覚醒感覚クオリアは脳が生んだ最終産物
覚えなければいけない情報を有用化して保存する汎化のために、脳はゆっくりとあいまいに情報を蓄えていく
あいまいさは脳のシナプスの結合力、しかしパーツだけみても全体はわからず、部分と全体は互いに不可分で相互に影響を与えている
Posted by ブクログ
高校生向けの講義とは言え、なかなか難しい部分もあったのですが、脳が想像以上に複雑なことをしていること、そして自分が見ている世界は脳によって作り出されている部分が多く、現実とは何かということを考えました。
続編も読みたいです。
Posted by ブクログ
脳の基礎知識について、大雑把に分かった気がする。言語化できない意識下にここで学んだ脳のつくりの情報が埋め込まれた気がして、性格がちょっと変わったような気さえする。半年前に読んだものなので、あまり具体的に書けないが、難しいことをわかりやすく書いてる本だと思った。
自分の性格というか、知識というか、教養というか、そういうものを根底から変えたし、そう実感できるほど納得感のある内容だったし、今後の読書の時の予備知識としてすごく役立っているという事から、俺の読書人生における、分岐点とも言えそうかもしれん。
特にシナプス結合については眼福ですな。アドレナリンとかそういうものの構造がミクロで理解できたのは今後の人生において重要な気がする
Posted by ブクログ
フィクションばっかり読んでいたので、気分転換にノンフィクションを読んでみる。
脳に関して知りたいと思っていた訳ではなかった。
ただ、心って、意識って何??っていう問題には興味があったし、今もある。
心って、意識って、考えていくと結局は脳なのかなぁと。哲学の本とかも読んでみたいけど、難しいしなぁ。
この本に関しては、非常に読みやすく脳に興味が持てた。興味を持つのも脳なんだけど。
じゃあ、興味って何なんだ。
Posted by ブクログ
「脳」というものを研究するということは、神経学や医学の分野だけではない。心理学や哲学、倫理学なども結束した総合的な学術であることを改めて認識した。刊行から20年経った今、脳科学は人口に膾炙するところとなり、メディアでも沢山の学者が意見を交わしている。著者の先生は本書では、高校生にもわかりやすいように、しかし、肝心な箇所は誤魔化しなく脳の面白さを語ってくれた。人類にとって1番身近で1番未知数な、脳は興味深いと感じた。
Posted by ブクログ
ほぼ同時期に心の盲点の方も読んだので内容はうろ覚えだし心の盲点とごっちゃになっているかもしれないがどちらも面白かったし、認知バイアスがあることに気が付くきっかけとなった記憶。科学の難しいことはわからないが池谷さんがわかりやすく興味をもてるように書いてくださってる。もっと脳科学について知りたいと思わせてくれた本。
Posted by ブクログ
自分の頭の中ってどうなっているのだろうと思い読みました。
中高生と授業形式のやりとりが書かれていて、学生時代を思い返す懐かしさを感じました。
内容は、正直に言うと高校の生物を履修していないとついていけないかと思います。
内容は、生物を履修している人なら教科書で習ったことは、こんな感じに繋がっているんだってことがわかりとても楽しいと思います。
この中で一番面白かったのは、人間の意識、無意識についての記載のところです。
彼女が好きになった理由に書かれているのですが、私が嫁に聞かれて答えた内容と全く同じで爆笑しました。
Posted by ブクログ
第1章まではワクワクしながら。
それ以降は難しかったので、もう少し簡単な本を読んでみてから、読み返そうかな。
池谷さんのテンポ感など含めて、とても良い本。
Posted by ブクログ
池谷裕二先生はコメンテーターのイメージが強いが、物凄く頭が良くて物凄く誠実な方ということが伝わってくる。脳の仕組みを非常に分かり易く解説している。高校生に対して端折ったり誤魔化したりするのではなく、抽象的かつ専門的な話を具体例に落とし込みながら分解し論点整理しながら必要な要素を漏れなく端的に講義している。また講義に対する高校生の理解度や質疑応答が凄い。第3回の講義のときには、確実に私の知識レベルは高校生たちに負けている自信がある。その反応を見ながら池谷先生が説明を変えたり新たな気づきを得たりする様子がわかる。まさに脳内神経の仕組みのような講義。読みやすく、科学的探究心と知識刺激を満たしてくれる一冊だ。
Posted by ブクログ
仕事の関係で池谷先生の講演を聴いた際に、あぁこんなに楽しく聴いていられたのは初めてだな、本もきっとおもしろいんだろうと思い、手に取った。
この本自体も中高生向けの4回の講義+出版後の大学院生向けの1回の講義をまとめているものであり、まるで出席しているかのような臨場感があった。
化学に弱いのでイオンの話はきつかったのはさておき、脳という壮大な営みのテーマを楽しく学ぶことができたと思う。
Posted by ブクログ
著者30代での中高生への講義の書籍化で、内容も若々しく溌剌としている。
ブルーバックス初版2007年、2023/3は40刷。帯には朝日、毎日、日経新聞の書評があり、朝日書評は「何度も感嘆の声を上げた。これほど専門的な内容を、これほど平易に説いた本は珍しい」と絶賛。20万部突破。
内容は盛り沢山。科学的な神経細胞やシナプスの話から、・意識や感情とは、・「見る」と脳の解釈、・言葉と抽象思考、・記憶のあいまいさの理由、等々、話はどんどん広がり、理解はしきれないが大脳生理学の先端とその広がりに触れた気がする。
読み終えて、人間の脳って、意識って、とても不思議と改めて感じた。
Posted by ブクログ
講談社 ブルーバックス
池谷裕二 進化しすぎた脳
中高生に行った大脳生理学について講義録。脳と体、脳と心、意識の条件など 大脳生理学の立場から説明
脳と体の関係性は意外。環境に適応する以上に進化してしまった脳と 脳をコントロールする体という意外な関係性
驚いたのは、人差し指と唇が異常に大きく描かれた 人間のホムンクルス(大脳との関係性から感覚器として重要なものを大きく示す図)。人差し指と唇の重要性を意識したことがなかった
科学者の倫理観を超えた脳解明の野心に執念を感じる。戦争により脳を欠損した兵士の症状研究やネズミにラジコンを埋め込んで自由自在に操る実験から 脳科学を進歩させている
大脳生理学の立場から、意識の条件(表現の選択、短期記憶、可塑性)を提示し、動物の行動や植物人間の反応から 意識の有無を検証している
心とは
*脳が作った精神作用
*人に心がある理由は言葉があるため
*人に心がある目的は汎化(共通のルールを見つけ出す、一般化する)するため
人は 心を活用して、抽象的な思考をして〜共通ルールを抽出して〜環境に適応していく
「世界があって、それを見るために目を発達させたのではなく、目ができたから世界が世界として初めて意味を持った」
Posted by ブクログ
この著者の本はどれも簡単に噛み砕いた文章で書かれており、専門知識のない人でも読みやすいなと思う。
章が細かく分けられているのでスキマ時間に読める。
Posted by ブクログ
人間の脳はどこまで進化すれば気が済むのだろう。最新の神経科学を手がかりに、私たちの思考や感情の正体を解き明かす。便利さを生んだ高度な知性は、同時に不安や錯覚も生み出すという逆説を示す。脳が「完璧」ではなく、むしろ不完全さゆえに創造性を持つ存在だという事実である。進化しすぎた脳をどう使いこなすかが、これからの人間の課題として差し出される。
Posted by ブクログ
新作がおもしろすぎたので遡って。
・人が成長していくときに、脳そのものよりも、脳が乗る体の構造とその周囲の環境が重要
・能力のリミッターは脳ではなく体
・「意識」の条件
①判断できること、表現を選択できること
※クオリア(覚醒感覚)は無意識
②「短期記憶(ワーキングメモリ)」が働くこと
③過去の記憶による経験と学習(「可塑性」)があること
・シグナルと言語の違い
・下等な動物ほど記憶が正確で融通が利かない。
・人間の脳では記憶はほかの動物に例を見ないほどあいまいでいい加減だが、それこそが人間の臨機応変な適応力の源
・脳の考え方は汎化・帰納法
・複雑系の中で生まれる秩序
魚に群れ
Posted by ブクログ
結構ちんぷんかんぷんだったなぁ。
脳みそが体のそれぞれの器官に指令を出すと思われがちだけど、ほんとは逆とか。
脳の特性を理解して、生活に活かしたいなと思って手に取ったのだけど、これだけでは私には足りないみたい。
Posted by ブクログ
人間の脳が動物界で1番大きいわけではないこと(うさぎの脳の方が大きい)、人間は体の機能以上に脳の進化が大きすぎて脳のポテンシャルが引き出せてないことなど脳について知らないことがたくさんあるなと感じた。心理学について興味は過去あったが、脳と心については密接に繋がっていることにも気づけた。「見る」という行為は網膜から入った光の情報に脳が補完してわたしに見せており無意識的行動であることも知った。思考は言語に依存している(p159連想ゲームより)ことから他言語を学ぶことは思考の幅を広げることにもつながるかなと感じた。p203〜262までのシナプス、スパイク、N MDA受容体の内容は専門的でよく分からなかった。
Posted by ブクログ
テンポのよさ、潔さ、自信と勢いをもとに脳科学講義を行った本。
記憶が曖昧だから別々の記憶がポンと繋がったりする。
【関連書籍】
シンプルで合理的な人生設計、科学は人格を変えられるか、失敗の科学