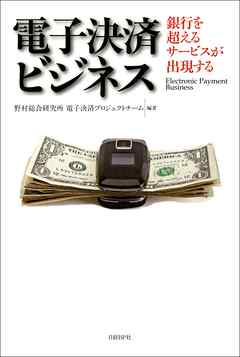あらすじ
2010年4月に施行された「資金決済に関する法律」によって、送金サービスが銀行以外の一般企業でも提供できるようになりました。これにより、携帯電話、ツイッター、SNS、電子マネー、Eコマースを利用する人の間での送金が可能に。また、同じサービス内での送金だけでなく、携帯電話の料金から電子マネーへの送金などにも発展させることができます。この送金サービスや電子マネーなどに代表される電子決済ビジネスによって、新たな市場の創出が期待されています。今まさに大きく変わろうとしている電子決済ビジネスについて、その全貌と参入の可能性を明らかにします。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
電子決済ビジネスについて。
将来的な電子決済サービスについても取り上げられつつも、
現行についても素人の自分にもわかりやすくまとめられていた。
それにしても、読めば読む程に
難しいビジネスだなぁ…と。
Posted by ブクログ
以下はまとめと気になった点のメモです。
第1章 資金決済法で何が変わるのか
「資金決済法」が2010年4月1日に施行された
・サーバー型電子マネーの規制
・「資金移動業」として登録することによって、送金サービス事業に進出することが可能に
→国際間送金などのサービスが新たに大きく広がる可能性
□資金移動業の規制と課題
・移動資金の全額保全
・登録制度
・10万円を超える送金には本人確認が必要(マネロン防止)
→代金引換、CVS収納代行、ポイント交換での現金化に関する法制度化は位置づけはグレーのまま
□CtoCの電子決済ビジネスの主役
・業種ごとの利用頻度の統計より、スーパーやコンビニなどの業種の参入(資金移動業における入出金拠点として)が、
新たな送金サービスを活性化させる
・今後、資金決済法の施行により、既存の銀行以外でも送金サービスが可能となり、
圧倒的な契約者数を持つ携帯電話事業者が既存の銀行に縛られずサービス提供が可能となる
・ネットオークションが活性化(本人確認についての課題もある)
・SNSやツイッターの簡易送金サービス
・ソーシャルレンディングを活用した個人間でのお金の貸し借りも普及が進む可能性がある
※ソーシャルレンディングとは、現在のインターネットにおけるバーチャルなネットワーク力を利用して貸し手と
借り手を結びつけ貸し手自身が借り手の与信能力を評価しながら、個人間でお金を貸す仕組み
□ケータイですべてが完結する可能性
資金決済法により送金サービスが可能になれば、電子化されて携帯電話やインターネットなどで接続されている
あらゆる事業者や個人の間でお金のやり取りが可能となる。
通信ネットワーク上がそのままお金の流れるネットワークとなりえる。
第2章 誰が参入して何をすべきか
□海外事業者の襲来
・Paypall・・・インターネットの電子メールを活用
・safaricomのM-PESA・・・携帯電話のネットワークを活用(SMS)
・WesternUnionの国際送金
これら3つのサービスは送金という仕組みをメインに発達してきたが、
支払の手段としても利用されていることに注目
→携帯電話事業者、銀行、クレジットカード事業者、ECサイトなどが、
海外の送金事業者と提携することで国内送金や国際送金のサービスを提供することも考えられる
□国内の参入事業者
携帯電話事業者
クレジットカード事業者
・・・数百~数千万ユーザー単位での幅広い顧客基盤を持つ利用者で自社既存のNWを活用することでコストを抑え、
送金サービスの利用件数も膨大に獲得できる事業者
EC事業者・・・楽天、JTBはすでに資金移動業者として登録済
流通事業者・・・スーパー、コンビニ(多数の加盟店、顧客接点、電子マネー保有の点で7&I、イオン有利)
システムインテグレーター・・・決済代行事業者
□今後の展開
・参入した事業者のユーザー間での広がり
・海外送金サービスがはやる(手数料が高いため)
・複数事業者のユーザー同士での送金サービスにつながる
→利便性が高まり爆発的に利用増加
※はじめは異業種同士の送金から始まる可能性が高い
□電子マネー、カード送金サービスで社会インフラ化
・これまでは売主から加盟店手数料を徴収するモデルだったが、
今後は送金サービスとして送金手数料を徴収するビジネスモデルを展開することが可能に。
・異なる事業者間の送金
・資金決済法による換金
・プリペなど電子マネー以外でも実現できる
→リアルとバーチャルの融合も劇的に進化
□クレジットカード送金
・資金決済法の施行に伴い、VisaやMasterが海外で展開するソリューションの展開が可能に。
・このクレジットカード間の送金は同一事業者だけでなく他のクレジットカード事業者にも送金可能。
→国際決済ブランドが用意した仕組みであるため参入は容易
→ユーザーから送金手数料収入を徴収を得られることは非常に魅力的であろう
□参入事業者の課題
・保全額・・・「未達分100%に加えて、もし返す場合の手続きの費用を上乗せ」して保全
・責任分解点
・本人確認
・コスト(サービス参入時とお提供時)・・・コストを安く抑えるにはもともと送金サービスに類似なサービスを流用
※銀行のインフラなどがすぐに思いつくが、アウトソーシングビジネスなどが考えられる
・相互運用性
・顧客獲得と利用促進
第3章 法制度はどう変わってきたか
□今後の課題
・収納代行サービスに取扱いをどう考えるのか
・ポイントの法的性格をどう考えるのか
・電子マネーと電子記録債権との関係
第4章 電子決済の仕組み
□国際ブランドカードの規格と仕様
・カードの番号体系、電子データの記録方式などは国際規格で決められたもの
・ISO/IEC7812にて国際基準が規格化されている
・カード番号の一桁目は主要産業識別子(MII)
→Visaは金融産業識別子の「4」、Masterは同じく「5」、JCB・Amex・DinersはT&Eの産業識別子の「3」
・さらに国際決済ブランドは取得したMIIの中から各国のカード発行イシュアにIINを割り当てる
・イシュアは割り当てられた6桁のIINから始まるカード番号の残りの桁について、
重複を防いだりチェックデジットを入れたり各社独自の方法で採番しカードを発行する
・カード業界ではこのカード番号頭の6桁の数字をBINと呼ぶ
□国際決済ブランドのデビッドカード
・審査不要でネットショッピングや海外利用ができる決済手段として、発行するイシュアが増えていくと予想される
→課題としてオフライン加盟店の存在、オーソリ金額と売上金額の不一致などインフラ面の課題有り
□国際決済ブランドのプリペイドカード
・デビッド同様伸びていくと思われるが同じ課題がある
・JTBの「Visaトラベルプリペイドカード Global Money」を発行している
□国内のデビッドカード「J-Debit」
・セキュリティ対策として高額利用ができなくなったことや、「預金引出し用カード」と根付いたカードでの買い物利用が。
さほどユーザーに受け入れられず、今後も縮小傾向と思われる
□ギフトカード
・汎用性が低い商品券市場自体が縮小傾向だが、そう客ツールやCRMツールとしていかに本業とうまく組み合わせて
展開できるかがカギ
□電子マネー
・発行目的や仕組みは事業者ごとに異なるものの、カード端末のコスト削減や加盟店の拡大、UIの利便性向上、
クーポンやポイントなどの他サービスとのインフラ共用化といった命題に向かって協調した取り組みが展開されることで、
さらに便利な決済サービスとして普及していくだろう
第5章 日本の携帯電話市場のオープン化
□垂直統合により発展してきたモバイルにおける小額決済
・重畳課金が日本の有料コンテンツの成長に大きく寄与
□海外市場は携帯電話事業者と端末ベンダが分離
第6章 おサイフケータイと非接触ICサービス
□非接触ICを活用したサービス
①決済サービス
②交通サービス
③本人確認
④セキュリティ
□おサイフケータイならではのサービス
・ディスプレイでICの中身を確認できる
・R/Wがなくても手元でICの中身を変更できる
・携帯電話の通信網を利用して遠隔からICの内容を変更できる
・電子ポスター、電子クーポンのサービス〜ユーザーの情報が取得可能
□課題と今後の展開
フェリカネットワークスの最も重要な仕事
①おサイフケータイ内のFeliCaチップの領域管理
②通信回線を経由しておサイフケータイのFeliCaチップへアクセスするシステムのASP提供
サービス拡大の阻害要因
①領域使用料やトランザクション料の負担感が大きい
②ユーザー視点では、アプリケーションをダウンロードして設定を行うことなどまだ馴染みが薄い
③店頭に設置するR/Wを、サービス専用に開発しなければならない
→ユーザーへの啓蒙活動、R/Wの共通化を図りながら、全体のコストを下げて行く必要がある。
→カードコストの安いタイプAなども利用できるようにしていけば非接触ICサービス市場全体でのコストダウンも期待できる。
→NFC
第7章 ID連携からID間決済へ
消費者向けのEC市場は2014年には約12兆円に達する見込みであり、これからの5年間、市場拡大を牽引するのはモバイルECである。
□今後の課題
①EC事業者の情報活用
→プロモーションはリテラシーの高いユーザー向けとなってしまっている、認証や決済、物流での先進的な取り組み
②CRMのためのID収集
ライフログ収集の一環として、ID数を増やし、紐付く情報の質をあげて情報分析の角度が高まると経営の意思決定の成功率が高まる。
→企業価値が高まり、IDを他社に渡す、送客するビジネスも成り立つ。1000万程度に達すると世間に広く認知されたといえる。
第8章 ポイントプログラムで変わる消費者と企業
ポイントは電子マネーではない
□ポイントの定義のひとつ〜「金銭によるポイント購入ができない」
電子マネーの原資の負担者は消費者であるが、企業ポイントの原資の負担者は企業であるという点が、大きな違い。例えポイントという呼称が用いられていたとしても、金銭によろ購入ができるのであれば、それは企業ポイントではなく、むしろ電子マネーとして位置付けられる。
□企業のポイン導入メリット
①囲い込み
②優良顧客化
③新規顧客獲得
④相互送客
□メリットを教授するための秘訣
①ポイントがたまりやすい
②顧客のポイントに対する知覚価値が高い
③ポイントの交換対象に関する限界費用が安い
□お得感を醸成できないなどの問題に各社が選択したのが、共通ポイント導入、ポイント交換
→共通ポイントのメリット
⑴ポイントのたまりやすさの演出
⑵2015年以降導入される国際会計基準IFRSの対応を任せることができる
Posted by ブクログ
この手の本には、法律や、プレイヤー、新しいテクノロジーについての記述が中心のものが多いですが、将来どうなるかというモデルケースがいくつか紹介されているので、イメージしやすかったです。入門書として最適だと思います。