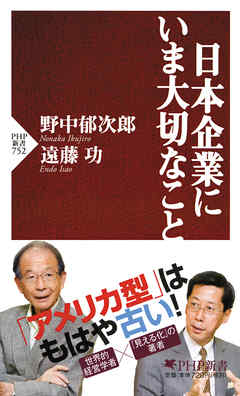あらすじ
成功しているグローバル企業の共通点、それは「日本的」であった! 本家本元・日本の強みをいまこそ自覚し、逆転の経営戦略を語ろう。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
読み終えた後、引用に使おうと、ページの端を折ったをみてみると、かなり多く印をつけていた。それだけ、この本がおもしろかったのだといえる。
震災後に出版されたこともあり、震災についても触れている。
最初は日本にはモノはつくれても、コトを起こす「イノベーション」を起こすことが苦手であるということに触れている。
日常を普遍化してとらえそこから必要性のあるものを生み出す、そういった能力が足りないと。
その次は、グローバル化より日本の強さを売り込め、というもの。世界に進出するために、世界に売り込んでいくためにグローバル化が行われたが、それも飽和状態といえる。ともなると、差別化を図るため、「強み」を示していく必要がある。
最後は企業のリーダーについて。最後が一番面白かったかな。リーダーは部下をその気にさせなければならない。「大丈夫か?」というのではなく「大丈夫だ!」と言ってやる。よくわかる話だ。
部下と仕事するとき、基本的に責任は自分がとる。そして、部下に指示を出しながら仕事をこなしていくのだが、そのなかでいくつかの作業を完全に部下へ任せる。部下にも考える(考えさせる)箇所を用意しておく。それは言われたことだけをこなすのではなく、自分で考えさせることもさることながら、それが自分の力で出来たことへの達成感を生み出すため。もちろん、途中途中のサポートはおしまない。
自分の目的の達成のためならば、他人をどんどん巻き込んでいくようははみ出しものの課長、というのは連想するひとがいなくもない。
そういった課長などは皆、トップがけしかしているからだ、と書かされているが、あのひともそうなのかな、と考えたりする。
Posted by ブクログ
「日本の経営者は『実践知のリーダー』である」「意思決定のスピードをいかに上げるか」「優秀なミドルをどう育てるか」「賢慮型リーダーの条件」など、改めて考えさせられる奥深い内容が綴られた書籍である。最後の記述である「現場を労り、勇気づけ、そしてその底力を発揮させることが出来るリーダー」が今最も求められているとする著者の考えに共感する。
Posted by ブクログ
「知識創造理論」を広めた野中さんと「見える化」を唱えた現場主義の遠藤さんが、日本の価値観を語り合う と紹介されている本です。
各章で野中さんと遠藤さんがそれぞれコメントしています。あまり本質と関係ないですが、どうやって本書を仕上げたのか気になってしまいます。対談を元に再構成されたとなっていますが、それぞれの主張をうけとめて、持論に展開して、このような形でまとまるのか?ってちょっと不思議。
さて、本書では直球でいうと、
「日本企業は自分たちの強みにもっと自信をもて」
というメッセージだと思います。
しかし、その話の展開としては、今までのお二人の持論をそのまま展開したとも読み取れます。
野中さんの「知識創造」の話や遠藤さんの「現場力」の話。それらをベースに議論が展開されている感じです。なので、お二人の本を読んだことがあれば、その復習もかねている感じもあります。
ただ、アジャイルスクラムの原型が野中さんの論文とは知りませんでした。ウォーターフォール開発とアジャイル開発がここで出てくるとはちょっと驚きでした。野中さんてシステム開発にも造詣が深いのですね。
さて、チーム力の話のなかで、「個性」と「連携」の両立が出てきました。
なでしこジャパンの佐々木監督の言葉で
「個人の力不足を組織で補うと、個人もチームも力が頭打ちになる。一対一の攻守など個人の強化でも妥協はしなかった」
のコメントがあり、チームは個人の弱点を支えあうのではなく、強みを連携させることが重要と感じました。
そして、「個性」と「連携」の両立ができるのが日本の強みということでもあります。
最後に野中さんのリーダが持つべき6つの能力について忘れてもいいように(^^;;ここにメモっておきます
(1)「良い目的」をつくる能力
(2)「場」をつくる能力
(3)現場で本質を直観する能力
(4)直観した本質を概念化し、表現する能力
(5)概念を実現する能力
(6)賢慮(フロネシス)を伝承、育成し、組織に埋め込む能力
そして、その章の中で印象的だったのは
「ディシジョン」ではなくて「ジャッジメント」
その時々の関係性や文脈を読み取り、タイムリーに最善の「ジャッジメント」を下す能力がリーダに求められている。
なるほどっと思いました。