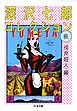深沢七郎のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
深沢七郎の、音楽に関連する小説を集めた短編集。
深沢七郎は小説を書くよりも前からずっとギターを弾き、歌ったり作曲したりもしていた。彼の音楽上のスタイルはよくわからないが、たぶん、民謡系/歌謡曲系/本来の意味での日本フォーク系だったようだ。
この短編集に収められている作品には、既読のものもあり、相変わらず妙な味を残すもののどうということもない小品もあるが、最後の2編にとりわけ惹かれた。
「変化草」は中学生のとりとめもない日常を描き、なるほど深沢の語り口は、思考のまとまりのない中学生的光景をうつしだすのに適していたんだな、と気づいた。イデオロギーとも芸術とも「内面」とも関係なく、ひたすらに生き続け -
Posted by ブクログ
深沢七郎のこの本を読みたいなあと思っていたら、ちょうど中公文庫が出してくれた。ありがとう。これからも深沢七郎出して下さい。
最初の「序章」と「おくま嘘歌」はちくま文庫の『深沢七郎コレクション 転』にも掲載されていたので再読。
「序章」は「インテリ」や庶民あがりの金持ちとの談話で「庶民とは○○だ」という可笑しい議論を繰り広げるのだが、よく読むと、作者本人とおぼしき「私」が最後の方で自分は庶民なのか、庶民でないのかと自問する場面がある。
「庶民」ばかりが横溢する小説を書いた深沢は「庶民」だったろうか? ふつうの意味での「文学者」たちとは一線を画した彼はやはりどちらかというと「庶民」の方にいるのだが -
Posted by ブクログ
「笛吹川」「千秋楽」などと同様に、延々と流れ続ける無窮の川のような趣の、深沢七郎作品。
土俗的な「庶民」の生活をたいした起伏もなく描き続けるが、つまらないわけではない。退屈はしない。しかしクライマックスとか、見事着地、といった感の結末もない。
冒頭、笛吹川岸辺に住む貧乏家族の徳次郎がアメリカへの出稼ぎを決意しているところから、徳次郎が主人公で、彼の視点から語られていくのかと思ったら、彼がアメリカに行ったとたん、視点は彼の母親(オカア)に切り替わる。アメリカでの出稼ぎ生活が具体的にどんなものなのか、最後まで謎のままだ。
そしてアメリカから徳次郎が戻ってくると、まもなく彼の視点に語りの座は移り、ま -
Posted by ブクログ
深沢七郎の名作『楢山節考』を読んだのはたぶん高校生の頃で、よく覚えていない。その後見た映画版のほうが印象に残っているくらいだ。
しかし深沢七郎はどうやら「奇妙な作家」ということで他にも面白い小説をたくさん書いているらしいことは知っていた。
ようやく43歳を目前にして読んだこの短編集、実に面白い。
表題作の冒頭から、とにかく特異な文体にめまいを覚える。文法的にもなんか妙なところがあるし、「・・・なのだ」という文末が変なタイミングで執拗に出てくる。一体、こんなふうにしゃべる日本人がいるのか? これは異邦人の言語、ねじこまれ変容した日本語である。
そんな独特な語り口に乗せられながら、『楢山節 -
Posted by ブクログ
ネタバレこの本の一番最後に載っている「みちのくの人形たち」が読みたくて購入した.読みたかった理由は,昔どこかである人が,今まで読んだ中で最も怖いホラーとしてこの話を紹介していたためである.
この本には6つの話が掲載されている.「東北の神武たち」と「揺れる家」,「千秋楽」,「女形」,「流転の記」,「みちのくの人形たち」である.「女形」のみ中編であり他は全て短編である.以下それぞれについて覚えている限りのあらすじと感想.
「東北の神武たち」:確か,寡婦が毎晩村の男に順番に抱かれにいくというときに,主人公だけ順番を飛ばされるという話.主人公の執着心が凄まじかった.
「揺れる家」:主人公は子ども.母親と祖父が -
Posted by ブクログ
作家や著名人の犬エッセイショートショート。
著名な作家を中心に、漫画家、イラストレーター、映画監督など、著名人が犬について書いたエッセイ集です。犬との出会い、犬との思い出、別れなど、テーマ別にまとまっていて読みやすかったです。が、それぞれが短いということもあってなかなか頭に残りませんでした。印象的なエピソードは、椎名誠のお母さんのトラウマ級の非道で、そんなことされたら僕も一生恨むだろうなあ、と思いました。あとは彫刻家の舟越保武さんの章や、寺山修司の話もよかったです。いせひでこさんのイラストエッセイはほんわかしました。うんうんそうだよね、犬ってそういうヤツだよね。
しかし全体的には昭和が中心の