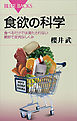櫻井武のレビュー一覧
-
Posted by ブクログ
ネタバレ「こころ」って何だろう?どこにあるのだろう? そんな疑問を脳科学から解き明かす本。
・もっとも進化的に新しくて認知や思考をつかさどる大脳皮質と、脳の深部にあり動物にも共通する情動をつかさどる大脳辺縁系。
・大脳皮質は前頭葉、頭頂葉、側頭葉、後頭葉に分かれ、領域ごとに機能が細かく分かれている。
・大脳皮質はものごとの要素を分解して情報処理を行う。視覚情報は左右別々に傾きや色、明るさなどの要素が入力され、脳内で再構成されてイメージを作る。「味、におい、色などは意識の中だけに存在する」→音楽も脳の中だけに存在する…?
・共感力も大脳皮質に存在し、こころに影響する。
・情動は脳大脳辺縁系でつくられる -
Posted by ブクログ
【献本当選作】第1章で出てきたホムンクルスの図は、有名なのだが正確に記憶できない思い出がある。「こころ」とは原始的で非自律的な大脳辺縁系で生み出される情動と、我々人類が発達させた大脳皮質の論理的思考、そして脳以外の身体から血液を通じて伝達される神経伝達物質の総合的かつ複雑な結果から表出されるという科学的知見が良く判った。「こころ」について知ると、いいね!されると「報酬」として快感が得られることに納得できる。しかしながら、他の読書記録サイトでは一時に多くのいいね!をもらうことで恐怖を感じ、いいね!を送った相手をブロックするユーザーがいる。自分も一日に同じユーザーから100以上ナイスをもらったら(
-
Posted by ブクログ
「なぜ人間には食欲があるのか」という疑問は、「生命維持に必要だから」ということで調べるまでもなく理解できるが、「どのようにして空腹/満腹を感じるのか」という疑問に答えられる人は少ないだろう。本書はそんな空腹の欲求と脳の活動の話。
αメラノサイト刺激ホルモン、ニューロペプチドY、プロオピオメラノコルチン、コカイン・アンフェタミン誘導転写産物などの読みくい物質から、弓状核、外側野、室傍核、視交叉上核という読み方すらあやうい脳部分まで説明なしで用いられるため、全てを理解するには新書では足りなすぎる。だが図は豊富なため、かろうじて関連性は理解できる。そして細部は理解できなくとも、食べたものが分解され、 -
Posted by ブクログ
睡眠は時間も食うし無防備になるし明らかに不利なのに、なぜ動物は眠らないですむように進化しなかったのか?
それは睡眠が欠かせない重要な役割を担っているから。
睡眠は記憶の固定に深く関わっており、眠ると新しい記憶が定着する。とくに手続き記憶(技巧や運動技能)に睡眠が重要。
ノンレム睡眠は脳の急速と老廃物の洗浄、レム睡眠は入出力はカットされた状態で脳は活発に活動。体は動かないが夢を見る。夢の特徴は論理的判断はできなくなっているが感情と運動が関わること。
レム睡眠は単なる浅い眠りではなくノンレム睡眠とは異なる役割を担っているらしい。通常はレム睡眠は睡眠時間の1/4だがレム睡眠だけ邪魔すると入眠後すぐレ -
Posted by ブクログ
感情がたかぶって耐えられないことがあったので手に取った(笑)。
ブルーバックスで中高生向けに、脳科学の観点から感情=情動のメカニズムに迫る。
へー。そうなんだ、あ、コレは知ってる、コレは知らない、とパラパラ読んだ。
個人的にとても印象に残ったのが、報酬系の働きについて。報酬を得た瞬間ではなく、そこに至るプロセスに快感を得る、だとか、なるほどと納得してしまう。
さらに個人的にショックだったのは、p149から始まる扁桃体の説明。
身近なひとの様子にそっくり。
そんなわけで、またもラインの文字認識能力を使って引用メモさせてください。めちゃ長いです。
p151の心理的距離と物理的距離の図解にも思 -
Posted by ブクログ
仕事がら、生活習慣病の治療に関するあれこれが多いため、その原因の1つである肥満をもたらす”食欲”に関する科学的な研究をクイックに把握したいと思いセレクトした講談社ブルーバックスシリーズの1冊。
様々な欲望の中でも”食欲”に関して、ここまで膨大な研究労力が費やされていた(もちろん、まだそのすべてが解明できているわけではないにせよ)という点に率直に驚いたのが率直な感想。
食欲に関連するホルモンであるレプチンを発見するまでの40年にも渡る先行研究の軌跡や、脳の働きを分析することで食欲発生のメカニズムに働きかける研究など、長年の科学研究の成果をコンパクトに知ることができた。 -
ネタバレ 購入済み
こころを科学的に理解できる本
「こころ」を科学的に解析した本。
最も興味深かったのは、感覚系から入った情報が2つの違った経路、理性と情動に分かれて伝達するということ。
一次視覚野を切除したサルは目が見えていないのにヘビを怖がるという。
子育て中なので、子供が感情を抑えられずに爆発させたりするのは理性に結び付く経路の未成熟が原因だったりするのかな、と想像したり。
専門的な事も多く取っ付きにくかったが、自分で興味深いと思う部分だけでも、自分なりに要約すると面白い。
-
Posted by ブクログ
睡眠は、まだまだ分かっていないことが多い。
このように覚醒は、食物などの報酬を探索する行動や、恐怖や不安などの情動に深く関係している。つまり「食っていくため」、そして「食われないため」に、覚醒が必要なのだ。
逆に満腹で、しかも安全な状態であれば、脳や身体を休めるために睡眠をとるチャンスである。睡眠は、安全と適切な温度が確保された環境で行われる。睡眠をとるために適した時間は動物の生活環境によって異なるため、概日リズムによっても制御されている。つまり、昼行性の動物では昼間に摂食行動を行い、夜間に休息期が多くなり、夜行性の動物では逆に夜間に主に摂食行動を行い、昼間に睡眠が多くなる。
…ニ -
Posted by ブクログ
睡眠は、まだまだ分かっていないことが多い。
このように覚醒は、食物などの報酬を探索する行動や、恐怖や不安などの情動に深く関係している。つまり「食っていくため」、そして「食われないため」に、覚醒が必要なのだ。
逆に満腹で、しかも安全な状態であれば、脳や身体を休めるために睡眠をとるチャンスである。睡眠は、安全と適切な温度が確保された環境で行われる。睡眠をとるために適した時間は動物の生活環境によって異なるため、概日リズムによっても制御されている。つまり、昼行性の動物では昼間に摂食行動を行い、夜間に休息期が多くなり、夜行性の動物では逆に夜間に主に摂食行動を行い、昼間に睡眠が多くなる。
…ニ