無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
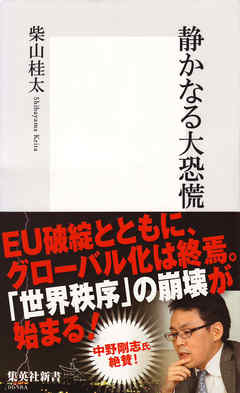
世界は「静かなる大恐慌」に突入した。危機的なのは経済だけではない。国際政治は、1929年の世界大恐慌をはさんだ、ふたつの世界大戦の時代と同じコースを歩み始めた。グローバル化が必然的に招く、社会の不安定化と経済の脆弱化。これに耐えるシステムは、通説とは逆に「大きな政府」の復活しかない、という歴史の趨勢に我々は逆らうことはできないのだ。このグローバル化の行きづまり、急反転というショックを日本はいかに生き抜くか。経済思想、国際関係論、政治・経済史の知見を総動員して、新進気鋭の思想家が危機の本質と明日の世界を精緻に描き出す!【目次】はじめに/第一章 「静かなる大恐慌」に突入した/第二章 グローバル化は平和と反映をもたらすのか?/第三章 経済戦争のはてに/第四章 行きすぎたグローバル化が連れてくる保護主義/第五章 国家と資本主義、その不可分の関係/第六章 日本経済の病理を診断する/第七章 恐慌以降の世界を生き抜く/註/主要参考文献/おわりに
...続きを読む※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。