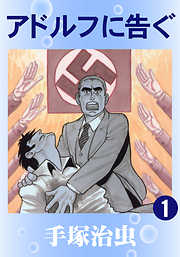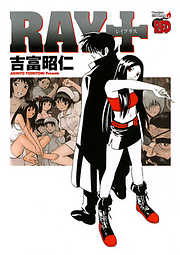田中圭一×宮崎克先生&吉本浩二先生インタビュー

手塚治虫タッチのパロディー漫画『神罰』がヒット。著名作家の絵柄をまねたシモネタギャグを得意とする。また、デビュー当時からサラリーマンを兼業する「二足のわらじマンガ家」としても有名。現在は株式会社BookLiveに勤務。
インタビューインデックス
- 「刺身のつま」のつもりでスタートした
- 最後に聞いた「ひとこと」が作品の方向を決めた
- 取材したからこそ描けた感動の一コマ
- これが一番!と言える手塚作品が決まらない
「刺身のつま」のつもりでスタートした
――そもそも、『ブラック・ジャック創作秘話 ~手塚治虫の仕事場から~』(以下『ブラック・ジャック創作秘話』)の企画はどうやって立ち上がったんでしょうか?
宮崎:『週刊少年チャンピオン』の「ブラック・ジャック特集号」内での1作品としての企画でした。色々なブラック・ジャック関連企画の中にあって、この作品だけノンフィクションだったんです。なので、あまり期待されてなかった読切マンガでした。1回で終わる予定でしたね。ノンフィクションは人気取れないジャンルですから。
――言い方は悪いですが、「刺身のつま」のような位置づけですね。
宮崎:はい。私は以前に別の雑誌で『松田優作物語』というノンフィクションマンガの原作をやっていたので、この企画に声がかかったんです。作画についても『松田優作物語』で絵を担当していただいた高岩ヨシヒロさんが適任だと思って推薦したんですけれど、連絡が取れなくて。で、どうしようかと思っていたところ、担当編集さんが吉本君を推してきたんです。見ると、劇画調の絵じゃないし、「えっ、この絵でやるんですか?」って思ったんだけど、どうせ読み切り1回だし、高岩さんは連絡取れないし、まぁいいか、って気持ちで決定しました。吉本君に。
吉本:ちょっと待ってください、初耳ですよその話…(一同笑)。
宮崎:でも依頼した時、吉本君も日本一周のバイク旅行の最中だったんだよね?
吉本:旅行から戻って来た日に、ちょうど電話がかかってきたんですよ。
――ほう!そりゃ、運命的な話ですね。
吉本:他誌での連載が終わって暇だったので、4ヶ月ほどバイクで日本中を旅して回っていたんですよ。…で、残りは茨城と千葉を回ればぐるっと日本一周できるはずだったんですが、台風が接近してきたので、もういいかと思って東京のアパートに帰ってきたんです。でも、仕事もないしどうしようかな?と。新しい作品の企画を持ち込もうかと思っていたところに、『週刊少年チャンピオン』の編集さんから連絡があったんです。でも、最初は一回断ったんです。
――それはどういう理由で?
吉本:恐れ多くて。
――たしかに!やっぱり恐れ多いですよね、漫画家として手塚先生を描くなんて。…僕が言っても全然説得力ないですけど(一同爆笑)。
吉本:恐れ多いのと、あと自信がなかったので…。
――でも、これは昭和の実話なので、吉本さんの絵がしっくりきますよね。
吉本:その後、担当編集さんから、手塚先生の元チーフアシスタントだった福元一義さんの話が聞けますよって囁かれて、連載の依頼がどうこうじゃなくて、漫画家としてその方の話を聞いてみたいと思って、依頼を引き受けました。
宮崎:取材が始まって福元さんに話を聞いてみると、それがとても興味深かった上に、他の関係者の方たちからも、面白い話をたくさん聞けたんです。だから編集長に「これ1話で終わるのはもったいないですよ。2話分くらい書けますよ」と言ったら、漠然とだったんですけど、編集長も「そうだね」と。その後、吉本君のネーム (※1)を見たら「ああっ!すごく面白い!」と感じて、編集長も「もう1本やろう!」ということになりました。正直、僕はそれまで吉本君がいいとは思わなかったんだけど(笑)、ネームを見た瞬間「これならいける!」と思ったんです。
――面白いネームを描く力って、漫画家の画力とは別の能力ですよね。『ブラック・ジャック創作秘話』は、どんどん読み進められて、読み終わるとすぐ2巻が読みたくなる。これ、実は凄いことで、吉本さんの「ネーム力」が高い証拠なんですよね。
宮崎:そう思います。
コマ割り・構図・セリフ・キャラクターの配置などを大まかに示した、漫画の設計図にあたるもの。
――2話までやることが決定して、そこから長期連載になっていった経緯について聞かせてください。

宮崎:最初の2本とも、アンケート結果が1位だったんです。ノンフィクションマンガで1位なんて僕も初めての経験で、普通ノンフィクションなんて10位以内なら上出来だったのに、ダントツの1位だった。吉本君のネームもさることながら、昭和テイストな絵柄もマッチしたんじゃないかと思います。
――エピソードが昭和20年代から40年代の実話なので、あの時代の空気感を伝える上で吉本さんの絵が…
宮崎:ぴったり合っていたんですね。
最後に聞いた「ひとこと」が作品の方向を決めた

――さて、長期連載が決まって、手塚先生の伝説的なエピソードが次々と紹介されていきますよね。この作品を読み返して思うのは、あの時代の漫画家さん・編集さん・アニメーターさんのとんでもないバイタリティー、これって絶対に平成の人には真似できないなって思いました。昭和のオトコだからできたんだって。平成どころか昭和生まれの僕ら世代(1960年代生まれ)でも絶対に真似できない。何を食べたらあんなふうになれるんだろうと思います。
特に手塚番と呼ばれる担当編集者さん達って、原稿をもらうために各社の手塚番が何日も詰めているわけじゃないですか。その中で順番決めたりケンカしたり。その間は他の仕事ができないですよね。今だったら出先でもネットを使って合理的に仕事ができるけど、あの時代では無理でしょう。なんか、合理性とは真逆にあるパッションだけですべてを乗り切っていた感じが、ホントに凄まじいなあと。

宮崎:僕がデビューした時代(1980年代)には、まだそういう人たちが残っていました。テンションがものすごく高くて。打ち合わせしていてもテンションが高いので、ついついケンカになったり。秋田書店には、そういうタイプの人がけっこう残っていましたよ。壁村さん (※2)の血を受け継いだ人たちが何人もいて。ノウハウとともにテンションも受け継がれていった感じですね(笑)。
――今だったらブラック企業とか言われちゃいますが、昭和の時代ってブラック企業だらけでしたよね(笑)。
秋田書店のマンガ編集者だった壁村耐三のこと。『まんが王』で手塚治虫を担当し、後に『週刊少年チャンピオン』の編集長として黄金時代を築いた。
――次に、吉本さんの「絵」についてお聞きします。恐れ多いと思いながらも、描いてみてどうでした?似顔絵や当時のエピソードを再現する苦労も聞かせてください。
吉本:空気感を知りたいので、トキワ荘の跡地や今も現存する並木ハウス、初台の家、虫プロ、越後屋ビルを見て回りました。それが昔の情景を思い浮かべるヒントになりました。また、マンガを描くために使っている道具が今とは違うので、これは苦労しました。
――枠線を引くのに当時はカラス口 (※3)を使ってましたよね。
吉本:そうです。昭和30年代と現在とでは、漫画家の机の上に置いてある物が色々と違います。
均質な線を引くための製図用具。先端がカラスのクチバシに似た形状になっており、ネジを使ってクチバシの開きを調整し、その隙間にインクを注ぎ線を引く。現在ではロットリングやマーカーペンに取って代わられ、マンガの現場で使われることは少ない。
――吉本さんが描かれる手塚先生がものすごく汗だくなのは、昭和の時代を意識してのことですか?
吉本:取材に行く前は「天才である手塚治虫先生が優雅に描いている」という感じで描こうと思っていたんですよ。元アシスタントの福元さんに「マンガを描く時にベレー帽なんかかぶってなかったよ」と言われたので、ああいう感じになったんです。
宮崎:取材が終わって、吉本君が福元さんに「手塚先生はどんな姿で描いてらっしゃったんですか?」と聞いたら、その話が出てきたんです。それがまさに帰り際で。あれは聞いておいて本当に良かった。逆に聞かなかったら、ああいう絵(汗だくで描いている手塚先生)に辿り着けなかったもの。
吉本:仕事中の手塚先生を描く時に服の情報がなかったので、「手塚先生がよく着ていた背広はどんな柄だったんですか?」と聞いたら、「背広なんて着てないですよ。夏はランニングシャツだけです」と言われて。一気にビジュアルが見えてきて、それまでの手塚先生のイメージからは真逆の絵になりました。
――考えてみたら、あれだけ多くのマンガを量産していたんですから、ジャケット着てベレー帽かぶって描くなんてことはありえないんだけど、普通の人はそう思っちゃいますよね。これは取材することで初めて出てくる事実ですよね。
吉本:僕も漫画家のアシスタント経験があるので分かるんですが、〆切間際の修羅場の時ってみんな服装なんて気にしないんですよね。だけど、手塚先生は違うんじゃないかなって思っていました。でも、やはり同じだった。
――『ブラック・ジャック創作秘話』を読むと、手塚先生は天才とか神様とかじゃなくて、マンガを描くのが大好き、アニメを作るのが大好きな、いつまでも心は少年という実像がよく見えてきます。手塚先生がどうやって多くの連載を抱え、やりぬいてきたのか、その実情もすごくよく分かりますしね。
取材したからこそ描けた感動の一コマ
――さて、その話の流れで今回の「一コマ」についてお伺いしましょう。まずは、吉本さんの選んだコマがこちらですね。