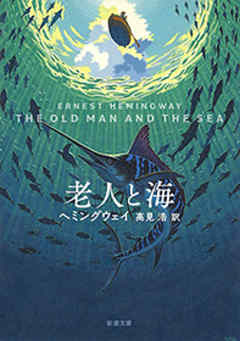あらすじ
八十四日間の不漁に見舞われた老漁師は、自らを慕う少年に見送られ、ひとり小舟で海へ出た。やがてその釣綱に、大物の手応えが。見たこともない巨大カジキとの死闘を繰り広げた老人に、海はさらなる試練を課すのだが――。自然の脅威と峻厳さに翻弄されながらも、決して屈することのない人間の精神を円熟の筆で描き切る。著者にノーベル文学賞をもたらした文学的到達点にして、永遠の傑作。
...続きを読む
「叩きつぶされることはあっても、負けやせん」
自らを慕う少年に見送られ、一人漁に出た不漁続きの老漁師。やがてその釣網にかかったのは、見たこともない巨大なカジキだった。老人とカジキは死闘を繰り広げるが・・・
カジキとの対決の際、老人からは何度も「あの子がいてくれりゃ」というセリフが出てきます。あの子とは自らを慕ってくれている少年のことでしょう。実際には少年はその場に存在せず、一人でカジキと戦わねばなりません。「人は人を望むが、結局は孤高に戦わねばならない」ということを暗に示しているかのようです。
自然の雄大さ、脅威。そして、それらと対峙する人間の、老いてもなお失うことのない尊厳。眩しいほどに力強い作品です。ぜひご一読ください!
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
老人が小舟に乗り、カジキと死闘を繰り広げる話。
独り言を言いながら、自分を奮い立たせ、手のひらをボロボロにしながらも自分を見失わない。
大きなカジキを釣り上げるもそれで終わりではなく、自然は厳しい。目に見えない大切なものに気づける物語。
Posted by ブクログ
とても前向きに、自分自身も勇気を貰った。
老いた漁師が小さな舟で、超巨大カジキと対決、奮闘する話。
自分の身も心も精神をもすり減らしてでも、カジキと向き合う少年のような好奇心や熱意や覚悟を持ったサンチアゴ。
己自身にも厳しく、カジキに親しみさえ覚える…。ただただ感心。
帰路に向かうまでにも、休む暇もなく次々とカジキを狙うサメと闘う姿に格好良いとまで思った。
そんな描写がハッキリと頭に浮かんでくるくらいだった。
少年との絆も素敵で、心が暖かくなって泣きそうにもなった。
Posted by ブクログ
客観的な評価は星4.
個人的には大好きな本で星5
自分と同じように海を愛する人に読んでほしい。海という環境、人、それに対する愛、すべてを感じられて心地良い本。
老人のプライドにカッコいいと感じた。自分も海の男として、プライドを持って慕われる人になりたい
要約
老人は一人弟子(少年)と船で漁に出るが2ヶ月不漁が続く。少年は老人を慕っていたが、周りの大人が少年に気を使い、別の船に乗る。
老人は沖でカジキをかける。老人の経験を元に3日間の戦いが始まる。カジキを釣りながら自分が生きるための魚を釣り食べ、手足がボロボロに攣ってもプライドを胸に闘う。
ようやくカジキを釣り上げるものの、大きすぎて船に乗せることができず、船の横に引きずりながら港へと戻る。その最中、幾度となくサメがカジキを襲い、それに対抗する老人であったが、港へと着く頃は頭と骨と尾ビレだけ。
しかし、老人は身体を休めるため、家に戻りる。周りの漁師はその魚の骨死体を見て、驚く。また市民はサメかなと思ってる。