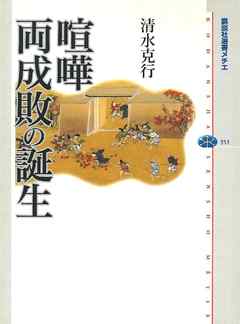あらすじ
中世、日本人はキレやすかった!大名から庶民まで刃傷沙汰は日常茶飯、人命は鴻毛のごとく軽かった。双方の言い分を足して二で割る「折中の法」、殺人者の身代わりに「死の代理人」を差しだす「解死人の制」、そして喧嘩両成敗法。荒ぶる中世が究極のトラブル解決法を生みだすまでのドラマ。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
イスラム国とか、カルトとか、そういうレベルじゃなくて、異文化を考えるときに、我々がこうやって生きていた歴史があるということがとても助けになる。
Posted by ブクログ
読んだのは半年ほど前のことになるが、感想を思い出しながら書くことにする。
この本は中世に漠然と興味を持っていたころ、中世人の考え方を理解するのにおすすめの本という評価を見て、読んでみることにしたものである。
この本は法制史の本で、室町時代の中世人という現代と異なる価値観をもつ集団の中で、喧嘩両成敗という有名な法がいかに誕生したかということが書かれている。
私の中で印象に残っていることは2点ある。
一つは、中世人の異質な価値観である。中世人は非常に短気で名誉を少しでも傷つけられたらすぐに喧嘩に発展し、殺傷事件に至ることも珍しくない。個人間の争いに留まらず、その人たちが属している集団同士の争いに発展し、役人が仲裁に入ってなんとか収まる、ということもままあったようだ。喧嘩の具体的な理由は現代から見ると取るに足らない理由も多い。本には書いた短歌が児に笑われたという理由で児を殺害した人が登場していた。この人は異常者ではないというのが驚きである。
歴史を学ぶ上でつい現代の感覚で昔の出来事を見てしまいがちであるが、当時の価値観を考慮した上で、出来事を解釈していくという必要があるのではないだろうか。
もう一つは喧嘩両成敗の成立の背景についてである。喧嘩両成敗は訴訟を個人間で解決した自力救済型の社会から統治機構による裁判権が確立した近世社会の移行期に誕生したもので、裁判権の統制を行っているが個人間の解決の要素もある、と記述されていたと覚えている。また、喧嘩両成敗は当時の衡平を重視する価値観からも受け入れやすいものであったものだという。喧嘩両成敗という言葉は現在も使用されることがあり、どっちも悪いの意味で使用されることが多いと思うが、その背景には社会の価値観や社会制度の移行など複雑なものがあり、とても興味深かった。
この本は、以上のようなことを根拠となる資料を提示しながらわかりやすく論を展開して説明する。喧嘩両成敗自体に興味がなくても、室町時代の日本人がどのような人たちであったか知りたい、という方にも自信を持って勧めることのできる本であると思う。
Posted by ブクログ
室町人の常識が分からないと読み物の登場人物の行動が理解できないな(それほど狂ったヤツら)
中世社会の衡平感覚と相殺主義が心情にあるからこそ、法理に基づいた判断が複雑(あるいは一筋縄でいかない)な時は「喧嘩両成敗」こそ苦渋の選択として定着した
日本人の知恵ですね(´・ω・`)
Posted by ブクログ
誤解されやすい古典の言葉。
・天は人の上に人を作らず
・健全な精神は健全な肉体に宿る
・初心忘るべからず
そこに僕の中でもう一つ、「喧嘩両成敗」が加わりました。
確かに「喧嘩したものは理由によらず両方成敗にする」という意味自体は合っているのですが、「成敗」とは「死刑」なのであって、積極的に運用するものではなく、諍いがこじれて解決の目処が立たない時の窮余の策という位置付け。
つまり「お前ら、争いが起こったらちゃんと法廷で解決しようとしろよ。私闘で解決しようとしたら両方死刑にするからな」という「見せ札」な法として生まれた、ということ。私闘、過剰な復讐を防ぐという観点で「目には目を」のハンムラビ法典に通じるものがある。
何でこんな法が必要になったか。室町時代の京都での例。
【例1】
北野天満宮の僧侶が金閣寺を訪れる
↓
僧侶に連れられてきていた稚児が、金閣寺の小僧が門前で立小便をしているのをみて笑う
↓
笑われた金閣寺側の僧侶が、負けじと天満宮の僧侶を罵る
↓
天満宮の僧侶が怒り、金閣寺の僧侶を追い掛け回す
↓
金閣寺の老僧が騒ぎを抑えようと天満宮の僧侶をなだめる
↓
天満宮の僧侶の怒りは収まらず、金閣寺の老僧に刀で切りかかる
↓
金閣寺の老僧は、これは手が付けられないと寺の鐘を乱打する
↓
大乱闘になり、一説によれば3人死亡
↓
そのまま天満宮と金閣寺の全面戦争になりかけるが、将軍足利義教の派遣した奉行によってなんとか事が収められる
【例2】
店に元結を取りに来た下女、品物が出来ておらず店主を罵倒
↓
店主が逆ギレし、下女を店から叩き出す
↓
怒った下女、主人の侍に訴える
↓
侍が店主を手討ちにしようとしたところ、その行動を予測した店主が仲間を引き連れ市中で矢を射かける
↓
侍、店主たちを返り討ちにするも力尽きる
↓
店主のバックにいた関口家の集団が出張る
↓
侍が仕えていた三条家の侍たちも出張る
↓
洛中で軍勢同士の喧嘩発生
↓
吉良家が裁定してどうにか解決
【例3】
ある侍が馬で出かけたとき、道中でちょっとした用事があり下馬
↓
そこに通りがかった別の侍、下馬している侍に気づき「下馬している侍には自分も下馬して礼を表す」という当時のマナーに従い、こちらも下馬
↓
最初に下馬した侍、「俺は別の用事があって下馬しただけで、お前に用はない。なのに下馬しやがって。これじゃあまるで俺が目下のお前に対して先に挨拶したみたいに見えるじゃないか。俺を見下す気か(意訳)」と激怒
↓
目下の侍、「ただあなたが下馬しておられたので礼儀に従って下馬したまでです」と弁解
↓
目上の侍、弁解を聞かず刀を抜いて目下の侍に切りかかる
↓
目下の侍も応戦した結果、刺し違えて両者死亡
こんな具合に、当時は極めて些細なことがあっという間に殺し合い、それも集団同士のものまでに発展するほど、現代から見れは異常に喧嘩っ早く、異常に面子に重きを置く時代だったようです。
ネットの表記を借りると、当時を構成する人々は「『シグルイ』の虎眼流門弟と、『北斗の拳』のモヒカン、あとは福本伸行の漫画や『闇金ウシジマくん』あたりに出てくるどうしようもないダメ人間」しかいない世紀末状態だったようで、そりゃあ末法思想が流行って浄土真宗や日蓮宗のような新仏教が起こる訳だと。「トラブルが起こったら裁判しなさい」を定着させるためにいかに当時の為政者が心を砕いたか、という苦労話に見えてきて、実に興味深かった。
ちなみにこの著者、清水克行氏の他の著作には「現代のソマリランドと室町時代って似てるよね」という趣旨らしい「世界の辺境とハードボイルド室町時代」というどっかで聞いたようなタイトルの本もあり、心惹かれるものがある。その路線で今度は「足軽大将殺し」みたいなタイトルでも書いてくれないかな。