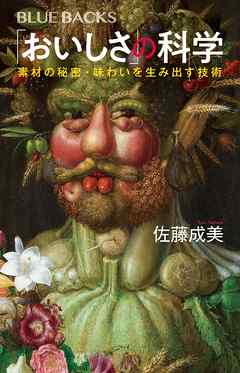あらすじ
うま味成分に関する研究が注目されるなど、「食」の科学的な研究が進んでいます。食品メーカーで分子レベルの研究から新商品が開発されたり、フランス料理などで科学的な知見にもとづく調理技術が応用されたりしています。「食の科学」分野で活躍中の大学研究者やメーカー研究者から取材した、「おいしさ」を感じるとは、また「おいしさ」を作るとはどういうことか、「食」分野での研究の最前線を、わかりやすく紹介します。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
大学のレポートのために読んだ。
「おいしさ」や「旨味」にとても興味がある私にとって、とてもためになる本だった。わかりやすく書かれていたためすぐに理解できた。日常の細かな疑問が解決していく所にとても爽快感を感じた。
本能的なおいしさもあれば、好き嫌いのおいしさもあることが分かった。
様々な技術と知恵があり、おいしい食品を食べられるのだと知った。
Posted by ブクログ
目的 食物の科学的な側面を学ぶため
感想 料理の過程でどのように栄養素が変化するかなど詳しく書いてありとてもわかりやすかった。また包装について、ポテトチップスの例が挙げられていて美味しさを保つための包装の大切さもわかった。
自分の行動 これから料理するときは、食材や調理方法でどのように味が変化していくのか科学的に思考する癖をつけていきたい。
Posted by ブクログ
人間はどういう原理で「おいしい」を感じるのか、食品が保存や調理や発酵を通してどのように変化しおいしくなるのか等、科学的に説明してくれる本。特に料理をする人だと、普段無意識で行っている行動に際し食品に何が起きているのかを知ることができて面白いと思います。よく「お菓子作りは化学」と言われますが料理もそうで、物質世界においては森羅万象これサイエンスだなぁ……と思った。人間の味覚は老化で衰えにくいとされているの、非常にありがたいことですね。
Posted by ブクログ
サイエンスライターによる料理や食に関する解説
料理をされる方なら感覚や経験的にご存じのことも少なくないだろうが、そういったことも科学的に説明されている。
関係企業や大学の近年の研究も反映されていて、流し読みでも大変刺激的で興味深い。
Posted by ブクログ
飲食業は今ものすごい競争の中にあります。しかし差別化の原動力であるメニュー開発は旧態依然としたものかもしれません。
「おいしい」は分解できるか。説明できるのか。
科学はどこまで切り込んだのでしょう。
旨味を増す組み合わせは意外なところにありました。
キレとコクも正体がほぼわかりました。
今後は経験に頼ることなくこのような科学的な見地からおいしさを分析することがカギになってくると思います。
Posted by ブクログ
タイトル通り、おいしさを科学的に分析する本。とは言ってもかなり分かりやすく解説されている。食材そのものが持つおいしさの成分から、調理方法、保存方法などによってもたらされる科学的な変性がもたらすおいしさ、人間の本能など様々な角度だ。
科学的な背景を知るとさらに味への理解が深まるが、本能の赴くまま食べ、飲むのもまた良し。しかし表紙はやや不気味だ。
Posted by ブクログ
おいしいってどういうことなんだろう?というぼんやりした疑問を抱き、読んでみました。
一言で言い表すのは難しく、またまだ解明されてない部分もたくさんあって、追求しがいがある分野なんだなという印象でした。
いろいろな食材のおいしさについて触れられているので、入門書のような感じで活用すると良いかもしれません。
Posted by ブクログ
おいしさを巡る、ブルーバックス的な良質なアクセス本。
結果的に、料理とは、アートであり、サイエンスなのだよと。思った。
具体的なレシピとかはもちろん書いてるわけじゃないんだけどね。
これ読んでも、料理上手くはなりません。
でも、なんで料理が美味いのかは、理解できると思います。
でも、料理教室でうんちく語ったら、あかん気がするので要注意です。
Posted by ブクログ
うーん、食品の成分や調理方法によってこう変わる!というのはよくわかったのだけど、タイトル的に「人はなぜこれを美味しいと感じるのか」みたいな話を期待してたため、肩透かし感はあった。
Posted by ブクログ
・アミノとカルボニルによるメイラード反応でパンの焼き目がつく
・野菜を加熱するとタンパク質が変性してクロロフィルのMgイオンが脱離して黄褐色になる。MgがCuやFeに置換されると緑色が安定化する
・ナスなどの紫色はアントシアニンがFeやAlと錯形成すると安定化する。ミョウバンで安定
Posted by ブクログ
科学技術としての面白さとか興味深さはありましたが、自分が美味しい料理を作ったり、世の中のものを美味しく楽しんだりするための情報ではないもよう。
Posted by ブクログ
味覚
出生時に基本が完成。
高齢になっても衰えにくい。
味細胞の寿命が短く、
一定周期で新しい細胞に置き換わっているため。
美味しさは大脳皮質の精神回路の変化によるので、
食経験を積めば味覚は鍛えられる。
脳の偏桃体に内蔵の感覚情報と味覚情報が集まり、
好き嫌いが記憶される。