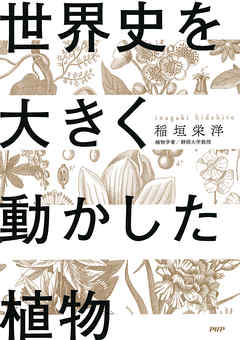あらすじ
一粒の小麦から文明が生まれ、茶の魔力がアヘン戦争を起こした――。人類は植物を栽培することによって農耕をはじめ、その技術は文明を生みだした。作物の栽培は、食糧と富を生み出し、やがては国を生み出した。人々は富を奪い合って争い合い、戦争の引き金にもなった。歴史は、人々の営みによって紡がれてきたが、その営みに植物は欠くことができない。人類の歴史の影には、常に植物の存在があったのだ(本書の「はじめに」より)。 【本書の目次より】コムギ――一粒の種から文明が生まれた/イネ――稲作文化が「日本」を作った/コショウ――ヨーロッパが羨望した黒い黄金/ジャガイモ――大国アメリカを作った悪魔の植物/ワタ――「羊が生えた植物」と産業革命/チャ――アヘン戦争とカフェインの魔力/ダイズ――戦国時代の軍事食から新大陸へ/チューリップ――世界初のバブル経済と球根/サクラ――ヤマザクラと日本人の精神……
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
人類の進化に深く関わった植物や穀物を紹介する本。
雑学としてとても読みやすく、おもしろい本だった。
・タンパク質や脂質を種子に持たせるためには、親の植物に余裕がないとダメ
・草原に生きるイネ科植物にそんな余裕はない。そのため、光合成で得ることができる炭水化物をそのまま種子に蓄え、芽生えは炭水化物をそのままエネルギー源として成長するというシンプルなライフスタイルを作り上げたのである
ジャガイモは、もともと「ジャガタラ芋」と呼ばれた。「ジャガタラ」というのは、現在のインドネシアのジャカルタのことである。ジャガイモは南米原産の作物だが、ジャカルタに寄港したポルトガル船が持ち込んだことから、そう呼ばれている
インドでは、カレーはとろみがなく、スープ状である。しかし、イギリス海軍では船の揺れに対応するために、カレーにとろみをつけるようになったと言われている。
カレーライスの調味料をカレー粉から、身近な調味料である砂糖と醬油に変えると「肉じゃが」になる。
世界で最も多く栽培されている作物はトウモロコシである。次いでコムギの生産量が多く、三位はイネである。トウモロコシ、コムギ、イネという主要な穀物は世界三大穀物と呼ばれている。四位がジャガイモ、五位がダイズであり、食糧として重要なこれらの主要な作物に次いで生産されているのがトマトである。
抹茶は日本に渡って生きながらえたのだ。そして抹茶は、日本のわび・さびと結びついて「茶道」という独特の進化を遂げる。
福建省では「茶」を「テ」と発音する。これが、ヨーロッパでは「ティー」となったのである。
プランテーションは大量の労働力を必要とする。最初のうちは戦争で得た捕虜を使っていたが、それでも足りない。次第に奴隷を必要とするようになっていくのである。
このときの醬油を意味する薩摩弁の「ソイ」が、ソイビーンの由来と言われている。
た。このときの醬油を意味する薩摩弁の「ソイ」が、ソイビーンの由来と言われている。
う。地球の支配者は作物であると思わないだろうか。
Posted by ブクログ
13種類の植物を取り上げ、それぞれの植物と人類との関わりの視点から世界史を紐解いている。
植物という自然側からの視点で、世界史を見るのは新鮮で、より立体的に世界史を感じることができた。そして何より、人類の生活に対する考え方が変わった。
特に興味深かったのは、イネやコムギ、トウモロコシといった穀物の章。人類の文明には、それを支えた作物があり、それぞれの大きな文明と主要な穀物の農業はセットだった。
人類は、砂漠に水路を引き、そこに種子を播いて育てることで農業をスタートさせ、保存が可能な穀物は、「富」を生み出し、社会や争いを生み出していった。
現代では、その植物の起源地ではない場所に運ばれ、栽培されている作物が多い。和食に使われる食材も、もとを辿れば、海外にルーツをもつものばかりだ。一見人類が好き勝手に植物を支配しているようにも感じるが、実は支配されているのは人類の側なのだと思えてくる。
「恵まれた地域の方が、農業は発達しやすいように思うかも知れないが、そうではない。農業は安定した食糧と引き換えに、重労働を必要とする。農業をしなくても十分に食糧が得られるのであれば、農業をしない方が良いに決まっているのだ。」
「栽培作物は、人間たちに世話されて、何不自由なく育っている。そして人間は、せっせと種をまき、水や肥料をやって植物の世話をさせられているのである。そのために、人間の好みに合わせて姿形や性質を変えることは、植物にとっては何でもないことなのだろう。人間が植物を自在に改良しているのではなく、植物が人間に気に入るように自在に変化しているだけかも知れないのだ。」
Posted by ブクログ
p32
イネ科植物はタンパク質や脂質を種子に持たせる余裕がないから、光合成で得た炭水化物をそのまま種子に蓄えた。
人間の胃袋には限界がある。保存出来る種子は財産であり分配できる富である。
p43
15世紀コムギの収量はわずか3〜5倍、17世紀の江戸時代の米は20〜30倍だった。現在でもイネは110〜140倍もの収量があるのに対して、コムギは20倍前後の収量しかない。
p50
戦国時代は、価値が安定しない小判より、米の方がずっと信用できた。徳川幕府の時代には米本位制が完成。田んぼを作るのは投資。しかし米の生産量が増加すると米の価値が減少し、米以外の物価が高くなる。つまりインフレが起こる。
徳川吉宗は米の価格を上げるために享保の改革を行った
p62
スペインやポルトガルは自国の貿易の独占を守るためにオランダ人は野蛮であるとアジアの諸国に伝えていた。悪評を払拭するためにオランダは現地の君主と友好深めると務めた。また乱暴な征服や強引な植民地支配によりスペインやポルトガルといった大国が瞬く間に凋落していく様子を目の当たりにしたオランダイギリスは丁寧な植民地支配を心がけたのである。
オランダでは複数の商社が競ってコショウを入手しようとしたため現地でのコショウの価格は高騰した。さらにオランダ国内では競ってコショウ売ったのでコショウの価格が下落した。そのためオランダは複数の商社をまとめて東インド会社を作り貿易の権限を独占させた。航海技術が進み、大量供給でコショウの価格は下落した。
コショウはむしろステータスを表すシンボル的な存在だったのだ。そのため金と同じと言われたコショウの価格は急激に下がっていった。
p76
カプサイシンは舌を強く刺激しそれが痛覚となっている。人間の体は痛みの元となる唐辛子を早く消化分解しようと胃腸を活発化させ食欲が増進する。カプサイシンを排出しようと体の機能が活性化され血液の流れを早まり発汗もする。(暑い地域での体力維持に適している)
エンドルフィンも分泌される。辛ければ辛いほどエンドルフィンは分泌される。
p82
日本と韓国の料理の辛さの違い。
日本では「唐辛子」と呼び、韓国の古い書物では「倭辛子」と記されている。
日本では仏教で肉食を禁じていたが、韓国では騎馬民族の元の支配下で肉食が習慣になり、ヨーロッパと同じように肉を保存するため香辛料が必要になった。
p89
じゃがいもの葉のソラニンは有毒で、その致死量はわずか400ミリグラム。
じゃがいもは種子でなく芋で増える。聖書では神は種子で植える植物を作ったとされ、じゃがいもは悪魔の植物であると言うレッテルを貼られ裁判にかけられた。刑罰は火あぶりの刑。
ジャガイモの花を愛したベルサイユのマリーアントワネットは、ギロチン台でバラの花びらのように散った。
p97
ジャガイモさえあればたくさんの豚を一年中飼育することができる。さらにジャガイモが食料となったことによってそれまで人間が食べていた麦などを牛の餌にすることができた。こうしてヨーロッパの国々は冬の間も新鮮な肉を食べられるようになった。
p106
イギリスの船乗りたちは日持ちのしない牛乳の代わりに保存性の高いカレーパウダーを利用してシチューを作った。このシチューに航海食として欠かせなかったじゃがいもが入れられた。こうしてイギリス海軍の軍隊食となった。インドではカレーはスープ状だが、イギリス海軍では船の揺れに対応するためにカレーにとろみをつけるようになったと言われている。1902年に日英同盟が結ばれるとイギリス海軍を見習って日本軍もカレーが食べられはじめ、日露戦争が終わると家庭へ普及した。
肉じゃがはカレー粉を砂糖と醤油に変えたもの。
p113
リンゴは紫色のアントシアニンと橙色のカロチノイドの二つの色素を巧みに組み合わせて赤い色を出している。対してトマトはリコピンという真っ赤な色素を持つ。
p116
ケチャップは古代中国で作られていた「ケツイアプ」という魚醤だったと言われている。ケチャップは今でも調味料を指す言葉でマッシュルームケチャップもある。
トマトの生産量は1位中国、2位インド。
植物学的にはトマトは「植物の果実」でフルーツ。
一般欧米人的にはデザート的に食べないので野菜。
日本で「果物」は木になる実なので、トマトは野菜。
p127
工業が主産業であったアメリカ北部の人々はイギリスから輸入される工業製品に高い関税をかける保護貿易を行いたかった。しかしイギリスにワタを輸出している南部の人々は自由貿易を推進していく必要があった。
北部と南部は利害を対立させ、南北戦争が起こる。
イギリスの援助を阻止したかったリンカーン大統領は奴隷解放宣言を出しイギリスの支援を難しくさせた。南北戦争は北軍の勝利で終わりを告げる。
p131
アラル海を干上がらせたワタ畑
ワタは塩害に強くまた海に近い干拓地は海運に都合がよかった
p133
秦の始皇帝が不老不死の効果があると信じて飲んでいた、茶。
唐代には座禅の眠気覚ましとして煎茶が用いられ、宋代になると抹茶が飲まれるようになる。臨済宗の栄西はこの抹茶の技術を日本に広めた。
ところが、明の洪武帝が富裕層の飲み物であった茶を庶民に広めるために散茶を広めたため、中国では抹茶は廃れてしまった。
名誉革命後、イギリスの上流階級にチャが広がった。チャが広まる前はコーヒーが飲まれていたが、コーヒーハウスは男性の社交の場だったため、女性のためにティーガーデンが作られた。独立戦争 アヘン戦争
p144
現在チャは中国種とアッサム種の2種類。
緑茶はアミノ酸の旨味を楽しむ飲み物で、紅茶はカフェインの苦味を楽しむもの。
p171
味噌は軍事食。ダイズのみで作ると赤味噌、米麹を加えると白味噌。
p179
タマネギのオニオンはラテン語のユニオ、真珠に由来。
建造物の擬宝珠(ぎぼし)はタマネギではなくネギ坊主を模している。
p196
織田信長が愛した花は、トウモロコシの雌花、絹糸
Posted by ブクログ
とても面白かった。
学生の頃、こうゆう本と出会っていたら世界史の見方ももっと面白くなったかもしれない。
人間が植物を利用しているようで、植物に利用されているのかもしれない。
読書メモ
・熱帯に香辛料が多いのは、病原菌や害虫の多い熱帯で、植物が身を守るために蓄えていた辛味成分こそ香辛料だから。
インドのお茶は抗菌作用のカフェインが多い。
・原産地ではなく輸入経路で唐から日本へ輸入されることが多く、トウガラシやトウモロコシなどの名前が付いた。カボチャがカンボジアを語源としているのと一緒。
・辛味は味覚にないから、痛覚で感じ取っている。
・肉を食べる韓国では肉の保存の香辛料としてトウガラシが受け入れら、仏教国の日本では逆に肉を食べないので受け入れられなかった。
・牛はジャガイモを食べないが、豚は餌としてジャガイモを食べる。こうしてベーコンやハム、ソーセージが食卓を彩ったのがドイツ。
・ナス科は有毒植物が多い。
・抹茶は中国から伝えられたが、中国では廃れたため、日本独自の文化となった。
・アメリカでもかつては紅茶を飲んでいたが、イギリスの植民地となり茶の規制が開始。アメリカの人々は紅茶の代わりにコーヒーを飲み始めた。紅茶の味に似せ浅く焙煎したのがアメリカンコーヒー。
・戦後アメリカの農業政策により、アメリカの重要輸出品目のダイズは日本では生産が縮小された。自給率が低い要因のひとつ。
・私たちが食べている玉ねぎは葉っぱの部分。
・明治時代、コレラが流行した際、玉ねぎが効くという噂が広がり、玉ねぎが受け入れられていった。
・世界最初のバブルはチューリップバブル。
・トウモロコシはガムや栄養ドリンクなど、さまざまな食品に入っている。
・園芸で盛んだった江戸の染井村が吉野のブランド力にあやかって作った桜がソメイヨシノ。
Posted by ブクログ
面白かった。 個人的に好きなのはトウモロコシの章、マヤ文明の人類がトウモロコシから作られたって話から、現代の人間の体の半分はトウモロコシを摂取して出来ているという話に繋げるの上手い。 あとは、トマトやジャガイモと言った異形の作物がヨーロッパで受け入れられる過程も印象に残る。 世界史なのにラストがサクラなのは違和感有ったけど、日本人の作者だし、ほぼ後書きみたいなもんだよね。
Posted by ブクログ
タイトルにもある通り、本作は主に食物(植物)を取り扱います。
やや劇的なタイトルではありますが、確かに歴史にインパクトのあった食物がフィーチャーされています。
列記しますと、コムギ、イネ、コショウ、トウガラシ、ジャガイモ、トマト、ワタ、チャ、サトウキビ、ダイズ、タマネギ、チューリップ、トウモロコシ、サクラ、となります。
・・・
何が良いかというと、やはり稲垣先生の徹底的な植物好き、植物に関する深く広い知識が面白くてよいですね。
植物の生態だったり形状だったり進化の理由とかを説明しちゃう。そしてそれがまた非常に合理なのでついつい「へぇー」となる、という感じです。
例えば、イネ科の植物について。イネ科の葉は全般に繊維質が多く、消化しづらいそうですが、これは葉っぱを食べられにくくするためだそう。また成長点が地面スレスレにあり、それより上の茎が動物に食べられても成長点から再び生えてくることが出来るそうな。
って、世界史とは関係ないのですが、こういう「ちなみに、」的な話の方が印象深かったりします笑
こうした実った種は、単なる食糧であるに留まらず、将来の収穫を約束してくれる財産、分配可能な余剰、富ともいえるとし、貨幣経済の黎明とも連結していることをほのめかしていらっしゃいます。これまた「大きな」はなしなのですが私はこういうのが好き。
・・・
それから、農業についての逆説的な説明も面白かったですね。
農業は重労働で、食物が豊かなところでは行われないという話。例えば稲作は弥生時代に九州に伝わり、東海地方まで瞬く間に広がったとされますが、東北地方にはあまり広まらなかったそう。これは稲垣先生がいうには「縄文時代の東日本は稲作をしなくても良いほどゆたかだったから」(P.35)とのこと。
東日本では西日本の10倍の人口密度があり、それを賄える豊かな食物が自然の中で手に入れられたとのこと。確かに東北や北海道に多くの縄文時代の遺跡がある話を思い出しました。
なお上記イネについての話が印象に強かったのですが、それ以外にもピーマンとかトウモロコシの話も面白かったですね。
・・・
ということで稲垣先生の著作でした。
途中、あっという間に終わってしまう章もあり、何だか編集者に乗せられて書いたのか?みたいな素人の勘繰りをしてしまう所もありますが、植物についてはどれも詳しく、面白かったです。
故に、広く浅くで読むのには丁度よい書籍かと思います。
逆にもっと深堀りして歴史の移り変わりを知りたいかたは、よくある「〇〇の歴史」「○○の世界史」みたいな本を購入されたらよかろうと思います。
食べ物好き、うんちく好きにはお勧めできる一冊。