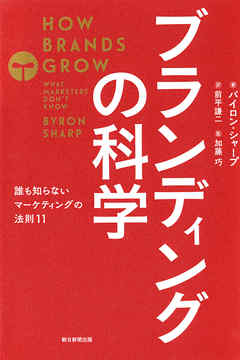あらすじ
かのP&Gに影響を与えたマーケティングの名著が遂に発売。コトラーなどのマーケティング主流派に異論を唱え、新しい視点からマーケティングやブランドの育成方法を提案する。コトラーを超える最新マーケティングの神髄。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
難しかったけど参考になるところが多かった。
・ダブルジョバティの法則
・ブランドは顧客を共有し合ってる
・ロイヤル顧客はライトユーザーにもなるし、ライトユーザーはロイヤル顧客にもなる
など他にもたくさんあるが、マーケティングで見落としガチなところの視点を増やせた。
Posted by ブクログ
売上(シェア)は顧客数×平均購入回数に分解できるが、マーケッターとして目指すべきことはシンプルだ。
①ダブルジョパティの法則
・シェアを上げるためには顧客数を増やさないといけない。
その際に離反率を下げようとするのは間違いだ。
また平均購入回数も増やそうとするのもうまくいかない。
CRMなどのロイヤルティプログラムは効果が薄い。
そんなことをするよりも未購入顧客を増やすようにする方が正しい。
購入回数(ロイヤルティ)は顧客数が増えることで少し上がっていくが、トップブランドとビリのブランドでロイヤルティが大きくことなるかというとそんなことはない。
Posted by ブクログ
従来のブランドロイヤリティや差別化といった戦略とは異なる視点のマーケティング戦略についてまとめられた本。某大手消費財メーカーのマーケティング戦略もバイロンシャープの考えに則っている。企業のマーケッティング担当者は試す意義がある。
Posted by ブクログ
> 示唆されるのは、消費者の購買行動やマーケティング指標を測定する重要な科学的法則─本書ではその法則についてこれから解説していく─が無視されているということだ。(あなたならどう答えるか?)
マーケティングのベストプラクティスとされている事の誤りを指摘し、実際の数値を示しながら論を展開していく。
常識を疑うことは常に大切ではあるが、本書で提示されている新しい法則が科学的に正しいかどうかの判断はできないし、おそらく再現性の観点では既存の法則が正しくない程度には正しくない。本書は一般的な法則を見つけたと主張するが、今までも同様の営みがされてきたのだろう。
常識に対して批判的な指摘は勉強になるものの、本書を読んだ結果読者が身につけないといけない能力は法則を鵜呑みにせずに実際の数値から結論を導ける能力だろうし、本書ではそれは提供されていない。
Posted by ブクログ
今までのマーケティングという学問では、エビデンスが少な過ぎた。
個人としては、なんかマーケティングって胡散臭いなと思ってたのですが、その要因の一つかと思います。「なんか当たり前のこと言ってない?」とか「うーん、そう言われればそうだけど、全部が全部当てはまらないよな」みたいなことが多々ありました。
ただ、胡散臭いと思うけど、上手く言語化ができていなかった。
そういう面では、この本はエビデンスを提示して、今までの学説に異議を唱えている。ある程度は納得はしました。
ちょっと言葉の定義を説明せずに突き進むので読みにくさはあります。
この本を読んで面白かったのは、「カテゴリー内では各ブランドの顧客基盤はあまり変わりない」「ブランドの想起させることが大事」
Posted by ブクログ
「マーケティングの科学的法則の集約という初めての試み」だそうである。やや誇張気味に言い換えると、フィリップ・コトラーのマーケティング理論はエビデンスを欠いた妄想だとする意欲作。
「支配的なブランドはこうなっている」ことの説明が多く、それは突き詰めれば「シェアを持っていると強い」ということで、割と身も蓋もない。
ターゲットを絞って商品を差別化することには意味はないという主張で、弱小ブランドへのコンサル業務で稼ぐ人々から「余計なことを言うな」と怒られそうな記述が続く。
そういう意味では「呪縛を解く」もので、有意義である。
でも、弱小ブランドがのし上がるために何をしたらよいのか、という点では直接的に役立ちそうな印象を受けなかった。
Posted by ブクログ
今までのマーケティングで良しとされてることを全否定してくるような本。
最近流行りのSNSマーケティングとは離れてるのかな?共通点あるのかなぁと不思議に思った
最近はSNSの普及によってマーケティングも変わってきてるから、直近の筆者の見解が気になる
pgが出してる製品に言えることなのだろうなと感じた
Posted by ブクログ
学術的な内容。
マーケターの常識とは反する部分もありつつ、体験的に納得することも多い。
ただし学術的が故に抽象度も高く、現実のビジネスに実装する場合にはマーケティング戦略の超上流、方針レベルにしか影響を与えづらい。
Posted by ブクログ
エビデンスに基づいてマーケティングを行う。一見当たり前のようで、多くのマーケターができていないという事実にまず驚いた。
ダブルジョパディ、アベイラビリティなど数多くの使える理論が学べた。実際の仕事で使い始めている。
じゃあどうしたら?という点は下巻に記載されている。
Posted by ブクログ
マスマーケティングに携わる者として必読の書だと思ったし、P&Gマーケの方にとってバイブルともなっているのうなづける。
盲目的にCRMに取組、流行りの、顧客ID統合によるセグメンテーションした1to1マーケに対して、データに基づく懐疑的な視点がとても勉強になる。
電通博報堂をはじめ、TVCMを中心としたマスマーケのプロフェッショナル集団は、いまいちど、じぶんたちのマスマーケの力を客観的に評価をし、自信と誇りをもってもいいのでは、と。顧客基盤構築によるDXマーケにゆらぐ業界にあって、いまいちど、現時点の立ち位置をデータから冷静にみつめる必要があると感じました。
Posted by ブクログ
ブランディングに関する、新たな視点が得られた。
差別化、ロイヤリティなど、マーケティングでよく語られる観点を、事例をもとに批判的に考察している。
事例が、日用品や食料品など、そもそも差別化が難しいものが多く取り上げられており、そこまで普遍的な法則とは言えないのでは、と感じた。
Posted by ブクログ
『確率思考の戦略論』(森岡・今西著)に出てきた確率モデルの一種、ディリクレNBDモデルについて記述されている本だったので読みました。
一般的なマーケティングの書籍は、ロジックを組み立てあらゆる事例を参考にしてマーケティングを読み解いていくことが多いですが
一方で、本書は市場シェアや購入頻度など実データからマーケティングの規則性・法則性を導き出している点が新しいと感じました!
統計データから本質を明らかにすることは、世界的なマーケティング企業P&Gやユニリーバ、コカコーラが実施しているので、そのメソッドを知るのにこの本は役立ちます。
しかしながら、唯一翻訳が残念。英語からそのまま日本語にしたようで所々読みにくいのが−1星です。
Posted by ブクログ
コトラーに慣れ親しんだわたし(ブランドマーケター )感覚からすると、ん?と思うことがありつつ、今の時代に沿った考え方もあり、学ぶ事が多い内容でした。
Posted by ブクログ
既存のブランディング・マーケティングの常識をデータや数字を使い否定していく一冊。その中でも著者が注目するマーケティング法則もいくつか紹介されている。各章ごと、まとまりごとに結論や要点ををまとめた文を挿れてくれているので読み進めて理解できなかった部分はそこで改めて読むこともできる。具体的なデータや数字、表、グラフも多く説得力のある本。
Posted by ブクログ
マーケティングやってる方向けの本で、軽い気持ちで手に取った身としてはピンとこない説明が多かった。聞いたことのない海外ブランドが例として使われてることが多いのもあるかな?
ブランドロイヤルティが高い層以外からの売上が大きいので大事というのが印象に残った。
Posted by ブクログ
学術的で難しい内容。
少し恣意性の高いデータからではあるが、自分の消費行動から照らし合わせても納得できる部分は多数あった。
マーケティングは本当に難しい、と感じる一冊。
答えのない文系寄りの学術書は統計学的なアプローチが主になり、そのデータの取り方は無限にあると思われるため、恣意性が働くことは仕方がないとも感じた。
個人的に印象に残った内容。※個人的な解釈含む。
・ダブルジョパディの法則、結局消費者はブランドへのロイヤリティは高くなく、シェアに依存しているということ。シェアが低ければ、ロイヤリティよ低い。
・ブランドの顧客基盤は、競合の顧客基盤と重複する。専門的なロイヤリティを持つ顧客などほとんどいない。そのため、ブランドの損失と獲得は競合ブランド間で巡り続ける。
・メンタルアベイラビリティもフィジカルアベイラビリティの高さが、消費者の買いやすさにつながり、シェアにつながる。
・ロイヤリティの高い顧客を取り入れ、売上に変えることは、費用対効果も低く、現実人々はそこまでヘビーバイヤーではない。(ほとんどがライトバイヤー)そのため、常に新規顧客の獲得を広げることを忘れては行けない。結果的に費用対効果も高い。
・ブランド体験がブランドロイヤリティに繋がる。ので、販売を広げることは大切。
・広告はブランドの認知を忘れさせないために必要。消費者は忘れてします。
・ロイヤリティプログラムはまやかし。顧客が一つのブランドに集中すると信じることは間違っている。多くの顧客は購買率も高くない。既存の顧客を取り込むことには有用だが、他の新規に繋がらない
Posted by ブクログ
全体的に難しい。
でも、きちんと読めばなんとなく理解でき、知らないことも多かった。
コカコーラのヘビーユーザーが、年に3回しか買わないのには驚いた。
Posted by ブクログ
データを元に書いてあるのでそういう例があるのねとなり面白かった。大規模なブランドの有利さが説明されてるので早いうちにそうなりましょうという感じだった。広告による売上額の変動のなさにも触れられているのは良かった。
ただ、全体的に読みづらい。文が長ったらしいのとせっかくの図や表をもっと活かして欲しいとなった。なんかもっとすっきりまとめられたんじゃないのかと思うんだけど自分の読解力が足りないだけかもしれない。
Posted by ブクログ
1.ブランド化が騒がれるようになって、ふと「ブランド化ってそもそもなんだ?」ということを思うようになったので購入しました。
2.この本は、根拠に基づく理論を実践することが大切だということを前提に、11の法則を掲げています。広告にはどんな機能があるのか?ロイヤリティプログラムがなぜ失敗するのか?顧客のリスト管理をどうしていけばいいかなど、マーケティング分野で必要なことを述べています。
著者が述べている11の法則
1.エビデンスに基づくマーケティング
2.ブランドはどのやうに成長するのか
3.顧客基盤を拡大させる
4.ブランドにとって最も重要な顧客を探す
5.顧客のパーソナリティプロファイルを知る
6.真の競合ブランドを探す
7.消費者のコミットメントを知る
8.差別化ではなく独自性
9.広告の機能
10.価格販促の役割
11.ロイヤリティプログラムがなぜ失敗するのか
3.それぞれの法則がどんなものなのかはなんとなくですがわかりました。しかし、それではこの本の知識を活かすことができません。従来のマーケティング理論どどこが違うのか、何度でも読み直して理解できるようにしていきたい。