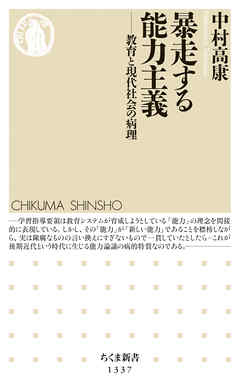あらすじ
学習指導要領が改訂された。そこでは新しい時代に身につけるべき「能力」が想定され、教育内容が大きく変えられている。この背景には、教育の大衆化という事態がある。大学教育が普及することで、逆に学歴や学力といった従来型の能力指標の正当性が失われはじめたからだ。その結果、これまで抑制されていた「能力」への疑問が噴出し、〈能力不安〉が煽られるようになった。だが、矢継ぎ早な教育改革が目標とする抽象的な「能力」にどのような意味があるのか。本書では、気鋭の教育社会学者が、「能力」のあり方が揺らぐ現代社会を分析し、私たちが生きる社会とは何なのか、その構造をくっきりと描く。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
近年、ビジネスや学校教育の現場では、働く個人や学生に対して、コミュニケーション力や問題解決力といった「新しい能力」が求められている。これらの「新しい能力」は、社会的影響が大きいにもかかわらず非常に抽象的であり、また昔から求められてきた能力を言い換えただけのものも多い。本書では、それらの能力が個人に真に求められているわけではなく、能力主義(メリトクラシー)という社会構造の再生産の一部に過ぎないことを、前近代、前期近代、後期近代という時間軸を通して明らかにしており、とても面白い。
Posted by ブクログ
本書は、能力主義について、その「再帰性」という観点から、社会全体を分析対象にして論じている。国内外における近年の大学や就職に係る能力観の議論は、やや食傷気味の感があったが、本書はアプローチの方法も結論も大きく異なる。能力主義は再帰的な性格を帯びるものであることを、明瞭に示したこの仕事はとても重要である。
第1章では、「『新しい能力』であるかのように議論しているものは、実はどんなコンテクストでも大なり小なり求められる陳腐な、ある意味最初から分かり切った能力にすぎない」(p.46)と早々に断じた。能力観が変わってきた、という固定観念に対処するために、これまでの議論から「最大公約数的な陳腐な能力」を毎回定義し直してきている、という見方は、非常にわかりやすかった。
また個人的には、この「再帰性」という言葉の説明力の大きさに気づかせてもらったことは有益だった。再帰性とは、「常に反省的に問い直され、批判される性質がはじめから組み込まれている」(p.51)状態を指すとここでは解した。再帰的に、能力に関する議論を社会が求めていることを実証するために、著者は以下の5つの命題を設定してる。
命題1 いかなる抽象的能力も、厳密には測定することができない 【2章】
命題2 地位達成や教育選抜において問題化する能力は社会的に構成される 【3章】
命題3 メリトクラシーは反省的に問い直され、批判される性質をはじめから持っている(メリトクラシーの再帰性) 【4章】
命題4 後期近代ではメリトクラシーの再帰性はこれまで以上に高まる 【5章】
命題5 現代社会における「新しい能力」をめぐる論議は、メリトクラシーの再帰性の高まりを示す現象である 【5章】
この議論の立て付けは参考になった。上の「能力」や「メリトクラシー」を、同じくらい議論が重ねらている「教養」に置き換えた上で検討すると、よい仮説が導けるのではないか。またそれらは、近年の大学教育における議論に通ずることがあるのではないか。本書はこうした点に気づかせてくれた論稿だった。211頁に示された再帰的メリトクラシー理論の図表は秀逸。
Posted by ブクログ
新しく求められる能力が求められる社会的な背景が詳細に説明されている。頭が冷める。
特に能力をめぐる議論は英語教育関係者として読んでおいたほうが良いと思った。
Posted by ブクログ
能力は正確には測ることができず、そのために「能力がある」とされる状態は例えば=学歴(学校歴)等として社会的に構築される。ところがその社会的に構築された能力判定は必ずしも社会の求める能力と完全には一致せず、常に修正を迫られるようになる‥これが本書の中で後期近代のメリトクラシーの実情として整理される姿である。
興味深かったのは3章で、社会学に多い「メリトクラシー幻想論」について「いつもチャンスが十分に開かれていないとの結論になる」と批判的に言及されるのだが、「大学に行く条件をいかに完全平等にできるか」に血道をあげている研究がメディアで紹介される度に個人的に感じていた疑問を言い当てており、この方向の議論をもっと読みたかったが、さすがにやりすぎると業界の中で「角が立つ」のだろうか。
読んで思うのは、現在の能力主義は再帰的にその基盤が問われる状況さえ超えて、アメリカのMAGAに象徴されるように憎悪の的にさえなっているのではないか、ということ。末尾で少しだけ反知性主義に触れているが、本書の刊行後、能力主義そのものへの懐疑が極まりつつある現在において、著者の処方箋を聞いてみたい気がする。
Posted by ブクログ
この本は、個人が持ち、磨いたり評価したりできると信じられている「能力」という概念が、実はそれほど明確なものではないことを示している。
特に、近年新しい能力として注目されているコミュニケーション力や課題解決力は、それほど目新しい概念でなく、今も昔も変わりなく必要とされてきたものであると指摘する。
「メリトクラシーの再規性」
この本が焦点を当てるのは、能力そのものの新しさではなく、近年高まってきている「新しい能力を求めなければならない」という議論の論拠である。
その根拠は、複数の命題を証明する形で説明される。キーとなるコンセプトは、「メリトクラシーの再帰性」だ。
- メリトクラシーは、「能力主義+能力による支配」を意味する。
- メリトクラシーの再帰性とは「反省的に常に問い直され、批判される性質を初めから持っている」ことを指す。
この性質は、デモクラシー(民主主義)が自己修正機能を持っていることに似ている。
本書は、具体的な、「じゃあどうすればいい」という解決策は提示していない。しかし、新しい能力を身につけるための教育内容の改革などについて、一歩下がって深く考える視点を与えてくれる。
Posted by ブクログ
分断、分断ということが、実際のところはどうなのだろうか?ハイ・モダニティにおける貨幣経済や専門家システムが抽象度を上げ、ローカルコミュニティへの帰属を薄いものにしてきたというギデンズの主張も分かりやすく、「学力主義」もその抽象性からこの分断を生み出す要因の議論に含んでも良さそうだが、そもそもそこまで人は孤立し、孤独を感じているのだろうか。
不登校や自死者の増加を分断による証左として挙げるのは少しムリがあるような気がしてきたな。
しかし熾烈な生存競争が、他者を敵として認識させるという力動を作り出すというのはある気がする。となると、分断という言葉は、その内的な敵視性が投影されている、すなわち分断されているような気がするというのにとどまっており、実際はそこまで分断されていない可能性もあり得るか。
あるのは「分断気分」なのかもしれない。
Posted by ブクログ
人間の能力は、基本的に測定不能であり、社会で必用とされる能力の変遷に伴い、教育内容を変えるべきということを「メリトクラシーの再帰性」という言葉で説明した。
◆Aiの発展で単なる暗記に偏った勉強だとAiに仕事奪われるよ→マークシートによるセンター試験(共通一次)の廃止、
◆記述式の共通テストへ、英語は読書きメイン→読書きだけでくヒアリング・リスニングも、
と言った現象は、まさにメリトクラシーの再帰性の高まりだろう。
しかし、早急(拙速?)な改革が行われつつあるという印象は否めない。
記述式テストは採点の難しさ、採点者による評点のバラツキを発生させ、その調整には多大なコスト時間がかかるし、藤原正彦の言っているように英語が流暢に操れる人間は全体の2-3%もいれば十分だろう。("1に国語、2に国語、3.4がなくて5に数学"と藤原氏は言っている)
現在の教育改革(メリトクラシーの再帰性の高まり)は、何を生み出すのか? 全く予測できないが、近い将来に、また再修正されることになるだろうという気がするねぇ。
(あまり批判的なことを言っていると代案だしてみろと言われるので、ここら辺でやめておこう。)、
Posted by ブクログ
タイトルは著者が理論的にインスパイアされたギデンズ『暴走する世界』にちなんだもの。現在の「教育改革」を席捲する「コンピテンシー」論を理解する補助線として。
著者の議論の要諦は、21世紀に入って以降の日本で次々と提案されている「新しい能力」論は、後期近代における「メリトクラシーの再帰性」のあらわれとしての「能力不安」言説の反映に他ならず、基本的な論点は過去の反復でしかない、というもの。その点は明快だし、説得力もあるのだが、次々と簇生する「新しい能力」論をギデンズ的な「嗜癖」(=一時的な不安の置き換えとしてのaddiction)と見なしていることには違和を感じる。
というのも、日本における「新しい能力」論は、まちがいなく新自由主義的な人的資本論というイデオロギーと、そこに焦点化することで駆動する教育投資市場の拡大という問題がある。つまり、本書の枠組みで言うなら、それぞれの「新しい能力」論が、誰の・どんな欲望に応じて・どのように構成されてきたかが決定的に重要ではないか。「嗜癖」という理解は、問題を過度に一般化する(それは現代社会に通有の病理なのである)か、過度に個人化する(それはイデオロギーに目を曇らされている個人の問題である)おそれなしとしない。
Posted by ブクログ
非常に読みやすい。スルスル読める。
階級、学歴の次に基準となる「新しい何か」は見つかるのだろうか。メリトクラシーを俯瞰で見たときに今、学校教育で行うべきはなんなのだろう。「自分の中の答え」みたいなものがまた遠くにいった気がした。
Posted by ブクログ
なぜ新しい能力が求められるのか?コミュニケーション能力、非認知能力がなぜこんなにも叫ばれているのか、教育改革がなぜ成功しないのかということをメリトクラシーの再帰性という現象から説明している。
メリトクラシーの再帰性とは、メリトクラシー(業績主義)が常に自己反省的な性質をもっているということである。必要な能力は定義することができないという性質上どんな能力を想定してもそれは批判可能性を秘めており、それに対する能力が提示される。
現代において教育はどんなあり方であるべきなのだろうか。
相対主義が蔓延する中で、学校が担う義務は何か。
反知性主義をどう考えればいいのだろうか。
Posted by ブクログ
能力主義に代わるものはまだない。
暫定的な社会の枠組みにすぎない。
不完全ながら、良い代替案が無いため暫定的に、今の世の中の常識に据えられている能力主義。
そういう意味では資本主義に似ている。
この本でも代替案は示せてはいない。
ただ、大事なのは能力主義を所与のもの、自然の摂理、現代社会の常識で完全無欠、不変なものとして認識するのではなく、常に相対化する視点を持っておくこと。
そう。知識は物事を相対化するためにある。
次はマイケル・サンデル読んでみよう。
Posted by ブクログ
確かに、「これからの時代に必要な能力」みたいなものってめっちゃ抽象的でありふれてることが多いと納得してしまった。
考えてみると、プログラミング教育みたいなものも、プログラマーである自分からしてみてもなんでやってるのかよく分からないので、本で説明されている、再帰性の現れなのかもしれないと思った。
近代という時間軸で説明が丁寧になされており、自分でも普段目にする、「新しい」何かや、世の中の自己啓発圧の起源がよく分かった。面白かった。
Posted by ブクログ
構造は非常にわかりやすく、①能力を厳密に測定することは難しい、②身分が属性によって規定されない、オープンな社会では何らか能力により身分の配分をせねばならず、社会的要請として暫定的な能力の尺度を決めねばならない、③上記により、測定される能力には常に反省すべき点が必ず含まれる(メリトクラシーの再帰性)、④情報化社会の中で相対比較を壮大にできるようになったことで、自分の身分を決める能力の尺度の不正確性や相対の可視化により、能力不安に陥る、⑤これらが、より平等で能力を重視する社会では増幅していく。この構造はその通りだが、人権を根本原理とする、現代的な平等社会においては、正確だから決められない、では機能せず、社会的にキメの部分が必要なはずで、それが常に反省的に新しい能力を求める流れになったとして、新しくないからそれが問題、とは思えない。新しいことに価値があるわけではなく、社会や人がそれによって学習され、成果を出せるか、が重要であり、文脈依存性が高いとはいえ、基礎的なコンピテンシーの尺度は必要だと思う。
Posted by ブクログ
<目次>
まえがき
第1章 現代は「新しい能力」が求められる時代か?
第2章 能力を測る~未完のプロジェクト
第3章 能力は社会が定義する~能力の社会学・再考
第4章 能力は問われ続ける~メリトクラシーの再帰性
第5章 能力をめぐる社会の変容
第6章 結論:現代の能力論と向き合うために
<内容>
著者は、「新しい学力観」には与していない。というか、「新しい学力観」は「新しくない」ことを証明している。また、「コミュニケーション能力」や「協調性」が公平に測れるはずがないともいう。それは基準を決めるのが、社会だからだという。
ここまではついてこれた。しかし、第4章は全く分からなかった。もう少しうまく説明してほしかった。