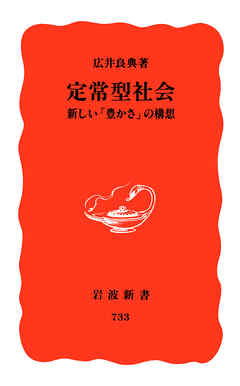あらすじ
経済不況に加え、将来不安から閉塞感をぬぐえない日本社会。理念と政策全般にわたる全体的構想の手掛かりは何か。進行する少子高齢化のなかで、社会保障改革はどうあるべきか。資源・環境制約を見据えて、持続可能な福祉社会のあり方を論じながら、「成長」にかわる価値の追求から展望される可能性を提示する、問題提起の書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
内容:
「(経済)成長」・「物質的な富の拡大」という目標が機能しなくなった現代において、「定常型社会」という新しいコンセプトを提示する
MEMO:
・定常型社会
① マテリアルな(物質・エネルギーの)消費が一定となる社会
② (経済の)量的拡大を基本的な価値・目的としない社会
③ <変化しないもの>に価値をおける社会
・情報の消費から、時間の消費。
・ひいては、経済とは離れて、時間自体を楽しむこと。
・福祉政策が需要の増加(経済の拡大)に寄与する点をあらためて認識できて面白かった;
Posted by ブクログ
今年、パラダイムの転換を予感させる、「ポスト資本主義」という本を出した著者の、2001年の著作。同じ岩波新書から出ている。
十数年前の本作でも、成長一辺倒で突き進んできた「資本主義」が、人口動態からの需要の限界や、地球環境の限界から、成長が頭打ちしており、今後「定常化」せざるを得ないという主張がなされ、最近作と同じものであった。以前より、分かる人には分かっているものであり、現実や社会の大勢の感覚が、ようやく追い付いてきたのだと思う。
最近作では、拡大・成長と、成熟・定常を繰り返す歴史のサイクルを受けて、この次にくるのが、定常ではなく、技術的特異点(シンギュラリティ)が来るといった議論も紹介している。いわゆる、ポスト・ヒューマン的な断絶が来る想定で、著者は否定しているのだが、さすがにこちらにはまだその手の議論はなかった。
最近作になかった点で、参考になった点としては、「機会の平等と潜在的自由」の議論があった。
公平にするということは、一方で自由の侵害であるとし、公平や平等と自由を対立するものとする考えがある。しかし、機会の平等が保証されていなければ、それは個人の(潜在的な)自由の浸食を意味し、実は、自由と平等は重なり合う概念であると指摘している。こうした認識に基づいて、社会保障制度の見直しなどが必要であると指摘していた。
今後も、もちろん科学・技術的な発展もあるだろうし、当然、そうしたものから得られる豊かさも期待できる。しかし、現代が向き合っているのは、成長か定常かといったレベルを超えて、社会制度を成り立たせるわたしたちの価値観や認識の変革であると感じた。
Posted by ブクログ
問題意識を持つ大切さを思い出させてくれた書。
このまま「成長」信仰でいいのか?より根源的な豊かさがあるのではないか?理想論でなく、時代の趨勢として、そのような問いに答えていく針路が見えた。
・介護に加えて、相続の社会化。
・障害者福祉も、事後的な保障ではなく、機会の平等のための支援策と考える。
・人件費を高くし、エネルギー費用を低く抑えるため、自然資源を使いすぎ、人間の労働力を十分使わないのが、現在の税制や社会保険料。
・地域が再び前面に出ている。1.高齢化=生産人口の減少:高齢者と子どもは土着性が高い。2.雇用の流動化と形態の変化。3.情報化
・エコマネー=地域通貨。交換・決済機能は持つが金融=信用創造機能は持たない。
・21世紀後半に向けて、世界は高齢化が高度に進み、人口や資源消費も均衡化するような、ある定常点に向かいつつあるし、そうでなければ持続可能ではない。
・経済成長はナショナリズムと関連。
・1.共同体からの離陸。2.土地などの自然的制約からの離陸。3.物質からの離陸=情報消費 =>拡大・成長の歴史(200~300年)
・生物として生きていくのに必要な量の40倍ものエネルギーを人間は消費。かつてより40倍も時間が早い。
・ケアという営みにおいて本質的な意味を持つものは「時間」という要素。遊び、自己実現も。
・成長が目標であり限り、都市に求心力が働き、地方分権は進まない。
Posted by ブクログ
「個人」が「共同体」から、次いで「自然」から離陸していく構図を社会保障(福祉)、環境の面から鮮やかに描き出したこの書の特徴は、当然並立するはずの経済/市場という概念(「私利の追求」等含む)を真っ向からとらえ、しっかりと組み込んだところにあるように思う(個人的に第4章冒頭の簡単な経済史概観は、経済関連を学びたい者としてとても嬉しかった)。
本書の構成の内、政策提言など現実的な打開策もその主要な柱となってはいるが、その根底にはこれからの社会が「どうあるべきか」というより「どうなっていくのか」という分析がある(その境界は非常に曖昧で、また連続的なものではあるが)。この分析が非常な説得力を持って、政策提言にかなりの威力を与えている(ex.「物質、エネルギー」→「情報」→「時間」)。
筆者は、氏が本書を通して一貫として主張してきた「定常型社会」のコンセプトを巧く描き出せたようである。「定常型社会」と聞くともしかしたら感じてしまうようなネガティヴなイメージは実際に本書を読んでいただければ払拭されるように思う。理想を求めつつも、しっかりと現実を見据えた本当の良書だ。
拙いレビューじゃとてもその良さが伝わらないと思うので、少しでも気になる人は実際に読んでみてください。
(2006年04月02日)
Posted by ブクログ
「ゼロ成長」やら「環境制約」など、一見するとネガティブな印象を受けてしまいそうな言葉にポジティブな意味を持たせてくれる本。難しそうなタイトルの割には、非常に分かりやすい(一部、非常に分かりにくい部分もあるけれど)。様々な概念の対比や、類似点などを挙げたりして、社会保障から環境問題から、「トータルな社会論」が展開されてます。広井先生の十八番の思想が充分に出ているのではないかと思います。広井先生、すごすぎます。
Posted by ブクログ
以前から広井良典氏の著作には関心があり、初めて読んだのがこの一冊。
「持続可能な福祉社会=定常型社会」という概念を軸に据えながら、社会保障、環境、コミュニティなどについても述べてある。
話がかなりいろんな方向に波及しており、論の根拠があまり示されていないような箇所もあったが、非常にわかりやすく、構想自体もとても魅力的なものであった。
「学びの流動化」「時間の消費」といった、これから学んでいくうえでも重要な概念を得ることができた。哲学的な内容にもっと踏み込んだ彼の著作もぜひ読んでみたい。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
経済不況に加え、将来不安から閉塞感をぬぐえない日本社会。
理念と政策全般にわたる全体的構想の手掛かりは何か。
進行する少子高齢化のなかで、社会保障改革はどうあるべきか。
資源・環境制約を見据えて、持続可能な福祉社会のあり方を論じながら、「成長」にかわる価値の追求から展望される可能性を提示する、問題提起の書。
[ 目次 ]
第1章 現代の社会をどうとらえるか―環境・福祉・経済(基本的枠組み 二つの対立軸―富の成長と分配)
第2章 個人の生活保障はどうあるべきか―ライフサイクルと社会保障(「インフォーマルな社会保障」とその解体 これからの社会保障)
第3章 福祉の充実は環境と両立するか―個人の自由と環境政策(機会の平等と潜在的自由 社会保障と環境政策の統合)
第4章 新たな「豊かさ」のかたちを求めて―持続可能な福祉国家/福祉社会(「成長」という価値―経済システムの進化 定常型社会―時間観の転換 新しいコミュニティ―定常型社会における個人と公共性)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
『コミュニティを問い直す』で著者に興味を持ってこれも読もうと思い立った。
環境負荷を考えると、マテリアルな消費が持続可能な範囲で行われる必要があり、人口に着目すると、人口が一定になる必要がある。これはどちらも『定常化社会』というコンセプトに結びつく。
というのが本書のメインテーマ。『持続可能な未来へ』が工業化社会をバブルと言っていたけど、人口爆発も間違いなくバブルで、永遠につづくのは不可能だから、たしかにこのコンセプトは大事になってくると思う。
いくつか本書の中で出てきて印象に残ったのをメモ書き程度に↓
「ケインズ政策」
日本では公共工事のイメージが強いが、ヨーロッパに於いては福祉国家と強く結びついていた。そして両方共成長に価値を見出していた。日本ではパイを増やすということにのみ力点を置いていたのに対し、ある程度成長してしまっていたヨーロッパでは、再配分を行うことにより、低収入層に収入を分配し、そのことを通じて全体の消費を活性化することで成長を目指した。
『定常型社会』の定義
1.物質・エネルギーの消費が再生可能な範囲内
2.量的拡大を基本的価値としない
3.変化しないものにも価値をおく
バブル型社会から定常型社会へ移行する必要性
1.環境・資源による制約
2.基本的需要の有限性
Posted by ブクログ
成長社会から脱皮して、定常型社会への変革を説いた本。
現状の日本はほぼ成長率がほぼゼロで、定常社会になっているので、本書のような内容が実現すれば、多くの問題が解決する。
しかし、現状の利権構造を考えれば無理だろう。
Posted by ブクログ
大学院の課題に取り組むために読みました。
発行されてから随分と年月が経っている本ですが、現在のSDGsの考え方と結びつけて考察することができる書籍と思います。
Posted by ブクログ
★本書のメッセージ
「成長」に代わり「定常」であることを新しい豊かさとよう
★読んだきっかけ
戸田氏の『働く理由』に引用されていたため。今後の社会において、どういった働き方をしたいのか考えたく、読んでみた。2001年に書かれた内容であるが、現在にも十分通ずる内容。そう思うと、今の政府の在り方・価値観は全く転換するに至ってないのだと分かる
★本の概要・感想
人口が減少し、GDPも伸びていかない社会で、どのような国・政策の在り方がよいかを考える。社会保障や政策の知識が無いとスムーズに理解するのは難しい。
ムリに成長を志しても苦しいだけだろうなぁ。
★本の面白かった点、学びになった点
*「成長」という概念の位置づけ自体が、実は経済学の理論パラダイムの中では必ずしも重要視されていなかった、ということ
・経済成長に価値があるとされたのは、失業問題との関連である
・実物経済で需給が均衡しても労働市場が均衡するとは限らず、そのため政府が追加投資を行って実物経済を高い水準に引き上げる必要があった
→労働市場が改善されていないのであれば、経済成長には本来の意義はかなり弱まる
*定常型社会とは変化のない、退屈な社会ということではない
・量的な変化は志向しないが、質の変化は継続しておこるものとなっている
*もともとヨーロッパにおいては、大きな政府を志向する社民系も、小さな政府を志向する保守系も「経済成長を志向する」という観点では共通に意識していたこと
・経済成長をより効率的に達成する手段として、自由放任なのか、ケインズ的積極的財政政策を取るのか、といった違いなのである
*不断の経済成長は「人間の需要は制限なく拡大する」ことを前提に考えられていたため、現在はその仮定にムリが出てきている
*本質的な現代の先進国の課題3つ
・外的な課題ー資源が有限であること
・内的な課題ー人間の欲望、消費需要が無限に拡大しないこと
・分配の課題ー富の総量を増やしても、きちんと、貧富の差が埋まるようには分配されないこと
*定常型社会の3つの意味とその条件/根拠
・第一の意味「マテリアルな消費が一定となる社会」
→脱物質化← 情報化や「環境効率性」の追及を通じて
・第二の意味「経済の量的拡大を基本的な価値ないし目標としない社会」
(=脱量的拡大)←「時間の消費」を通じて
・第三の意味「<変化しないもの>にも価値を置くことができる社会」
←「根源的な時間の発見」を通じて、行われるものとなっている
●本のイマイチな点、気になった点
・そんなに簡単な本ではない。社会保証やサステナビリティ、マクロ経済学の知見がベースに無いと理解できない
→勉強し直して、また今度よもう
●学んだことをどうアクションに生かすか
・社会保障の政策についてもう一度考えたいと思った際、もう一回読みたい
・やっぱり、いまだに物質的な成長、量的成長だけをひたすらに志向するのはナンセンスっすよね
Posted by ブクログ
…本章でこれまで述べてきたような方向(基礎年金及び高齢者医療・介護の財源を税にし、またライフサイクルの区分に応じて税と保険の役割を整理する)をとる場合、全体として、社会保障給付費の財源のうち「税」の占める割合が相対的に多くなることになる。このようなことから、特に社会保障のための「税」財源をどこに求めるかが大きな課題として浮上することになる。 結論から述べると、筆者自身は、今後の社会保障財源(のうち税の部分)については、「消費税→相続税→環境税」がその有力な財源となるものと考えている(p63)。
ところで、先ほどふれたような背景(企業にとっての社会保障の負担の重さと失業問題など)だけでは、社会保障財源として「なぜ(他でもなく)環境税なのか」という、積極的かつ十分な理由づけが与えられているとは言えない。これについては、次のような点がその根拠として考えられるだろう。
まず挙げられるのは、特に医療ないし健康問題との関連であり、環境に負荷を与えている企業は、何らかのかたちで人々の健康状態やQOL(生活の質)を損なっていると言えるから(したがって医療や福祉に関する社会保障コストを高めていると考えられるから)、いわば加害者負担の原則のルールとして社会保障の財源を負担するべきだというものである。
さらに、より実質的でかつ広範な視野に立つ論拠としては、次に述べるような「労働に対する課税から資源・環境への課税のシフト」という視点が重要ではないかと考えられる。(中略)言い換えれば、現在の税体系では企業がエネルギーや資源生産性(資源効率性)を上げることよりも、労働生産性を上げることに注力するのは無理のないことであり、したがって、こうした税・社会保険料体系を「労働への課税からエネルギー・資源への課税」へと転換していくことで、企業行動を「労働生産性から資源効率性重視」へという方向に誘導・転換させてゆく効果をもつことが論じられている(p97-98)。
ここで、本書の後の議論とも関わる本質的な議論として、次のことを明らかにしておきたい。それは、「自由」ということを「潜在的自由」という意味で理解するならば、「機会の平等」の保障とはすなわち「(潜在的な)自由」の保障ということと同じである、という点である。(中略)
さらに、こうした発想で「自由」と「平等」の意味をとらえなおしていくと、その必然的な帰結として、「社会保障とは、(個人の)自由の実現のためにある制度である」という、新しい認識が生まれることになる(通常、社会保障は「平等」のための制度と考えられているが)。つまり、前章から述べているように、これからの社会保障は「個人の機会の平等」(の保障)ということを基本理念として再編されるべきであるが、そこでの「機会の平等」とは今論じているように「潜在的な自由」ということと重なり合っている。したがって、社会保障というシステムは、様々な個人がその「潜在的な自由」を実現できることを保障する制度に他ならないし、またそうあるべきではなかろうか(p78-79)。
以上の点を踏まえた上で、ここで先にふれた「定常化社会における個人と公共性」という問題について考えてみよう。(中略)
すなわち第一に、人々の基礎的なニードに対応する、いわばベーシックなサービスないし保障については、あくまで「公的」な財政の枠組みで対応する。このうち、?ミニマムな生活保障に関わる部分(言い換えれば所得再配分的な施策。具体的には生活保護など)についてはもっとも公的ないし措置的な性格を強く残し、一方、?普遍的な「対人社会サービス」の領域(たとえば医療、介護、保育など)については、いわゆる「擬似市場」の仕組み、つまり「財政面は公的に保障しつつ、サービスの供給主体は営利・非営利を通じた民間の主体の積極的導入を図る」かたちが妥当であろう(p166-169)。
論点はたくさんあると思いますが、ここでは一点だけ。
社会保障の一つとして<公教育>を考えた場合、上に挙げた引用文の「対人社会サービス」に該当するのでしょうか?<公教育>が医療や介護と決定的に違うのは、将来の職業配分との問題に関わってくるということです。その意味では<公教育>は「人々の基礎的なニードに対応する、いわばベーシックなサービス」に属するのはないかと僕は思います。
そのために<公教育>はどのようなサービスを提供すべきなのか。これから考えていきたいと思います。