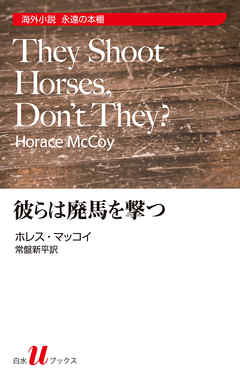あらすじ
1930年代、大恐慌時代のアメリカ。映画監督になる夢を抱いて青年はハリウッドにやってきた。しかし現実は厳しく、エキストラの仕事にもあぶれ、ドラッグストアのバイトで小銭を稼ぐのが精いっぱい。その彼が出会ったのが、テキサスからきた女優志望の女の子。2人はペアを組んでマラソン・ダンス大会に参加することに。これは1時間50分踊って10分間の休憩を繰り返し、最後の1組が残るまでひたすら踊り続ける過酷な競技だ。大会を渡り歩くこの競技のプロに、逃亡中の犯罪者、家出娘など“わけあり”の参加者も。経過時間が800時間を越え、残りが20組に絞られたとき……。競技中に発生する様々な人間ドラマ、若者たちの希望と絶望を巧みな構成で描いたアメリカ小説の傑作。シドニー・ポラック監督、ジェーン・フォンダ主演の映画化《ひとりぼっちの青春》でも知られる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
1935年に書かれ、1970年と1988年に出版されてはいずれも廃版となっては、三度の光を浴びて復刊したのが本書である。しかしこれもまた再版とはならず現在は廃版の状態である。「廃版」とタイトルにある「廃馬」に重なるイメージがあるのだが、本も馬も人もいつかは廃棄される運命にあり、撃たれる運命にあるのかもしれない。
先日読んだばかりの『屍衣にポケットはない』で独特な感性とタフでぶれない軸を持った作家ホレス・マッコイの名を知り、二つの世界大戦の合間に展開するアメリカという社会の、大戦間ならではの独特な歪みをさらに検証することができるのが本書であると言っていいだろう。
『屍衣にポケットはない』では、街を牛耳る悪玉金持ちに新聞という名の報道まで持ってかれようという権力悪に、ただの一匹で立ち向かう男を主軸に据え、彼を支える一筋縄ではゆかない男女のアシスト役も目立っていた孤立チームの奮闘ぶりが何とも言えない魅力に満ちていた。本書はその二年前に出版された、中編というほどの短い物語であり、180ページに満たない物語だが、衝撃度はこちらの方が強いかもしれない。
戦争で儲かる一握りの権力者に対し、戦争で疲弊する社会の悲惨を強く感じ取ることができる本作は、『屍衣にポケットはない』と同様、一握りの金持ち対大勢の貧者という図式があり、そこにたくましく生きようともがく青春群像がはかなくも作品として燃え立っている。
本書で描かれる二人の男女は、さして深い知り合いでもないが、映画のエキストラをお払い箱になり、千ドルの賞金がかかったマラソン・ダンス大会に出場する。一時間五十分踊って十分間の休憩を取るという無期限のダンス競技に勝てば千ドルの賞金を手にすることができる、というほとんど狂気と言っていいような酔狂な金持ち主催の過酷なイベントなのである。
日々の休みなきダンス・レースの中で一日一日と多くの男女が脱落してゆく姿をマスコミが食いつき、見物客も絶えない。金持ちのスポンサーがそれぞれのカップルにつくこともあるらしく、一体この狂騒のダンス大会は何なのだろうと首を傾げているうちに、作品のなかの日々は少しずつだが過ぎてゆく。
ラストの衝撃がちと応えるのだが、そこで改めて本書の風変わりなタイトルのイメージが銃弾のように読者の感性を抉る。本作は1969年代に『ひとりぼっちの青春』という邦題で映画化されている。マイケル・サラザンとジェーン・フォンダ主演のこの英画を当時の映画誌『スクリーン』で知った覚えがあるが映画自体は記憶にない。
本書は最初から最後までカルチャー・ショックである。馬鹿げたマラソン・ダンス大会を道楽で開催する金持ち
たちと、そこに参加するしか生活の寄る辺さえ稼げない貧しい男女たち。おまけに本書の主人公たちは知人ですらなく、ただこの大会のために出合頭的にペアを組んだ二人である。だからこそ衝撃のラストが切なすぎる。
時代を投影する作品として『屍衣にポケットはない』とどちらも強烈な印象を残すのがこの時代の作家ホレス・マッコイ。職業小説家とは言え、小説だけで食べてゆけるほどの売れ行きにも恵まれなかったこの作家の才能は、時代を超えて、今のぼくらの手の届くところで生き続けている。食べてゆくだけでも大変なこの時代と、それに負けぬエネルギーを秘めた若い男女とその生き様、滅びの美学、すべてのノワールの要素を凝縮したような震撼の一作と言えよう。
Posted by ブクログ
映画『ひとりぼっちの青春』の原作。1935年にアメリカの作家ホレス・マッコイによって書かれた、マラソン・ダンス大会を題材にした小説。
マラソン・ダンス大会とは、最後まで踊っていた男女ペアが優勝する、ダンスの耐久コンテストのこと。1時間50分踊っては10分間の休憩の繰り返しで、その10分間に睡眠や食事、風呂に入ったりと必要なことを済ませるという、なんともクレイジーなコンテスト。小説はフィクションでも、こんな狂騒的な催しが実際に行われていたのは驚きでした。
あらすじ:
ときは、大恐慌後の不況下のアメリカ。映画監督を目指すロバートが、エキストラで生計を立てる女優志望のグロリアと街で偶然出会います。お金に窮する二人は、食事も寝場所も得られるマラソン・ダンス大会に参加し、あわよくば映画関係の人達のお眼鏡にかなったり、賞金も得られることを期待します。はたして、大会での連日繰り広げられる過酷なダンスは、ロバートとグロリアに何をもたらし、そしてその行く末は……。
“被告は起立しなさい”との裁判長の発言から始まる本作は、裁判の過程で言い渡される判決の合間に、主人公がグロリアを撃ち殺すに至った過程が語られていきます。その判決文がページ一枚を占めており、章の間に収まっていますが、その判決文が読み進めるほど文字フォントが大きくなり、主人公の語るグロリアの様子の変化とともに物語が終局に向かっていく構成になっています(故に、紙の本で読む醍醐味が味わえます)。
主人公がグロリアを殺害することは決定事項として始まるので、最後まで読んで最初に戻ると、序盤のグロリアの様子がよくわかるという演出は見事です。ただし、硬質で乾いた文章は、あまり心理描写がないのでグロリアの本当の心の内は想像するしかないけどね。そして、最後の一文ですが、どうにもならなかった救いのない悲哀を感じさせる、切ない終わり方でした。仄暗い生い立ち、なかなか叶わない夢や貧しい暮らし、不況下に喘ぐ社会などの逃げ場のない男女を、同じく踊り続けなければならず、逃げたら失格になるマラソン・ダンス大会を引き合いに出す暗喩が印象的な作品でした。