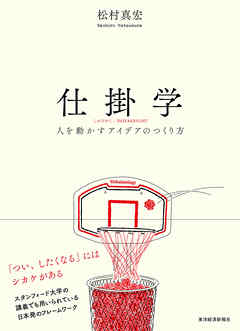あらすじ
「ついしたくなる」にはシカケがある。
スタンフォード大学の講義でも用いられている、日本発のフレームワーク、仕掛学【Shikakeology】。
押してダメなら引いてみな。一言で言うとこれが仕掛けの極意です。
人に動いてほしいときは無理やり動かそうとするのではなく、
自ら進んで動きたくなるような仕掛けをつくればよいのです。
ただ、言うは易し行うは難し。そのような仕掛けのつくり方はこれまで誰も考えてきませんでした。
本書では仕掛けの事例を分析し、体系化。
「ついしたくなる」仕掛けのアイデアのつくり方についてご紹介します。
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
「仕掛け」という言葉は罠とか悪いイメージが強く、最初手に取るか迷った。読んでいくと仕掛けは良いようにも悪いようにも使える物になっていると知り、すっきりした。
今後、自分がやりたいこととして、老若男女問わず健康的に動くようになるための仕掛けを作っていきたい。
場所によっても環境は全然違うためアイデアを出すだけでも大変だが、1つ成功したらもっとハマっていくだろうな。
もう少しアクティブな内容に関する事例が欲しかったので星4つにした。内容は読みやすく、頭に入りやすい!
Posted by ブクログ
仕掛けとは
・誰も嫌な目に合わないもの
・「〜したい」もしくは「〜したくない」気持ちにさせるもの
・仕掛けられた人と仕掛けた人の目的が違うもの
例
トイレの的、串をポイ捨てさせないための投票箱
Posted by ブクログ
仕掛学―人を動かすアイデアのつくり方 単行本 – 2016/9/22
なるだけ金をかけずに創意工夫する点は改善に通じる
2017年3月11日記述
松村 真宏氏による著作。
1975年大阪生まれ。大阪大学基礎工学部卒業。
東京大学大学院工学系研究科修了。博士(工学)。
現在、大阪大学大学院経済学研究科准教授。
2004年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校客員研究員、
2012〜2013年スタンフォード大学客員研究員。
研究テーマは「仕掛学」や「ソーシャルメディアの影響力」など。
データの分析から仕掛けの実装まで幅広く取り組んでいる。
趣味は娘たちと遊ぶこと(遊んでもらうこと)
本書は松村氏がこれまで研究してきたことを平易にまとめた本だ。
予備知識は必要ない。
ページ数はそれほどなく読みやすく書かれている。
読み進めて感じたのは企業の改善活動に似た要素を持っているように思える。
P160で紹介しているような技術や開発にこだわるのではなくロシアは鉛筆を使ったというようなアプローチ。
なるだけ金をかけずに創意工夫する点は改善に通じる。
コロンブスの卵的な発想の転換も改善、仕掛け作りに必要な考え方だ。
本書を通じて世の中に溢れる仕掛けに気付くようになり
自分自身の発想を鍛えるのに役立ちそう。
仕掛けは特に子供の観察によって見つかることが多い。
スマホで写真を撮っている人を観察するとその先に仕掛けがあることも多い。
表紙になっているゴミ箱にバスケットゴールを設置して思わず投げ入れたくなる仕掛け。
行動を誘導するものばかりではある。
しかし仕掛けによって知らず知らずの間に目的が達成されるのが重要点だ。
本書内で紹介された仕掛けで印象に残ったものを紹介したい。
ファイルや書籍の整理に斜めの線を引く(例・ドラゴンボール)
男性用小トイレに的をつける
コインスライダーのついた募金箱
小さな鳥居(ゴミのポイ捨て防止)
世界一深いゴミ箱(落下音が面白い)
ホームベーカリー(パンの焼き立ての臭いで目覚める)
駐輪場の線(自転車等を揃えて止める)