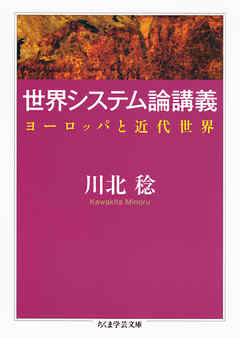あらすじ
“近代世界を一つの巨大な生き物のように考え、近代の世界史をそうした有機体の展開過程としてとらえる見方”、それが「世界システム論」にほかならない。この見方によって、現代世界がどのような構造をもって成立したかが浮き彫りとなる。すなわち、大航海時代から始まるヨーロッパの中核性、南北問題、ヘゲモニー国家の変遷など、近代のさまざまな特徴は、世界システム内の相互影響を分析することで、はじめてその実相を露わにするのだ。同時にそれは、歴史を「国」単位で見ることからわれわれを解放する。第一人者が豊富なトピックとともに説く、知的興趣あふれる講義。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
近代世界システムとは、16世紀以降の歴史を世界的な構造として捉えようとする概念。資本主義の本質を歴史的に捉えることもできたので、読んでよかった。
近代世界システムとは、世界的な分業体制をとることで、それぞれの生産物を大規模に交換する体制のこと。 16世紀の東ヨーロッパでは、西ヨーロッパへの穀物輸出が激増したため、農奴の労働が強化された。今日の南北問題は、北の国々が工業化、開発される過程において、南の国々がその食糧・原材料生産地として「開発」された結果、生じた。
12世紀から13世紀にかけての北西ヨーロッパでは、人口が増加し、耕地の開発も進んだ。1150年頃を境として、西ヨーロッパでは多くの人々が、食糧のような基礎物質も交換によって入手するようになった。
火薬の普及によって戦術が変化すると、封建制度における騎士の存在が無意味になった。農民の抵抗を抑えきれなくなった領主層は、王権の支援に期待するようになり、絶対王政が西ヨーロッパ各国で見られるようになった。帝国は武力を独占し、武器の浸透や発展を阻止する傾向が強いが、国民国家の寄せ集めであったヨーロッパでは、各国が競って武器や経済の開発を進められた。その結果として、 16世紀にはヨーロッパと東アジアの間では、武力は圧倒的な差となった。
オランダは優秀な造船業を確立したことから、漁業と商業で圧倒的に有利になった。特に、バルト海貿易用に開発したフライト船は、少人数で大量の積荷を安価に運ぶことができたため、木材などを扱うバルト海貿易で圧勝した。このバルト海貿易は、東ヨーロッパと西ヨーロッパを結ぶ幹線貿易で、穀物や造船資材のほとんどを供給し、アムステルダムで取引された商品の4分の3を占めた。アムステルダムには世界中の資金が集まり、金利が最も低い金融の中心となった。
イギリスでは、1660年の王政復古から 1775年のアメリカ独立戦争前までの1世紀あまりの間に、それまでヨーロッパ諸国とトルコに限られていた貿易相手地域は、カリブ海、北アメリカの植民地を中心に、東インド会社の活躍したアジア、奴隷貿易の展開したアフリカに急展開し、貿易の規模が劇的に上昇した。それまでほとんど増えていなかった貿易量は、17世紀後半の半世紀で3倍に増え、18世紀の初めの60~70年間にも数倍に増えた。輸出品は、それまでのほとんど唯一のものであった毛織物のほか、金属製品や家具などの工業製品と植民地物産の再輸出が加わった。イギリス政府は税によって得た資金のほとんどを軍事費にあてた結果、対仏戦争に勝利し、大英帝国の形成に繋がった。イギリスは世界で最初の産業革命に成功したために大英帝国を作り上げたのではなく、帝国を作り上げたからこそ産業革命に成功した。前のヘゲモニー国家オランダの資金もイギリスに流れた。
砂糖プランテーションが行われたカリブ海には、まともな学校がなかったため、カリブ海の砂糖プランターたちは、その子弟をイギリスに送り込んだ。子弟はそのままイギリスに住み着き、プランテーションを引き継いでも不在化したままイギリスの政界に進出し、議会に強力な圧力をかけて、カリブ海植民地の砂糖を保護させた。これに対してアメリカ大陸のタバコ植民地では、プランテーションを現場監督に任せて不在化できるほどの金持ちにはなれなかったため、不在化しなかった。そのため、アメリカ大陸の13植民地が独立を宣言したとき、カリブ海の植民地は追随せず、20世紀まで植民地の立場を保った。不在化したプランターは、現地に道路も学校も公園も作ることはせず、上下水道のような生活基盤も整備しなかった。不在化が進行しなかった北アメリカ南部では、社会資本の整備はカリブ海よりもはるかに進行した。
イギリス近代史では、植民地を社会問題の処理場としてきた。失業者は植民地の労働力になるべきとみなされ、非行青少年や犯罪者、売春婦、反体制派、結婚相手の見つからない女性も植民地に活路を見いだすことを奨励された。植民地時代にアメリカに渡ったイギリス人の少なくとも3分の2は、期限付きの債務奴隷とも言える年季奉公人であった。 18世紀のイギリスでは、死刑の対象となる犯罪の種類が急増して死刑判決が頻発し、恩赦によって植民地へ流刑されて年季奉公人と同じ労働力として扱われた。
近代世界システムにおいては、低コスト労働の確保のために人種主義や性差別などが行われる。フランス革命の理念である平等の観念も、能力主義と結びつくことによって、差別や生産的労働からの排除と結びついた。ヨーロッパを中核とする近代世界システムが世界を覆った19世紀には、オーストラリアやカリフォルニアの金鉱への中国人クーリー、南アフリカの鉱山での黒人労働者、アジアの茶や綿花やゴムなどのプランテーションなどで、労働力の世界的な再配置が展開された。
近代世界システムにおける「周辺」の従属地域は、いったん支配的な中核との関係を断ち切らなければ、その立場から脱却はできない。鉄のカーテンを引いた旧ソ連や鎖国を行った日本は、その世界システム上の地位を高めたり、「半周辺」の地位にとどまることができた。アメリカ独立革命の意味は、イギリスからの投資、すなわち、低開発化の圧力を避けることにあった。
イギリスは、19世紀には自由貿易を前提とした軽い政府に移行したため、急速に工業化されたドイツとアメリカに敗れ、1873年以降の大不況の中でヘゲモニーを喪失していった。世界の工業製品輸出に占めるイギリスのシェアは、1870年代には45%前後だったが、世紀末には30%を下回るようになり、金融とサービス業で生きる国となった。
Posted by ブクログ
以前に同著者の学生向けのやはり名著『砂糖の世界史』を読んでいますので内容的には自分にとって新しくはありませんが、アメリカ史を学びつつ改めて読むと色々と繋がり腹落ちします。
アメリカの独立から南北戦争期の歴史って、まさにヨーロッパ(スペイン、イギリス、フランス)の「世界システム」の「中に組み込まれた」人たちとそれに対する「抵抗派」の確執であり、さらにヨーロッパの国同士の覇権争いがそこに絡んで来て、またそれを利用する力学あり、牽制する力学あり、の歴史なんですよね…
「アメリカ史を知ると世界システムの歴史が見える」と感じる次第です。
あ、話が若干逸れましたが、間違いなく一読の価値ある名著ですね。
Posted by ブクログ
世界の歴史を特定の国に注視するのではなく、世界を有機的に結びつけられたシステムとして考える本書。
ある地域で発生した事象をきっかけにそれが他の地域に影響を及ぼしていく様を追いかける。
まず、はじめの問いかけがなぜこの世界には現在に至るまで地域間の格差が生じているのか?という点から始まり、世界の中心がヨーロッパになったのはなぜなのかを深掘りしていく。
以下、個人的あらまし。
①15世紀くらいまではどこも似たり寄ったりの封建的国家であり、小領主が農民を武力で支配していた。
②技術の発展(火薬や武器)に伴い、農民の不満を小領主では抑えられなくなり、「国家」に頼るようになる。こうして国家が成立し始める。
③度重なる戦争や黒死病により人口激減したヨーロッパでは従来の封建国家では成り立たなくなってくる。よって新たな収入源を求めて海外へ飛び出す
ちなみにこのときの中国は欧州と同等か進んでいたが、単一国家であったために、他国との競争にさらされず、武力の増強、外への進出が遅れた。
④まずいち早く動いたのはイスラムから領土を回復し、海に面していたスペイン・ポルトガルであった。これらの国々はラテンアメリカを蹂躙し、アジアに進出した。
また、進出先で生産品を作るためにアフリカから奴隷を「輸入」した。
⑤南欧国家に続いて、イギリス、フランス、オランダも海外貿易に参入したが、やがて世界で新たに開拓できる地域が無くなり、発展が進みにくくなる。
⑥その中で頭角を表してきたのが、漁業と林業といった「生産力」に秀でたオランダであった。オランダはその優れた生産競争力を発揮し、覇権を握るようになる
⑦しかし覇権国家では賃金上昇により競争力は低下する。その隙を突いたのがイギリスであり、海外貿易により収益を伸ばしていく。
特に紅茶と砂糖の生産は著しく、これらの輸入を機にコーヒーハウスが作られ、情報集積の中心となっていく。
⑧やがてイギリスの競争力が上がり都市化が進むに連れて、「産業革命」が、起こりイギリスの地位が安定的に覇権国家となる。
⑨しかし貿易の保護主義的側面に
Posted by ブクログ
各国を個別事象的に見て、ある国を「先進国」、またある国を「後進国」とラベリングするのは狭小な「単線的発展段階論」であると断じ、近代以降の世界は一つの巨大な生き物、有機体の展開過程の如く捉えるべきだとする論が主旋律。
封建制の崩壊と国民国家の成立に端を発し、その後スペインとポルトガルによってもたらされた大航海時代が近代世界システムの成立を告げ、やがてオランダ、イギリス、アメリカと、ヘゲモニー国家の覇権を巡って各国が「中核」の座を争った陰には、「周辺」として極度に低開発化された国々が。それはさながら「光」と「影」であり、この近代世界に影を落としてきたのは紛れもなく中核国そのものである。
この「世界システム」というスキームは、国際社会を見る視座を確実に一段高めてくれるものであり、また未来予測にも大変有益と感じる。
よく歴史は線で考えろというけれど、その一歩先、「複線」で考えるイメージかな。非常に勉強になったし、読み物としてシンプルに面白かったです。
Posted by ブクログ
超絶名著。近代ヨーロッパ史の流れがまるわかりできる。様々な断片的知識が繋がっていく爽快感はたまらない。
2017年1月6日追記
世界システム論について今一度考えてみると、中核―周縁関係の中で、垂直的関係があることが、南北問題が解決しない一つの理由として挙げられている。中核国家が産業の高度化を成し遂げたために、周縁国家は産業の低次化を強いられた。東方植民に見られるエルベ川以東の再版農奴制やインド植民地のモノカルチャー化はイギリスを筆頭とする西欧の産業化との関連性の中で考えられる。さて、そこで重要に思えるのは、低開発化された周縁では労働力のコストを下げるために、非/低賃金労働を強いられるということだ。いわゆる自給的労働は賃金の発生しにくい非/低賃金労働としてカウントされ、生産的労働に財が集まると考えられている。さて、WW2以前の世界では植民地における強制労働という形で、このような非/低賃金労働を賄ってきたが、植民地解放以降の世界では国内に低賃金労働者たる非正規雇用者を確保するために、雇用の非正規化が進む。サービス残業やブラック企業はシステムの存続に不可欠な非/低賃金労働の創出という歴史的側面で説明できる。そして、これが本題であるのだが、2016年12月に一世を風靡したドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」に隠されたメッセージは、世界システムの存続に必要な搾取の構造を、夫婦という解り易い関係に置き換えて世間に訴えていたのではないかと思う。最終回に近づくにつれて、主人公の平匡は解雇による年収の激減から、元々は賃金労働者として対価を払っていた妻の労働を結婚によって非賃金労働化することによってシステムの存続をしようと試みた。このシーンに象徴される含意は夫という中心がシステム維持の為に周縁を非賃金労働化するという世界システム論の中にある非対称な分業体制に由来するのではないか。
追記おわり。
Posted by ブクログ
ウォーラーステインに基づいた世界システム論の概説書。原本は放送大学の教科書なので、分量的制限からミニマムエッセンス的な記述となっており、取っつきやすい。大航海時代以後のヨーロッパ中心の近代世界を対象に、システム論的な見方で世界史を概括する。たとえば英国の産業革命ですら世界システムの影響から逃れ得なかったなど、示唆に富んでいる。近代世界の移民問題について知りたい場合にも重要な観点である。15世紀以前のヨーロッパ世界についてはアブールゴド「ヨーロッパ覇権以前」をひもといてみたい。
Posted by ブクログ
タイトル通り、ウォーラーステインによって主張された「世界システム論」についての概説書である。
随分前に書棚に収めていたが、先日、的場昭弘氏の『資本主義全史』を読んで、もしやと思って本書を手に取った。
直感は当たっていた。
「世界システム論」とは、西洋資本主義体制による国際的分業制のことを指していたのである。
世界システム論の目的は、各国史の積み上げを世界史とする旧来の史観を脱し、資本主義による国際的分業体制という観点を軸に近代以降の歴史を論じていくこと。つまり、一国史からの脱却だ。
この観点に基づくと、欧米各国が「進んで」いて、アフリカ等の諸国が「遅れている」という、それぞれの国が辿るべき進歩のルートを順番に辿っているのではなく、国際分業体制の中で欧米が「中心」となってしまったがゆえに、アジアやアフリカ等の地域が「周辺」となって同時代を進行してきた。ということになる。
なので、世界システム論に基づいて世界史を読み直そうとすると、どうしても資本主義が発生した西洋史を中心とした描写になる。
本書も大航海時代に始まるヨーロッパ近代の歴史の変転を、世界システム論の解釈を差しはさみながら進んでいく。
読み終わって、すぐに「世界システム論」はいつ頃提唱された議論だったかを確認した。
もう30年も前である。
今や世界史の潮流は「グローバルヒストリー」に移っているし、そのグローバルヒストリーですら例えばアジア史家からは西洋中心史観の誹りを免れず、今も様々な専門を背景に持った歴史家たちが「本当の意味での世界史」を追い求めているのが現状だろう。
そんな現状から何周かの周回遅れで本書を手に取ったわけだ。あまりに長いこと本棚の肥やしにしすぎたかな。
でも、著者自身がそれらの批判に末尾で抗弁している通り、現在の世界はどうあっても西洋資本主義のシステムを前提に構築されているのである。ゆえに、その切り口での歴史を学ぶことに意味はあると思う。
Posted by ブクログ
ウォーラスタインの世界システム論をベースに15世紀以降の世界史、資本主義史を読み解いていく。
どこまでがウォーラスタインの議論で、どこからが著者の見解なのか、境目がわかりにくい気がするが、一般の読者を対象とした入門なので、そのあたりまで知りたければ、専門書か、ウォーラスタイン本人の本を読めばいいということかな?
世界システム論を最初に知ったときには、すごく面白いと思ったのだけど、あまりにもマクロなアプローチで各論、具体論に入ると、だんだん怪しげになっていくところがあって、興味は薄れていった。
が、個別テーマの本をある程度読んだ今となると、もう一度、このマクロ的な議論がとても大事なものに思えてくる。
冷戦が終わって、同時にかつての植民地における東西両陣営による取り込み競争も終わって、30年以上経っているわけで、今の時点でもう一度システム論の観点から見ることはとても大切な気がする。
というわけで、これまで何度も読みかけて挫折したウォーラスタインの近代世界システム論を読むときがついに来たのかな?
この本は本当に大雑把な議論なのだが、全体観が俯瞰でき、準備運動はかなり進んだ気がする。
Posted by ブクログ
ウォーラステインが提唱した「世界システム論」という史観概念について解説されている。
世界システム論とは、歴史を国単位で捉えて、諸国が互いに不干渉な状況であるセパレートコース上での競争をおこなっているとする「単線的発展段階論」へのアンチテーゼとして生まれた。
つまり、勤勉国家が「先進国」、怠け者国家が「後進国」になっているとするのではなく、「中核国」が「周辺国」から収奪したために、「先進国」と「後進国」が生まれたというように、国単位ではなく、世界を一つの単位/構造体として捉え、構造体内の相互作用において全体の状況が作り出されているという考え方である。
近代初期においては、世界における西ヨーロッパの影響力は小さく、経済・文化・技術などあらゆる点において、アジア(特に中国)の方が進んでいた。
次第に、(火器などの暴力技術も含まれる)技術がアジアから到来し、一揆などに対応しかねた領主層が「国家」の存在を求めるようになり、封建制度から国家国民制度へと移行していった。
ここに、世界システムの萌芽が見られ、その後、西ヨーロッパ諸国は、大航海時代→植民地支配→工業化といった流れで世界システムを地球規模に拡大させ、常に新しい「周辺」を探し求める。
・世界システムは「中核」と「周辺」が存在し、周辺から搾取した富によって中核が充足されるという構造がベースとなっていること
・現代社会において、世界システムから逃れた地域は存在せず、新しい「周辺」の拡大が見込まれないこと
・搾取するシステムである「工業」の姿変化してきていること(IT/金融に重点が移動)
などを踏まえると、近代の世界システムから現代の世界システムへの更新を考えてみても良いではないだろうか。
<メモ>
・国家国民モデルが希求された背景として、ウォーラステインは「農奴統治のため」ゲルナーは「高文化教育普及のため」とそれぞれ違う観点で見ている
・ヘゲモニー国家の支配力の拡大/衰退の順序は、いずれも生産→商業→金融の順となる
・ヘゲモニー国家衰退の理由としては、生活水準の向上→生産における優位性低下となり、上記の衰退スパイラルに陥るため
・世界システムにおいて、「世界帝国」は存在せず「世界経済」のみ存在する。帝国モデルは支配体制としての効率が悪い
・ヘゲモニー国家において一番有利なのが「自由主義」。そのため、ヘゲモニー国家の首都は最もリベラルで芸術や亡命インテリの溜まり場となる
Posted by ブクログ
近代世界史がなぜヨーロッパを中心に展開していくことになったのか、それは世界は個別の主体(国家)による自由競争なのではなく総体として捉えるべきシステムであるから、という世界システム論で捉える本。元々は口頭の講義なのかとても読みやすいです。この書籍以降のアフリカ・中東の紛争と難民、欧米のナショナリズムの状況だったり、中国の台頭、あるいは気候変動問題なども地球規模の相互作用の中で捉えるという意味では今では当たり前の話ではありますね。それでもヘゲモニー国家の変遷と各国の文化の成立要因が連動しているところなんかはなるほど、と面白かった
Posted by ブクログ
感想
西洋の世界観の下に地球が一つのシステムにまとめ上げられる。ITCによって加速しているが、ローカルな動きも見られる現代。統一には限界があるか。
Posted by ブクログ
現在の世界がどのようにして一つの価値観に支配されてきたか、500年ほどの近代史をもとに解説されていた。
歴史をあまり勉強してこなかった自分にはわからない部分もあったけれど、ざっと500年間をまとめてくれていたので大きな流れを掴むことができた。
イギリスの甘い紅茶文化がなぜ形成されたのか?
インド経由のお茶と、三角貿易で得た砂糖が中核となるイギリスに集まったからということを知って、どんな文化にも歴史があるのだと感心した。
もちろん細かい部分でそれぞれの国の文化があるものの、ヨーロッパ的思想で統一化されている世界観と考えるのも面白かった。
Posted by ブクログ
世界の仕組みというか、現代社会を外観するために参考になる本。時々こういった本を読むと、ああ、そうだったという確認と、そいういう見方もあるのかという新たな視点を得られるのでとても良い。今回は近代ヨーロッパを中心に、経済システムの切り口で歴史を外観するもの。これまでの教科書や歴史解説書では、「国や王朝」単位で物事を捉えていることが多いが、この本は国境や〇〇家ではなく、モノ(農作物、工業製品、奴隷も)の流れで歴史を解説し、評価もしてくれている。この見方に立つと、大航海時代の世界の中心はインドや中国など東・東南アジア地域であり、この地域は域外との取引をしなくても十分豊かだった。従って、ヨーロッパ征服などということは起こらなかった。一方、次第に力をつけ始めた欧州では、ヘゲモニー国家が誕生し、農業、工業、金融の順で世界を支配しようとした。この動きが進展すると、周辺地域は搾取の対象となるので産業や民主主義などが育成されず、いまだに低発展国となっている、などなど。新しい見方をくれる一冊
Posted by ブクログ
川北稔(1940年~)氏は、イギリス近世・近代史を専門とする歴史学者。大阪大学名誉教授。
本書は、2001年に放送大学のテキストとして出版された『改訂版 ヨーロッパと近代世界』を改題・改訂し、2016年に出版されたもの。
「世界システム論」とは、米国の社会・歴史学者であるイマニュエル・ウォーラーステイン(1930~2019年)が、1970年代に提唱した巨視的歴史理論である。それは、各国を独立した単位として扱うのではなく、より広範な「世界」という視座から近代世界の歴史を考察するアプローチであり、複数の文化体(帝国、都市国家、民族など)を含む広大な領域に展開する分業体制により、「周辺」の経済的余剰を「中核」に移送するシステムを「世界システム」と呼んだ。その理論は、細部についての批判・反論はあるものの、世界を一体として把握する視座を打ち出した意義やその重要性については、現在も広く受け入れられている。
本書では、概ね以下のようなことが述べられている。
◆近代以前(12~13世紀)の地球には、4つほどの相互に独立した経済圏(=世界)が存在した(ビザンティン帝国~イタリア諸都市~北アフリカの地中海周辺、インド洋~ペルシャ湾岸、中国を中心とする東アジア、モンゴル~ロシアにかけての中央アジア)が、その一方で、のちに近代世界システムの「中核」となる北西ヨーロッパ(イギリス、ベネルクス、北フランス)はいずれの世界にも属しておらず、「周辺」の地位にあった。
◆14~15世紀、封建制の危機(その原因は様々な見解がある)に見舞われた北西ヨーロッパで、危機を脱する唯一の方法として、パイを大きくするために「大航海時代」が始まり、ヨーロッパが主導する近代世界システムの確立への動きが本格化した。当時の技術水準・生産力はアジアの方がヨーロッパより高かったとも言われるが、アジアは一つの経済圏として完結できるシステム(帝国)であったのに対し、ヨーロッパは小国家の寄せ集めで、政治的統合を欠いたシステムであったことから、各国が競って対外進出を図った。
◆「大航海時代」以降、キリスト教徒と香料を求めたポルトガルのアジア進出、スペインのアメリカ進出と世界帝国の形成、オランダによるヘゲモニー(覇権)国家の確立、イギリスのカリブ海・北アメリカにおける植民地の形成、アジアやアメリカからの商品(砂糖など)の流入によるヨーロッパの生活革命、黒人奴隷貿易の展開、イギリスの貧民の移民による北アメリカ植民地の形成、産業革命とフランス革命、ポテト飢饉によるアメリカへの移民の大流入、パクス・ブリタニカ、アメリカとドイツのヘゲモニー争いを背景とした世界大戦などを経て、ヨーロッパ・アメリカは他地域をそのシステムに組み込んでいった。
◆「近代世界システム」には、資本主義の根本原理ともいえる、飽くなき成長・拡大を追求する動機が内蔵されているが、そのシステムが地球のほぼ全域を覆い、新たな「周辺」が存在しなくなった今(帝国主義によるアフリカ分割や、ヘゲモニー争いとしての世界大戦などは、既にその始まりであったが)、過去500年の過程を踏まえて、これからの世界を考える必要がある。
本書が書かれてから更に20年が経過しているが、近年は「持続可能な開発」が国際的なキーワードとして定着しつつあり、明るい材料と言える。ただ、私は、(経済的な側面から見る限り)究極的には資本主義的な発想から脱却することができるかが、長期的にこの問題を解決する唯一のカギではないかと思うのだ。
著者が言う通り、過去を知ることは基本である。そして、残された時間が少ない今、我々に求められているのは、これからの世界をどのように方向付けていくのかを真剣に考えることである。
(2020年9月了)
Posted by ブクログ
最初はだるいが、半分過ぎて面白くなってきた。
産業革命は奴隷貿易の産物、
アメリカを作ったのは故国で食いつめた貧民と流刑者、
フランス革命は… と、
世界システムの目で見ると革命の神話は崩れ去る。
Posted by ブクログ
世界システム論講義
世界システム論について初めて読んだ本。
シヴィライゼーション界隈の人とかがたまにウォーラーステインとかの名前を出すので気になっていた。
放送大学のテキストだったらしい。
世界システム論は、世界史を個別の国単位の総合として捉えるのではなく、世界全体を1つのシステムとして捉える見方を言う。
16世紀に西欧で成立したため、「西欧システム論」と言い換えてもいいかもしれない。
世界システム論によれば、南北格差の問題は、中心国である帝国に1次産業供給地として周辺化されてしまい、その構造が固定化されてしまうことにある。(その国やその民族の特性に起因するのではない。)
面白かったポイント
・イギリスの産業革命は世界システムのうえにこそ成立したのであり、独立自尊なヨーマンの勤勉によって生じたわけではない
・ピルグリムファーザーズという神話。米国も豪州と同じく英国からの流刑民がほとんどだった。これが明らかになったのは歴史学にコンピュータによる統計が導入されてからだった。
・作る作物がサトウキビかタバコかで独立した後の発展に差が出る。サトウキビの農園主は本国にいるだけで、植民地へのインフラ投資はしない。タバコの場合、作物の性質上、現地で生活することが多いため、自分たちにインフラ投資をする。カリブにサトウキビプランテーションを展開したイングランドは発展し、東部アメリカにタバコを展開したスコットランドは低開発化された。
特にサトウキビの項目は薩摩と琉球、琉球と先島の関係に当てはめながら読んだ。
Posted by ブクログ
本書は、ヨーロッパ、特にイギリスを「中心」に、重要な史実を関連付けて、システム論という大括りにされた視座で解説がなされている。高校の世界史の授業で扱われたかすかな記憶が線で繋がったようだった。世界システム論の核となる「中核」と「周辺」の概念は、世界の大学の発達過程や、日本国内の大学間の関係を理解するときに活用できよう。例えば、中核となる大学はその機構を強化しつつ、周辺の大学は「大学間連携」の名のもとに当該大学を溶融させようとする効果が企図されている、というように仮定することは言い過ぎだろうか。また、著者は植民地が製品・商品の「生産地」であると同時に「社会問題の処理場」だった側面があるとしているが、これも国内の大学事情に無理やり当てはめると、思い当たる事象があるだろう。
Posted by ブクログ
イギリス近代史学者さんによる、近世からの世界の流れを少し広い目で捉えた本。ねらいは、現代社会がどう成立したのかを読み解くこと。
全体のボリュームは軽めで、各章ムチャクチャ駆け足で進んでいきますが、要点がまとまっていて明解です。世界史で習った「アレか!」的単語が登場したかと思うとサラッと去っていくようなシーンがしばしばあります。典礼問題とか。文章は平易なのですが、世界史習ってないとようわからんかも?
大して豊かでもなかったヨーロッパがなぜ覇権を握ることができたのか?今後世界で覇権を握っていくのはどこ(誰)か?などについて、歴史の流れを手繰りながらヒントを得ていく本です。
世界史は開拓の歴史で、新たな「周辺」を開拓してはそこから「中心」が資源を搾取してきた。よって、ある時期に低開発に甘んじていた地域は「中心」によってそうならざるを得ないような事情があった。とか、アメリカは紅茶を飲む文化圏の端っこにいるのではなく、新たにコーヒー文化圏を作ったという指摘はそうなのかなぁと思わされます。
基本は歴史書なので、今後の展望というところは軽め。世界の「余白」はほぼ埋められた中、現在もっとも有力なのは海洋開発か、また、IT技術による世界システムへの影響についても触れられたところで本編は終わっています。(全く別の本で、サイバー世界を新たな「余白」と捉えて金融システムが拡大したという論があったことをふと思い出しました)
参考図書に挙げられていたウォーラーステインも読もうかなぁと思わせてくれる良い本でした。
Posted by ブクログ
この世界はどのようにして成立したのか、その中でなぜヨーロッパが世界の中心となったのか、なぜその逆(アフリカや南米が先進国で欧米が発展途上国である世界)にならなかったのか、南北の差はなぜ生まれたのか、というのがこの本の議題で、議題自体は名著「銃・病原菌・鉄」と同様のものだと思います。ただ、「銃・病原菌・鉄」は人類の文明が始まる昔まで遡ってこの議題に挑んでいる一方で、この「世界システム論講義」は主に15世紀以降の世界の経済の動きに焦点を合わせている点が違うと感じました。250ページ程の文庫本なのに1,100円もして高かったけど、それに見合う内容だったと個人的には満足しました。この本を「銃・病原菌・鉄」みたいな感じで形容するとしたら、たぶん「船舶技術・奴隷・甘い紅茶」になるんじゃないかなと勝手に想像しています。箇条書きですが、個人的にこの本の中で面白いと感じた点をいくつか並べます。
・現在の南北問題は北の国が工業化すべく「開発」された過程において南の諸国がその原材料や食料生産地として「低開発」された結果生じたものである、本著では前者を世界システムの「中核国家」、後者を「周辺国家」と呼んでいる
・「中核」と「周辺」とが世界システムを構築している点は不変であるが、どの国が「中核」となるか「周辺」となるかは流動的である
(現在は「中核国家」の一員である日本が今後「周辺国家」になる事だってあり得る)
・オランダが当時開発した先鋭の船舶技術が、輸出物(悲しいかなこの中にはアフリカで調達された奴隷も含まれる)の輸送コストを抑えるばかりか、輸出物にかかる保険も安くした
・当時のイギリスの発展は、「英国人の禁欲と勤勉の賜物」なんかでは決してなく、不当な強制労働を強いられた奴隷制度なくして語られない
・英国から北米への移民の半数は、英国で職業不詳だった人たちだった
・甘い紅茶(紅茶に砂糖を入れて飲む英国の習慣)は当時の英国のステイタスシンボルであったし、短時間で効率的にカロリーとカフェインを摂る生活の術でもあったが、この紅茶と砂糖を英国人が手に入れるために奴隷は働き、人や物が船舶を介して移動し、船舶には保険が、物には関税が掛けられることで、英国が流通と経済の中枢となり得るシステムを構築した
・その後その中枢を英国が米国に明け渡す事になってしまった一因にミシンの開発が挙げられる、これは当時労働力が不足していた米国が衣服の縫製労働時間を節約するために開発したミシンが、労働力は特に不足していなかった英国に大量に輸出されて英国の労働者に取って代わった事で開発国としての主導権を米国に握られた
・英国は米国の発展を目の当たりにして今のやり方が時代遅れになっている事には気づいていただろうけど、一度完成した社会や技術体系を変革することは難しかった(これを本著では経路依存と呼んでいる)
・労働において、「平等」の観念が「能力主義」と結びつくとき、各種の新しい差別(性差別や高齢者・子供の労働機会からの排除)はとても簡単に生み出される
Posted by ブクログ
世界史の流れを、「国家」という単位ではなく、「世界」全体で見つめ直すべきだ、ということを様々な角度から講釈してくれている本。
この本が示そうとする事柄は、次の文に端的に表現されている、と思っています。
p26「近代の世界は1つのまとまったシステム(構造体)をなしているので、歴史は「国」を単位として動くのではない。すべての国の動向は、「一体としての世界」つまり世界システムの動きの一部でしかない。「イギリスは進んでいるが、インドは遅れている」などということはなく、世界の時計は一つである。現在のイギリスは、現在のインドと同じ時を共有している。両者の歴史は、セパレート・コースをたどってきたのではなく、単一のコースを押し合い、へし合いしながら進んできたのであり、いまもそうしているのである。いいかえると、「イギリスは、工業化されたが、インドはされなかった」のではなく、「イギリスが工業化したために、その影響を受けたインドは容易に工業化できなくなった」のである。
過去500年間にわたって、ヨーロッパからスタートした「近代世界システム」が、どのような流れで世界を飲み込んでいったのか、それぞれのポイントにおける解説がなされています。
Posted by ブクログ
先進国と途上国はそれぞれ別のルートで「進歩」しているのではなく、「世界」全体で一つの機能を成しているという立場に立って新大陸発見から冷戦までを描き直す
植民地政策や帝国主義、大英帝国の興亡などを新たに捉え直すことが出来て楽しかった
「イギリスは、工業化されたが、インドはされなかった」のではなく、「イギリスが工業化したために、その影響をうけたインドは、容易に工業化できなくなった」のである。
Posted by ブクログ
ちくま学芸文庫
川北稔 世界システム論講義
世界システム論の本
南北問題やヘゲモニー国家の変遷については 資本主義論と重複しているため、世界システム論の必要性が理解できなかったが
奴隷貿易や奴隷制プランテーションにより イギリス産業革命が起きたとする ウィリアムズテーゼの論証は わかりやすかった
「だれがアメリカをつくったのか」の論考に驚いた〜植民地時代にアメリカに渡ったイギリス人は、年季奉公人(期限付き白人債務奴隷)、死刑を逃れた犯罪者、失業者とのこと
「世界システム論〜近代世界を一つの巨大な生き物のように考え、近代の世界史を有機体の展開過程として捉える見方」
南北問題
*世界的な分業体制の中で、北の国が工業化して開発され、南の国が原料生産地として開発された
*中核〜世界的な分業体制から多くの余剰を吸収できる地域。西ヨーロッパ
*周辺〜食糧や原材料の生産に特化され、中核に従属させられる地域。東ヨーロッパ、ラテンアメリカ
ヘゲモニー国家の変遷が世界大戦へ
*近代世界システムが地球全域を覆い、新たな周辺を開拓する余地がなくなった
*アフリカ分割を契機に、世界が帝国主義とよばれる領土争奪戦に突入
*帝国主義とは、地球上の残された周辺化可能な地域をめぐる、中核諸国の争奪戦
世界システムは、その地域間分業の作用を通じて、西ヨーロッパ=中核では国家機構を強化しつつ、周辺国では国家を溶解させる効果をもった
ヨーロッパのシステムと中華システムの違い
*ヨーロッパのシステムは政治的統合性を欠いた経済システム〜国民国家の寄せ集めにすぎない
*ヨーロッパのシステムでは、各国は競って武器や経済の開発を進めた
*中華システムの中核は、一帯をひとまとめにして支配すふ帝国となっていた
ヘゲモニー国家
*中核地域のなかでも、圧倒的に強力の国
*17世紀のオランダ、19世紀のイギリス、第二次大戦後のアメリカ
*世界システムのヘゲモニーは、生産、商業、金融に及び、崩壊するのときも この順に崩壊する
*ヘゲモニーは長く続かない〜生活水準が上昇し、賃金が上がり、生産面での競争力が低下するため
*ヘゲモニー国家は、自由貿易を主張する
Posted by ブクログ
歴史学の分野でシステム論と呼ぶからには、当然、ニクラス・ルーマンのシステム論が根底にあるのだろう。ルーマンがひたすら抽象的な理論に徹したのに対し、これなどはその考え方を中世〜近代世界史に適用した、具体的な学説の例といったところか。
しかし本書ではじゅうぶんに「システム論」的なところが感じ取れず、世界史を「社会システムの自律的動向」として把握しきることは困難だった。
ところどころに面白い知見も見られるが、どういうわけかそうした個別の知が相互につながってくることがなく、単なる「雑学」のような、ばらばらの知識のように見えてしまった。なので、読んだときにはおもしろく思っても記憶に残らず、それは全体像のゲシュタルトに結びつかないからなのである。
本書が壮大な学術を語り尽くすには小ぶりに過ぎるということもあるだろう。個々の章はばらばらであり、「システム」の統一感が出てこなかった。
世界システムの中核としてのヨーロッパ文化と、中国などアジア文化等との関係など、示唆的なところはあったのだが・・・。