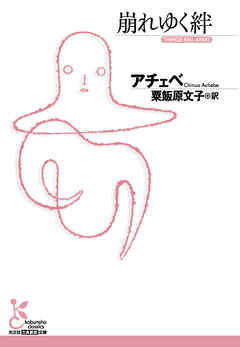あらすじ
古くからの呪術や習慣が根づく大地で、黙々と畑を耕し、獰猛に戦い、一代で名声と財産を築いた男オコンクウォ。しかし彼の誇りと、村の人々の生活を蝕み始めたのは、凶作でも戦争でもなく、新しい宗教の形で忍び寄る欧州の植民地支配だった。全世界で1000万部のベストセラー、アフリカ文学の父アチェベの記念碑的傑作待望の新訳!(『THINGS FALL APART』改題)
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
近代アフリカ文学の原点と称されるアチェべの名作小説。
舞台はヨーロッパ人によるアフリカの植民地化がはじまりつつあった19世紀後半の西アフリカ(現ナイジェリア)。
絶え間ない努力と武勇によって若くして富を築いたイボ人の男、オコンクウォを中心に物語は進む。
オコンクウォはレスリングのチャンピオンとして名をあげ、それからも堅固な意志と絶え間ない勤労により富を築いた。何人もの妻を抱え、村人からの信頼も厚い。
オコンクウォは自分だけではなく他人にも非常に厳しい性格で、頑迷な一面も持つ。揺るぎない自分の正義を持つが、それに従わないのであれば妻も子供も殴って言うことを聞かせるというかなりの男性主義思想の持ち主でもある。
オコンクウォを含む集落の人々は伝統を守り、アニミズムを信仰することで強固な絆を築き、平穏な日々を謳歌していた。
しかし、ある日オコンクウォは事故により集落を7年間追放されることとなる。
母の故郷で7年間の贖罪を務め、やっと集落に戻ってきたオコンクウォ。しかし、そこで見たのはヨーロッパからやってきたキリスト教に侵食され、人々の絆がバラバラになってしまった姿だった。
これが本書のあらすじ。
シンプルなストーリーだが、回想が急に挟まったり反復が多かったりして読みやすい本ではない。言語・文化面のギャップも当然大きいので、序盤は読み進めるのに時間が掛かった。
しかし、読み終えると非常に示唆的な内容だったと感じる。
本作が発表されたのは1958年、アフリカ諸国が長く続いたヨーロッパの支配から脱却して自立に向かって歩を進める、不安と期待に満ちた激動の時代。
そんな中、アチェべは敢えて植民地化前に存在していた複雑で成熟したイボ人の社会を描くことで独立前夜の同志たちを奮い立たせたと言える。
また、侵略が必ずしも真正面からの戦いによって行われるものではないというメッセージを発していると感じた。
本作でも、ヨーロッパ人によるはじめの侵攻は武器ではなく宗教を使って行われた。まずキリスト教の宣教師たちを送り込み、徐々にイボ人のコミュニティを分断していった。これは実際に起こった話でもある。
これは現代においても普遍的なメッセージだと思う。正々堂々とした侵略などないし、多くの人がそれに気付いた頃にはもう手遅れなのだ。
さらに、アチェべは本作でイボ人の社会において陰となっていた人々にもスポットを当てる。
作中では「オス」と呼ばれるイボ人の村から隔離され迫害されていた人々が、キリスト教の最初の担い手となり自分たちを迫害していたコミュニティを壊す一役を担う。
初めから内部に抱えていたある種の「ひずみ」が、外部からの変化によって浮き彫りとなり内部の瓦解に繋がる。このあたりの描写もよくできている。
内部のひずみを抱えるという面では、オコンクウォその人も同じだ。
彼は物語の終盤でヨーロッパ人に良いようにされる故郷を見て、ヨーロッパ人、さらにそれを諦観する村の人々に対する怒りを抱えきれなくなる。そして、彼はヨーロッパ人を殺し、自らも命を絶つことになる。結果、オコンクウォは新しい社会にも、古い社会にも居場所はなくなり、「犬のように」埋められてしまう。
この最期は悲劇である。しかしこれはオコンクウォの中にある暴力性、頑迷さが暴走した結果でもある。彼の性質は、基本的には対話と調和を重んじるイボ人社会と大きく乖離していたのだ。
これも、彼の内部に抱えたひずみが表出化した結果だと読み取れるだろう。
このように、本作はアフリカの歴史に大きな影響を与えた歴史的な作品でありながら、現代にも通ずる普遍的なメッセージを与えてくれる名作である。
注釈、解説も充実しており、いろいろな読み方ができる。おすすめの一冊。
Posted by ブクログ
アフリカ文学は当然初めて。解説も読み応えあり。
完全に未知なる世界である植民地支配前のナイジェリアでの日常自体が非常に興味深いし、ストーリーとしても面白い。登場人物名はンから始まったりするのでなかなか入ってこない。
急に地方長官目線で語られる終わりはあっけなかった。
村の運命を大きく変える白人は、スペインによる南米侵略とはまた違い、いくぶん平和的にも見えるがやはり傲慢である。主人公からするとキリスト教や改宗する人々は悪や腑抜けであるが、本書全体で見ると主人公の性格・村の風習の歪みはありありと見てとれ、単純な不正な侵略の告発といった形にはなっていない。
特に触れられてはいないが、終盤の主人公の自死は、ウムオフィア旧社会における「女々しい」行為だろうか?そうなのであればさらに悲劇的だ。
Posted by ブクログ
初めてアフリカ文学を読んでみた。内容としては特に難解というわけではない。始まりから2/3程度までは、主人公のコミュニティの儀礼、慣習、信仰などが細かく描かれている。若干冗長だなと思いつつ読み進めていくと、イギリス人がキリスト教という道具を持参して、植民地化の目的のもと渡来してくる。そこからはあれよあれよという間に物語が進展していき、あっけなく悲惨な結末を迎えてしまう。終盤のあまりに淡泊な描写には呆気に取られてしまった。だが、そこにはアチェベの思念が宿っているのだろう。長い年月をかけて築かれてきた現地の文化(始めから2/3)が、植民地化政策によってあっという間に瓦解していく。(残り1/3)その速度は、このページ数の配分によって具現化されていると感じた。
文化の脆さというのも感じずにはいられなかった。人間は空想する能力があるからこそ、神話や宗教を作り上げて、他の動物とは比べものにならない規模のコミュニティを形成することができる。そうして育まれた文化にも、どかしらに欠陥がある。この作品で言えば、差別対象とされていた人々が端的な例だろう。そうした人々をキリスト教が受け入れ、対立因子を徐々に拡大させていった。そうして、強固だったはずの絆は崩れてしまったのだろう。
帝国主義時代のダイナミズムを存分に感じ取れる一冊だと思う。
Posted by ブクログ
ヤムイモのリアリズム。アチュべはナイジェリア出身の作家。ナイジェリアはヤムイモ産出量世界1位。なによりもまず重要なのはイモであり、あらゆる食事にヤムイモなのである。
客人がやってきてに「コーラあるよ」ともてなすのだが、これはコカコーラの原料の「コーラの実」のようである。覚醒作用があるようなのでやっぱりお酒かドラッグみたいなものなのか。
ナイジェリアの生活様式が興味深い。村で生活するためのシキタリ。それを決めるのは長老かお告げ師である。長生きできることが尊敬に値する、というのは子供の生存率が低いということからも分かる。
コミュニティでは親分から種イモをもらって小作は畑を肥やしそれが生活の糧となる。一夫多妻制で、主人公の妻は3人いる。家屋は主人を中心とし放射線状に離れがあり、妻はそこで子供と暮し、毎日主人の食事を用意する。家長はとても威張っている。作ってくれた食事に文句を言うし、安易に妻へ暴力もふるう。いろいろとしょうがない。
村の余興はレスリング。もちろん強い男が評価される。村人たちはそれを見るのが娯楽。村には巫女がいて「憑かれていない」ときは普通に生活している。(←これはあとで豹変する)
近隣のコミュニティとの軋轢もある。おそらく生贄状態でやってきたよその村の子供を囲って主人公は息子同然に育てるが、村の長からお告げによりそいつは殺すべしと指示され、親代わりだった男が自ら手をくだすことになる。ひどい。それは成長した他所の男が女を孕ませることができる歳になっているという危機感による、原始的な男らしさでもある。
女性は16歳で嫁に行く。婿希望者は持参金を持って女性の父親とかけあう。男同士は椰子酒を飲んで仲良くなる。嗅ぎ煙草を入れている「山羊の革の袋」がよく出てくるが、これはおそらく山羊の胃袋で携帯するポーチのような役割として使われているのではないだろうか。
一夫多妻なので、男子を生むことが女性の地位をあげることになる。子供をたくさん産んでも成長させることが難しいのは悪霊のせいなのであったりする。あるいは大事な石をどこかに埋めてしまったからであったりする。
(登場人物がどんどん増えていく。舞台はアフリカなので「ン」ではじまる名前も多く、慣れないと覚えるのが難しい)
そして後半、突如外部から白人が宗教を布教しにやってきて、長く続いていた土着コミュニティはもろく崩れていく……。ここからですよキモは。キリスト教と白人の欺瞞が。ああ、アフリカの文学。コンラッド『闇の奥』が苦手だった人にもお勧め。今の時代、わたしたちが知るべきはこっちの世界だ。
Posted by ブクログ
ナイジェリア出身のイボ人作家 Chinua Achebe (1930-2013)による、アフリカ文学の金字塔と言われる作品です。
前半は、19世紀後半の植民地化前のイボ族の共同体が、複雑かつ精緻な統治、信仰、慣習システムにより運営されている様子が、主人公であるオコンクウオを中心に描かれています。後半では、それが白人の宣教師たちによるキリスト教布教を境に瓦解していく様へと進行していきます。このあたりが、題名である”崩れゆく絆”をよく体現しています。
この小説は1958年に出版されてますが、そのわずか2年後の1960年にナイジェリアが独立を果たしており、時代は違うものの過度期の不安定や焦燥といった気分が、当時の世相を反映していた、とも言われているようです。
しかし、この小説をそうした歴史的あるいは民族史的側面からよりも、私はオコンクウオという男一人の生き様からとらえるほうが、面白く読めるような気がしました。そして、守護神であるチが運命を先導しつつ、個人の努力にもある程度呼応していく、という宿命論と自力更生的考え方の対置など、自省を促すようなテーマも込められており、多面的な側面を持つストーリーで一気に読んでしまいました。