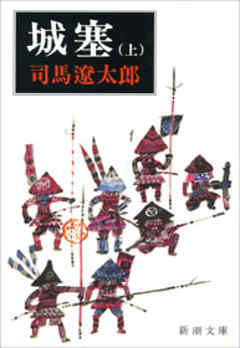あらすじ
「豊臣家をつぶす」──“関ヶ原”から十四年、徳川家康は多年の野望を実現すべく、大坂城の秀頼・淀殿に対して策謀をめぐらす。方広寺鐘銘事件など、つぎつぎと打ち出される家康の挑発にのった大坂方は、西欧の城塞をはるかに凌ぐといわれた巨城に籠城して開戦することを決意する。大坂冬ノ陣・夏ノ陣を最後に陥落してゆく巨城の運命に託して、豊臣家滅亡の人間悲劇を描く歴史長編。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
40年振りの再読。
大阪冬の陣•夏の陣で陥落してゆく大阪城と豊臣家を描く。
淀殿の戦さに対するトラウマと中途半端なプライド、大阪方に策謀をめぐらす家康と崇伝の大悪党ぶり、豊臣家家老の片桐且元の逐電などめちゃくちゃ面白い人間ドラマ。全3巻。
Posted by ブクログ
読みやすさ ★★★★★
面白さ ★★★★★
ためになった度 ★★★★
司馬遼太郎の戦国ものが好きでよく読むが、この作品も面白かった。
大坂夏の陣や冬の陣については、具体的にそれがどういう事件なのか、どうして起こったのかということはほとんどわからなかったが、この小説を読んでよくわかった。
小説なので、どこまで史実を反映しているかという問題はあるが、司馬遼太郎は一作書くにあたって神保町でトラック一台分の資料を入手し、それをもとにしたという。この作品も時代考証はしっかりしているのではないか。
Posted by ブクログ
関ヶ原の合戦後、片桐且元の退去までを描く上編。徳川方、豊臣方の人物を小幡勘兵衛を通して浮き彫りにしていく。共感できるかどうかはともかく家康の心理描写が見事。
Posted by ブクログ
大阪城内の女社会を鮮やかに描き出し、徳川と豊臣の板挟みになる片桐市正の苦悩と、家康とその取り巻きの悪知恵が、非常に分かりやすく書かれている。
絶えず機会を狙い、勝つべくして勝った徳川家と、滅ぶべくして滅んでいく豊臣家の没落をこれほどまでに分かりやすく書いている書を私は知らない。
上巻は、まだ冬の陣の前(片桐市正の放逐前後)で終わっているが、既に読み応え十分である。
Posted by ブクログ
文句なしに面白い。司馬遼太郎の家康嫌いは相変わらずだが、豊臣方が負けるべくして負けたということがよくわかった。結局のところ、淀殿にきちんと物を申す人間がいなかったということだろう。真田幸村にしろ、後藤又兵衛にしろ、秀頼にしろ、なぜあそこまで淀殿に気を使うのかが理解できない。あの時代のあの場所にいないとわからないことかも知れないが、今の会社組織でも上司が間違っていると分かっていても言えないのと同じことなのだろう。
Posted by ブクログ
大阪冬の陣、夏の陣を扱った作品。「関ケ原」と比べ、こちらの作品での家康は、一層、老獪さを増し、豊臣勢を手玉にとる。悪役といってもいいほどの役回りである。
様々な登場人物の背景の解説の細かさや、心理の動きの描写はさすが。個人的には、不利な状況にあっても最後まで戦う真田幸村の姿が最も印象に残った。
Posted by ブクログ
関ヶ原の戦いは終わったが、大阪城には未だ豊臣家の威光は健在。自身の寿命ある内に徳川による治世を完成させたい家康を、類のない陰謀に走らせる。
本書で描かれる家康はなんとも鼻につくイヤな奴。こんな奴が天下を取るなんて許せない、大阪ガンバレと思ってしまうが、その大阪方の人材の乏しいこと。なんせトップが現実を直視せず感情だけで思考する淀殿に、寝たきり老人のように影の薄い豊臣秀頼。そんな幻想家が支配する大阪城内の空気は乱れきっていた。
歴史を知らず、次巻を読むまでもなく、勝敗はすでに決しているのだが、その勝敗外でうごめく人間模様が見どころ。この巻の主役は片桐且元。家康、淀殿からのパワハラを受けまくり板挟み、そして爆発。サラリーマンの中間管理職ならではの悲哀。
Posted by ブクログ
大坂の陣から400年。大河ドラマ真田丸でも描かれるしってことで、平積みになっていたのを手にした上中下の上巻。
真田丸だったら有働さんのナレーションでぶった切るような大坂城内の動き、東西の駆け引きが司馬遼太郎の文体で細かく描かれている。400百年前の出来事を描いておきながら、時々出てくる、筆者の現在の目線。嫌いじゃないです。
真田丸も最終章に向かいます。中巻、下巻もさっさと読まないと。
Posted by ブクログ
関ヶ原の戦いで勝利し、隠居した後も家康は健在でした。家康60代。現在の60代と違って当時は老年期だと思うのですが。健康診断で生活習慣病を指摘された中年のおじさんが、健康管理に励むかのような様子が記されていました。毎朝の火縄銃射撃、鷹狩、時に水泳と体を動かす様子は現代のジム通いのようです。頭の方も切れ味良好で、豊臣家を潰してやるぞという意欲満々の巧妙な策略。恐るべしです。
豊臣家側の人物の内情がよく分かりました。(秀頼、淀殿、大野修理、小幡勘兵衛【徳川のスパイ】、片桐且元)セリフが面白くて、特に淀殿。ホントにエンタメ歴史小説だと感じることこの上なく、笑ってしまいます。大野修理の登場の記述で能筆家とあり、書が残っていれば見てみたいと思いました。
方向寺鐘銘事件について、知らなかったのですが(大方の日本の方は知っているのかと思うと自分が情けないのですが)何で、こんな重箱の隅をつっつくようなこと、家康はよく考えるなあと、本当に細かくてねちっこい人だと思いました。考え方を変えれば、発想はすごいと言えるかも知れませんが。
中巻以降、豊臣家を潰しにかかる家康の様子の描き方、興味あります。
Posted by ブクログ
あれ、、これは家康が主人公なのに、家康のことがますます好きではなくなっていく…
関ヶ原後からの物語で片桐且元が退去するところまでが上巻。
個人的には有楽町は織田有楽の江戸屋敷があった場所というミニミニ知識が好き。
Posted by ブクログ
大阪の陣をテーマにした小説。文庫本で読むと上中下の3分冊なのだが、この上巻ではまだ大阪の陣は始まらない。随想部分が多い歴史ものというよりは、人物が生き生きと動き回る時代小説のような雰囲気が強い。個人的な好みで言えば、「覇王の家」のようなものの方が好きなのだが、それでもさすが司馬遼太郎の小説、楽しみながら読み進めた。
Posted by ブクログ
家康って、ホントに人が変わったみたいに残酷ですね。強者の論理。強ければ許される。それに比べ豊臣家の頼りなさ。哀れですね。 小幡勘兵衛という人はあまり知りませんでしたが、この人を通して物語が展開していくのでしょうかね。この人物の部分は物語的なところも多いのでしょうが、司馬さんはストーリーテラーとしても凄いですねー。 登場人物が皆活き活きとしていて、円熟の役者さんたちが総出の映画を観てるみたいです。
Posted by ブクログ
どのようにして大坂の陣に至るのか、という経緯をじっくり描いている。
次巻の冒頭から真田信繁などが大坂から声を掛けられてとなるので、それまでの話になる。
この巻では有名な五人衆などは影も形もない。
前哨戦も前哨戦なので話は静かに進んでいく。家康方の緻密な政治工作や、豊臣方の道理に依った若干現実離れした考え方など、互いのスタンスの違いがよく描かれている。
派手な動きや人物が出ないので、小幡官兵衛が実質主人公として物語らしく動き、家康サイドと豊臣サイドの思惑の間を行き来する。
この官兵衛、どことなく国盗り物語の道三とキャラが被っている(笑)本人の才覚と大胆さと女を使って、情報収集・工作という役割。
有名所の話が見たいと思うのなら中巻からでいいかもしれない。
が、大きな山場などは無いながらも着実に戦に至るまでの空気を感じ取ることが出来るので、余裕があるならば手に取っていいと思う。
有名所の登場を巻跨ぎにしない辺り親切だし、上巻は一貫してそういう役割の巻になっている。
Posted by ブクログ
秀吉の作った'城塞'、すなわち大阪城の陥落を描いた長編。真田幸村、後藤又兵衛をはじめとする稀有の武将たち、潜在的な可能性を秘めた豊臣秀頼、何より天下の城塞たる大阪城の存在にもかかわらず、淀殿を中心とする人間たちがことごとく足を引っ張る様子が本当にもどかしい。秀頼の両側に幸村、又兵衛がつき、全体が統制された行動をとっていれば、大坂の陣はどうなったのかと、どうしても考えてしまう。その中でも、先の真田、後藤のほか、木村重成、毛利勝永など、部下が共に死んでもよいと思えるほどの漢達の生き様、死に様は、男として感動せざるをえない。
Posted by ブクログ
家康による大阪城攻略の顛末を描く長編。司馬遼太郎の得意なストーリーテリング展開として、複数の登場人物の視点を同時に使うが、特に小幡勘兵衛とお夏というキャラが一番絵になる。
当時70歳を越えた家康がかつての主家豊臣家を滅ぼすために矢継ぎ早に行う政略がえげつないのに対して、淀君のヒステリーっぷりが痛々しい。
Posted by ブクログ
大坂の陣を描いた作品。謀略の限りを尽くして豊臣方を追い込んでいく徳川家康の悪辣振りは嫌悪感を覚えるほど。そして、彼に翻弄される淀君は自ら滅亡の道へと歩んでいきます。最後に一花咲かせようと、死に体の大阪方に馳せ参じた真田幸村、後藤又兵衛ら武将たちの生き様は胸を打ちます。
Posted by ブクログ
大坂の陣を描いた作品。真田幸村をはじめとする優秀な牢人達がせっかく助けに来てくれたのに、家康の策略にまんまとハマり彼らの邪魔ばかりする無能な大坂方の上層部がもどかしい。それでも家康を何度か窮地に陥れる場面があり歴史のifを感じずにはいられない。
Posted by ブクログ
関ヶ原の戦いで勝利して征夷大将軍に任官された徳川家康が、豊臣家を滅ぼすお話です。関ヶ原から続けて読んだが、前回のようなスケール感が全く感じられない。読んでいて辛くなるとともに徳川家康の人気が、織田信長や豊臣秀吉よりもないことはよくわかる気がします。
Posted by ブクログ
いやぁ、すばらしい。
久しぶりにこれぞ司馬良太郎を読んだ。
明治ものもいいが、戦国ものはまさに司馬遼太郎の真骨頂だと思われる。
徳川家康が悪すぎる。
目の前で徳川家康が小躍りしているのが、手に取るようにわかる。
それに対しての、大阪。
次巻も大期待。
Posted by ブクログ
戦国時代の終結を告げる大坂の陣を題材にしながら、実に現代的な本だ。
大坂方の中枢は、世の中の流れが完全に関東にいっていることが分からない。「豊臣恩顧」などという論理も、力でくつがえるという現実を見ようとしない。そんな沈む舟から、脱出する人がいる。裏切って内通する人がいる。(総大将に指名され、すぐに逃げた織田信雄には笑うしかなかった)。昭和体質を捨てられず、没落する日本企業を見る思いだ。
一方で、関東方には、権力のためならいくらでも学問をねじ曲げる御用学者がいる。ようは勝てばいい、政権が続けばいい。そんな権力中枢のリアルが描かれる。現代日本政治を見る思いだ。「関ケ原」とあわせて読みたい。名品。
NHK大河ドラマ「真田丸」の役者たちを念頭に置きながら読んだ。とくに大蔵卿局と片桐且元。
Posted by ブクログ
家康による悪巧みの物語。
戦国時代の幕引きとなる「大阪の陣」だけど、関ヶ原から十数年後で歴戦の武将はもういない。家康1人が戦国の気風を知っているという書き方になっていて、自軍の若い武将を嘆くところも時代の変わり目というところでしょうか。
それにしても徹底して家康を悪者にし、豊臣方は無能の集団として描く。近年、これほど無能な「淀の方」は描かれていない。どこで潮目が変わったのかね。
Posted by ブクログ
~全巻通してのレビューです~
大坂冬の陣、夏の陣を描いた物語。
「関ケ原」など今まで読んできたものと比べて、大野修理、淀殿、秀頼など小者がよく登場した影響で、なかなか読み進めず集中力の持続が難しかったですね。
一か月かかりました。
そんな中、真田幸村や後藤又兵衛、毛利勝永が出てくる場面は興味をもって読むことができました。
ただ彼らの献策が大野修理や淀殿に受け入れられることが少なく、だんだんと彼らの登場場面も減っていきました。夏の陣になって最後増えはしましたが・・・
大河「真田丸」を見ていた影響で、幸村は心の中で躍動しました。(もちろん幸村=堺雅人)
冬の陣での講和で家康は大坂城の外濠だけでなく内濠も埋めたり、だいぶ印象は変わりました。
山岡荘八の「徳川家康」では描かれなかったブラック家康でした。
Posted by ブクログ
大坂の冬の陣・夏の陣を、戦が始まるきっかけから大坂城落城まで描いた歴史小説。
2016年大河ドラマ「真田丸」の予習として読んだ。
主人公は小幡勘兵衛という牢人で、後に軍学者となる人物。彼は、戦の表舞台には立っていないが、徳川方の間諜として豊臣方に入り込んでいた人物であるため、両者を行き来しつつ狂言回しとして物語を進めていく。でも、途中で時々、全く登場しなくなり、誰が主人公だっけ?となることも。司馬小説ではよくあることだけど(いわゆる「余談だが現象」)。
たまに勘兵衛が、恋人お夏のために豊臣方に肩入れして徳川を裏切りそうになり、その場面だけはグッとくるものがあるのだけど、最終的には打算と私利私欲で動く人物なので、途中からはそんなに感情移入は出来ない。
それ以外の、戦の表舞台に立つ登場人物は以下の人達
豊臣:淀殿、豊臣秀頼、大野治長、真田幸村、後藤又兵衛、片桐且元
徳川:徳川家康、徳川秀忠、本多正純、本多正信
どの人物も、何かしら足りないところや汚いところがあって、他の司馬小説の主人公(竜馬・高杉・土方・信長・秀吉ら)みたいに純粋にカッコいいと思える人はいない。でも、その人間臭さこそが、司馬さんが群像劇としてこの小説を描いた意味なのだろう。
そして、女優で歴女の杏さんが本の帯か何かで書いていた、『最強の城も、人間や組織次第でこうも簡単に滅びるのか』みたいなことが、この小説の一番のテーマ。最強の城と、実戦経験豊富な現場担当者。これらが揃っていながら、なぜ大坂城は落ちてしまったのか。上に立つ者が世間知らずでマヌケだったから、なのだろうけど、その一言だけでは片づけられない、数々のボタンの掛け違いによる失敗から学ぶことは多い気がする。
以下、印象に残ったエピソード
片桐且元の豊臣方から徳川方への転身
- 豊臣を裏切る気持ちは無かったのに、家康の策略と豊臣上層部の疑心暗鬼から、やること全て裏目に出て、転身せざるをえなかった片桐且元。豊臣への忠誠心は誰よりも強かったはずなのに、最後は大坂城へ向けて大砲を打つことまでさせられた彼の心境は、言葉に出来ない。人と人との些細な擦れ違いから、人生を狂わされてしまうこともあるのだ。大河ドラマ「真田丸」小林隆さんの悲喜劇入り混じった演技も、印象深かった。
大坂五人衆集結
- 真田幸村、明石全登、後藤又兵衛、毛利勝永、長曾我部盛親ら五人衆。戦う場所を欲して、家の再興、キリスト教布教許可など、各々の理由を持ちつつ大坂城に集まって来て、団結して戦いに臨む。大河ドラマと並行して読んでいたため、映像とシンクロしてワクワクして読み進めた(負けるのは分かっているのだけれど)。
犯罪者家康と、純粋な豊臣方牢人たちとの対比
- 司馬さん曰く、徳川家康の大坂攻めは戦争というよりも、本質は「犯罪」(主家である豊臣家に対し、騙したり、約束をすっとぼけたり、内部分裂させたりしたから)。家康をとことん悪人に描いているが、それは彼が「後世にどう思われるか」という発想が無かったから、との解釈。一方、真田幸村・後藤又兵衛ら大坂方牢人は、豊臣が滅んだら他に頼るものが無いわけで、自然、死を恐れず武名をあげ、後世に向かってよき名を残すことに純粋に研ぎ澄まされていくようになる。それぞれの生き方の違いだったのだろう。
Posted by ブクログ
大阪の陣が起こる前の主要人物の人間性、状況が細かく描写されているので大きく物語が始まる序章としていると思われる。
太閤がどれ程偉大であったかを残された愚鈍で保身に走る大坂城内の家臣との対比で表現していると感じた。
Posted by ブクログ
関ヶ原の戦いで東軍が勝利をおさめ、東軍の大将である徳川家康はその後、江戸に幕府を開いた。誰もが天下は徳川家のものと認識していた。
しかし、そんな中、西側に取り残されている城がある。
それが大坂城だ。
大坂城の城主は豊臣秀吉のあとを継いだ秀頼。そして実質的に力を持っているのは、生母淀殿。
淀殿は、秀頼が天下のぬしという思いにとらわれている。その意識は、もはや世間一般の意識とは異なったものとなっていた。
上巻では、大坂冬の陣の前の大坂城がどんな存在だったのか、そこで何が起きていたのかが、えがかれている。
世間一般から取り残された、大きな城。
男中心の武家の政治と異なる、女の感覚に支配される城。
外の世界を知らない城主秀頼。
いつの間にか中に入り込んでいる諜者たち。いつの間にか諜者になっていた武将。
そして、取り囲む武将たちの意識も、既に関ヶ原以前とは違う。誰もが天下のぬしは徳川家にうつったと知っている。
そして、世間は戦をのぞんでいない。
関ヶ原で秀頼が出陣していたら… 世の中、かわっていたでしょうね…
あの時点で、豊臣家は負けたんです。石田三成に罪を着せたって、何の意味もない。
ここまできたら、何か大きな転換策を用いなければ、もうあとは大坂城がどう消えるかしかない。
でも、大阪城は秀吉の作った強固な城。そして、まだ中に秀頼がいる。
権力を持つのが淀殿であっても、淀殿には城内での権力しかない。でも秀頼だけは城外の武将たちに影響力を持てる可能性がある。
だから、徳川家も簡単には豊臣家を滅ぼせない。
慎重な家康がどう事を運んでいくのか、続きが楽しみです。