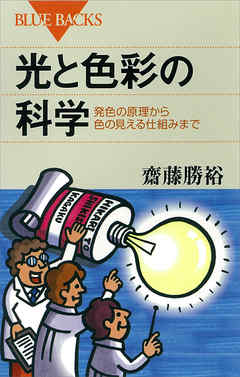あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
なぜわれわれに色が見えるのか? 同じ赤でも自ら光を発する赤と光の反射によって見える赤は違って見えるのか? 色を認識する視覚と脳の関係、色と光の物理的・化学的関係、色と心の関係、光を使った最先端技術まで光と色彩のさまざまな話題が満載。(ブルーバックス・2010年10月刊)
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
<光と色と物理と化学。そして生じた色を認識する生理学と心理学。ヒトに色が見えるのはどうしてか、バランスよく解説した色彩学入門書。>
昨年、青色LEDがノーベル物理化学賞を受賞して以来、色とは何か、少し詳しく知りたいと思っていた。何かと取り紛れて間が空いてしまったが、わかりやすそうだったこちらを読んでみた。
専門用語を多用せず、使用する場合は適宜、解説を付け、数式・化学構造式も必要最低限という親切設計。それでいて、色が生じる仕組みから、私たちがそれを感知する機構まで、だいたいのイメージが掴める。
まずは色彩学の基礎である。
ニュートンのプリズム実験に始まり、色が見えるとはどういうことかを探る。ニュートンはいみじくも、見た目が赤い光を「赤い光」と呼ばず「赤を作る光」と呼んだ。光と感覚の本質を突いたひと言である。
赤く見えるとはどういうことかといえば、ヒトが持つセンサーのうち、赤を認識するセンサーが反応するということである。センサーには3種があり、それぞれ赤・緑・青を認識する。すべての色はこの3種の混ざり合いで作り出される。
色彩は、この色相に加え、明るさ(明度)と鮮やかさ(彩度)の度合いによって生まれる。
明るさとは光の反射率によるもので、これが高ければ明るく、低ければ暗く見える。赤といっても明るい赤と暗い赤があるのはこのためである。鮮やかさとは色彩に混じる白や灰色の成分で、灰色が混ざるほどくすんだ色彩となる。
この3つの成分の組み合わせによって生じる色彩を客観的に表示したのが色立体である。表示の方法によっていくつかの種類があるが、このうちの1つであるマンセルの色立体は日本工業規格(JIS)に採用され、工業やデザインに利用される。例えば5R4/14と指定すれば、比較的明るい赤といった漠然としたものではなく、統一された色で製品が作れることになる。
さて、色を感知する器官とは何かといえば、ヒトではもちろん目である。
光を感知する目の網膜には、視細胞があり、これには桿状細胞と錐状細胞がある。桿状細胞はロドプシンと呼ばれるタンパク質によって明暗を感知し、錐状細胞はフォトプシンによって色彩を感知する。フォトプシンには3種があり、それぞれが青(420 nm)、緑(534 nm)、赤(564 nm)の光を感知する。どの錐状細胞がどのくらい反応したかによって、感じられる色味が変わってくることになる。
つまり、光の三原色に合わせてセンサーがあるというよりも、ヒトのセンサーが三原色にあたる波長を感知するものであったため、(ヒトが感じる)光の三原色が青・緑・赤となった考えるのが妥当だろう。
物体が赤く見えるということは、そのものが赤以外の光を吸収し、赤い光を反射するということである。光と色の三原色は補色の関係にあり、光の三原色を重ねると白になる一方、色の三原色を重ねると黒になるというのも頷ける。
光を吸収するのは分子であり、どの波長の光を吸収するかは分子の構造による。有機化合物の場合、原則として二重結合が多いほど吸収波長が長くなる傾向があるが、これが当てはまらない例もあり、この部分を理解するには本書から発展して別の本で学ぶ必要がある。
さて、ここまで見てきた「色」は、分子による光の吸収・反射によって説明できるものである。
一方、この概念ではまったく説明できない色もある。例えばタマムシの虹色、空の色、青い瞳、サンマの銀色である。これらは構造色と呼ばれる。構造色とは光の干渉による発色現象である。波としての光の性質に基づき、さまざまに反射された光が増幅されるかまたは相殺されるかによって、光(色)が強まったり弱まったりする。
構造色が生じる例として、薄膜や多層による干渉(シャボン玉や蝶の鱗粉、タマムシの色)や、微粒子による散乱(青空、雲、青い瞳)がある(*青い瞳に関しては、子犬の青い瞳について触れた『犬と人の生物学: 夢・うつ病・音楽・超能力』のレビューにまとめた)。
このほか、蛍光とは何か、光とエネルギーの関係はどうなっているか、可視光と紫外線・赤外線の違いとは何か、染めに関係する化学反応のあれこれ、色が人に与える心理的影響など、興味深い話題が満載である。挿入されているコラムもおもしろく、メタノールでどうして失明するのか、ホタル・ルシフェラーゼを用いたさまざまな検査法等々、へぇと思う話があれこれ紹介されている。
さらに知りたい人向けに、巻末に参考文献が挙げられているのも親切である。
色と光の目眩く世界の入り口としてふさわしい1冊と言えるだろう。
Posted by ブクログ
色彩の生理学の項目がおもしろかった。
見るということは、光が目に入る物理的な現象から始まり、レチナールという分子が光によって化学変化を起こし光が来たことを伝え、電気信号で3層の細胞を通過し、脳が送られてきた情報を総合判断する現象(で合ってるかな?)
普段無意識に見るということをしているけど、体の中でこんなに細分化された伝達が行われているなんて驚いた。
Posted by ブクログ
光学よりも色彩についての解説が中心でした。
それほど深みはないものの「おさらい」としてはわかりやすい。染料による色彩の解説はかなりおもしろかった。
Posted by ブクログ
著者は名古屋工業大学名誉教授で、有機化学や光化学などを専門とする方。バラが赤く見えること、ネオンサインが赤く見えること、空が青く見えること、雲が白く見えることはそれぞれ違う発色の原理である、など、いろいろと目から鱗なことがありおもしろかったです。色という身近な現象の背後にも深い物理の世界があることを感じました。こうした本を中・高生くらいのときに読んだら物理にもっと興味持っただろうな。中・高生にお勧め。
Posted by ブクログ
色彩と光についての基礎知識がまとめられている。ネオンのように光って見える色と発光しない物体の色は見える原理がまったく異なるのだ。光らない色を認識できるのは反射光を認識しているから。色は物体が吸収する光の色の補色なのだ。これは見えている世界の認識が変わる。
人間の見る仕組みも科学的に解説されている。文系の自分には細かい理屈は分からないけど知識として知っておけばまた別の本で生きることもあるはず。構造色の話も仕組みはよくわからないけどそういうものがあることを知っておくのは意味がある。色の心理学的な効果も面白いが入門レベルでもっと詳しい本を読むのもいいかも。