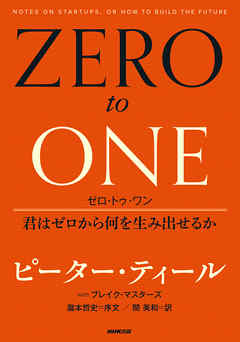あらすじ
空飛ぶ車が欲しかったのに、
手にしたのは140文字だ
「もし本気で長期的な人類の発展を望むなら、
ただの140文字や“永遠の15分”を超えた未来について考えなければならない。
ZERO to ONE はシリコンバレーを教科書に、
難題を克服してこれまで存在し得なかった偉大な物事を築きあげるための本だ」 by Peter Thiel
たとえば、日本が「失われた20年」と言われている間に、世界のイノベーションを引っ張っているのはアメリカ、特に西海岸のシリコンバレーだ。アップルやフェイスブックといった名前がすぐに思い浮かぶけれど、数多のスタートアップが起業しては消えていく世界でもある。
そんな中、次々と成功する企業を立ち上げる起業家集団がある。
オンライン決済サービス・ペイパルの初期メンバーとして繋がりが深く、現在もシリコンバレーで絶大な影響力を持つことから「ペイパル・マフィア」とも呼ばれる彼らは、ご存知ユーチューブ(YouTube)をはじめ、電気自動車のテスラ・モーターズや民間宇宙開発のスペースXからイェルプ(Yelp!)、ヤマー(Yammer)といったネットサービスまで、そうそうたる企業を立ち上げてきた。
本書はそのペイパル・マフィアの雄、ピーター・ティールが、母校スタンフォード大学で行った待望の起業講義録である。
■日米同時発売■
ピーター・ティール with ブレイク・マスターズ=著
関 美和=訳
日本語訳序文=瀧本哲史 推薦!(ビジネス書大賞『僕は君たちに武器を配りたい』)
[目 次]
日本語版序文 瀧本哲史
はじめに
1.僕たちは未来を創ることができるか
2.一九九九年のお祭り騒ぎ
3.幸福な企業はみなそれぞれに違う
4.イデオロギーとしての競争
5.終盤を制する―ラストムーバー・アドバンテージ
6.人生は宝クジじゃない
7.カネの流れを追え
8.隠れた真実
9.ティールの法則
10.マフィアの力学
11.それを作れば、みんなやってくる?
12.人間と機械
13.エネルギー2.0
14.創業者のパラドックス
終わりに―停滞かシンギュラリティか
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
『Zero to One』は、キャピタリストや起業家にとって重要な視点を提供している。特に、従来の競争優位性を否定し、「独占」を目指すべきだと強調している点が特徴的である。
ただし、本書が示す「成功」とは、単に小規模なサービスや事業を数億円で売却することではなく、社会を大きく変革するレベルのものを指している点に留意したい。
感想としては、多くの"中小企業"にとっても独占は理想ではあるが、完全な独占を継続するのは現実的に困難である。そのため、本書の視点を参考にしつつ、リタ・マグレイスの理論(競争優位性を一時的なものと捉え、変化に適応し続けるアプローチ)と組み合わせると、より実践的な戦略が立てられるのではないかと感じた。
学び
① 競争優位性の持続性に関する視点
・従来の「競争で勝つ」という発想ではなく、「競争せずに独占を築く」ことが重要。
② バックキャスティング的思考
・ 「独占的な未来」を描いた上で、そこに至る戦略を逆算して考える。
③ その他、今後意識したい点
・既存市場の破壊を目的としない
新規事業を考える際、つい「既存市場を壊すこと」に意識が向きがちだが、本質は破壊ではなく、新たな価値創造にある。理想は、既存市場も含めた全体の発展。
・「タイムマシン経営」のリスク
これも案として思い付きがちであるが、他国・他市場の成功モデルを持ち込むビジネスは、一見新規性があるように見えても、大企業が本気になれば模倣可能であり、持続的な競争優位を築くのは難しい
⭐︎ベンチャー企業を就職先、転職先の候補に入れている場合には、本書の投資家目線を自分ごととして取り込むことで、良い企業を選ぶきっかけになりそう
Posted by ブクログ
ゼロ・トゥ・ワン
―君はゼロから何を生み出せるか
ペイパルの創始者で今はベンチャーキャピタルをやっている著者が、スタートアップに特化した自らの体験に基づく考えを披露しています。
まず、大胆に通常信じられている以下の常識に対して
1. 漸進主義
2. リーンスタートアップ
3. 革新より改良
4. 販売よりも製品
著者は以下のように主張しています。
1. 大きな賭けをしろ
2. 成功するための計画を持て
3. 競争するな
4. 販売は製品と同じくらい大切
自らいくつかの会社を経営しながらドットコムバブル、リーマンショックを生き延びてきた著者の言葉には重みがあります。
他にも以下のポイントが印象に残りました。
* スタートアップでは少数精鋭のチームが大切だが、個性豊かなメンバーの相性も大切
* テクノロジーは他の競合品より10倍の性能でないとだめ
* 成長する時にリニアなものなどなく、指数的な動きになる
ビジネスで成功するためには以下の7つの質問に答えられるようなビジネスプランが必要
1. エンジニアリング
2. タイミング
3. 独占
4. 人材
5. 販売
6. 永続性
7. 隠れた真実
そして一番わかったことは「竹蔵はスタートアップには向いていない」ということ。
まあ、序文を書いたような人が跋扈するその世界はこちらから御免こうむりたいです。
竹蔵
Posted by ブクログ
イーロン・マスクらと肩を並べるIT世界の大物ピーター・ティールが、
2012年にスタンフォード大学で行った起業講義をまとめた本。
独占的企業こそが繁栄を生むこと、
隠れた真実を見つけることで、
ゼロからイチを生む独占的企業になるスタートをきれることといった、
本書の中盤の箇所が特におもしろかったです。
独占的企業といえば、たとえばgoogleがそうであり、
そういった企業は研究開発や社会貢献に
お金をつぎ込むことができたりもします。
隠れた真実を見つけることは容易ではないかもしれないですが、
たとえば会社から離れて考えてみれば、
文学といったものも、隠れた真実をあぶりだすものであったりしますから、
それほど珍しいものでもないことがわかります。
また、人間と機械に関しては、
置換と補完がある、といいます。
発達したAIなどの機械が、人間にとって代わる、
つまり仕事を奪うのが置換ですが、
人間の助けになる形で発達する補完の方向もあります。
技術が人間を補完する例だと、
パラリンピックの選手たちの義足がそうですが、
あんなふうに、AIや機械が人間を補完するように
発達していく方向はあるのでしょう。
また、これがキーとなる「モノの見方」であり、
起業して成功するにしても最重要なんじゃないかと思える考え方なのですが、
それはなにかというと、
未来がどんな世界になっているかを意識すること、なんですね。
未来を正確に予測できる人はいないけれど、
未来は今と違う形になっていることを想像できる人は強い。
多くの人は、「未来はどうなっているか?」と問われると、
異なる視点で現在をみているだけの答えを返すそうです。
未来は今とは違うが、
だけど未来は今の世界が元になっている、と著者は言います。
未来を見る感覚、
そして、バックキャスティングで考えていくことが大事なのかもしれないです。
Posted by ブクログ
トランプ氏の元政治顧問ということもあり、どのような考え方を持つ人物か知りたいと思い、読んだ。結論から言うと、著者の個別の考えについては同意できない部分も多いが(というよりも、著者の考えは一場面においては有効かもしれないが、その考えが有効ではない場合も多々あると感じた。)、著者の考え方、ひいては今のいわゆるテクノリバタリアン的な考え方、アメリカ政権の行動の背景にあると思われる考え方については一定の理解が得られたので、有益だった。
簡易な文章と、具体例な事例の紹介により、読み進めることは容易。しかし、元々は講義だったものを書籍化したためか、特定のテーマについて著者の考えが論理的に示されているというよりも、(起業・ビジネスという大きな枠組みは存在するものの)異なるテーマについて、散発的に著者の哲学・考え方が示されるため、全体として著者がこの本で何を言いたいのかという点はわかりづらい(中には、著者の政治的見解と思われるものも含まれる)。ただ、著者の考えが刺さる人にとっては、かなりバイブル的な存在になることは理解できる。
この本で最も著者が強調したい点は、競争を避け、独占可能な分野を発見し、そこで成功をつかめという点だろう。しかし、この考え方自体は、特に新規性があるものではない上、多様な側面を有するビジネスの一側面をとらえたものにすぎないだろう。著者は、競争にまみれた、著者から見ればいわば「劣った」事業として、航空事業やレストラン事業等を挙げるが、そのような事業も社会にとっては必要な事業である。あくまでこの書籍はエリート大学生に向けられた講義をベースにした、これから起業家や投資家を志す者に向けられたものであるから、このような内容になることも理解できなくはないが、やや一方的な見解であるように思えた。
おそらく著者がこのような見解に至ったのは、著者が実際に果たした社会的成功とその方法論によるものだと考えられるが、それだけでないように思われる。本書では、著者が、極めて優秀な米国ロースクールを卒業し、法曹として最高のキャリアを志したにもかかわらず、残念ながらそれには失敗し(とはいえ、それでもなお相当高いレベルのキャリアを築いていたものと思われるが)、今のビジネスの道に進んだことが語られている。つまり、著者の競争への強い嫌悪感は、競争社会での挫折による、おそらくはコンプレックスの感情がベースになっていることが推測される。また、著書では、著者が立ち上げた企業が、その後、同業のイーロンマスクの企業と競争状態になったものの、結局は熾烈な競争を避けあえて合併の道を選び、これが今のペイパルとなったことが語られる。競争の回避という考えは、当時の著者の判断の事後的な正当化ではないかとも考えられる(内情はわからないが)。
他にも、計画を立てることの重要性や、ベンチャー企業への投資における方法論、営業の重要性等が散発的に語られ、様々な文献の引用による著者の主張の補強を試みられるが、多くは、著者のこれまでの人生の正当化ないし著者のビジネスにおけるN=1の成功体験による記述ではないかと感じた。ただ、一部の記述はかなり具体性が高く、おそらく著者の実体験によるものなのだろう、興味深く読める部分も多かった。
重要なのは、彼ないし彼と思想を同じくする者の政治への影響だろう。この本を通じて各テーマに対する著者の考えに通底するものとして、強い目的・計画志向(本では、執筆当時のアメリカの現状を「あいまいな楽観主義」と批判する)、新しいテクノロジーないし思想による事態の打開(彼はこれを「隠れた真実」と呼ぶ)を感じた。すごくSF小説的だ(この本でも頻繁にSF小説が言及される)。今のアメリカ政権が、これまで予想もしなかった新しい試みを次々と打ち出していっているのも頷ける。アメリカのダイナミズムを感じるとともに、おそらくはこの強い目的・計画志向の下、破壊・毀損される従来の価値が今後多く現出するであろうことへの恐れも同時に感じる。彼らは、ここ数年ではなく、数百年・数千年の人類(若しくはアメリカ国民)の行く末を感じているのかもしれない。やはりSF小説だ。