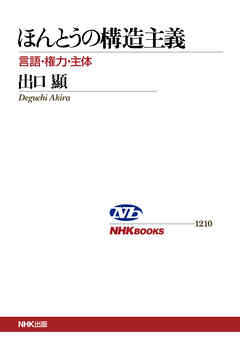あらすじ
レヴィ=ストロース、バルト、ラカン、フーコー。
誤解を一掃し、現代的意義を見出す
二十世紀半ば、それまでの哲学・社会思想の基盤を崩壊させてしまった構造主義。世界を席巻する思想となったが、いわば早すぎた流行であり、その真に革命的な意義は理解されていなかった。自己責任、自己啓発、「絆」への賞賛が氾濫する現代にこそ見直されるべき原典を読み解く、構造主義“再入門”。
[内 容]
はじめに
序 章シベリアのラカン
第一部 主体と作品の解体
第一章 作者はなぜ死んでいるのか
第二章 言語は何を伝えるか
第三章 「構造」とは何か
第四章 「神話が考える」とはどういうことか
第五章 類似から相似へ
第六章 権力はいつ変容したか
第二部 権力と主体の解剖
第七章 代理から代替へ
第八章 古代における「主体化」
第九章 言語の権力を揺さぶる
第十章 悲劇の人格論
第十一章 「ない」という「ある」こと
第三部 今こそ読み返す
第十二章 人を喰う社会と人を吐き出す社会
第十三章 分人論を先取りし、のりこえる
終 章 新世界のレヴィ=ストロース
注 釈
あとがき
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
著者の専門は文化人類学なので、レヴィ=ストロースを中心とした「構造主義」の話しかと思ったら、レヴィ=ストロースは最初の方で少し出てきたら、あとは結構、フーコーの話しが続く。そして、バルト、ラカンの話しを経由して、レヴィ=ストロースに戻ってくる。
非政治的で、静的にみえるレヴィ=ストロースとは、かなり違うものにみえるフーコーの権力論なのだが、実は、かなりの共通点をもっているんだな〜。
というか、お互いを必要としあう対称的な存在。つまり、構造主義的な構造にこの2人はあるというわけ。
フーコーは、ポスト構造主義と位置付けられることもあるけど、構造主義としての側面もしっかりあるんだよね。というか、ポスト構造主義と呼ばれるものも、構造主義とかなり連続したもので、構造主義を単純に否定的に批判することはできないと思う。
前から思ってたのだけど、その辺のところが、すっきりと、そしてとてもスリリングに論じられていて、面白かったな〜。
個人的には、今、「関係性のなかの自己」みたいな概念を深めようとしているところで、いくつかの疑問点、たとえば身体とか、うちなる他者、複数性、言語みたいなのについて、手がかりがもらえた。
レヴィ=ストロース的な言い方だと「人を喰らう社会」と「人を吐き出す社会」があるということになる。レヴィ=ストロースもフーコーもともに「人を吐き出す社会」への批判として、「人を喰らう社会」というオルタナティヴをレヴィ=ストロースは「未開社会」に、フーコーは、西欧の古典主義社会だとか、キリスト教以前の社会とかに見出す可能性を探っていたということかな?
そうか〜、こうなるといよいよ「神話論理」に挑戦する日がやってきたということかな?
Posted by ブクログ
レヴィ=ストロース、ラカン、バルト、フーコーの4人の思想を読み解きながら、「構造主義」と呼ばれる人文科学の方法論的革命の意義を論じた本です。
著者は、構造主義からポスト構造主義への発展という図式を退け、レヴィ=ストロースの神話分析の中に、ラカンの『S/Z』やフーコーのマグリット論、あるいはラカンの鏡像段階論と共通する志向を読み取ろうとしています。4人の仕事に共通しているのは、他者を巻き込み他者に巻き込まれる中で主体や自己が形成されるという発想であると著者は主張します。神話や文学作品などの対象を分析的に捉える西洋近代の主体を相対化することは、自己の視線が他者の視線と輻輳する場へとみずからを開くことであり、そうした志向が彼らの仕事の根底にあることが明らかにされています。
また著者は、そうした構造主義の発想に基づいて、代理出産をめぐる「生=権力」の分析や、マリリン・ストラザーンと平野啓一郎の「分人」批判を展開しています。
若干議論が拡散してしまっている印象があるものの、論じられているテーマはおもしろいと思いました。