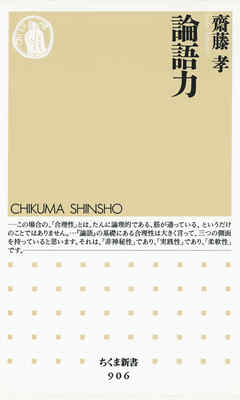あらすじ
多くの人々の「精神の基準」となった大古典『論語』。そこに収められた言葉は、学びへの意欲を高め、社会の中での自分の在り方を探るのにこの上ないヒントを与えてくれる。また、柔軟で合理的に、弟子たちに対してそれぞれに配慮した言葉をかける孔子の生き方は、多くの現代人にとって最高のロールモデルともなるだろう。「学び」を軸にして、人生を向上させる、決定的入門書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2017/03/03
論語は格言集のようなものだと思っていたけど、その中には孔子と弟子たちのストーリーがあり、だからこそ説得力もあり、読めば読むほどに奥深さを感じることができそうだ。すぐに原文が読みたくなったが、まだ原文を読み込む力量がないので、差し当たっては中島敦の『弟子』を読むことにした。
Posted by ブクログ
著者の現代語訳『論語』は、なぜか手にとっても買えなかった。論語に対する何かの抵抗感が働いていたような感覚であった。そんな中で見つけたこの本、弟子たちの人物評まである。ぐっと親近感が沸いてきた。次は買えるだろう、きっと。
Posted by ブクログ
斎藤氏が解説する論語。
「中庸」「礼」「仁」についてはとても詳しく書かれている。
また、プラトンの書との共通点・相違点なども説明されていて思しろい。
著者の文章はいつもわかりやすい。本書でも然り。
Posted by ブクログ
現代の社会をリクエスト社会と称し、自己実現とリクエストの交差点を導く、それを論語から読み取るための手引書である。論語は読んだことがなかったこともあり、本書と同時に手を出してみたい!
Posted by ブクログ
論語の考えを現代の生活に置き換えてわかりやすく解説してあり読みやすい。
マッカーサーが指摘した明治と昭和の軍人違いに論語の素読が関わっていたかもしれないという考え方は興味深い。
Posted by ブクログ
齋藤孝さんが好きで、この本もすぐに目を付けました。
ずばり、「論語」を現代に生かすよう試みた1冊というわけです。
弟子と孔子のエピソードをもとに、孔子の言葉について
取り上げるというスタイルになっており、とても読みやすい!
齋藤さんの本は、長々と難しい言葉が書かれていなくて良いですよね…!
お気に入りの言葉をいくつか紹介します。
弟子が孔子に、「先生の志は何か」と問うてみると、
「老人には安心されるよう、友人には信頼されるよう、
若い人には慕われるようでありたい。」と答えました。
孔子の人柄が伝わってくるような気がしませんか?
ほかにもこんなエピソードがあります。
ある弟子が「自分はなかなか力がなくて、道を学ぶことができません」
というと、孔子はこういいます。
「本当に力が足りない者なら、やれるだけやって、
途中で力を使い果たしてやめることになるが、
お前はまだ全力を尽くしていない。
今お前は自分で自分の限界を予め設定して、
やらない言い訳をしているのだ。」といいます。
「論語」は古くて難しくて、私たちの生活には関係ないんじゃないか。
そう思っている人にオススメ。
現代の私たちの世界でこそ、読まれるべき1冊なのかもしれません。
Posted by ブクログ
人生の中で勉強の教材として論語は扱ってきましたが、読み物として論語を読んだことがなかったので、本書でその導入を学べたらなと思い手に取りました。
齋藤先生の文章は何本か読みましたが、本書も非常に読みやすく、論語の構造や本筋について勉強することができました。
もう少し掘り下げた内容も学びたくなったので、また別の書物や原作を読もうと思います。
Posted by ブクログ
同じ「ちくま新書」から『論語』の現代語訳も出版している著者が、『論語』の魅力について語っている本です。
著者はこれまでも、多くの作家や思想家、偉人についての本を刊行していますが、「学ぶこと」をスタイル化したという意味では、著者の思想と孔子との相性はかなり良いのではないかと感じました。孔子とその弟子たちの師弟関係に関しても、教育学者としての著者の立場からユニークな解釈が示されています。