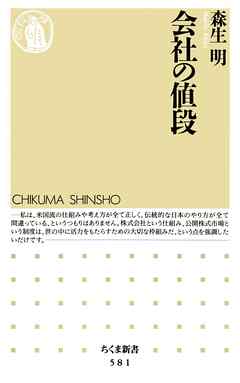あらすじ
日本では、「会社買収」に対する違和感を持つ人が多い。しかし、株式会社というのは、そもそも「会社を売り買いする仕組み」ではなかったのだろうか?本書は、会社に値段を付ける、ということはどういうことなのかを根本にまで立ち返って考え、資本主義というシステムの本質から、現在、世の中で何が起こっているかまでを、腑に落ちるまでしっかりと解説。また、「企業価値算定」の基本公式を紹介し、「賢い投資家」になるためのコツをも伝授する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「会社の買収」についてなんとなく物騒なことだというイメージだけ持っていましたが、この本を読むとだいぶイメージが変わりました。
株式会社という仕組みが、社会を変える意欲を持った起業家を支援するとともに、それを支援したいパトロンのハードルを下げる役割があり、世の中に活力をもたらすための枠組みとのこと。
ハゲタカファンドがやっている(悪い)買収の意味もよくわかり、そういった外国のファンドに狙われないためにも正しい株価にしておくことが必要で、会社はその成果を正しく株主にアピールする活動が必要ということがよくわかりました。
会社に値段をつけることが正しいか正しくないかではなく、それを正しく算定しておくことが(今の米国ルールにのっとってグローバル社会で生きていくには)大切ですね。
Posted by ブクログ
この濃い講話を自分専用で受けられるとは、極めて良心的。熱いハートとクールな頭と独自の視点で、日本と日本人がアイデンティティを活かしつつ、グローバルな一員として共生していく。筆者は自分と同じ願いを持つが、何と頭の良いこと。
Posted by ブクログ
書かれたのは2005年、ホリエモンが主人公だった年だ。
その後の騒動、リーマン・ショック、東電やオリンパスの経営問題を経たからこそなお知っておかなければいけないことが書かれている。
株式会社というルール、M&A実務、PEファンドなどへの入り口としても優れている。
おそらくメッセージは2つ。
市民へ:銀行に頼るのではなく、市場のプレイヤーとして最大限努力する義務と価値を学んでほしい
経営者へ:株主価値という言葉の真意を理解して、責任を持って経営の決断を下してほしい
ということだろう。
Posted by ブクログ
株式会社は誰のもの?企業価値とは?といったところについて、分かりやすく書いてある。これらに関心がない人がはじめて読むのに適している。この本を読んで、企業価値評価、ファイナンスについて興味が出てきた。
Posted by ブクログ
会社の「そもそも論」を、わかったつもりでいる人に「気づかせる」ようにポイントのみ説明していて、決してファイナンス全般を網羅的に扱ったものではないが、新書の役割というものを十分意識されているいい仕事。ファイナンスというとちょっととっつきにくいという人にも、平易な文章でわかりやすい説明なので、あっという間に読みきれる。
Posted by ブクログ
ライブドアに端を発した一連の騒動。一度冷静に見直してみませんか?
企業価値、株主価値など色々ありけれども、それって一体何?
このような問いにわかりやすく答えてくれます。
学生、ビジネスマンの方にオススメです。
Posted by ブクログ
「会社は誰のものか」という問いに答えてくれる本。もちろん答えを教えてくれるわけではなく考え方をガイドしてくれているのだが、腹に落ちるポイントがいくつもある。
Posted by ブクログ
有名なMBAバリュエーションの著者の本。テクニカルな部分は相当省いて結論のみとしている印象。後半のアクティビズムについての部分はやはり力がこもっていて面白い。
Posted by ブクログ
ライブドアとフジテレビがM&Aをめぐって激しい攻防を繰り広げられていた時期に書かれた一冊。企業は誰のものか、経営者と株主の関係など今後とも日本企業にとって避けて通れないいつものテーマの解説や、M&Aの裏側など興味深い内容が、極めてわかりやすく解説されている。
企業価値を数字で表すことが、フェアなビジネス関係の第一歩という指摘は、言われてみれば当たり前のことだけど、多くの日本人にとって、数字に表せない人間関係や価値に大きな価値を置くなど、まだ違和感があるところなのだろう。
本書の最後でもコメントがあったが、日本企業は全てアメリカ的価値観を正しいと考える必要はなく、むしろ日本的な和や長期的な関係を重視する発想を、グローバルビジネスの中で活かすことこそが生き残りのカギだと思う。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
日本では、「会社買収」に対する違和感を持つ人が多い。
しかし、株式会社というのは、そもそも「会社を売り買いする仕組み」ではなかったのだろうか?
本書は、会社に値段を付ける、ということはどういうことなのかを根本にまで立ち返って考え、資本主義というシステムの本質から、現在、世の中で何が起こっているかまでを、腑に落ちるまでしっかりと解説。
また、「企業価値算定」の基本公式を紹介し、「賢い投資家」になるためのコツをも伝授する。
[ 目次 ]
第1章 なぜ会社に値段をつけるのか
第2章 基本ルールとしての「米国流」
第3章 企業価値の実体
第4章 「会社の値段」で見える日本の社会
第5章 企業価値算定―実践編
第6章 ニュースを読み解く投資家の視点
第7章 M&Aの本質
第8章 日本の敵対的M&A、米国の敵対的M&A
第9章 日本らしい「会社の評価」のために
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
米国的 (1)単純明快に数字で判断するのを好む「経済合理性」、(2)ルール化を大切にする「法の支配」、(3)でたとこ勝負で決断がはやい「スピードは力、時は金なり」
企業価値 = C/(r-g) , C=現在のキャッシュフロー、r=リスク、g=成長性
「企業価値」とは誰にとっての価値か?誰が判断するのか?
「会社の存在そのものに価値の価値、すなわち社会における存在価値」は答えになっていない。会社は仕組みであって目的ではない。
企業が価値を生んでいない場合にその責任が経営者にあるならば、企業価値を創造するのは経営者である。リスクを背負い、厳しい決断を一つ一つ下して、結果責任をとる。この役割を担っているのが経営者であり企業価値の創造者である。
企業価値創造の担い手は経営者であり、その経営者の評価は株主が行う。
PER = 株価/一株当たり利益、
言い換えるとPER = 会社の値段(株式時価総額)/会社の利益
会社の値段 = 会社の利益 X PER
PERという倍率は、(r-g)という現在価値への割引率の逆数と同じ。例えばPER20倍は、(r-g) が5%ということ
外の人たちに、自分たちの考え方、やり方をきちんと説明するのが礼儀であり務め。説明責任。
Posted by ブクログ
1/29/2015 森生先生のfinancial reorganizationクラス受講をきっかけに、久々に再読。ファイナンスで扱うどんなに難しいケースも、実は全て基礎に根付いていると仰っていた。本書は、ファイナンスで抑えておかなければいけない基礎の基礎となる理論からニュースに出てくるような買収や投資家の視点まで、本質をついた解説によって分かりやすく読み進められる良書。「MBAバリュエーション」とセットでいずれも良書。
---
「企業価値」という言葉は日本独特の表現、アメリカ人に言うと、「何それ?」という反応が返ってくるらしい。
本書では、会社に値段をつけることにより資金の流れがよくなり、経済活動が活発になること、そして正しく値段をつけなうと、いかに社会、経済が混乱するかということを論じ、なぜ会社に値段をつけるのか?会社に値段をつけるというのはどういうことなのかを根本まで徹底解説。
この不透明な時代に新しい資本主義のあるべき姿に向けて、日本人が主体的に投資して発展していく将来のビッグピクチャーを示してくれる。
グロービス定量分析松本先生のお勧めの一冊。
Posted by ブクログ
企業価値とは何か?その言葉の意味すること、それをどのように測るのか、ファイナンス基礎についても学べる本。
企業の価値算定の方法を知っていること、その上で経営者目線で世の中の動きを見る視点が大事だということを改めて認識する。
株式市場で起こる株式の取得やM&Aについて、経営者としては、自身の会社の企業価値を適切に把握し、割安/割高であればそれを正しく修正できるよう指揮を取り、株主の利益を上げるための責任を負う。自身の会社の企業価値を常に考えること、それをどのように高めていくのかを計画し説明でき実行できること、購買相手型となる対象の会社の企業価値を適切に把握し、株式の取得やM&Aを行うことにより、企業価値を高めることができるのかを考えられなければならない。
その他、アメリカと日本における株式市場に対する考え方、姿勢の違いなどの背景も知ることができ、学びとなった。書籍の書かれている時と現在とで、日本における株式市場の活況具合も変わってきているとは思うが、特に米国など諸外国と日本とでは価値観や姿勢の違いがあるということもよく理解しておく必要がある。
Posted by ブクログ
株式会社は誰のものだろうか。法的には株主のものであるが、そう割り切ることは難しい。本書では、これに答えを与え、それにより株式会社の値段、価値を算定する。ウエットな部分をすべて切り捨て、アメリカ流の株主至上主義を貫く姿勢には、かなり違和感を覚えた。が、良し悪しを超え、定義に立ち戻った主張は納得せざるを得ない。しかも、「このアメリカ流は、ある方向から見たときの絶対的正しさであり、もしその正しさを受け入れない会社があるのであれば、予め市場に対してその旨を主張することがIR活動でもある」との言には感服した。確かにそうだろう。現金を200億円も持っていて、なおかつ市場価格(株価×株式総数)が100億円なんて企業は、ハゲタカファンドに買われて当然、というか自分が100億円もっていたら買うだろうことこ考えれば、著者の主張は正しいといわざるを得ない。重要なのは道徳的善悪の問題ではなく、このルールに則った経済に我々が乗ってしまっているということである。
Posted by ブクログ
財務諸表の読み方。アメリカ流の株式会社についての考え方。会社の客観的な値段などは存在しない。EBITDA。M&Aの例などから会社の値段を主観的に推測する。M&Aがおこるときは会社の経営権の争奪戦になり、結局争点はどちらの経営者の方が株主価値を高めれるかという問題に還元される。