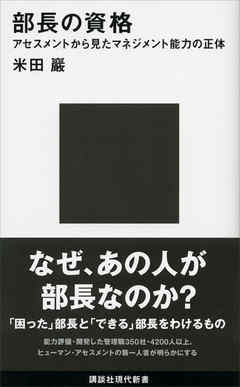あらすじ
世に「困った」部長は「困った」課長以上にあふれている。では、ボードメンバーの一歩前の部長の役割とは? 必要な能力とは? ヒューマン・アセスメントの第一人者として、350社、4200人以上の管理職の能力判定・開発に携わってきた筆者が明らかにする、言動で測れるマネジメント能力の本質。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
①とりあえず、円満至上主義を自覚し、プロセス・スケジュール管理と整理整頓を徹底する
②部長の仕事は改革・創造とチーム力の発掘
③信頼性はコンプライアンスの徹底や規則・ルールの遵守といった基礎的な行動
Posted by ブクログ
日経の広告をみて、スグに書店で購入し、読み切りました。
もちろん、自身が部長ではありませんが、どの様な能力をアセッサーが見定めているのかが、よく理解できました。
ただし、理解したからと言って、小手先の対応だけで済まないということも。
本書で解説している様に、アセッサーは、面接や行動演習などを通じて、対象者の言動特性を観ています。
言動特性は、対象者の今までの生き様がそのまま写し出されるそうです。
自分も数年前に面接方式のアセスメントを受けましたので、受講後のフィードバックで実感しました。
他に本書で感銘を受けたのが、リーダーシップとマネジメントの違いについての解説です。
自分は、今の激変の時代には、変革するためにはリーダーシップありきであり、マネジメントは管理・統制に主眼をおいた受動的イメージと理解してました。
しかし、本書ではマネジメントの包括性・奥深さ、リーダーシップをマネジメントの下位においているということを、冷静に解いており、その論に納得しました。
近年のリーダーシップ論の学者の主張に、自分は少し引っ張られていたかなぁと実感。
また、自身のマネジメント能力開発手法についても、詳細に解説しており、早速試してみようと思いました。
マネジメント能力は、人として他の人達と関わりながら生きて行く以上は、どの様な立場の方でも必要な能力だと思いますので、その部分だけでも必見の価値ありだと思います。
自分にとっては、期待以上の良書でした。
Posted by ブクログ
冒頭からダメ部長のオンパレードで面食らいました(笑)が、ダメ部長への対策というか対処法、部長と課長の役割の異同、そして部長の能力開発について丁寧に解説。特にダメ部長の能力をいかに開発するかを詳述しています。どんなコンピテンシーを伸ばし改善するかなどに説明の力点が置かれていますが、その手法自体には新鮮味なかったので、むしろ部長に求められる役割についてもう少し紙面を割いて欲しかったなと。部長というミドル層のキャリア形成やモチベーション維持は重要性を増しているし、個人的にも関心あるところなので、考えを整理するのに有益な一冊でした。
Posted by ブクログ
部長の価値は落ちていないか、落としていないか? そのような嘆きをよく耳にする。
本書は部長が開発すべき能力を整理している。
まず第1章で「困った部長パターンと対処法」が記されている。
(あーあの人・・・ココで躓いている。あーこれは自分も陥りやすい点だな)などと考えながら読み進めた。
第2章以降から部長の役割、能力、その開発の考え方が記される。
スーパー部長を目指せ!的な内容すぎるために共感は減るが、現実を突きつけているので理解はする。
理解しつつスーパー部長を評価できる上役がいない組織は外部アセッサーの登場となる。
人事部が外部アセッサー並みの能力開発がまず必要だと考えた。
あと360度評価の運用懸念点を確認できたことはよかった。
本書は、部長を目指す人は良いが、部長を評価すべき人がまず理解すべき内容だと感じた。
Posted by ブクログ
アセスメントから出てきた特性から部長タイプの陥りやすい「困った部長」分類が面白い。
「強み」も状況やバランスの持ち方などで「困った部長」に陥る要素もあるということ。
また、「困った部長」から「変われる」というのも大きなメッセージ。
【これからの部長のあり方】
①与えられた部門のにおける取締役執行役の機能を果たす存在であること。(常に自己革新)
②改革のイニシアチブをとり、その主役、推進役を務めること。(改善して守ることではなく、改革し変えて攻めること)
→意思決定力、変革力、目的志向性、挑戦力、ビジョン構築力、戦略設計力、メッセージ力、胆力
③価値創造者として機能すること。
→創造力、倫理力の一部、洞察力、環境認識力、問題分析力、判断力、適応力、顧客志向性
④非常時対応力。
→トップの迅速な意思決定支援
→状況によっては、与えられた分限を超え、自らの責任において統治・命令・調整する気概を持つこと
→迅速な判断、決断、実行指令のための自律性の涵養
Posted by ブクログ
若干、斜め読み気味ですが、「困った部長」の類型を示し、本来、部長はどうあるべきものか、「困った部長」から「できる部長」になるためのマネジメント能力開発を説くもの。興味深く読めました。自分にどう適用していくかが問題だ。
Posted by ブクログ
タイムリーなことに読書中は360度評価の研修を受講している最中。著者の能力開発は何歳からでもできるという信念、言動が評価行動という主張に迷いがなくある種の迫力を感じた。
自己評価が低めの自分にとって、それがリスクになり得ることを自覚しよう。そのために成果や貢献をまず考えることが大事なのは言うまでもない。
Posted by ブクログ
どうしてこの本を選んだかと聞かれれば、上司の事勿れ主義に悩んでいたからとしか答えられないんだよね。ぼくはどうしても彼を変えなければならない。
長という肩書きがつく者は、言ってみれば一家の長と同じ。一つの判断ミスが命取りになるときもあれば、沈没していく船の上でヘラヘラ笑いながら何もせずに沈んでいく。
一家の長がこんなんだとみんなが不幸になる。だからぼくは彼を変えなければならない。ここでは激動の時代の真っ只中の部長の資質について語っているのさ。
まあ、そんな完璧な上司がいたら拝みたいわとか思ったりもするけど、そんな上司にぼくはなりたい。理想の部長像を頭の中に映しておいて、ぼくは反面教師を目の前にして、どんどん理想の上司に近づいていこうと思っているのさ。
みんなを幸せにするためにね。
Posted by ブクログ
マネジメントのヒューマン・アセスメントについての解説書。部長としてどう仕事に取り組むべきかというような自己啓発の書ではない。マネジメント能力はいつからでも開発できるという主張には賛成です。
Posted by ブクログ
部長の資格とは?
→言動特性こそがマネジメント能力を一番正しく反映できる
マネジメントにとって最も重要なのは何を目的とし、そのために何をするかを明らかにする能力
課長とは違い新たな価値創造をしていく必要がある
ビジョンと改革実践のバランスをとるには現場の実践経験が必須
Posted by ブクログ
部下の仕事を考えるときは、その人に与えたときの事業の効果と人材育成の2点から考える。
支援と指示のバランスでリーダーシップのあり方が変わる。
自分自身の自分の能力に対する認識は他人が自分に対する評価よりも高いことが多い。
Posted by ブクログ
チームリーダーと部長の役割の違いを再認識するのに、この本はいい契機を提供してくれる。僕のように部長未満の役職にある人が読んでも十分有用だと思うが、単に自分の上司の粗探しをして独り悦に入る、などという使い方は避けるべき。個人的には以前受けたコーチング研修の良い復習になった。
Posted by ブクログ
アセスメント専門家(はじめて聞いた職種)の米田巖さんの部長評論。
テーマは面白いし、世の中の部長のあるある本が狙いなんだろうが、少し偉そうな感じがするんだよな。
いわゆる、上から目線というやつ。
こういう本は著者のような年配の人が書くとどうも理想論で説教臭くなるよな。
テーマは面白いので、同じテーマで課長クラスの若い年代の人があるあるを書くと面白いんじゃないかな。