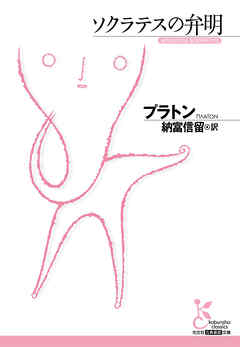あらすじ
ソクラテスの生と死は、今でも強烈な個性をもって私たちに迫ってくる。しかし、彼は特別な人間ではない。ただ、真に人間であった。彼が示したのは、「知を愛し求める」あり方、つまり哲学者(フィロソフォス)であることが、人間として生きることだ、ということであった。(「訳者あとがき」より)。ソクラテスの裁判とは何だったのか?プラトン対話篇の最高傑作、ついに新訳で登場!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
3人のソフィストたちによって告発されたソクラテス。
弁論に長けたソフィストたちを対話によってその矛盾を突き、自身や社会、あるいはこの世の全てを知らないと思うソクラテスの営みこそ彼自身が裁判にかけられることとなった理由である。
もちろん、「弁明」とはその裁判におけるソクラテスの主張のことであり、ソクラテスは当然これらの容疑について善きものであると捉え、憎まれていることこそが真実を語っている理由であるとしている。
古典的名著である作品は多くの分析がなされ、その重要点についてあらゆる箇所で論じらている。私は自身が印象に残った点を取り上げたい。
ソクラテスがいかに論じることでその矛盾をついたのか
ソクラテスは裁判の告発者の1人であるメレトスが、
「ソクラテスこそが若者を堕落させた」、その容疑として告発を行ったという旨の主張に対して、このように弁明、論駁するのである。
以下引用、
「馬の場合でもこういうことがあると思うだろうか。馬をより善くしているのがすべての人間なのに駄目にしているのは一人だけだ、ということか。それとも、まったく逆で、馬をより善くできるのは一人か、あるいはごく少数の者、つまり馬の調教師だけであり、他方で、多くの人々は馬と一緒に過ごして取り扱っていてもそれを駄目にしてしまうのではないか。」
ソクラテスの死生観は決して主題ではないが、魂の善い悪いという思考の軸に基づいた死生観は合理的であり、「私は何も知らないと思っている」(俗にいう「無知の知」、著者はこの表現を否定)からこそ生まれる希望的観測が興味深い。
以下引用、
"死が善いものだという大いなるに希望があることを考えてみましょう。死んでいる状態とは、次の2つのどちらかなのです。無のような状態で、死んでいるものはなんについても何一つ感覚を持っていないか、あるいは、言い伝えにあるように、魂がこの場所から別の場所へ向かう移動や移住であるか、このどちらかなのです"
"もし夢さえ見ないような深い眠りに就いているそんな夜を選び出して、自分の人生で過ごしてきた夜や昼と比べてみて、この夜よりも善く快い昼と夜を自分の人生においていくつ過ごしてきたかを考えて言わなければならないとしたら、どうでしょう"
また弁明の最終盤、判決後のコメントにおいては自らの息子(実際の息子を指すものか、あるいは弟子たち(プラトンら)を指しているかは不明、著者解説より)たちが金銭やその他のものに執着をしたり、自らを大層な人物だと勘違いしていた時には、ソクラテス自身がアテナイの市民、皆さんに論駁をしていたと同様に仕返しをしてほしいと願っている。
これは私たちが哲学という営みと付き合い続けている以上、私たちに課せられ、同時に私たちが吟味されるということではないだろうか。(著者解説にも同様の記述あり。)
肉体のうちに秘められた魂に私たち自身も反省をして、見つめ直すことで自らや現代の社会がどう映るだろうか。その営みを体験できるのは、ソクラテスではなく私たち自身である。
ただし、いささか疑問点も残る。無知であることを自覚する、無知であると思っているとするソクラテス。何もしらないということはすなわち善いことであるのだろうか。仮にソクラテスが何も知らなかったとするならば、神という存在をなぜ認識できたのだろうか。なぜ「弁明」においていわば客観的に自らが恨まれていることは真実を語っているかであると述べることができるであろうか。知らないということを知ろうとするための営みは、一見ソクラテスの主張を顧みれば反比例のグラフを描くのではなかろうか。何かを知ろうとする営みが増えれば増えるほど、知らないという認識度や解像度が増していく。しかし、知らないという認識を増やすということは知らないことを知ることの蓄積でもある。「知らない」というスタンスは何かを生み出すのだろうか。
現代日本に生きる我々は強く、そして根底に当たり前のように資本主義経済のもとで生活をしている。我々が当たり前のように受ける義務教育も資本主義を否定するものなど当然ない。私も決して資本主義を否定するつもりはない。しかし、ソクラテスの主張はいわば資本主義を否定するものではなかろうか。
自らの息子たちが、大層な人物であったり、私利私欲にまみれ自らの財産を求めるようになった際には、自身が行ったように論駁を行なってもらいたい、と願ったソクラテス。
我々が当たり前に生きる社会でこれを否定、論駁することは難しいだろう。民主主義と資本主義は相容れるものであろうか。
またソクラテスの主張は、のちにマズローが提唱した欲求階層説との矛盾を孕む。どちらが正しいといった議論を図りたいのではなく、その差異を示したい。近年、自己承認欲求といった言葉ばかりが若者を指す言葉として一人歩きしているようにも思えるが、この階層は生理的欲求、安全と安定の欲求、所属と愛の欲求、自尊と承認の欲求、自己実現の欲求と続いていく。ソクラテスが選んだ選択はこれに反しているのではなかろうか。
そして、私はソクラテスとメレトスのやり取りにもはや感銘を受けるほどである。それは真っ当な議論が成立しているからである。国会における答弁は今に始まった事ではないが、問いに対して正面から回答しているのだろうか。国会だけではない、我々自身もである。都合が悪い時、議論において劣勢になった際に、関係のない過去のことを掘り下げる、議論をすり替える、またとにかく論破こそが議論における勝利であるといった風潮。議論というようなものは自身を磨く行為でもあるはずである。ディベートといったものは、どちらを説得できるのかといったビジネス的要素もあるが、他人を人格否定したり、根底を覆して議論から逸脱を図った上で勝利を目指すものではないはずである。
我々はなぜソクラテスを最初の哲学者として扱うのか。受け身ではなく、能動的に捉えてはいけないだろうか。