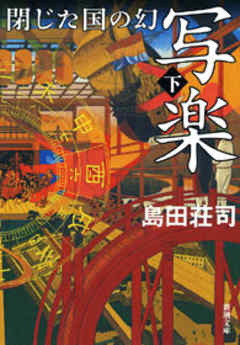あらすじ
謎の浮世絵師・写楽の正体を追う佐藤貞三は、ある仮説にたどり着く。それは「写楽探し」の常識を根底から覆すものだった……。田沼意次の開放政策と喜多川歌麿の激怒。オランダ人の墓石。東洲斎写楽という号の意味。すべての欠片が揃うとき、世界を、歴史を騙した「天才画家」の真実が白日の下に晒される──。推理と論理によって現実を超克した、空前絶後の小説。写楽、証明終了。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
佐藤と出版社の常世田たちが、写楽は誰かの考察を進める中、オランダ商人の記録の写しをオランダで入手した片桐教授のお陰で、写楽は外国人という説が一気に可能性を帯びてくる。
一方、江戸編にて当時の状況長崎に滞在していたオランダ商人が参府した際の蔦屋重三郎とのやりとりが描かれ、ぐんぐん引き込まれてしまった。
写楽は誰かという議論や当時の江戸文化など、興味深い内容満載で、特に江戸編が面白かった。
大河ドラマの"べらぼう"をフォローしていなかったが、今更ながら、少し興味が湧いてきた。(笑)
Posted by ブクログ
2013/5 初読時のメモより
作者が提示した、写楽の謎:写楽が誰にせよ(既に知られた人物の変名にせよ)何故出自などが全く伝わって無いのか、接触していた筈の周りの人々が写楽について何故なにも語っていないのか。写楽はオランダ人だったという仮説は、これを合理的に説明していると思う。役者絵は、ブロマイドと芝居の宣伝を兼ねるものなのに、写楽は本来対象にならないような端役も描いていたという事も本作で初めて知った。
Posted by ブクログ
生き生きと描かれる400年ほど前の江戸町人に、羨ましさを感じる。著者の作品は初めて読んだが、歴史考証が飽きずに読める筆力。重くなりがちな歴史的な謎を、写楽作品への想い入れを消すことなく、娯楽作品として描いておりワクワクしながら読むことが出来た。他作品も読みたい。
Posted by ブクログ
多分外人なんだろうなーと思わせる個所はあったので、正体には然程驚かなかったものの、こういう解釈を持ってくるのが凄いなぁと。
実際のところどんな風に落としているのかな??
美術史研究の面白さを見つけられた本だった。
正直ラストはもうちょっと食い込んで欲しかったけど。
Posted by ブクログ
このミスベスト10、2011年版2位。作者もあとがきで書いてるとおり、現代編は全然中途半端だし、途中退屈な部分が続き全体のバランスも悪く小説としてはダメなんだけど、作者が長年あたためてた、写楽が誰かについての新説にはとても説得力があるし、仮説にもとづいた江戸編は小説としてもしっかり書き込まれてて、無茶苦茶面白い。後半はなんだかすごく泣きました。ただ、前半は現代編の方がやや面白いが写楽の説明が長く、江戸編は時代の背景説明に終始ばかりでしんどかった。この本が出た1年ぐらいあとに、NHKのドキュメントで長年謎であった写楽が誰だか分かったって言いきってる番組があって、それ観た記憶があったから、こっちの説は学者さんとかには相手されてないってことなんかなーと不思議でした。当時はNHKのドキュメントで結構新説をバシバシ取り上げて言い切ってる番組あって、NHK強気だなって思ったりしたけど。まあ、この本の続編も出てないようだしやっぱあかんかったのですかね。
Posted by ブクログ
そこで終わりますか!感がすごかったです。
江戸編の描写は好き。
高橋克彦や夢枕獏の同時代の作品を読んでると特に。
現代編はどうも煮え切らない感じがな~。
子供の事故とか夫婦仲とか謎の美女あたりが消化しきれなかった感じ。
最初の切っ掛けになった絵もなんだかうやむやだし、それに対する教授の態度も微妙だし。
続編あるのかなぁ…。
Posted by ブクログ
写楽はオランダ人のスケッチをベースに浮世絵の工程に載せたものだった。なるほどと思わせる推論は楽しめる。ただその推論と、並行して流れる江戸時代編が長くなりすぎて、もともとあった、子供の事故の裁判、主人公夫婦はどうなる、など宙に浮いたトピックも多い。続編が出てくる気もする。
Posted by ブクログ
東洲斎写楽の正体に迫った歴史ミステリー。
鎖国であった当時の江戸文化の様子、歌麿や京伝、そんな絵師などを取り仕切る蔦屋重三郎たちの交流の様子がとても良く伝わって来る。
そして描き出される写楽の正体。
「閉じた国の幻」まさのこの副題の通り、閉じられかつ規制された不満が高まっていた時代に、蔦重を中心に国内外関わった全ての者たちが紡ぎ出した幻こそが写楽だったのだろう。
と面白かったのはこの作中にある「江戸編」まで。
正直「現代編」はいらない、江戸編の合間に解説があるだけで良かった。
説明を兼ねているが物語にしてしまったために冗長過ぎてわかりずらい。
回転ドア事件も風化させてはいけないという思いはあろうが、それはそのテーマで書けば良いわけで、写楽とは一切関係ない。
この現代編のせいでものすごくつまらない物語になってしまった。
だって江戸編、全体の3分の1もないぐらい短いから。
江戸編が非常に感動できる物語なだけに、ただただ残念。
(下)で正体に迫るので、江戸編もそれなりに分量があったので(上)より楽しめた。
江戸編だけだったら間違いなく★5つだった。
Posted by ブクログ
<下巻あらすじ>
【江戸編Ⅱ】
蔦屋重三郎が写楽の絵に出合う
【現代編Ⅲ】
佐藤は様々な調査を経て、写楽=平賀源内ではなく
オランダ人ではないかと推察する
【江戸編Ⅲ】
ラスというオランダ人が写楽の正体だった
【エピローグ】
佐藤は、オランダとインドネシアのハーフでオランダ商館の館長を務めた
ウィレム・ラスが写楽の正体だと結論し本を執筆することにした
おわり。
【後書き】
著者が本作の執筆過程を語る
【オランダ商館長の江戸参府日記】
著者が本作を書くのに参考にした実際の日記(13P)
<オチ>
回転ドア事件は訴訟とか一切進展せず棚あげ
話の発端となった肉筆画も写楽じゃない?みたいな話のまま棚あげ
佐藤が本を書くぞ!ってとこで突然おわり。一切完結していない