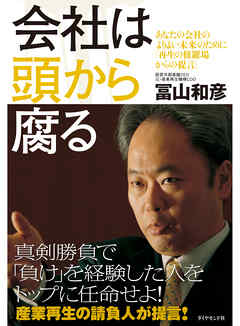あらすじ
産業再生機構で41社の企業再生の陣頭指揮を執った著者。再生の修羅場には経営の本質が見えてくる。経営の悪化した企業に共通していたのは、「一流の現場を持ちながら、経営が三流だった」ということ。そもそも経営者を選ぶ仕組みに問題を抱え、相応しくない人がトップに立っているという悲劇をまざまざと経験する。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
冨山氏の名著
経営、人間ドラマのリアルが描かれており素晴らしい。
自身も出向経験があるだけに共感できる部分なども一部あった。
メモ
・ほとんどの人間は土壇場では各人自身の動機付けの構造と性格に正直にしか行動できないという現実。
・腹落ちするコミュニケーションの重要性
・余計なことを考えず、ひたすら何をやらなければならないのかを整理する。合理的に必要最低限の人間と的確な能力と動機付けを持つ人間を揃え、しかるべき役割ときて権能を名実ともに与えて、マネジメントできれば本部機能は少人数ですむ。
・一人の人間も集団としての組織も、インセンティブと性格の奴隷である。
・私たちの判断や行動は情理に支配されている。
・いかに組織の人間を組織目的、戦略目的に整合する方向で勇気つけ、動機づけるか。
・市場や競争状況は頻繁に変わるが基本的な経済構造は実はあまり変わらない。
・将来に向けた戦略は予測できない状況変化の察知能力、適応力、戦力の柔軟性。みたい現実でなく、ありのままの現実をみられるか。
・戦略的自由度を大きく変える意思決定が重要となる。店舗を出店するかどうかなど。
・情理は日常の小さなところから、実践していくしかない。
・ガバナンスとは究極的には人間に対するリアルな影響力。自らをリスクに晒さなければその統治力は現実の影響力にはならない。
・一部のエリートが計画的にものを考えよりも、それぞれが自由に考え、自由にお金と人が結びついた方が効率的。社会主義と資本主義経済で実証されている話。
・リーダーに必要なのは人間性✖️能力=人間力。そのベースにあるのは一人一人の市井に生きる人々の切ない動機づけや喜怒哀楽というものが理解できるか。
・
Posted by ブクログ
筆者は、ボストンコンサルティングや産業再生機構で豊富な実務経験をお持ちの冨山和彦氏。著者自身、本書の中で「経営と事業のリアルな本質を語れるものは企業価値や資本政策を語るべからず」と述べられており、実際の現場経験をベースに書き綴っている内容にとても説得力を感じます。
組織を動かしていく上で、筆者が重視する視点の一つとして、「人間の弱さ」が挙げられている。人間は物事を認識する際、「見たい現実を見る」生き物とのこと。「性弱説」に立って人間を理解すれば、社会、組織の多くの現象が理解可能になる。そして、そのような現実にこそ、経営や組織がとんでもない過ちや腐敗を起こす根源があると述べています。
「現場にいる人たちのパワー」の重要性にも触れています。「経営とはとにかく人である」と言い切っておられます。細々した職務規定や指示命令なしに、自発的に働く現場人材の存在が求められる。そのため、小賢しい組織論やスキル論なんかよりも、人間集団に対する動機づけが必要とのこと。この部分が、リーダーシップの一つのポイントなのでしょう。筆者も、産業再生機構のご自身の経験を引用し、「合理」だけでなく、「情理」も踏まえたマネジメントの重要性を指摘しています。
官僚機構の問題点を指摘した部分では、「相互安全保障」を目的とした会議や根回しの業務量は人と人との組み合わせの数に応じて増えていくこと、スタッフ部門が超多忙な状況では、管理職や中高年オジサンの頭数は思い切って減らした方が業務遂行能力も意思決定のスピードと的確性も向上するなどと書かれています。思い切った意見ですが、現在社会のパラドックスの一面かもしれません。
私が個人的に注目した部分に、チームのメンバーの役割に関する記述がありました。筆者は産業再生機構で行っていた「再生の仕事」は「戦時」であると述べています。そして、極度の緊張感がある環境下で、他の職員に業務にも理解を求め、自分の専門外とする態度を認めないようにしたといいます。なぜそのように決めたかというと、仕事が佳境に入るほど専門家はプロであろうとし、チーム内に衝突を生むためだそうです。ただ、それぞれの専門家は壁を破るべく、猛烈な勉強をする必要があります。
私たちは組織の中で働きながら、社会を考えています。筆者は、自己益(=一人ひとりの動機づけ)、組織益(=企業組織として動機づけられている方向性)、社会益(=社会全体の有する動機づけ)がシンクロすることが重要であると述べています。「経営者は飲み屋での話題が昔の自慢話になったら引き際かもしれない。ゴールのない経営に自慢や答えがあるはずがないのだから」と書かれています。経営は本質的に絶え間ない努力が不可欠であり、そのためのリーダーシップが求められているのではないかと考えらさせられます。
本書の後半はリーダー論ですが、とても興味深く有意義な学びの時間を得ることができました。また、いつか、自分の立場が変わってから読み直してみたいと思う一冊です。
Posted by ブクログ
あたりまえのことをあたりまえにやることが大事。でもそれが難しい。
所詮、「競争ごっこ」。覚悟・決心は、生温い中からは生まれてこない。