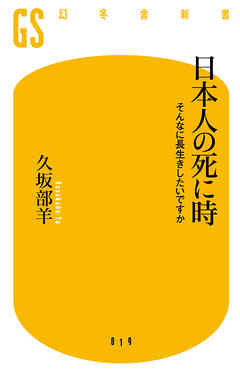あらすじ
何歳まで生きれば“ほどほどに”生きたことになるのか? 長寿をもてはやし抗加齢に踊る一方で、日本人は平均で男6.1年、女7.6年間の寝たきり生活を送る。多くの人にとって長生きは苦しい。人の寿命は不公平である。だが「寿命を大切に生きる」ことは単なる長寿とはちがうはずだ。どうすれば満足な死を得られるか。元気なうちにさがしておく「死ぬのにうってつけの時」とは何か。数々の老人の死を看取ってきた現役医師による“死に時”のすすめ。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
久坂部 羊さんの小説、新書を最近読んでいるが、この本は2006年に出版された本です。
書かれたこの時は、51歳でした。
高齢者医療にずっと携われてきて、人間の死、特に高齢者の死に多く関われてきての執筆活動です。
1955年生まれなので、私より6歳下で、70歳だと思います。
興味があったのは、51歳の時の執筆内容と現在の執筆内容との違いについてですが、主張されている本筋はまったく変わっていませんでした。
今回この本を読んでよかったのは、9月20日に76歳になる自分自身のしっかりとした「死生観」「諦観」を確立しなければならないと思ったことです。
内容ですが、
第1章 長生きは苦しいらしい
第2章 現代の「不老不死」考
第3章 長寿の危険に備えていますか
第4章 老後の安住の地はあるのか
第5章 敬老精神の復活はかのうか
第6章 健康な老人にも必要な安楽死
第7章 死をサポートする医療
第8章 死に時のすすめ
がんを受け入れて死んだ医師
死の達人・富士正晴氏の場合
死を拒否する人の苦しみ
現代のメメント・モリ
病院へ行かないという選択
寿命を大切にするということ
死に時のすすめ
おわりに
でした。
介護保険制度が出来、日本の医療費は鰻登り。
資本主義制度が基本の世の中、節度ある経済活動が必要です。
国として、堂々としっかりとした「死生観」「諦観」を養う教育が求められるでしょう。
しっかりとした「死生観」「諦観」を身につけていない人間の欲望に起因する諸行動から派生する医療経済活動、薬屋もマスゴミも健康産業屋さんもエエ加減にしなくてはなりません。
高給厚生労働官僚が天下っている業界に向かって規制することは不可能でしょう。
騙す方も悪いですが、騙されないようしっかり勉強する必要があるということです。
原因があって結果です。
まぁとにかく、自分自身は残りの人生、しっかりとした「死生観」「諦観」を養い、般若心経の極意に従って、その時を迎える準備に勤しむことにいたします(感謝)。
Posted by ブクログ
日本人の平均寿命が世界第一位であることは有名ですが、平均で男性は六年、女性は七年、最後は要介護状態になるという数字が出ているそうです。私の父方の祖母もパーキンソン病を何年も患い、胃ろうでした。最後の数年は精神的にも不安定だったことが母の日記から読み取れます。死ぬ時期や死ぬ要因は自分で選べないことがほとんどだと思いますが、延命治療は残される人たちの思いのために施されるべきではない、という一文を憶えておこうと思いました。
Posted by ブクログ
人の、少なくとも俺の生き方にまで影響しそうな本。残されたリソース(金、時間)をどう使っていくか。死ぬ事、老いる事を避けるより、日々を大事に生きていこう。ジタバタするなよ!
Posted by ブクログ
長生きはそんなにいいことばかりじゃないよと、悲惨な事例や老人の嘆きがこれでもかというほど紹介される。著者は、老人医療に携わる現役の医師だ。医者の口から、「医療によって無理矢理生かされることは、本人のためにならない」という言葉が聞かれようとは。
アンチエイジングや「スーパー老人」報道に批判的なことなど、著者は現代の欲望肯定主義や、若さを追い求める風潮に違和感を持っている。医師として多くの老人、多くの死を看てきたことも大きいだろうが、同時に、父親が仏教や道教に造詣が深いことや本書でも兼好や良寛を引いていることからして、著者自身が東洋的な死生観に共感を持つ素地があるんだろうという気もする。その意味で、少なくとも我が日本では、本書のような考え方が庶民の間に復活することは、存外たやすいのではあるまいか。
医師の中で著者のような考え方を持つ者がどれくらいの割合でいるのかは、知らない。だがゆくゆくは多数派になるんじゃないか。そうなってほしい。著者のような医師となら、治療方針についてスムーズに相互理解が図れる気がする。自分の「死に時」を看てもらいたいと思うのだ。
Posted by ブクログ
同感。最近はなかなか簡単に死ねない。
医者は病気を治療することに一生懸命になりすぎて「死」に対しては考えられてこなかった。
PPKがいかに難しいことか思い知らされる。
本人の意思ではなく周りの自己満足で無駄な引き伸ばしをされるほど辛いものはない。
末期になるまで症状がなく手遅れでパッと逝きたい。
Posted by ブクログ
久しぶりの久坂部羊さんです。2003年「廃用身」でデビューされたお医者さん。衝撃でした!今回は「日本人の死に時」(そんなに長生きしたいですか)2007.1発行です。タイトルは過激ですが、いつもながらの歯に衣着せぬ書き方に誠実さと読者(患者)への思いやりを感じます!いきなり、初体験の長生きは苦しいらしい から始まります(^-^)老眼、ハゲ、白髪、しわ、シミ、入れ歯、口が臭い、耳が遠い、腰が曲がる、もの忘れはまだ序の口、排泄機能の低下、筋力の低下(何もできなくなる)、不眠(眠るにも体力がいる)等と。(続)
Posted by ブクログ
昔から引退後の生活を見据えていまを犠牲にするという考え方に違和感があり、いつしんでもいいやと思ってテキトーに生きてきたが、それでも「上手く、しに時にしぬ」ことがいかに難しいか知らされるだけで果たしてラクな臨終を迎えることができるのか不安になる。もっともな主張とそれを裏付ける豊富な臨床例、構成もまとまっていて非常に読みやすかったです。ひさびさに新書でアタリだった気が、、、
Posted by ブクログ
やはり、衰弱して老死。が、一番幸福なようだと改めて思った。
私の家族で、病院で死んだ人がいないため、実は病院で死ぬとはどんなことなのかを知らなかった。無理やり生かされる、というのがどんなにつらいものなのか。よくわかった。
私の曽祖父・祖父ともに、自宅で看取った。二人とも幸せな最期を過ごせてよかったのだな、と今になって思える。
ただ、自宅で看取ってもらいたい人は、「家族」を大切にしなければならない。愛してもいないものを、たかが「家族」という繋がりだけで面倒を見ることができるわけがない。
病院で死にたくないと思う人が増え、家族を大切にする人が増えてくれればいいと思う。
Posted by ブクログ
高齢の母がコロナに罹って入院し、医師から万が一の時に延命治療を望むかと聞かれた。3年前に脳梗塞を患い、左手足が不自由ではあるが、週3回のリハビリには通っているし、ヘルパーさんの助けを借りながらも1人暮らしができていた。「私は100歳まで生きる」と日頃から話す母だったので、母と万が一のことなど話したこともない。とはいえ、いずれ確実にその日は訪れる。
老い、その先の死についてさまざまな事例を示してくれた。死に時を自分で決めて、悔いのないように生きるという考え方は参考にしたい。
Posted by ブクログ
この手の本は初めて手に取る。知識ゼロ状態で読むには、ちょうどいい本だった。
・死生観は、これまでは先に持つことで今を一生懸命生きれるという使い方だったが、本当の言葉そのままに「どのように死ぬか」という視点でも押さえておくべきだなと思った。いわゆる終活。
・なるべく長く生きたいと思っていたが、健康寿命を長くしたい、ということなんだな、と自己理解が高まった。ある意味甘かったなあ。
---
・長寿は反対、天寿なら良い。健康寿命までを人生と捉えてそれまでにやりたいことはやっておけ、それ以降は抗わず死んでいけ。という論。
・なぜならただ生き延びるだけの生き方は、本当に悲惨だから。精神的、体力的、社会的に、辛いよ。という見地から。看取りをやってきた医者からの提言。
Posted by ブクログ
私はそんなに生きたくないです。
だから書いてある内容には大賛成で、
その時が来たら無理に延命する必要はないと思っている。
こういう本って基本的に
「生きられる限り何をしても生きる」って思っている人は
手に取らないんじゃないかね。
そもそも、寝たきりになっても管がいっぱいつけられても
できる限り生きるっていう“問題”を作り出すのは
無理して生きる必要がないと思う人間の意識であって・・・
難しいね。で片付けちゃいけないけど、
とりあえず、難しいね。ということでまとめます。
Posted by ブクログ
いろいろと考えさせられる著作だった。
延命治療が必ずしも本人のためになっていないどころか、逆に本人を苦しめることになっているとは。
身内の死はもちろん、自分の死に時を真剣に考えなきゃいけないと思った。
Posted by ブクログ
私も安楽死を認めることに賛成。治癒する可能性の低い病気に罹って、耐えがたい激痛や不快感に苛まれた場合は、行使する権利が欲しい。どうしても死に関する事柄はタブー扱いされてしまうけど、これから更なる高齢化社会を迎えるのだから安らかに死をむかえる為の研究や法整備が益々必要になってくるはず。世の中誰もが健康な老人で人生を楽しんでいる訳ではないのだから、PPだけじゃなくKのケアが重要だよね。
Posted by ブクログ
メメント・モリ。後延ばししない。治らない治療はしない。
廃用身に通ずる考え方。現実的だし、私は支持するけれど。日本のマスコミ的にはNGみたいね。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
何歳まで生きれば“ほどほどに”生きたことになるのか?
長寿をもてはやし抗加齢に踊る一方で、日本人は平均で男6.1年、女7.6年間の寝たきり生活を送る。
多くの人にとって長生きは苦しい。
人の寿命は不公平である。
だが「寿命を大切に生きる」ことは単なる長寿とはちがうはずだ。
どうすれば満足な死を得られるか。
元気なうちにさがしておく「死ぬのにうってつけの時」とは何か。
数々の老人の死を看取ってきた現役医師による“死に時”のすすめ。
[ 目次 ]
第1章 長生きは苦しいらしい
第2章 現代の「不老不死」考
第3章 長寿の危険に備えていますか
第4章 老後に安住の地はあるのか
第5章 敬老精神の復活は可能か
第6章 健康な老人にも必要な安楽死
第7章 死をサポートする医療へ
第8章 死に時のすすめ
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
サブタイトルに「そんなに長生きしたいですか?」
「アンチエイジ、バンザイ!」な現代に、死に際の「美」だって捨てたもんじゃないと説く。
「死」という言葉をひたすら忌み嫌うのじゃなく、安らかな死、幸せな死だってあるんじゃないかと提案。多くの老人介護に接する現役医師だからこその説得力がある。
考えたら、人間の最後の目標って、自分にも周囲にも迷惑をかけずに死ぬことじゃないか。
Posted by ブクログ
久坂部さんの今までの小説をすでに読んでいるなら、もうわかりきったことが書かれている。『破裂』や『廃身用』なんか特に、彼の考え方が如実に表れているんだと、改めて実感した。いくら長生きはできても、寿命は決して変わらない、という事実にはハッとさせられた。寿命を迎えてから医療にすがった長生きは、死んでいる身体を無理やり生かせているだけ。長生きすればするだけ、1つずつ何かを諦めていかなくてはならない。例えば歩行。そして飲食。そして意思の疎通。何を諦めてでもいいから生きたいかを、意識しておかなくてはならない。気づけば心臓が動いているだけ・・なんてなりかねない。一度病院に頼ったら最後。まず、自然な死を迎えることはできない。病院へ行かないという手段は、選択の1つのうちに入れておくべき。
Posted by ブクログ
ぶっちゃけ読んでて楽しい本ではない。けど、読む価値はある。特に年配の人ほど。
長生きして、体のあちこちに障害がある人、寝たきり状態の人、痴呆患者、など色んな人達(及びその家族)がどれだけ苦労しているかを書いた本。「長生きしたい」と何も考えずに求めることがどんなことか考えさせられる。
Posted by ブクログ
人がどう生きるかはそれぞれの人間だけが決められる、というのが近代社会の大原則なのだが、どう死
ぬかは死期が近づくと、実質的に自分では決められなくなる。
今の何がなんでも延命、アンチエイジングという「とにかく生きさせる」行政・医療・介護全体の方針
は、死が絶対に避けられないものである以上、本質的にムダな部分を含んでいるのに、生きたいという
それ自体は当然の欲望を煽り利潤化する資本主義にばかり貢献して、実質的にそれぞれの人の生を決め
る権利を奪っている。
スーパー老人、元気なお年寄り、あるいはその逆の極端な例ばかりメディアは取り上げるな。
「普通に死ぬ」ことは、今では健康年齢と肉体年齢にどうしてもタイムラグを生じ、その間の生死の権
利を奪われているに近い。
というのが筆者のだいたいの主張。
考えなければいけないことだが、考えるには憂鬱なテーマ。第三者の医者だから言えるんだよ、という面もある。個々人の生は周囲の人間の生ともだぶっていて、切り離せるものではないので、どうしても基準化・ガイドライン化とそぐわないのが難しいところだが、難しいで止まっていて、議論の手がかりもない、とにかくたとえば無条件で安楽死は許されないのが日本。
自分一人だけで生きているのだったら、そんなに迷わなくて済む気がするが。
Posted by ブクログ
ずいぶん前に読んだんだけど、何となく内容を思い出してしまい、つい読み返してみる。長生き(し過ぎること)をリスクとして捉え、けして後ろ向きではなく、あくまで前向きに生きていくための方法が書かれていて、なんだか納得してしまう。人生を逆算して考え、今をどう生きればいいか…。サブタイトルがなんだか妙にしっくりきます。
Posted by ブクログ
怖さと荘厳さを兼備した鮮烈なタイトルだと思います。新書でこの内容が読めるのはありがたい。
この副題の問いについてはつねに自問していく必要がある気がします。
Posted by ブクログ
何かを選ぶということは、それ以外のことをあきらめるということです。
まわりの介護の熱心さー介護される本人がもともと立派な人であった 自然な敬意を呼び起こすのは、やはりそれに値する態度でしょう。思慮深さや、自己抑制、謙遜や達観など
家族の同意があろうがなかろうが、安楽死はすべて違法だということです。また本人の同意があっても、刑法202条の自殺関与罪、同意殺人罪が適応される。
文明は進むばかりが能ではありません。人間を幸せにしないのなら、ある部分を棄てることも、また文明の智慧であるはずです。
死に時が来たときに抗わないことが一番楽です。受入れる準備さえできていれば、心も穏やかになれるでしょう。