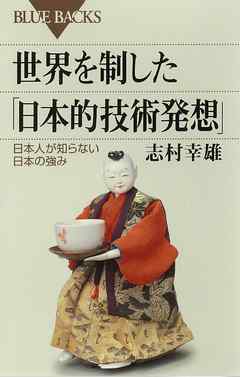あらすじ
日本が「ものづくり大国」となったのは、決して「手先が器用で勤勉だから」だけではない。独自の「技術」を生んだのは、どの国にも真似できない独自の「発想」であり、それを培った「文化」だった。「ものまね大国」と批判するだけでは見えてこない、オリジナリティあふれる発想がなぜ生まれ、どう技術に生かされているのかを検証し、これからの日本が進むべき針路を見出す!※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
世界を制した「日本的技術発想」
日本人が知らない日本の強み
ブルーバックス B1622
著:志村 幸雄
紙版
太古から技術大国であったニッポンはいまも健在であることということを誇る一冊
技術とモノづくりに関する、日本人が意識していない日本人を語る
こういう本なら、いくつかあってもよいと感じました
読んでいて、自分が日本人であることを誇ることが出来る内容でした
気になったのは、以下です
・本丸の技術要因はしっかりしていても、それを取り巻く、非技術要因にむしろ、問題が多い
・技術とは、いうなれば、アイデアや着想を、もの、に転換する方法論である
・伝える機能を超えた使う機能:日本の携帯電話の最大の特徴は、多機能化と複合機器化である
・心機能の付加こそが差異化を図る最前の手段と考えている
・死の谷:基礎研究と、製品開発の間にある研究成果の移転を許さない壁のこと
・日本文明は、手の文明:情報化社会の到来が喧伝されるあまり、ものをつくる、技術に必ずしも正当な評価が与えられていない
・人間は本来、知恵のある人=ホモサピエンス、であると同時に、工作する人=ホモファーベルである
・ものづくりの3要素といえば、事物の定義、定理の基本である「科学」、設計の概念を提供する「技術」、実際の製作の手段・手法である「技能」である
・技能は、一般的に、生産過程で人が発揮するワザとしてとらえられている
・あくなき、精緻、精密、の追求
・基礎研究で弱く、基礎技術に強い
・ストロング・カントリーになるためには、ストロング・マシンツール(機械をつくる機械)を持たなければならない
・工作機械の数値制御(NC)化とマシニングセンターの開発で世界最強の地域を築き上げた
・平安の世から、小さきものへのこだわり
・枕草子:うつくしきもの、「なにもなにも、小さきものは、皆うつくし」
・「軽薄短小」半導体やコンピュータなど高技術・高付加価値型の新産業を読んだもの
・詰める、取る、削る、引き寄せる、込める、折り畳む、握る、寄せる、捕らえる、凝らせる、これを「縮み志向」という
・軽薄短小な文化、縮み文化:俳句、石庭、盆栽、茶室はどれも、「縮み文化」だ
・ボータブルラジオ、電卓、が現代の縮み文化
・世界市場を席巻する産業用ロボット
・日本はものまね大国なのか、すべて模倣と決めつける不条理
・模倣から独自の技術、新規の発明に至るもの、日本の伝統的な文化の中で育まれた 守・破・離
・タカジアスターゼ、アドレナリンの高峰譲吉、「戦艦を作る金があったら、研究所をつくれ」
・日本の強みは、民生技術に特化したことで軍事技術に匹敵するような高度化がなされた 技術のデュアルユース、軍事技術と民生技術
・日本人の完全主義信仰、顧客第一主義という思想
・今なお、日本人が信奉する、「完全良品主義」 設計段階から品質を作り込むことで、最高の品質水準が保たれるようあらゆる努力が払われる
・顧客第一主義に加えて、サービス・イノベーション 使いやすさ、人との親和性、便利さ、サービス性、完全性、確実性、安全性を追求
・日本人は新しいものが好き 新しいものに期待する
・価格の引き下げに最大の努力を傾注し、だれもが、容易に入手できる価格にしてしまう
・日本人は、自然共生型の思想、対して、西洋人は、自然を客体とみなす二元論の思想
・環境への取り組みが企業価値を決め、生き残りの条件になる
目次
第1章 日本的技術発想の突破力
第2章 「発明」と「商品化」のあいだ
第3章 ものづくりに宿る「軽薄短小」技術
第4章 からくりをロボットに変える「合わせ技」
第5章 模倣を超える「工夫力」と「考案力」
第6章 軍需に頼らない「民需王国」
第7章 一億人の「わがままな消費者」
第8章 基本機能になった「環境」「安全」
第9章 技術文化国家への道
ISBN:9784062576222
出版社:講談社
判型:新書
ページ数:254ページ
定価:900円(本体)
発行年月日:2008年11月20日 第1刷
発行年月日:2009年03月03日 第5刷
Posted by ブクログ
日本といえば、やっぱり軽薄短小ですね。
自動車の安全技術の紹介では、フードエアバック と
グリルエアバック が 興味深かった。
ちょっと気を抜くと、すぐに追い抜かれることを気をつけていたいと思いました。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
日本が「ものづくり大国」となったのは、決して「手先が器用で勤勉だから」だけではない。
独自の「技術」を生んだのは、どの国にも真似できない独自の「発想」であり、それを培った「文化」だった。
「ものまね大国」と批判するだけでは見えてこない、オリジナリティあふれる発想がなぜ生まれ、どう技術に生かされているのかを検証し、これからの日本が進むべき針路を見出す。
[ 目次 ]
第1章 日本的技術発想の突破力?携帯電話の事例研究
第2章 「発明」と「商品化」のあいだ
第3章 ものづくりに宿る「軽薄短小」技術
第4章 からくりをロボットに変える「合わせ技」
第5章 模倣を超える「工夫力」と「考察力」
第6章 軍需に頼らない「民需王国」
第7章 一億人の「わがままな消費者」
第8章 基本機能になった「環境」「安全」
第9章 技術文化国家への道
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
思ったより概括的で、先の畑村先生本とはほぼ逆の趣向。ロボット、安全、環境等、従来から言われている強みに、地域化等の、これまた既存の言論を当てはめたようにも思える。どちらかというと日本の技術史に近い論考。