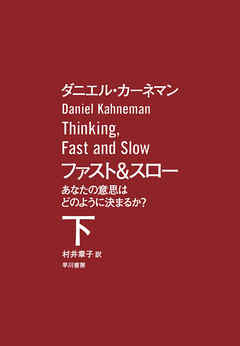あらすじ
我々の直感は間違ってばかり? 意識はさほど我々の意思決定に影響をおよぼしていない? 心理学者ながらノーベル経済学賞受賞の離れ業を成し遂げ、行動経済学を世界にしらしめた、伝統的人間観を覆す、カーネマンの代表的著作。2012年度最高のノンフィクション。待望の邦訳。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
直感的に働くシステム1と、熟考するシステム2という人間の意思決定について書かれた本。直感であっても、プロが下すものや長年の経験があれば正しく判断できたりするなど、システム1も侮れない。
より広いフレームで考えること、なるべく多くの選択肢を比較して決定することが大事。そうでないと「見たものがすべて」になり、狭い選択肢で判断してしまうことになる。
本書でプロスペクト理論と確率決定加重の、行動経済学にこける2つの重要な考えが出てくるので、是非読んでいただきたい。
Posted by ブクログ
上巻に続き、さらに深い世界へ。特にプロスペクト理論、「経験と記憶」は秀逸。いつも読み飛ばす解説も上下巻をうまく総括してくれており、さらにカーネマンの2つの論文付と魅力満載!
Posted by ブクログ
「エコン」と「ヒューマン」についてはあまり興味を抱かなかったが、「二つの自己」はストライクだった。経験と記憶がどのように相互関係にあるのか、その特徴がよくわかる。
巻末の論文の資料価値も高い。
〈スキル習得の基本条件〉
①十分に予見可能な規則性を備えた環境であること
②長期間にわたる訓練を通じてそうした規則性を学ぶ機会があること
→この二つがあれば直感はスキルとして習得可能である。まず規則性を見いだすこと、その上でその規則性を学ぶコンテンツを作成することが重要だ。
楽観バイアスは、認知バイアスの最も顕著なもの。人は自分の立てた目標は実際以上に達成可能だと思い込む。
行動して生み出された結果に対しては、行動せずに同じ結果になった場合よりも、強い感情反応が生まれやすい。後悔も含めて。
「フレーミング効果」
問題の提示の仕方が考えや選好に不合理な影響を及ぼす現象
〈経験と記憶〉
記憶の特徴は、「ピークエンドの法則」と「持続時間の無視」。
経験と記憶を混同するのは認知的錯覚。
過去から学んだことは将来の記憶の質を最大限に高めるために使われ、必ずしも将来の経験の質を高めるとは限らない。
きっと記憶に残るだろうと感じられる経験は、そうでない経験より大きな重みと意味を獲得する。
「焦点錯覚」
そのとき注意が向けられていた生活の一要素が、総合評価に置いて不相応に大きな位置を占めることになる。
システム1に起因するエラー防ぐには、認知的な地雷原に入り込んでいる兆候を見落とさず、思考をスローダウンさせ、システム2の応援を求める。
Posted by ブクログ
上巻では、システム1と2という2つの脳の働き(キャラクター)の違いと、それによる錯誤のメカニズムについて書かれていました。下巻では、さらに2種類の対比するキャラクターが出てきます。経済学で前提される合理的な人間(エコン)と、現実の間違いも犯す人間(ヒューマン)。経験する自己と記憶する自己。
これらのキャラクターの説明を通して、人間が何故、時として重大な間違いを犯すのかが書かれています。
最後にその間違いを重大なものに発展させない、政策や意思決定の可能性があるということ。それは個人では不可能に近いが、組織で行えば比較的可能であることが提案されています。
「なんでこんなことをしたのか?」という他人の行動を、もう少し近づいて考えることが必要で、人は全体で考えて幸せになる生き物なのだと考えさせられました。