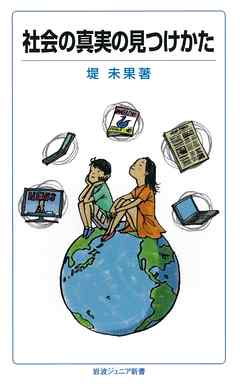あらすじ
メディアが流す情報を鵜呑みにしていては、社会の真実は見えてこない。9・11以後のアメリカで、人々の恐怖心と競争を煽ってきたメディアの実態を実際に体験し、取材してきた著者が、「情報を読み解く力」を身につける大切さを若い世代に向けて解説する。同時にそこにこそ“未来を選ぶ自由”があると説く。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
社会の真実の見つけかた
著:堤 未果
紙版
岩波ジュニア新書 673
メディアが流す情報をうのみにしていては、社会の真実は見えてこない
情報を読み解く力を身につける大切さを語る書です
■戦争
同時テロ以降のアメリカは、どうも、戦前の日本のようだ
治安維持法のような法案ができ、戦争に反対の意見は、封じ込められて、戦争反対者は逮捕され、拘留される
どの国でも、戦争開始直前の報道には、自由、民主主義、解放、正義、報復、自衛などの言葉がちりばめられる
そして、相手側には、理屈の通じない、悪魔のような、非道な、といった表現が使われる
テロに対する深いショックと怒りが高まるほどに、祖国への強い愛が湧いてくる
テレビも新聞も、テロリストの恐怖、そして、3000人の被害者と遺族についての情報を洪水のおゆに流し続け、みな恐怖に呑み込まれ、他のことは考えられなくなってしまったのだ。
「死の商人」とよばれる軍需産業にとって、恐怖はもっとも親しいパートナーになる
米国が戦争を始めるときは、いつもそうだ、米西戦争、太平洋戦争、そして、9.11テロも。
その裏にあるはずの歴史や、民族や、政治的利害関係のような複雑なところに目を向けなかったことが、大きな間違いだったと思う。
あの時のアメリカの国民に選択肢などなかった。
テレビや新聞、ラジオがふりまいていた情報は、敵、か、味方、か、善、か、悪。
手の中のカードは、戦争vs平和、ではなく、戦わず自由を奪われるか、自由を取り戻すために戦うか、の2枚しかなかったのだから。
■教育
全米に広がる教師のインチキ合戦
教師による大規模なカンニング事件がおきていた ⇒子どもたちの成績によって特別ボーナスがでるから
アメリカ国内の公教育が荒廃し続けているのは、現場の教師の責任だろうか
⇒ 教育が国の責任であるという議論が抜け落ちてしまったからです
肥満児が?なぜですか?
⇒ 体育の時間が大幅に減らされたからです。学力テストに関係ないから
行き場のない親たちの不安やストレスが、教師に向かうということです。
テスト至上主義や罰則だけで厳しくしても、結果がでないばかりか、教師や親、そして、最終的には子どもたちを追いつめてしまう
7年でかけ金が2倍になる投資「チャータースクール」
オバマ大統領の「予算獲得レース」の条件で最も大きな目玉は公立高校の民営化だ
チャータースクールは、投資先としては優良の商品ですね
2008年、ブロード基金とゲイツ基金が共同で6000万ドル出資した教育キャンペーンの柱は、
授業時間の延長と、能力給方式の強化だった
かつて、チャータースクールは、市民運動のひとつだった
今は違う 巨額の資金と市場原理に後押しされ、何千ドルもするスーツで国会に出入りするロビイストたちを抱える巨大な産業のひとつになってしまった
■メディア
テレビ社会のアメリカでは、日本のように新聞を読む習慣がない
⇒ でもある時から、テレビが流す情報について疑問をもつようになったんです
世界中のニュース報道を比べてみる
⇒ ウィキリークスのハッカーたちは、ネット情報の最大の弱点が情報の信頼性であることをちゃんと知っていた
偏った見方にならずに、全体像をつかむにはどうすればいいのか
⇒ まず手始めに、各メディアのニュースに注目すると良い
アメリカでも記者が現場に行かず記事を書くケースがふえている
⇒最大の理由は会社側の経費削減ですが、自分の足をつかって現場に行くより通信社からの情報で書くほうがらくだから
情報の信ぴょう性をだれかが保証したとしても、それらが本物かどうかは、自分で調べなければならない
インターネットとは、単なる進化した道具の1つであるということだ
インターネットの情報は単なる材料の1つでしかない
ワイドショーやスキャンダルは、重要ニュースとセットになって出てくるとみるべきでしょう
憲法改正レベルの重要法案の成立のニュースは、アイドルの逮捕報道にかき消された
■社会は変えられる
しあわせになりたきゃ、選挙にいけ
高齢者たちが政治家に圧力をかける道具が数であれば、若者だって負けていないはずだ
違いがあるとすれば、自分たちの世代が、不信感からすぐに選挙に行かなくなるのに対し、高齢者たちは、けっして途中であきらめない
社会を変える力をもつのは、いつだって、あきらめず、投票をし続けるグループだけだ
代議士だって、ちょくちょく顔をみにきてくれるような相手のほうを大事にするにきまっている
そういう相手の為に動けば、見返りもあるし、充実感も得られる
一生懸命自分を売り込んでも肝心の選挙の日に投票にも来てくれないような相手に何かしたいと思うか
選挙に来ない若者や政治に無関心な連中は、政治家たちにとって都合のいい透明人間と同じなんだよ
彼らは選挙が終わっても、引き続き、そのテーマについての状況を会報やホームページに載せ続ける
それを改善するために必要な法改正はこれとこれで、今この時点にいますという具合に、ひと目でわかるように工夫されているのだ
選挙と選挙の間こそ本番なのよ
社会を変えるためには、ある一時期だけ燃え上がるだけではだめなの
毎日の生活の中でその火を絶やさないようにする地道な努力の積み重ねがある日大きな結果を出すんだから
最高の投資商品がある、それは、若者への教育です
インターネットが国境を消しつつある今、語学力は何よりも最大の武器になる
英語だけは、簡単な文章を読めるくらいにしておこう
目次
第1章 戦争の作りかた―三つの簡単なステップ
第2章 教育がビジネスになる
第3章 メディアがみせるイメージはウソ?ホント?
第4章 社会は変えられる
あとがき
ISBN:9784005006731
出版社:岩波書店
判型:新書
ページ数:224ページ
定価:940円(本体)
発売日:2011年02月18日第01刷
発売日:2016年05月16日第11刷
Posted by ブクログ
この本はジュニア新書ですけど、「子ども向け」と思って敬遠するのは本当にもったいない!
アメリカの中でも、2001年からのイラク戦争に向かう時代やブッシュ〜オバマの教育改革などについて、メディアで報じられる内容と当事者の言葉をもとに組み立てられている。
耳障りのいい政府の言葉の裏に隠れていること、金の流れを丹念に追い、メディアが報じないことを見抜くこと、政治に参加し社会を変える方法などが全て当事者の声とともに書かれている。
他山の石とする内容がたくさん。知らぬ間に戦争に巻き込まれたり、知らぬ間に搾取されることのないよう、政治にはプレッシャーを与え続ける必要があることがわかった。
Posted by ブクログ
"アメリカで実際に起こっている事実を検証しながら、政府やメディアに踊らされずに行動することとはを考える。
良書。政治に無関心でいる層は確実に食い物にされる現実を見せつけられる。
政治とは無関係には生きていけないゆえである。ある目的をもったそれなりの多くの人が長期的に政治家に働きかけることで法制化が進む。結果的に政治に無関心な若者を虐げる社会になってしまったアメリカ。
対岸の火事ではなく、日本にも同様の波が押し寄せている。目覚めよ。若人。"
Posted by ブクログ
希望が見出せない現代社会においては、ややもすると「希望なんて持てないからもう終わりだ」とついマイナスの思考へと進んでしまいがち。この本においてもその前提は同じ、「一部の人間にばかり有利で弱者には冷たい社会」だ。けれどこの本の良いところは、たとえ現状がそうであったとしても、そこから立ち上がって自分の力で歩いていこうという前向きな姿勢にさせてくれることだ。
戦争は巨大な利権者によって意図的に起こされ、教育にはビジネス要素がどんどん入り込む。メディアが流す情報は利権者に都合のいいものばかりだ。犠牲になるのはいつも社会的弱者。でも、そこで腐ってしまっては本当の終わりだ。事実として認識されていることをもう一度疑い、検証して本当の真実を自らの力で暴き出すことの重要性をこの本は教えてくれる。たとえばこんな風に。
◼️p66 何か事件が起こった時、過ちを犯した犯人を責めることは簡単だ。だが原因に目を向けない限り、同じようなことは何度でも繰り返されるだろう。目を向けるべきなのは、その悲劇を作り出した背景と構造なのだ。
◼️p109 アメリカに浸透している、チャリティは美しいものだという概念が、今起こっていることへの判断力を狂わせているのです。特に「子どもたちのために」という言葉は情緒的に国民の子の心をつかむ力を持っている。でもどんなにきれいな言葉を並べても、彼らは民間企業なのです。寄付ではなく投資。彼らにとって教育は国のための人材を育てるためのものではなく、たくさんある事業計画のうちのひとつにすぎないのです。
社会に対して単に悲観的になるのではなく、社会を疑い自らでより素晴らしい社会を作っていくことはもしかするととても面白いことなのかもしれない。この本を読むとそんな風に思えるし、学ぶことの意味を再発見させてくれる気がする。
Posted by ブクログ
これ!すごくおもしろい。
森達也さんともちょっとかぶる部分はあるけど、だからこそこのひとの本にも相当な重みがあった。
これを読んで、アメリカにしても、日本にしても、ほんとうに弱者が容赦なく虐げられてしまう社会になっていくような、そんな気がした。無力感、どんよりした気分になる。
Posted by ブクログ
テーマはメディアの見方と政治の参加について。
第1章、2章はたしか『ルポ貧困大国アメリカ』の話でも取り上げれていた、米のリクルートの話と教育制度の話。これが報道が真実を曲げてしまったり、もしくは取り上げないことの例として書かれています。格差の拡大、軍事増強と補助金、助成金のカット、さらにTPP加入でますます自由化、競争化の波が押し寄せそうな日本にとって、以前『貧困大国アメリカ』を読んだ時以上の切迫感を感じました。
3章以降はメディアの見方について、そして社会の変え方についての話に入ります。
ポイントはいかに一つの情報を様々な媒体、時には自国のニュースサイトからも離れて海外のニュースから探るかということ。そして政治参加についての有用性についても語られます。
参議院選挙が間もなく始まる中で非常にいろいろと考えさせられます。選挙が終わってから政治に対して無関心になるのは大衆だけではなく、メディアも同じだなあ、と思います。というのもメディア自身も選挙が終われば、政策の話うんぬんより政局がどう動くか、という話の方に終始している気がするからです。
メディアが伝えないことをいかに知るか、そういうことを考えさせられた本でした。ジュニア新書というレーベルながらも全世代の人が読む価値のある一冊だと思います。
Posted by ブクログ
ジャーナリストである堤氏の一冊。
一方的な情報や偏った情報源のみを信じていると、真実が分からなくなってしまう。一つの物事に対して、様々な観点から見る必要性があると説く一冊。
僕たちが無関心を貫き、何も行動を起こさなければ、
何も変わらない、ということを、9.11以降のアメリカの移り変わりを玲にして、教えてくれた。
僕自身も情報は、原典に当たる、当事者の話を聴く、現地へ赴くを大事にして、自分で積極的に考えて情報収集をしたい。
Posted by ブクログ
貧困大国アメリカで有名な堤未果氏の著作。第一章。二章は著書「ルポ貧困大国アメリカ」からの刷り直しの内容の為、ざっと読み流す。
内容を書き換えただけかと思われた本書ですが、第三章から「社会の真実の見つけかた」が始まります。
先ずは世の中の情報操作の行われ方、また実際に行われた情報操作方法。対策として如何にすべきか(情報の裏取り、情報発信者のスポンサー、批判対象または批判をしない対象とは何かを知る)など、有益な情報が記載されている。
また第四章ではどうすれば世の中を変えられるのか、具体的な事例を交え紹介。キーワードはスタミナ。粘り強く。
個人的に印象に残った事柄としては、立場によって情報は変わること。そして、実際に現場に立ち会った人間・当事者の話を聞くことの大切さ。ウィキリークスの情報開示によって避難されたアメリカ軍人の言葉はとても印象的でした。人は世の中を「アクとセイギ」に分けたがるがそんな単純なモノではありませんね。
情報収集の手段としても英語もまた有用であるということで、使わないからと止めていた、語学の勉強をまた始めようと思います。
Posted by ブクログ
現在の日本の電力事情や原子力発電所に関する「真実を見つける」には、テレビや新聞だけじゃなく、自分から広くネットや外国からの視点も踏まえて情報を集めなきゃね、ってことを若い人たちに考えてもらうのにとっても良い本だと思う。
若い人たちに「第4章 社会は変えられる」を是非読んで欲しい。デモもいい、ツイッターもいいけど、社会を変えるなら「選挙」だし、「政治」だし、「予算」を自分たちの手に取り戻さなきゃね。できるよ!君にも。
books216
Posted by ブクログ
『国が戦争に向かってつき進み始めた時、まっさきに隠されるのは本当に知るべき情報だ。ならば一体どうすれば、それを見極めることが出来るのか。過去を振り返り、歴史を検証することが大きな助けになる。』
Posted by ブクログ
著者は、『貧困大国アメリカ』の堤未果さん。
メディアが流す情報を正しく読み解く力を身につける大切さを、若い世代に向けて解説した本。
興味深かったのは、第1章「戦争の作りかた」と第2章「教育がビジネスになる」
ブッシュ大統領がはじめた「テロとの戦い」をさらに進めたオバマ大統領がノーベル平和賞を受賞したのってやっぱりおかしい。
「アフガニスタンに増兵しながらノーベル平和賞」(p.144)と皮肉を言われるのもやむなしと思う。
「学校で好きなことを学んだり、けがや病気をしても請求書の心配をせずにすぐ病院に行かれたり、真面目に働けばいつか好きな人と結婚して子どもを持つことができる、そんな普通の人生が、“高望み”だって言われる社会に住んでいる子どもは、それを手にする方法がひとつしかなかったら絶対に手をのばす。たとえそれが“戦争”であっても」(p.51)
教育に「競争原理」を導入することは絶対にしてはいけないと自分は思っている。
「子どもたち一人ひとりの個性を伸ばしてやり、何があっても自信を持って堂々と生きていかれる人間として、教え子たちを社会に送り出」したい(p.77)、それが教師の願いなのであって、決して「テストでいい点数を取るためのロボット」を作り出したいわけではない。アメリカで「落ちこぼれゼロ法」(2002年)が施行された後、テスト中に教師が歩き回って解答を教えているという実話(!)には笑ってしまった。これが人間の真理というものだ。
ただ1つだけ!本書の中の「教師だってほめられたい」(p.92)という部分だけは自分と意見が異なると思った。少なくとも自分は、「ほめてほしい」とか「感謝されたい」と思ったことはない。生徒をきちんとほめてあげられる教師になりたい、ただそう思っている。
点数で見えない部分、お金にならないことにどれだけ心と時間を傾けられるかというのが、今後自分が追求していかなければならないことだと思った。
あとがきにある次のことばに、本書の作者の思いが集約されている。
「教育が人間を育てる種まきだとしたら、すぐに結果が出なくても、その子の中にある善きものが機を熟し花開くのを信じて待つ余裕を、先生や親たちが持てるかどうか。その環境を整えることが、国や行政の役目だろう。競争で追いたて、数字で切り捨て、市民をモノのようにバラバラにする社会では、種は枯れてしまう。
私が出会った大人たちは、それをちゃんとわかっていた。真実を教えることよりも、それを自分で見つけるやり方を教える方がずっと大切だということを。「待つ」ことの価値が、決して数字で測れない大きなリターンをもたらすことを」
Posted by ブクログ
『ルポ貧困大国アメリカ』の著者。
ジュニア新書と侮るなかれ、読みやすさがちゃんと内容と向き合わせてくれる。
イラク戦争とアメリカの貧困の関係。
9.11後の一色化された報道。
徴兵を担うリクルーターと、彼らの甘言に未来を託さざるを得なかった若者たち。
国を想う気持ちは、ともすれば国自身が創り出した幻だったとしたら。
民間人をも殺めてしまう、そんな正義の闘いの裏側には、ゲーム化して笑い飛ばさなければ自分の心が保たない苦しさが漂っていた。
ボタン一つで見えない世界を崩壊させられるのは一部の狂った権力者だけで、その末端には今尚、身体を使って戦地に赴く兵士達が沢山いる。
そして彼らは自分自身を社会復帰しようがないマーダーだと話すのだから、切ない……。
軍事の面でも、教育の面でも、インタビューには日本を羨む声があった。
だけど、私が一番驚いたのは、日本とほとんど変わりないじゃないかということだった。
公教育にサービスや結果だけを重視し、ノルマをクリア出来ない学校や教員を淘汰する。
教員はクビにならないために生徒の成績を誤魔化したり、成績を上げるためだけに労働時間の増加と、サービスを求める保護者の声に対応することに追われていく。
学生は大学に行っても学費ローンの増額が負担になり、社会人になった瞬間に経済的自立が破綻してしまうシステムを背負わされる。
政治は、声をあげない若者よりも、マジョリティである高齢者に有益な機能ばかりを整える。
そこで、若者の武器としてインターネットやスマートフォンがあるのだから、見る目を養って自分で真実を見いだすべきだという繋げ方をしていく。
この結論については、考えよりもモノに傾きがあるように思わなくもないが……子ども達が守られる側から、自分自身を守る側に移るためには、何を持っていなければならないのかが書かれている。
良かった。
Posted by ブクログ
「真実を見つけるには、ただ座って待っているだけじゃダメだ」なのだ。誰かが差し出してくれる情報にばかり頼っていると、いつの間にかフェイクをつかまされてしまう。
窓の向こうにある膨大な情報の中から「本物」をえり分けるために、しっかりとアンテナを立てて本物をつかむのは、使う側の私たちなのだ。社会について不満を抱いているだけではなく、自分の持っている権利を大いに使える方法を私たちが持っていることを自覚しなければならないと思った。それは憲法で定められた人権であったり、選挙で政治を変えること。未来へ投資するために情報リテラシーを磨くことだ。
Posted by ブクログ
岩波ジュニア新書です。
アメリカ社会の現在を見ていきながら、
その背景や原因を探って白日のもとにさらす内容。
アメリカ社会も極まっているなという印象。
そして、そういったアメリカ社会の問題点を、
因数分解するように解いていく過程を示すことで、
読み手であるぼくら自身が、
真実を見つけていくやりかたとはどういうものかを、
読みながら学んでいくような体裁でした。
この本を読んで現代アメリカ社会通になる中学生だとかいるだろうけど、
それもおもしろい存在だなと思う。
学級会なんかで「たとえばアメリカなんかじゃ・・・」って
うんちくをたれていい気になるのも、
オトナになれば(いい意味で恥ずかしい)思い出になる。
それはそれとして。
日本で、のほほんと暮らしているからか、
アメリカの実情をこの本を通して耳にするとすごく世知辛く感じる。
競争原理バリバリで傲岸不遜な政治のように見えるし。
大量破壊兵器もなかったイラク戦争への突入の仕方だとか、
9.11から対テロ戦争へと傾いていったそのやり方、
「愛国者法」や「落ちこぼれゼロ法(経済徴兵制度成立法とも言える)」
を成立させていった過程をしるにつけ、
そんなだから、例えばウィキリークスって、
そういうのに対抗するのにバランスとしてちょうどよかったんだろうなあ、
日本じゃ受け入れられない手合いのものだったとしても、と思ったりする。
日本はまだほんわかしているところがあるから、
ウィキリークスみたいなのはやりすぎでけしからんということになるけれど、
アメリカだとかにすれば世知辛さの真剣勝負だから、
真剣に両足を不正に突っ込んでやってたりするわけで、
つまりはそういうののカウンターとして、ウィキリークスくらいの過激さっていうのは、
「当然」と言った体で出現したものなのかもしれない。
といいつつ、本書を読む進めると、反体制だとかそういったものに限らず、
情報のあり方までを変えて見せたのがウィキリークスなんじゃないか、と
著者は述べているのだけれど。
最終章の「社会は変えられる」はとくに秀逸でした。
この章を読むと、高齢者による巨大な団体であるAARPのことなど
面白いポジティブな情報が得られるし、なにより希望のある章でした。
若者は熱しやすく冷めやすい、それがウィークポイントだ、もっと粘れ、
といろいろと政治に働きかけて社会を少しずつ変えてきた高齢者のひとりは言います。
投票してそれで終わり、では変わらないことだし、
ちょっと駄目だったからといってそこから離れるのはナイーヴすぎるのかもしれない。
アメリカならば、自分たちの抱える学生ローンの問題や就職難の問題などなど、
それら生活に根差した問題を政治にぶつけて働きかけていくことが、
きっと、政府などの政治の暴走を防ぐことになるのでしょう。
弱い立場の国民は、でも、「数」でもって戦えると著者は言います。
そしてそれは、真実でありましょう。
Posted by ブクログ
事例の大部分は他の著書でも見られるもの。それを岩波ジュニア新書モードで表現してありますが、やはり内容は重い。本書で一番印象的だったのは、高齢者団体のパワーと若者組織の無力感を対比的に描き、しぶとい行動こそが必要と説く点。自分がどこに属するかはさておき、すごく共感できます。
Posted by ブクログ
著者の岩波新書3部作の少年少女版。質は同じで子どもに関わるところを丁寧に取り上げている。この前、「アメリカが世界で一番良い国」という若者に出会い衝撃を受けたが、読んで欲しい一冊。我が国の未来、とりわけ教育を、若者を、どういう方向へ持って行こうとしているのか考える上での好著。
Posted by ブクログ
子供向けということでとても読みやすいが内容は非常に重い。だが、これは日本国民、特に若者は絶対に知っておかなければならない。ぜひ、学校の課題図書などに加えてほしいと思う。
本の中で紹介されている、今アメリカで起きている様々な事実はまさに日本でも起きようとしていることで、デジャブを見ているかのようでした。
ブッシュ大統領が決めた「落ちこぼれゼロ法案」。教育に市場原理を持ち込み、過度な競争と能力主義を入れた。現場では、授業はどんどんテストでいい点を取るコツを教ええる内容が中心になっていき、ひとつの事柄をじっくり議論することが減ってしまい、また、体育の時間が大幅に減らされたので肥満児が増えているとか。親の栄養知識のなさと貧困もその大きな原因であると。そしてオバマ大統領による「予算獲得レース」によって公立高校が民営化させられている。これらの恩恵は投資家が得るとのこと。
また、今までアメリカはチャリティ文化という素晴らしい文化があると思っていたのだが、これも上辺だけ。彼ら三大巨人(ビルゲイツ、ウォートンファミリー、エリ&エディス)らにとって寄付とは目に見えるリターンをもたらすべき投資。資本主義型チャリティいとか、ベンチャー型チャリティと呼ばれ、達成すべきゴールも期限も投資する側が決める。そしてそこに最短距離で達成するための人材や経営方法もすべてパッケージで提供する。これによって公共の教育現場が、優良投資先として投資家の食い物とされてしまった。しかし彼らを批判するものはいない。なぜなら彼ら投資家たちはメディアや政治家たちに莫大な影響力を持っているからだ。
アメリカの教育現場の実態を知るにつれ、これは日本でも起きようとしていることなのだが、今一度、教育とはどうあるべきか、そして、どんな人間を世に送り出したいのか、それはどんな未来を我々が望むのかと同じことで、その根幹は教育にあるということを胸に刻まねばならないと思う。
また、私自身も、メディアを買収している企業について、あまりに無知だった。たとえばABCはディズニーに、NBCはGEに、CBSはどこかの投資家に。日本は・・あとで調べてみよう。マスコミは企業の下で働いているのであれば、その会社のビジネスに都合の良いニュース飲み流すようになるのは当然のこと。たとえそれが「戦争」だとしても。テレビを見るときは、その局のオーナーがどこの国の誰なのか、政治的にどういう立場をとっている人なのか、そこまで見ないと危ない。
テレビや新聞は見ても良いが、それをうのみにすることはかなり危険である。大量兵器など見つからなかったイラク戦争は、事実じゃない報道を繰り返したマスコミの責任が大きい。携帯端末から一行ニュース的なまとめサイトでニュースを見ていたが、いつも、頭がマヒしてしまうと思っていた。常に新しい、しかし取るに足らない内容ばかり。重要そうな内容は短すぎて読んでも不明だしまとめ方も変。変だなと思ってもそのニュースはすぐに消える。それもメディアのやり口の一つだったようだ。また、まとめニュースにでてくる内容自体も、すでに仕分けされているのだ。一行ニュースに操作されないために、その情報の裏を自分の手で取ること。同じ内容の報道をテレビ、ラジオ、雑誌、本、海外のニュースなどありとあらえる方向から見ることが大事。そしてここで英語力が重要になってくる。
イラク戦争以外で紹介されている例として、Wiki leaksの例。日本ではちょこっとしか報道されなかったが、これはアメリカでも同様だったらしい。
日本のメディアは日本は海外から良い印象を持たれているような方向で伝えるが、本当は全部がそうでもない。海外で日本のニュースがどのように報道されているかということを知るためにもインターネット・英語力がキーとなる。
また、人間は冷静な熟慮ではなく感情的に動かされると、政治家やメディアは良く知っている。ヒトラーもその著書に書いている。
紹介された例で思い知ったのは、イラクでアメリカ兵が冗談をいいながら笑いながら民間人を殺しているwiki leaksの内容。多くの人はこれを見て、アメリカ兵に対して腹を立て、憎しアメリカ!こんな兵士は殺してしまえ!と思うことだろう。しかし、この状況の背景を知る必要もある。兵士たちは戦場で人を殺しても平気でいられるように冗談でも言って平静を装うようになってしまうということ。また、その兵士たちは国に戻ってから、日常生活に戻れず、うつ病や自殺していまうということも。
こうやって批判しているアメリカ社会ではあるが、一方で日本も見習うべきところがたくさんある。たとえば、AARP(退職者のNPO団体)やバージニア21。彼らは自分たちの望む政策をしてくれる政治家を見つけ出し、選挙時も集団になって応援し、そして、常に各法案の進捗状況をチェックし共有している。若者集団のバージニア21では、市民運動のように暴れたり大声を上げたりしない。そんなやり方をすれば警察を呼ばれてまた若者か、と言われるだけ。怒らず、声を荒げず、紳士的にふるまうことをモットーとして、「どちらが得になるかじっくりとご検討ください」と有能なビジネスマンのように自分たちの望む未来を論理的に政治家が動きやすいように提示する。日本の原発反対デモに参加していた人たちのことが思い浮かんだ。日本人はまだまだ幼稚だ。だからアメリカの言いなりになってしまうのだが、私たち一人一人が国に依存せず、冷静に客観的に判断できる賢い日本人にならなければならないと痛感した。
Posted by ブクログ
この本の中で取り上げられた出来事とよく似た出来事が日本の中で、起こったり、これから起ころうとしている。
若い世代が、自分の眼で現実を観て、何が真実で何が正しいことなのかを
しっかりとつかんでほしいと思う。
Posted by ブクログ
私たちが持っている力を、私たちの未来のために。
知らなかったことがたくさんあった。特に、オバマ大統領には、なんとなく無条件で肯定的に見ていた自分を反省。twitterくらいは受信の道具として使おうかと思う。あと、せっかく一定レベルをクリアしているのだから、英語を活かそう。
インターネットの便利さは、自分たちの道具として、武器として。溢れかえる情報に流されないように、常に警戒し、隠された真実に耳を傾けて。ネットでのつながりと、リアルのつながりの両方を、上手に使いこなして。
与えられた情報をうのみにするのではなく、たくさんの情報を自分から取りに行き、取捨選択する。これからの、デジタル・ネイティブが目指す姿は、これでないか。中学生、高校生に、ぜひ読んでもらいたい本。
Posted by ブクログ
高校生向けの本かな?
でも、大人でも十分な読み応えです。
やっぱり堤さんの本はすごいなぁ~vv
第4章の「社会は変えられる」は考えさせられました。
選挙は行かないとダメですね。
もうすぐ選挙があるかもしれないので、テレビ、新聞、ネットなど、いろいろなものを駆使して臨みたいと思ってます。
Posted by ブクログ
戦争の作り方
教育が ビジネスになる
メディアが見せるイメージは 嘘本当
社会は変えられる
米国での例が挙げられているが 日本も近い将来こうなるのか
Posted by ブクログ
9.11テロ後、イラク戦争に突き進んだアメリカ、テレビも新聞も、国全体が敵か味方か、全か悪かしかなかった。落ちこぼれゼロ法、生徒の試験点数で教師や学校を競争させ、評価で予算が決まる。ウィキリークスをスルーする大手メディア。
若者向けに書かれています。若者がんばってほしいです。
Posted by ブクログ
中1の娘に薦めようと思って事前に読んでみた。
自分にとっては分かりやすく、意識を変えるきっかけになったが、中1の娘には少し難しいトピックスが多く、興味を持って貰えなかった。良い本なのでまた機会を改めて薦めようと思う。
Posted by ブクログ
凄まじいまでのアメリカの借金漬けの実態をみた。経済徴兵制も恐ろしい。最早、洗脳ではなく、頭を使っていない愚かものを騙して食い物にしているだけだ。解決策は、政治しかない。政治家に任せるのではなく、自分の欲しいものが得られるまで、しつこくしつこく活動、監視していくしかない
ARRPの活動、バージニア21の活動など参考になる。
ARRP の活動家の以下の言葉を心に留めたい
俺たちは決して手綱を緩めない欲しいものを手に入れるまでは