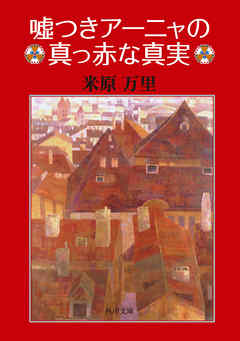あらすじ
1960年プラハ。マリ(著者)はソビエト学校で個性的な友達と先生に囲まれ刺激的な毎日を過ごしていた。30年後、東欧の激動で音信の途絶えた3人の親友を捜し当てたマリは、少女時代には知り得なかった真実に出会う!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
オーディブルで聴いた。
面白かったー!!
1960年代にプラハのソビエト学校で小・中学生時代を過ごした著者の、当時の友達の話と、大人になってからその友達に会いに行く話。
冷戦、東欧諸国の民主化など、現代史でさらっと習った出来事に、まさに影響を受けた人たちの話で、私にとって遠い世界の話だったけれど、そんな世界の中で生きている人たちが、著者の親友だったから、本を読んでいる(聴いている)間はとても身近に感じられて面白かった。
3人の友達が、3人とも魅力的で個性的で忘れられない。
まだネットやスマホが普及していない時代だったから、すぐに連絡もつかなくて不安だっただろうな…。ネットが普及してても、30年前の友達を探すのは大変なことだと思うから、再開できて良かった。
ロシア語というか、外国語を話せて、外国の友達がいて、外国の文化に触れられるって改めていいなと思った。
ロシアやロシア語ってだけで毛嫌いする年配の日本人をたまにみかけるけど、やっぱりロシア語ができて、プラハで小中学校時代を過ごした経験って羨ましいなと思った。
ルーマニアの特権階級のアーニャの話や、アーニャのご両親やお兄さんの話、ユーゴスラビア人のヤスミンカの話は特に、貴重なお話を聞いたと思った。
ルーマニアのブカレストのシャンゼリゼ通りのコピーとか、豪華な国民の館とか思わずネットで調べてしまった。
Posted by ブクログ
実体験をもとにしたノンフィクションで、すごく濃密な本だ。
チェコのプラハでソビエト学校に通う小学生のマリ。ここには50もの国からやってきた子供たちが通っている。マリの父親は、日本共産党から派遣されて、国際共産主義運動の理論誌の編集局に勤めており、そのため家族でプラハにやってきた。(この学校に通う子供たちは外交官や共産主義運動の幹部たちを親に持ち、それなりにブルジョアな暮らしぶりが散見される。しかし同時に社会主義国としての計画経済による、融通の効かなさみたいなところも描写され非常に興味深い)
米原万里がプラハで過ごした9〜14歳までの期間に出会った、3人のかけがえのない友人たち。リッツァ、アーニャ、ヤスミンカ。それぞれを主役にした三篇からなるお話。
同時に、社会主義、共産主義思想を掲げる東ヨーロッパ諸国の、激動の二十世紀後半記でもある。ロシア語同時通訳者、エッセイストである著者の豊富な異文化体験と、民族に対する冷静なまなざし。読み進めるほどに、なんと聡明な人だろうと驚く。
P247から引用。
『ところで日本ではいとも気楽に無頓着に「東欧」と呼ぶが、ポーランド人もチェコ人もハンガリー人もルーマニア人も、こう括られるのをひどく嫌う。「中欧」と訂正する。』
こんなことぜんぜん知らなかった。
彼らはもちろん地理的正確さを期して東を嫌うのではない。「東」とは、より西のキリスト教諸国の発展から取り残されてしまった、また冷戦で負けた社会主義陣営を指す記号でもあるという。貧しい敗者のイメージ。憧れ、劣等感、蔑視と嫌悪感。これは、明治以降に脱亜入欧を目指したわたしたち日本人に通じる。
民族紛争や異宗教との諍いに、否応なく巻き込まれていくかつての少女たち。
しかし、かといって悲壮感に溢れるだけではない。多感な時期の少女たちの、華やかで明け透けで、ときに大人顔負けの知的さを垣間見せる、希望に溢れた感性も見事に描写される。
歴史に疎い自分にとってはとても勉強になるし、それどころか10代の女の子たちがここまで社会や民族について学び理解し、自分なりの考えを持って生きていたことに頭が下がる。
総じて、いい本を読んだなぁ、という気持ちになった。
Posted by ブクログ
軍事政権の弾圧を逃れ東欧各地を転々とし、チェコスロバキアに亡命した共産主義者の父を持つギリシャ人のリッツァ。
同じく共産主義者の父を持つ、インド生まれ中国育ちのルーマニア人アーニャ。
15歳でパルチザンの一員となった共産主義の父を持つユーゴスラビア人のヤスミンカ。
日本人の著者と少女時代を過ごし、その後30年という月日を経て再会する。
当時の時代や歴史、共産主義、社会主義、民族意識…さまざまな視点で考えるきっかけを与えてくれた一冊。
Posted by ブクログ
この本は本屋で紹介されてて面白そうって購入した。が、なかなか手を付けず、少し読んでみたけどなかなか進まず。今思うとそのタイミングじゃなかったんだなと。最近読んだらまぁすらすら読めて面白くて止まらなかった。
まず作者がすごい体験をしているということに驚き。小学校を海外で過ごしていろんな国から来た子に囲まれて育つなんて知り合いにいたことないし、そんな方の経験談を本で読めるっていうのは貴重なことだなと思った。
そしてとっても面白かったのはアーニャの章で、自分の生まれた国から時間的にも距離的にも離れていればいるほど自分の国を愛しているという話。これは自分が実際住んでいる時間が少ないことで嫌な部分も見えにくいって言うのもあるのかな?あとまだ小学生ぐらいの子って自慢したがるとこあるよなと思った。こういう普段考えないようなことだけど、自分がもし同じ境遇になったらやっぱり日本って素晴らしいよって言うのかな?って考えて、小学校の自分だったらいいそうな気がするなーと。
大人になってから3人を探しに海外に行き全員見つけられたのは本当に運がいいし携帯もなかった時代で奇跡。
Posted by ブクログ
面白かった!米原万里、他の著作も読もうと思う。
プラハ時代の友人に実際に会いにいく彼女の行動力も、大人になってからの顛末も面白くて、人生という感じで。。
リッツァの夢見た青空、嘘つきアーニャの真っ赤な真実、白い都のヤスミンカの三本。それぞれ苦労して、大人になって、親たちの世代の話もあって、現代に繋がっていて…
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」
…異国、異文化、異邦人に接したとき、人は自己を自己たらしめ、他者と隔てるすべてのものを確認しようと躍起になる。自分に連なる祖先、文化を育んだ自然条件、その他諸々のものに突然親近感を抱く。これは、食欲や制欲に並ぶような、一種の自己保全本能、自己肯定本能のようなものではないだろうか。
この愛国心、あるいは愛郷心という不思議な感情は、等しく誰もが心の中に抱いているはずだ、という共通認識のようなものが、ソビエト学校の教師たちにも、生徒たちにもあって、それぞれがたわいもないお国自慢をしても、それを当たり前のこととして受け容れる雰囲気があった。むしろ、自国と自民族を誇りに思わないような者は、人間としては最低の屑と認識されていたような気がする。(p.123)
単に経験の相違だと思います。人間は自分の経験をベースにして想像力を働かせますからね。不幸な経験なんてなければないに越したことないですよ。(p.161)
そう言える、通訳の青年の強さ。
…抽象的な人類の一員なんて、この世にひとりも存在しないのよ。誰もが、地球上の具体的な場所で、具体的な時間に、何らかの言語を母語として育つ。どの人にも、まるで大海の一滴の水のように、母なる文化と言語が息づいている。母国の歴史が背後霊のように絡みついている。それから完全に自由になることは不可能よ。そんな人、紙っぺらみたいにペラペラで面白くもない (p.188)
リッツァとヤスミンカの話が特に好きだったのだけど、印象になった文章は、アーニャの章だった。
Posted by ブクログ
【プラハのソビエト学校での友人との記憶と再会の記録】
また目を見開かれるような新しい人生について学びました。
ロシア語翻訳者で著者の米原万里さんは、1959年から1964年、中学校1年生までの5年 プラハのソビエト学校に通われていたそうです。
その当時に親しくなった3人の友人それぞれと、30年の月日を経て40台になった著者がその地を訪れて再会されています。
著者がそもそもなぜプラハのソビエト学校にいたのか、それは父親が共産主義関連の仕事をしていたからで、同じ学校に通っていた子どもたちも、同じような境遇にいて。
ブルジョワ階級と戦い、平等な社会を築くという思想であるはずの自分たち共産党員の家庭が、とても大きな家で暮らし、政権の庇護を受け、特権を享受している。
子どもからすると、ほんとうに知らない間にそんな状況にあって、そこから皆がどういう人生を生きていくのか、という点もとても興味深かったです。
・・・
「リッツァの夢見た青空」のリッツァは、ギリシャ人でした。実は見たこともないギリシャの青い空について話しているのですが、大人になったリッツァはドイツ・フランクフルトで、あれだけ勉強も苦手だったのに、開業医となって忙しくされていました。
夫・アントニスは、ギリシャ移民二世の労働者とのことで、その結婚時の両親との意見の対立や、兄・ミーチェスの悲劇的な現状も。
「ねえ、リッツァ、質問していい?リッッアは、なぜ、ギリシャに帰らなかったの。ギリシャは民主化されて、帰還は可能になったのでしよう。いつもギリシャの青い空のこと自慢してたから。てっきりもうギリシヤに住んでいるものと思ってた」
「マリの言うとおり。軍政が打倒された七ハ年、すぐにも飛んでいこうとしたらビザがなかなか下りなくてね、ようやく行けたのは、ハ一年だった。夢にまで見たギリシャの青空は本当に素晴らしかった。目がつぶれてしまうほど見つめていても見飽きないほど美しかった。でもね、マリ、私にとってギリシャで素晴らしかったのは、青空だけだったのよ。一番、我慢できなかったのは、ギリシャでは、女を人間扱いしてくれないこと。それに、子どもをメチャクチャ可愛がるのはいいけれど、 犬猫なと動物に対する嗜虐性にはついていけなかった。ああ、それにあのトイレの汚さは耐え難かった。結局、私はヨーロッパ文明の中で育った人間だったのね。思い知ったわよ」
「それで、ドイツ人やドイッでの生活には満足しているの」
…
自分のアデンティティを柔軟に変えていくような、彼女の強さが伝わってきました。
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」のアーニャは、ルーマニア出身で、父は独裁的大統領のチャウシェスク政権の幹部。地位ある職についてきた父親の特権と思惑もあり、最終的にイギリス人との国際結婚を果たし、ロンドンでエリート(Upper middle)な暮らしをしていました。著者はのちに、彼女がユダヤ人でもあったことを知りました。一方、兄の一人ミルチャは、異なる人生をルーマニアで築いていました。
著者はアーニャのストーリーの中で、愛国心、望郷の想いは、異国に暮らすと、そして自分の国が小さく弱い場合、また不幸な国であるほど強く大きくなる、と書かれていました。
ルーマニア人の青年通訳ガイドとの会話で印象的だった会話が、
著者「たしかに、社会の変動に自分の運命が翻弄されるなんてことはなかった。それを幸せと呼ぶなら、幸せは私のような物事を深く考えない、他人に対する想像力の乏しい人間を作りやすいのかもね」
青年「単に経験の相違だと思います。人間は自分の経験をベースにして想像力を働かせますからね。不幸な経験なんてなければないに越したことはないですよ」
また、著者は、アーニャの父親の生き様を前に、
「どこから、彼の人生は狂いはじめたのだろう。」と問う部分があります。
社会・時代の流れと人生、世界の見方がどう形成されるかについて考えさせられるストーリーでした。
「白い都のヤスミンカ」のヤスミンカの故郷はベオグラード。1990年代には旧ユーゴスラビア連邦が崩壊し、戦場となってしまう中、彼女の行方を追い、幸いベオグラードで再開を果たします。彼女は外務省での通訳の職を離れたところでした。父親は古郷ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国からの最後の大統領だったとのこと。絵を描く才能に秀でており、なぜか葛飾北斎を信奉していたヤスミンカが、実はムスリムであったことも著者は後に知りました。
才能についてのヤースナの言葉は印象的でした。
「西側に来で一番辛かったこと、ああこれだけはロシアのほうが優れていると切実に思ったことがあるの。それはね、才能に対する考え方の違い。西側では才能は個人の持ち物なのよ、ロシアでは皆の宝なのに。だからこちらでは才能ある者を婚み引きずりドろそうとする人が多すぎる。ロシアでは、才能がある者は、無条件に愛され、皆が支えてくれたの」(本文より)
私たちが単に西欧・東欧という、東欧について、東欧と中欧を区別する見方についても紹介されており、興味深かったです。
・・・
他者の世界について想像し、共有する素晴らしい想像力をお持ちの方なのだと思いました。
Posted by ブクログ
1960年~1964年、プラハのソビエト学校(9才~14歳)で学んでいた日本人作者が大人になってソビエト学校時代の友達に会いに行く、というノンフィクション。20世紀後半の東欧の出来事に絡んでいて、(共産主義、ソビエトの崩壊、独立戦争、内戦、等)歴史は詳しくないので読むのに時間がかかりましたが、1990年代の東欧の歴史がわかり面白かったです。
Posted by ブクログ
ラジオ「高橋源一郎の飛ぶ教室」で聴いて。
著者が生きていたら・・・とラジオでも話していたけれど、どんな発信をされるだろう。
30年以上前のノンフィクションだが、今現在、世界は全く変わっていない。まさに今読むべきかもしれない。
古代から、宗教、民族、思想と難しすぎて、ヨーロッパをはじめ、なかなかすべてを把握できないけれど、とにかく変わらず争いが続いている。
ただ、この当時、3人ともに再会できたことが救いでもある。