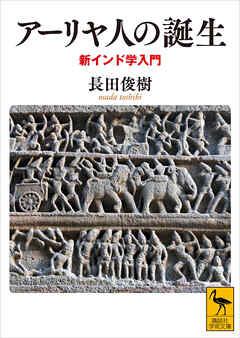あらすじ
ヨーロッパのラテン語・ギリシア語とインドのサンスクリット語に共通の祖となる、失われた起源の言語――。そんな仮想の言語の話し手として「アーリヤ人」は生み出された。そして、それは瞬く間にナチス・ドイツの人種論に繋がる強固な実体を手に入れる。近代言語学の双生児「アーリヤ人」は、なぜこれほどまでに人々の心を捉えて離さないのか。
言語学誕生の歴史から、「すべての起源」インドに取り憑かれた近代ヨーロッパの姿が克明に浮かび上がる!
「インド学」はインドで発達した学問ではない。18世紀末からサンスクリット語文献を集めてきたヨーロッパを中心に発達してきた。私たち日本人が抱く「インド」イメージもまた、近代ヨーロッパという容易には外しがたい眼鏡を通して形成されている。
植民地インドで「発見」された古典語サンスクリットの存在は、ラテン語やギリシア語との共通性から、ヨーロッパとインドに共通する起源の言語の存在を想像させた。類稀な語学の才に恵まれたイギリス人ウィリアム・ジョーンズ(1746-94年)によるこの「発見」によって、近代言語学は誕生する。同時にオリエンタリズムがヨーロッパを席巻し、『シャクンタラー姫』をはじめとするサンスクリット語文献が次々にヨーロッパで翻訳された。
その奔流のなかで『リグ・ヴェーダ』を英訳したのが、ドイツ出身で英国オックスフォード大学に職を得たフリードリヒ・マックス・ミュラー(1823-1900年)である。彼は比較言語学の成果から、『リグ・ヴェーダ』の成立年を紀元前1200年頃と推定し、「アーリヤ人の侵入」を紀元前1500年頃とした。日本の教科書でもよく知られる記述の源は、ここにある。
19世紀ヨーロッパで言語学とともに誕生した「アーリヤ人」は、20世紀にはナチス・ドイツによるユダヤ人迫害を生み、さらにはインダス文明が発見されたインドに逆流して、考古学的成果と対峙しながらさらなる波紋を生んでいく――。
近代言語学の双生児「アーリヤ人」は、なぜこれほどまでに人々の心を捉えて離さないのか。なぜ言語は常に民族という概念を呼び寄せずにいられないのか。言語学誕生の歴史をひもとくことで「起源」というロマンに取り憑かれ、東洋を夢見た西洋近代の姿を克明に描き出す。インドの実像に目を開く一冊。(原本:『新インド学』角川書店、2002年)
【本書の内容】
第1章 インド学の誕生ー―十八世紀末から十九世紀初頭のインド・カルカッタ
第2章 東洋への憧憬ー―十九世紀前半のヨーロッパ
第3章 アーリヤ人侵入説の登場ーー―十九世紀後半のヨーロッパ
第4章 反「アーリヤ人侵入説」の台頭――二十世紀のインド
第5章 私のインド体験ー――多様性との出会い
補 章 出版二十年後に
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書の内容は、著者自身によって次のように要約されている(193-194頁)。
近代比較言語学の祖と言われるウィリアム・ジョーンズと、インドのカルカッタにおいて彼らによって創設されたベンガル・アジア協会の活動により、西洋におけるサンスクリット語の発見、そしてそれが印欧比較言語学へと発展する(第Ⅰ章)。
このサンスクリット語発見ののろしは、ヨーロッパに広がり、オリエンタル・ルネッサンスの華を咲かせることになる(第Ⅱ章)。こうして印欧比較言語学が成立すると、そこから印欧祖語という概念が生まれる。理論上の産物であった印欧祖語は、「再建」の手続によって実体をもったものとなっていくのだが、そこには言語学的古生物学という学問の寄与があった。こうして実体をもった印欧祖語の話し手たちはアーリヤ人として、ヨーロッパを席巻することになり、そしてヴェーダ文献の解釈から、紀元前15世紀ごろにおける「アーリヤ人の侵入」という説がマックス・ミュラーによって主張され、今日に至っている(第Ⅲ章)。
しかし、近年の考古学のめざましい発達によって、「アーリヤ人侵入説」には様々な疑問点があることが明らかになってきており、特に1990年代以降のヒンドゥ―・ナショナリストの台頭の中、その攻撃目標になっている。その主張の是非はともかく、学問的に見ても数々の問題点の訂正が迫られている、と著者は言う(第Ⅳ章)。
著者はインド諸言語のうち、ムンダ語族を専門とするのだが、そうした著者からすると、現在のインド学には、サiンスクリット語中心主義的なインド理解という重大な欠陥があると言う。サンスクリット語文献=ヒンドゥー教=インド文化という単一的インド観を乗り越えて、多元的インド観を確立すること、それが、本書の副題の「新インド学」の目指すところである。
今回の文庫化に当たり、「補章 出版二十年後に」が加えられた。危機に瀕する人文学系学問の状況などが赤裸々に綴られている。
本全体の構成からすると、アーリヤ人の問題に関する部分と新インド学に関わるところの関係とがあまりうまく繋がっていないように思えたし、少し詰め込み過ぎのように感じたが、著者の考えなどがストレートに表れていて、面白く読めた。