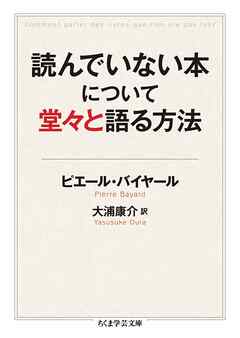あらすじ
本は読んでいなくてもコメントできる。いや、むしろ読んでいないほうがいいくらいだ――大胆不敵なテーゼをひっさげて、フランス文壇の鬼才が放つ世界的ベストセラー。ヴァレリー、エーコ、漱石など、古今東西の名作から読書をめぐるシーンをとりあげ、知識人たちがいかに鮮やかに「読んだふり」をやってのけたかを例証。テクストの細部にひきずられて自分を見失うことなく、その書物の位置づけを大づかみに捉える力こそ、「教養」の正体なのだ。そのコツさえ押さえれば、とっさのコメントも、レポートや小論文も、もう怖くない! すべての読書家必携の快著。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本を読んでも、その内容の受け取り方は人それぞれ。これまで触れてきた本や経験がちがえば、同じ文章でもまったく別の景色が見える。そもそも本のすべてを覚えておくことは難しく、心に残るのはほんの一部分だけ。だからこそ、誰かが語る「その本の話」は、断片的な記憶と、その人自身の人生が混ざり合ったひとつの作品になる。つまり、ざっと流し読んだだけでも、目次しか見ていなくても、そこから想像して語ることはできるし、意外と気づかれない。
この本は、そんな「読書とは何か」を考え直すきっかけをくれた。一冊の本でも、読む人や読む時期によって解釈が変わる。その広がりは無限で、楽しみ方も同じだけ果てしない。そう思うと、読書は一生かけても飽きることのない遊びなんだと感じさせられた。とても刺激的な一冊だった。
Posted by ブクログ
本は読まない方が良いというテーマから創作の始点へと導いてくれる一冊。めちゃくちゃ面白い。
引用される本の引用の仕方が上手いから、古典的な作品すらとてもモダンに感じ、読まないというテーマに反して非常に読みたくなる。ネタバレが多いなと思っていたら、最後の方にどんでん返しがあって、やられた。上手すぎる。
Posted by ブクログ
陰謀論やとんでも歴史論を語る人は、本をたくさん読んでいるようだけど教養があるようには見えない。その理由は、個別の本の内容に深く入れ込んでいる一方で、知識体系の全体像が見えていない(本と本のつながりを理解していない)からなのだとわかった。
本筋ではないが印象に残ったことだ。
Posted by ブクログ
ピエール・バイヤールの著書を初めて読んだ。
タイトルからなんとなく想像できる通り、今までの当たり前をことごとく打ち壊していくような考えを持った人だなと感じた。
私自身、読書をすることで何かしら情報を得たり、影響を受けるため、読書は良い習慣だと思っていた。
しかし、この一冊を読んで、読書による"リスク"を知った。読んでしまうと、何かしら影響を受けるが故、それ以前の自分にはもう戻ることはできないのである。
これを読んでから、読書がより楽しいものになりそうであり、新たな読み方を発掘したような感覚に陥った。
読書にどう向き合ったら良いのか、初めから最後まで本は読むことが全てだと思っている人におすすめしたい。
Posted by ブクログ
ショーペンハウアーの『読書について』の後にこれを読むという流れをやりたかっただけだったけど、なかなか面白かった。
結局のところ「読んだ」ということ自体に様々なレベルがあり、『読んでいない本について堂々と語る』ことは、なんら悪いことではなくむしろ創造的な活動である、ということは新しい気付きだった。
『<他者>は知っていると考える習慣を断ち切る』
『しかし、読んでいない本について語ることが正真正銘の創造活動であり、そこでは他の諸芸術の場合と同じレベルの対応が要求されるということは明らかである』
Posted by ブクログ
・冗談みたいなテーマを扱いながら、最終的に読書の本質に着地する流れが匠の技。
・本来ならこのレビューも読まずに書くべきだし、なんならこの本(※1)について書くべきですらない。
・「ずっと本ばっか読んでると自分自身と向き合えないので良くない」って話、『書を捨てよ、町へ出よう』(※2)を思い出した。
※1 〈流〉〈聞〉◎
※2〈聞〉○
Posted by ブクログ
開始: 2022/7/13
終了: 2022/7/15
感想
読んでる最中から違和感はあったが、自宅の本棚を確認したところもう一冊本書があった。読んでいない本についての本を読んだが読んではいなかった。
Posted by ブクログ
読書家なら必ず持っている読書論について再考させられる本。
教養と時間は無限の関係にあるということ。
読むということは何かを読まないということである。記憶と時間は必然的に失われる運命にある。
同じ本を対象にしても読者の具合で、本の性質はガラッと変わる。
著者はパラドックスの専門家らしく細部にトリックが仕掛けられている。それは本を「読んで」いなければ絶対に分かり得ないトリックである。それこそパラドックスである。
私はそれらの本を実際に読んだことはなかったし、種明かしをされるまで違和感を覚えることすらなかったが面白く読むことができた。
「読む」とはどういうことか。「読み終わった」とは。
Posted by ブクログ
表紙だけ見てなんて不真面目なタイトルの本なんだと思いきや、タイトルの不真面目な目的のために「読書」という行為の本質を驚くほど真面目に深く考察した本だった。
読書とは何なのか、教養とは何なのか、教養としての読書に果たして本の内容はどれ程重要か。
そもそも本を読んだ/読んでいないという状態の本質とは何か 等々を鋭く考察し、その全てを「だから読んでない本について堂々と語っても良い」というタイトルに帰結させている。
その情熱たるや、よっぽどこの著者は「読んでない本について語らざるを得ない状況」と、それに対して後ろ指を指されて当然という風潮にストレスを抱えていたんだなぁと察されてしまった。
読書に纏わる構造分析本としても、読んでない本について堂々語る勇気をくれる実用本としても大変有意義な内容だった。
Posted by ブクログ
書かれてる内容はそれほど気にしていないけれど、著者がこの本を書いた主目的が読書至上主義に対する問題意識にあるのだとすれば、その主張は傾聴できるし、もっともだと思う。
つまり、本書は、具体的な方法を提示すること以上に、読書至上主義に対するオルタナティブとしての読書論を提唱しようとすることに主眼があり、それを相対化することに主目的があったのではないかと思う。
タイトルは「方法」となってるけど、「訳者あとがき」によると、直訳は「読んでいない本についていかに語るか」のようである(p.230)から、必ずしも方法のみを述べようとしていたわけではないことが示唆される。言い換えれば、方法のみならず、読書至上主義が蔓延する社会において、いかに書物と関係を取り持つかという広範囲の意味を含んだ本(のタイトル)だった、と予想できる。
この感想を書くにあたっては「訳者あとがき」を多く参照し、それこそ本書を読まなくても上記の感想を書けたのではないのだろうかと思ってしまう。
Posted by ブクログ
本を書くことは創造である→ただし、今の教育は「それ」を教えない→あるのは理解・記憶・だけで「」がない。
一方で読んでいない本を語ることは、新しい考えを創っている→「それ」は創造である。
本を書くこと、と読んでない本を語ること、は共に創造なので、大いにやれ、と言われたように思いました。
かく言う私もこの本の序と結びしか読んでおりません。笑
Posted by ブクログ
完璧な読書というものはなく、読んだか読んでないかは1と0の差ではなくうろ覚えの程度の差にすぎない。タイトルや著者とか時代背景とかのメタデータだけしか知らない人が、内容をほぼ理解している人と話しても構わない。
本の感想を述べるのは創造的な行為だから、自由に語って構わない。
何と心強い本なのか。
いろいろ例示されているところはあまり関心が持てず読み飛ばしてしまったが、自分が思った通りに語ればいいとこの本は言っている。これから安心して本を読もう。
Posted by ブクログ
本を読むという行動に違う視点があると知ることができた。本を語るためには全体を読むべきと思っていたが、読まなくても語ることができる。その例をいくつか述べていた。
Posted by ブクログ
表題からは若干不真面目な話を想像したが、全くそんなことはない。なんとなく罪悪感や、世間の目があり、本はみんなちゃんと読んでいるフリをしてるけど、本当はそんなことはないし、そうであることすら必要ない。そもそも本について語る時の本は個人の中にある幻影としての書物についてであり、厳密には各個人で全て違うものについて語っているし、それでいい。さらには、本質的に大事なことは全ての本をきちんと読むことではなく、それぞれの書物の位置付けを理解していることであるという主張は納得できるし、ほとんどの本に対しては基本的に流し読みで位置付けを理解することが大事という含意があると感じた。
Posted by ブクログ
この本は読書にフォーカスを当てているが、読書だけでなくネットなどの膨大な情報に触れる際の考え方として参考になる箇所が多いと思った。
とりあえず、全ての本を隈無く読む必要が無いことは感じられ、安心感が得られる。
ただ、所々抽象的な表現で読者を煙にまこうとしているのではないかという箇所があり、この本自体を読み飛ばそうかと思った。
Posted by ブクログ
読書する目的は人それぞれであろうが、こと本書の中で語られている読書は、伝達/議論及びその先の創造に目を向けられているものであると認識。
その前提の上で特に印象的であったのは、教養とは読書量を指すのではなく、全体の中で自身の位置付けを理解することであるという主張。
実際、創造へ向けた一種の触媒として読書を行う場合、様々な本の主張を並列するだけでは何も生み出すことはできない。その中で自身がどこに位置付けられているのか、自分はどの方向を向いているのかというビューなくしては、創造に繋がるようなジャンプは困難であると思う。
その意味において、本の位置付けさえ理解できていれば、読んでいない本であっても何かを語ることができる(むしろその本そのものについてのみ、正確に語ることは難しい;解釈の多様性?)という筆者の主張は、一定の納得感があった。
特に印象的であった部分を以下に引用
「読書のパラドックスは、自分自身に至るためには書物を経由しなければならないが、書物はあくまで通過点でなければならないという点にある。良い読者が実践するのは、さまざまな書物を横断することなのである」(p.263)
「より高いレベルでは、創造そのものが、その対象が何であろうと、書物から一定の距離をとることを要求する(中略)読んでいない本についてのコメントが一種の創造であるとしたら、逆に創造も、書物にあまり拘泥しないということを前提としているのである」(p.270)
Posted by ブクログ
「本を読んだ」とは何かという考察から始まり、どの程度本を読んだのか、本の内容についての認知に対する理解を深め、最終的に「読んでいない本でも語ってよい」という非自明な結論に到達する。
Posted by ブクログ
本書の内容を理解していない証左かもしれないが3度目の再読。
読書とは何か。読書についての規範や固定観念を問う機会を得ることが出来る本だと思う。
著者が指摘する読書のデメリットは示唆にとんでいる。しかし、読書欲に抗い実践することは難しいと感じた。
Posted by ブクログ
書物至上主義を当たり前に受け入れてしまっていた自分に気づき、本を読むことの「正しさ」ではなく「多様さ」を考えさせられるなかなか興味深い本だった。何より、淡々と真面目に論じていることが面白い。
私たちはいつからか
1. 本は読まないより読んだ方がいい
2. 本を読むとは、最初から最後まで読むことであり一部しか読んでいないのは読んだことにはならない
3. 本について語るにはその本を読んでいないといけない
という規範を勝手に受け入れてしまっている。
著者はそれを一旦脇に置いて、それぞれの規範はそんなに大切じゃないことを論じていた。
なんなら、本を読むことはむしろ自由を妨げ、創造することを阻害する営みですらあるという。
暴論とも思しき箇所もありつつ、この本の中に散りばめられた巧妙な仕掛けにやられるという、なんとも悔しい本。
「読み終わる」頃には本を読むことのイメージが瓦解し、次の本を読むハードルが下がっていた。
こうしてこの本もまた通読してしまったわけであるけれども。
Posted by ブクログ
著者は「読んでいない状態」および「読んでいない本について堂々と語る方法」について展開し、読んでいない本について語るという複雑な状況に対するテクニックを私たちに教授してくれるわけだが、そこで重要なのは「自分自身について語ること」だと言う。本について語るのではなく、本を接触点として作品と距離を置く。そして、自分自身について語ることで、創造的な活動が可能になるという。
「読んでいない本について語ることが正真正銘の創造活動であり、そこでは他の諸芸術の場合と同じレベルの対応が要求されることは明らかである。」とピエール・バイヤールは記しているが、その創造の起点がたとえ読んでいないとしても「本」である以上、もし仮にそれが「創造活動」であったとしても、そこには作者に対するリスペクトがあってほしい。
なので、私はやはり読んでいない本について堂々と語ることはないような気がする。読書に夢中になり、想像力を膨らませながらその世界に没頭し、自分の知らない世界のことを疑似的に体験したり、学んだりしたい。そしてその本に心を動かされてどうしようもないときにはじめて、語ってしまうものでありたい。
Posted by ブクログ
タイトルに釣られてしまいましたが、あまり読書をしない方や本を読むことに高いハードルを感じている方にはお薦めの一冊です。
また、読書バカになり、目的もなく読み漁ってしまう自分自身にも教訓として読み返したくなる本でした。
「読書の程度」は、人それぞれで異なり、「読んだ」「内容が理解できた」と決定するのは自分自身であるいう主張は最もであり、現代では本の要約や感想をこのようなサイトを通じて情報として得ることも容易に出来てしまうため、情報として取り入れるだけであれば、読まなくてもこと足りる。自分よりも多くの知識や深い理解で感想や意見を述べられている方も多いので、興味を惹かれる本があればその感想や要約を見れば、もはや読むよりもはるかに情報の吸収率は高いように思われます。
ただし、これはインプットの段階でどれだけの量や質を得られるかということであり、堂々と語る(アウトプット)するには、このインプットを右から左にそのままアウトプットだけでは不十分で、寧ろインプットを最大限にしてしまうと感想や意見、解釈がその情報に引っ張られた物となってしまい、堂々と語れたとしても面白味もなく、誰かが言いそうな感想や解釈程度しかアウトプットすることが出来ないのではないかと思います。一冊の本に対して想像力を巡らせて自由闊達に語ることで、自己も反復してより内容への理解を深めたり、知識を実生活に役立てられる武器に出来るようにも思います。
しかし、全体を見晴らし、想像力を豊かに考えを巡らせることで「堂々」と語ることが出来るは、やはり厖大な知識と読書の賜物であるようにも思います。
前提として、読んでいない本=全くもって情報がない物ではありません。
知らない言語で書かれた翻訳もされていない本を渡され「この本について語ってみて」と頼まれて、すぐに語れるという魔法のような方法を教えてくれる本ではありませんでした。寧ろ、蓄積された情報や対象となる本の前後に配架されている本を見極める洞察力が必要であること。そして、「全体を見晴らす」ための明確な目的が最も必要とされており、本のタイトルにある「堂々と語る」ことを目的とするならば、最低限の教養や論理的な思考がないと不可能であると思われました。
著者は読書をほどんどしないと語っていますが、これも程度の問題であり、おそらく活字から情報を得る機会は一般の人よりも多いと考えれます。
魔法のような本だと思い、購入してしまいましたが、そのような目から鱗のハウツー本ではなく、読書に関する考え方などが論理的に著名な作品を例示しながら述べれらている硬めの書物でした。<流>〇
Posted by ブクログ
てっきり目次やあとがきだけを読んで…といったような実践的なHow toが書かれていると思っていたが、実際のところは書物の脱神聖化(語りや共通認識の醸成のためのツールでしかない)や書物(ヴァーチャルな意味での)の可変性を再確認する本だった。し、ずっと本の中身の話してましたからね。(敢えて記憶誤り的な要素醸し出してたけど)
私はこうして、頭からお尻まで一応読み通した本をケチケチと一冊ずつ記録しているのだが、果たしてこれが人と話す契機になっているのか…むむむ
読まなければならない本かと言われればそうでないかも。
Posted by ブクログ
著者が大学の文学の教授とのことで、本書は主に読んだことがない文学・小説に焦点を当てて論じる構成だった。
書物を教養として考えるのなら、各書物の個別具体的な内容を知るよりも、その書物がどんな影響を受けて書かれ、どんな影響を周囲に及ぼしたのか、など、文学界での位置づけを理解するほうが重要とのこと。
実際、著者は読んだことがある本・ない本の両方を、本書で論じる上で使っており、なるほど読んでいなくてもこんなに文章を書けるものなんだなと感心した。
ところで本書の面白いところは、読書はしなくていい・流し読みでも大丈夫、と言いながらも、著者が言いたいことを理解しようと思ったらじっくり読まないといけないところにあると思う。難しかった。
3つの気づき
・「読んでいない」にも種類がある(完全未読、流し読みした、読んだけど忘れた、等)
・同じ本を読んだ同士で、必ずしも会話が成り立つわけではない
・本の批評はもう創作になりえる
Posted by ブクログ
なんかニヤニヤしながら読んじゃった。面白い。べつに読まなくても「どんな本か」という位置づけを知っていれば十分、とのこと。
京極堂の師匠もそうおっしゃっていましたね。
本と本は繋がっているし、人間は日々変化するし忘れるので実際読まなくてもOK、ということで励まされる(?)本でした。
Posted by ブクログ
読んでない本について語ることは正真正銘の創造活動。他の諸芸術の場合と同じレベルの対応が要求される。
気後れせずに
自分の考えを押し付けて
本をでっち上げて
自分自身について語る
という心構えでいればそれでOK!!!
訳者あとがきの、
本書の目的の一つは、読書コンプレックスからわれわれを解放することである。との一説は面白い。
本を読んだとラーメンを食べたで考えると、
ラーメンを完食は分かりやすいが本の完読は何を目安にするのかな?
Posted by ブクログ
本を読んだ人は誰しもがその時点で自分なりの解釈や意見を持つ。つまり、読んだ文章は一緒でも、受け止め方は十人十色なのだ〈スクリーンの書物〉。それは何を意味するのか。
すなわち、本を読まずに感想を述べても、本の「全体の見晴らし」を理解していれば読んでいない本について堂々と語ることができるのだ。読んだ人全員が同じ意見を持つわけでもないし、読んだ本の詳細な内容を完全に暗記している人はいないのだから。
どうせ本の内容は悲しいかな、忘れるのだからタイトルや作者から内容を創造〈横断〉するのも良いのではないか。
本書では、本を読む人の持つ感想のあいまい性を一貫して主張している。本文となる説明は知らないと理解するのが難しいので、各章の序文と結論だけでも得られるものはあると思う。