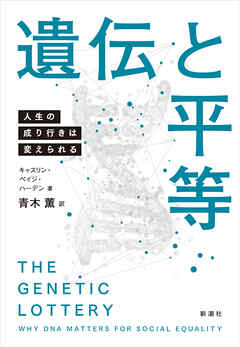あらすじ
遺伝とはくじ引きのようなもの――だが、生まれつきの違いを最先端の遺伝統計学で武器に換えれば、人生は変えられる。〈遺伝と学歴〉〈双子〉の研究をしてきた気鋭の米研究者が、科学と社会をビッグデータでつなぎ「新しい平等」を指向する、全米で話題の書。サイエンス翻訳の名手、青木薫さんも絶賛する、時代を変える一冊だ。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
とても読みやすい、とは言えないけど、必読。こうした遺伝の影響を考慮に入れずに、平等とか教育などは議論できない。ただ、とてもセンシティブで、繊細な理解が必要で、単純化するととても害のある暴力的なものになってしまう。理解も難しいが伝え方も難しい。平等も教育も、それこそこれからの国家や人類の行く末にとっても重要な課題で、この本に書かれているのはその根幹をなす知識なわけで、本当に重要なんだけど、単純化しないでちゃんと理解する必要がある。地道に読んで理解する価値あるし、そういう人が増えてほしい。
Posted by ブクログ
遺伝に関する言説について、特に優生学に繋がっていくような言質が蔓延っている中、決定論的に全てを形作るものではないが、人生の成り行きを形成する重要なファクターであるということを認識した上で、どう平等を実現するか、という思考への過程が記されていて、目が覚める思いでした。
遺伝による差は確かに存在するが、その生まれながらに得た人間の価値と、社会的に価値づけられた価値を混同してはならない、という言葉には、昨今の社会的な雰囲気に一つ明かりが見えた様な感覚になりました。
Posted by ブクログ
優生学は、理論的根拠として遺伝学を取り込み、間違った考えや歴史を生み出した。いまだに私たちの無意識にも、そのような悪しき優生思想の片鱗が存在しているかもしれない。
自己責任という言葉もそう言った優生学の考えが下敷きにあるからこそ、出てきて、物事の本質を見ないで責任をその人自身の責任にすり替える言葉だと思う。
この本は、遺伝学をニセ科学の優生学から取り戻すための、挑戦の書である。
親ガチャの呪いから我々は脱却することができるのだろうか?そのヒントがこの書には丁寧に記述されていました。
人はこの世に誕生する時、2種類のくじを引かされる。「社会くじ」と「遺伝くじ」だ。
社会くじは、格差や不平等に結びついている。一方、遺伝くじが、優劣や格差と結びついている根拠を丁寧に紐解く。遺伝子の違いは、能力の優劣ではなくて、能力の違いにすぎない。能力が違うからこそ、それらを受け入れ、包括的思考で公平な世界を作る提案をしているように思った。
この本では、遺伝的な違いを活用して人生を変える可能性について述べている。具体的には、遺伝学の成果を利用して個人の生まれつきの特性を理解し、それを武器にすることで、教育や社会的機会を最大限に活用できるとしています。これにより、遺伝がもたらす不平等を是正し、「新しい平等」を目指すことが可能になると主張しています。
読んでよかった。
Posted by ブクログ
子どもが育つ社会的環境的条件と、子どもの人生には関係があることは前提=社会くじ。
遺伝子の偶然も子どもに影響するか。遺伝子の影響も子どもは選べない=遺伝くじ。
遺伝子の影響を議論すると優生学的とみなされる。
人種間に遺伝的な違いは無い=人種とは、人類が分類したモノに過ぎず、遺伝子的には広汎な選択肢がある。
遺伝子は多様正がある。ふたりの親から生まれる子どもの遺伝型は70兆以上の組み合わせがある。一つの特徴的な遺伝情報は、プールの中の一滴のインクのようなもの。エンドウ豆のように単純ではない。
遺伝子はたんぱく質をつくるレシピ=レシピが同じでも同じ料理はできない。GWAS(ジーワス)=ゲノムワイド関連解析で遺伝子を調べても、遺伝的多様性のほんの一部しか分からない=ポリジェニック性がある。身長を決める可能性のある遺伝子だけでも10万以上ある。
人間の特性が遺伝的な人種間の違いがある、というのはあり得ない。
祖先は、遡ると広がる。しかし、数千年も遡ると全員は同じ祖先になる。その祖先の遺伝子が紛れ込んでいる可能性は低い。
人種は、政治的に差別するために人為的に作られたもの=血の一滴ルールなど。
アフリカの住民の祖先はアフリカ系遺伝子を持っているが、ヨーロッパ系の祖先も持っている。遺伝子はそれぞれがいろいろな祖先を持っていることを示している。
統計学の生態学的誤謬=平均としての違いをグループの平均と捉えること。遺伝子の違いを人種の違いと考えることは間違い。
人種に生物学的な根拠はない。しかし人種集団ごとに遺伝子が違うことは確か。
ルーマニアの里子実験。ルーマニアの孤児たちを里親に出すか、出さないかで後のIQを調べた実験。30ヶ月を超えると変わらないが、30ヶ月まででは、早い時期に里親に出した方がIQが高かった。
里親は、IQの原因か?原因と断定するには「反事実」性が必要=第1の対象がおこらなかったとしたら、第2の現象は起こらないこと、が必要=科学的思考の基礎。
ランダムに振り分けることはその一つの方法。薄い因果関係のモデル。染色体異常でダウン症になることは濃い因果関係。
遺伝子は兄弟間でも共有率にばらつきがある。50%前後。遺伝子が異なれば人生は異なるものになる。
高い方を削って全体を均し、格差を小さくする=最悪の環境をつくると格差は小さくなる。悪い環境より良い環境のほうが遺伝率は高い=遺伝的差異を発揮しやすい。
豊かな環境下での教育は格差が広がる。
遺伝的な運による不平等も憂慮すべき。
機会均等はごまかし、不平等を言い訳する方法。
マタイ効果=マタイの福音書による、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は取り上げられる、=介入プログラムはこの傾向にある。最も恩恵を受けるのは中流家庭の子どもたち。
遺伝情報が間違った方向に利用されないか。
遺伝学を正しい方向に使うべき。
遺伝を無視するのは、暗黙の共謀。
遺伝情報を得るコストは下がっている。
犯罪行為に対する遺伝情報は受け入れられないだろうが、うつ病や肥満はどうか。遺伝的性質が元々備わっている、とすると対処を必要とするのではないか。
発話障害の遺伝率は90%以上。
鉛中毒の測定にIQテストが使われた。
SATの特典はIQと0.8の相関がある。
優生学、ゲノムブラインド、アンチ優生学、どの道を選ぶか。遺伝データを活用して適切な介入をすべき。
数学のポリジェニックスコアが低い生徒は高校から数学をドロップアウトする。その時点で救う介入は成り立つだろう。機会の平等だけでは不公平。
アメリカはメリトクラシーの国=メリットとアリストクラシーを合わせた造語。社会のエリートは、メリット故に選ばれた人であるべきという考え方。カースト制よりはいい。
アメリカの絶望死=自殺、薬物過剰摂取、アルコール依存症、による死。
ロールズの無知のヴェールをかぶって考えれば、遺伝的性質を考慮した社会を作るべきと考えるだろう。
優生思想と戦うのは、遺伝的に平等だと考える方法だけではない。遺伝子を無視すると、環境因子を変える努力も無駄になりかねない。
Posted by ブクログ
三代遡れば8人分。我々は先祖代々受け継がれるものをランダムに配置されてきた。人は生まれながらにして違う。それを認めなければ格差はなくならない。得手不得手は遺伝子が決める。機会均等にしても結果には運が左右する。何が優位かは時代で変化する。バリエーションの多さは種の存続のため。更に、自由主義経済では消費が生産を促す。富の独占では生まれる価値に偏りが出る。優勢思想は今この時代をも衰退させる。苦手なことは補完されて、得意なことは活かされる。出来も不出来も受け入れて、素の姿を尊重する。そんな社会を目指していきたい。
Posted by ブクログ
著者はテキサス大学の心理学教授。本作が処女作ということになるようだ。訳者は「フェルマーの定理」の訳で有名な青木薫氏、最近ではブライアン・グリーンの大著「時間の終わりまで」などがあり、科学啓蒙書の翻訳には定評がある。本書もそれらの例に漏れず訳がこなれていて読みやすい。
著者の主張は本書で幾度となく言及されているように、政治哲学者ジョン・ロールズの思想の強い影響下にある。ロールズによれば、「遺伝子セット(自然的偶発性)」と「社会的環境(社会的偶発性)」は、内在的であるか構築的であるかの違いはあれど、どちらも人間の表現型(実際に発現し測定可能な特質)に作用し、人生の広範な局面に影響を与えるのであり、道徳的見地から甘受すべからざる不平等の原因であることには変わりない。
従って、前者は絶対的で後者は相対的だとする〈優生学〉の立場は、遺伝の存在を理由にそこから生ずる社会的不平等を放置する無責任なニヒリズムだということになる。また、本来価値中立的な遺伝的情報の差異を即座に社会構築的な(主に西洋白人種を中心とする)価値のヒエラルキーに還元してしまう伝統的な価値基準についても、遺伝子が社会的「価値」に与える影響を吟味せず、生得的なものに盲目的に価値を割り振ろうとする硬直的な価値判断基準であると批判する。
さらに、そもそも不平等の原因を炙り出すような遺伝子セットの研究自体を不道徳であるとして忌避しようとする〈ゲノムブラインド〉の立場も、不平等と「暗黙の共謀」関係に立っているとして強い批判の対象とする。個体差に遺伝の影響が存在することを認めることと、遺伝の結果生じる不平等を放置することは全く異なるというわけだ。
上記2つのアプローチを批判した上で、著者は〈アンチ優生学〉の立場に立って公平性に関する政策を遂行すべきだと説く。
双子研究の成果によれば、現在各国で用いられているゲノムブラインドなアプローチは、貧困世帯における認知能力の遺伝率(=遺伝子の表現型に対する影響度合)を低める、いわば優秀な遺伝子の発現率を阻害するように作用しているという。著者はそのように「高い方を削って全体を均す」のではなく、社会にとって遺伝的に最も不利な因子を持つ人々を遺伝子検査によって特定した上で、それらの人々が幸福な生を生きるために必要なリソースを割り振ろう、と主張する。このように本書には、「構築的であるにすぎない現代社会の価値観に照らして、生得的に有利な因子を持って生まれてきた幸運な個人は、その恩恵を社会に還元すべきである」という、ノブレス・オブリージュ的な発想が根底にある。
先述のロールズの提唱した有名な概念に「無知のヴェール」があるが、遺伝子検査にはこれと同じような機能があるのだ、というのが本書の梗概なのだと思う。無知のヴェールを被れば個々の前提条件が取り除かれ、最も不利な立場に立って公平とはなにかが考察できるようになる。同様に、遺伝子検査によってどのような遺伝子型が最も不利な表現型につながるのかがわかれば、その遺伝子と表現型の間の長い因果の鎖のどこにどのように介入すべきかを判断する際の不確定要素が取り除かれる事になるのだ。「遺伝子研究の歩みを止めるな、なぜならそれは単に功利的ではない公共の福祉、真に道徳的な公平性につながるのだから」という力強いメッセージを感じた。
Posted by ブクログ
ヒトゲノムが解読された時に「全ての人間は99.99%同一だ」と言ったクリントン大統領の発言は間違っているし、間違いの上に社会基盤を構築しようとするのも間違っている。遺伝による違いは歴然と存在しており、学業の達成度や社会的な成功に関係している。ただし、それは優劣という比較の対象になるようなものではなく、運良くたまたま受け継がれたにすぎず、次の世代に受け継がれていくという保証もない。
必要なことは機会の均等(全ての人に同じ教育機会を与える)ではなく、個別化、最適化された教育である。ろうやアスペルガーが障害でなく特性だ、というのはやや言い過ぎのように思うが、公平と平等の違いなと、遺伝的な差異と社会制度について考えさせられるとことも多い。
著者には二人の子供がおり、一人は普通でもう一人は発話障害があるという。このことからも行動遺伝学には馴染があったらしい。全般に翻訳が素晴らしく、出版社のサイトにも詳細な脚注が載せられていて出典にも当たりやすい
・過去の優生学への反省から、学業に関する研究は遺伝を一切無視したゲノムブラインドの立場をとる研究者も多いが、ここに遺伝が関与していることは明白で、無視すべきではない。
・GWASの結果、個人のポリジェニックスコアは計算されるし、それが学習の達成度などを説明はできる。ただし、GWASは個人の環境などは一切考慮していない
・遺伝子があるから結果が怒る、など因果というものについて、ヒュームは
1)AがあればBが起きる
2)AがなければBはない
の二点が必要と考えたが、1はともかく、2は通常の科学的な検証には乗りにくい。
・遺伝学は、比較的よく似た環境に生まれ育った人たちが、異なる人生を送ることになるのはなぜかを理解するためには役立つ方法だ。しかし、明らかに異なる出発点にたった人たちが、同じような人生を送らない理由を理解するためには役に立たない。
Posted by ブクログ
遺伝と「平等」と言うと、優生学とか過去の色んな犯罪学とか絡んできて若干引くところがある。
筆者も、それは否定しないし、実際過去にはそれが利用されて来たのも事実。
だが、社会的成功や人生に、「遺伝」が絡んでいることは、否めない事実であり、それに目を瞑ることもまた、誤りにつながると論ずる。
前半は、様々な遺伝に関わる研究の成果、手法の進歩、問題点について触れ、遺伝の影響を排除は出来ないことを述べ、後半でそれを前提にした上で、では、どう言う社会を作っていくのが望ましいのかを説明していく。
いい内容だと思う。
環境ガチャと遺伝ガチャは事実であるが、いくつかの特定の遺伝子に起因する病例などを除くと、極めてたくさんの因子が絡んでくる為、簡単にこの遺伝子が決定的とは言えない。あくまで統計と確率の問題ではあるが、それでも確実に、傾向はある。
遠くから見ればはっきりするが、近づくほどぼやけると言う言葉もいいな。
そうして、そうして「不平等」を一番背負った人が幸せになるための適切な介入はなされるべき。
生まれ持ったものを「手柄」には出来ない。
自分が何であるか、何になるのかが不明な状況で社会は設計されるべき。
感謝と謙虚と援助だな。
Posted by ブクログ
面白かった。
各種研究の結果は肌感覚に照らしても納得感が強かった。現代の知識社会で高い評価を受けがちな能力・特性に、遺伝はまあまあ影響している。
個人的には「遺伝学を優生学と混同しないで!」と言うためにどれだけ紙幅を割くのか……と感じてしまった。
内容の割に文が重たい。それだけアメリカの状況が複雑だということなのかもしれない。
Posted by ブクログ
優生学や人種主義と結びついた遺伝学の悪歴史が「人は皆同じ」に固執させ、最新テクノロジーとなった遺伝学の活用を妨げている。同じ遺伝子でも社会や成育環境が異なれば成り行きが変わるとはいえ、適切に使えば効率的な介入や政策が可能になる。
社会のタブーになってたり、一部の人たちだけのメリットになってたりじゃなくて、ほんとに、適切に扱えるようになるといいと思います。
Posted by ブクログ
遺伝の影響は軽視もできず、かといってタブーもしてはいけない。咀嚼が難しい本。ただ、我々はたまたまうまくいっている、という点を心には留めておきたい
Posted by ブクログ
少し内容的には難しかったが、今まで人を分ける時にはそれは優生論となってしまい、あまり遺伝と人の関係は研究されて来なかった。
だけども、人は誰しも違う遺伝子に生まれ、それが個性として現れることは事実である。
生まれた時の遺伝子と生きる環境によって人の人生は変わってくる。
よく言われる親ガチャは悪い意味で使われがちだが、人が親からもらってるもの、遺伝子が違うのは事実である。
それをうまく利用することで社会を良くすることはできるかもしれない。
そう思わずにはいられないが、持つものが結局は負担が大きくなる。それには結局は反感を買ってしまう部分があり、どうなのだろうと思ってしまう。