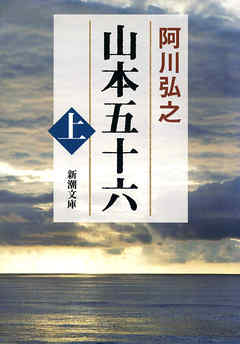あらすじ
戦争に反対しながら、自ら対米戦争の火蓋を切らねばならなかった聯合艦隊司令官山本五十六。今日なお人々の胸中に鮮烈な印象をとどめる、日本海軍史上最大の提督の赤裸々な人間像を余すところなく描いた著者畢生の力作。本書は、初版刊行後、更に調査し、発見した未公開資料に基づき加筆された新版である。上巻では、ロンドン軍縮会議での活躍を中心に、若き日の山本像が描かれる。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
山本五十六。背丈は160cm,60kg弱,骨組みも女性的で華奢な方で,指などはピアニストのような指をしていた。また,太平洋戦争では,山本の指は8本しかなかった。2本は日本海海戦の時,少尉候補生として乗り組んでいた軍艦『日進』にロシアの砲弾が命中してそのとき失ったのだ。
山本が海軍部内で頭角を現して来たのは,ロンドンの海軍軍縮会議予備交渉の海軍側首席代表に任命された頃からだった。日本国内ではもとより,アメリカや英国やドイツの政府,海軍上層部でその名を知られるようになったのだ。ワシントン会議では主力艦に関する英米日比が5対5対3に決定した。しかし,日本が対米英6割という比率に,海軍部内が満足したかというとそうではない。これは,海軍部内でも意見が対立し,やがて条約派と艦隊派と呼ばれる派閥を発生させる。
日本は始めから対米英6割を呑む腹で交渉に臨み,それがアメリカ側に外交電報を解読されていた。交渉は始めから負けていたと言える。ワシントン会議に全権で挑んだのが加藤友三郎である。広島出身だ。当時はアメリカを仮想敵国として八・八・八艦隊建設計画が着々と成果を上げてきており,中心人物は加藤であったが,海軍比は国家予算の3分の1を占めるようになり,やがて総軍事費が総予算の6割にまで膨張する計画となって,経済上国民の負担能力の限界という壁に突き当たってしまっていた。加藤自身が推し進めてきた艦隊建設を放棄せざるを得なくなり,放棄するその決心を固め,原首相とも話し合って会議に臨んでいた。八・八・八艦隊は,対米7割を目標とした海軍であり,これをもって米国を制することは不可能としても,アメリカの艦隊が西太平洋に進攻して来た場合,日本が互角の戦いをする最小限の海軍であった。したがって,対米英6割を呑む決心をすれば,仮想敵国アメリカという想定を葬ってしまわなくてはならない。
加藤はこの時,はっきりした考えをもっていた。金がなければ戦争ができず,米国以外に日本に金を貸してくれるところはない。米国が敵となれば,開戦時は仮に軍備が拮抗しても,その後が続かないのである。日本はこのため,アメリカと戦争をしてはならないと。国防は国力に相応する武力を整えると同時に国力を涵養し,一方,外交手段により戦争を避ける事が目下の時勢に於いて国防の本義であると,日米不戦論,不戦海軍の思想を述べている。しかしこういう考え方は,当然,一部の人々には米英の顔色を伺っている卑屈な弱腰に見えたのであろう。対米7割を主張し続けた加藤寛治提督は,ワシントン会議に海軍専門委員として列席していたが,帰国後,その不満をぶちまけるようになり,それが海軍少壮将校はもとより,国民の多くに強くアピールすることになった。仮想敵国はアメリカ,そのための所用兵力は八・八・八艦隊と,明けても暮れても唱え続け叩きこまれ続けた大勢は到底一朝にこれを転換しえぬものだった。軍艦土佐などは,当時世界最強の戦艦のひとつになるべき船であったが,ワシントン条約で廃棄処分が決定し,宿毛湾の南で海底に自沈させられた。日本人が食べる事も寝る事も置いて,まさに心血を注いだ巨大な戦艦を米英の圧迫と上層部の弱腰とによってむざむざ海底に廃棄してしまうのかと考えると,一部の人たちの国民感情としては,それは我慢のできないことであったろう。
加藤寛治は間もなく軍令部次長の地位に就き,その下に末次信正が座り,一方,加藤友三郎は大正12年の夏に亡くなって,部内の重石が取れてしまうと,対米強硬論の艦隊派と,加藤友三郎の流れを汲む条約派との対立が一層はっきりしだした。山本五十六が言う,負けるに決まった対米戦争に日本が突入する遠因はこのころにあった。ただ,どんな強硬派でも,昭和10年ごろまではアメリカに戦争をしかけて勝てると考えるほど勇ましく無知な人物はたくさんはいなかった。海軍の責任ある立場の軍人で,当時,無敵艦隊とか,無敵海軍とかいう言葉をみだりに用いるものはいなかったようだ。『無敵艦隊』とは景気付けの形容詞であって,のちに自らが『もしかしたら,ほんとうに無敵なのではあるまいか』と思い始め,歌謡曲で『無敵』と唱えだした時,帝国海軍はもう滅びの支度をはじめなくてはならなかったのである。ただ,強硬派にも論理はあった。戦時における洋上の力関係は,保有兵力Nの2乗に正比例する。静的状態での10対6は,運動を加味すると100対36になる。アメリカに侵攻して勝てるとは思わないが,優勢のアメリカ艦隊が日本へ攻めて来た場合,洋上にこれを邀撃して敗れないためには,少なくとも100対49の,つまり,対米7割の海軍兵力が必要であり,そうでなければ,国防の責任を負いかねるというのが,強硬派の言い分であった。したがって,彼らの間には,軍縮会議はもうこりごり。条約で縛られるのは真っ平という空気が強く存在していた。これら強硬派の人たちは,戦前,戦中,戦後を通じて,山本に対しては終始極めて批判的である。山本五十六は誰にも親しまれ,敬愛された人物のように一般には考えられているが,事実は必ずしもそうではなく,彼には部内にかなり敵がいたというのが実情のようである。
山本はアメリカ駐在2度の経験から,デトロイトの自動車工業と,テキサスの油田を見ただけでも,アメリカを相手に無制限の建艦競争など始めて,日本の国力で到底やりぬけるものではないとよく言っていた。6割,7割で深刻な対立が生じているが,7割で日本の安泰を保持できると言うようなものではないと山本や堀や井上成美は考えていた。日本に不利な条約を結ぶ事は好ましくないが,無条約状態に入る事の方がそれ以上に好ましくないと考えたのであり,5対5対3は,裏返せば,米英を日本の6分の10に押さえれたということの方が重要であるということであった。
ここで,山本の生まれについて言及しておきたい。山本は江戸時代で言う長岡藩出身である。実の祖父である高野秀右衛門貞通は,維新戦争の際,官軍と戦い,七十七歳の高齢で敵陣に斬り込んで死んでいる。長岡藩には,山本帯刀という,河合継之助が重傷を負って立つことができなくなった際に,代わって長岡藩の総司令官になった人がいる。この山本帯刀が系譜上の五十六の養祖父である。その帯刀も,官軍に捕らえられ,降伏を肯んぜず斬られている。山本家は代々長岡藩の家老職であったが,帯刀が死んで,維新の際,御家廃絶となり,明治十六年になって許されたときには跡が途絶えていた。その後,他家に嫁していた帯刀の長女が便宜上当主となり,家名を再興した,大正四年五月,五十六が少佐の時,高野貞吉の末子であった五十六は望まれてこの山本家の相続人となったのである。
ワシントン条約は有効期限が昭和十一年に満了する。日英米仏伊の5カ国で条約が切れた後の新しい海軍軍縮協定の予備交渉を始めることになった。ただ,仏伊は海軍国として日米英と格段の開きがあったので特に重視すべき交渉相手ではなかった。当時の日本の国内事情は,ワシントン条約をそのままの形で継続することはできないという雰囲気が支配的であったが,ただちに無条約状態に入っていいと考えていたわけではなかった。不脅威不侵略の原則の確立,その不脅威不侵略の方式は,各国の保有兵力量の共通最大限を規定したい,つまり,日米英,あるいは仏伊とも,海軍兵力をどの程度まで持っていいかと言う共通の限界を定めて,その線は各国平等にしてほしい,そのかわり,それを出来るだけ低いところに引いて,攻撃的兵器は廃棄し,防御的兵器の充実にお互い力を入れようということであった。この主張に対する米英の考えには違いがあった。アメリカは全く反対であったが,イギリスはアメリカの武力拡充に脅威を感じてきており,日本の考え方にはある種賛意を示したが,結局,アメリカが引かず,協議は物別れに終わってしまった。
山本は無類のギャンブル好きだった。いつも時間があれば,若手将校達と一緒にブリッジやポーカーなどをしていた。山本が初めてモナコで遊んだとき,あまりに勝ちすぎるので,カジノのマネージャーが最後には山本の入場を拒絶したという。そういう客はモンテカルロの賭場が始まって以来2人目だという,そんなエピソードもあったほどだ。
そして山本は昭和13年3月にアメリカから帰国した後,巡洋艦五十鈴の艦長になり,12月に航空母艦赤城の艦長に変わった。
2・26事件は,決起部隊を叛徒として鎮圧し,首謀者を軍法会議にかけ,非常の事態を収拾して粛軍を断行したかに見えたが,事実は決してそうではなかった。一口に言えば,これを境として,陸軍部内の皇道派が追われ,統制派が主導権を握り,軍の政治的発言力が頓に強化されたのであった。統制派を主体とする陸軍に下克上の風潮は一層甚だしくなり,それをひこずって終いには太平洋戦争までつっこんでいくのである。
陸軍の要求を呑んで組織された広田弘毅内閣は,国策の基準の大綱として,『外交国防相まって,東亜大陸における帝国の地歩を確保すると共に,南方海洋に進出発展するにあり』という多分に侵略的匂いのする露骨なものであった。山本は,航空本部長を何年でもやっていたいと思っていたので,こういう情勢下で永野修身海軍大臣から自分の次官になってくれと言われても,ありがた迷惑であったに違いなく,何度かこれを拒否したが,最後には仕方なく辞令をもらう派目になってしまった。こうして,山本は渋々海軍次官の椅子に座り,これより,広田,林,近衛,平沼の四内閣にまたがる苦闘が始まる事になった。
その永野も間もなくお手盛りで連合艦隊司令長官に出て行ったが,その代わりに,米内光政が海相に座った。この米内を最も強く押したのが山本だった。山本は次官として軍政面に携わるようになった以上,自己の政治的な責任,海軍の政治的な使命についても考えないわけにはいかなかった。海軍の政治的使命とは,このまま行けば道は戦争から破滅へと通じているだけで,事実上もう,陸軍の横暴をチェックできるのは海軍しかないという自覚があった。それには,末次信正大将ら部内の強硬派かつ陸軍への同調派を場合によっては首を切ってでも海軍を一本に立て直すよりほかはなく,そしてそれには米内以外に人はいないと山本は考えたのである。永野の置き土産の山本次官の上に米内光政が大臣として座って,海軍はこれ以後,初めて見事な統制の下に置かれることになったのである。
当時の日本国民も軍も政府も全てが余りにも緊張し伸びきってしまっていた。ゴムをいっぱいに引っ張り,伸ばしきってしまったら再びゴムの用をなさないのと同じように,国家として緊張するのも大切だが,その反面には常に弾力性を持つ余裕がなければならぬというものだ。
そうこう言っているうちに,平沼内閣の総辞職に際し,米内の海軍大臣もお役御免となり,後任に山本と同期で,連合艦隊司令長官の吉田善吾中将が決まった。そして,その吉田の後任に,連合艦隊司令長官兼第1艦隊司令長官に山本五十六が就任することになったのである。
第2次近衛内閣が出来ると,それまで米内が必死になって抵抗していた日独伊三国同盟があっさりと成立してしまう。これを機に,日本はアメリカとの戦争に不可逆的になったのではないか。建艦競争でも対米英作戦の問題でも,総人口がいくらで男が何千万人,そのうち工業に振り向けられる人間が何パーセント。水兵として徴募出来る者は最大限いくら,軍艦一隻に必要な乗員は何人,と,数字から割り出せば,無理に軍艦を造ってみても,動かす燃料がなく,乗せる水兵がいない,船は軍港に繋いでおかなくてはならないという結果が出て来る。そんな馬鹿な軍備はない。ただ,当時,そのような事を言えばすぐに”西洋かぶれ”といって罵られ,どんな不合理な事でも皇国日本は違うと言われ,下手をすると命まで取られかねない状況であったという。海軍部内でもこのような神がかりに同調できない良識派は,つい大声を出すのが嫌いで,概して沈黙を守っているということであった。そんな神がかりな議論を山本も嫌いだったという。