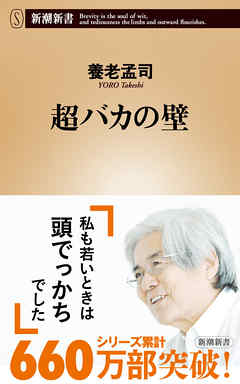あらすじ
「今の日本社会には、明らかに問題がある。どんな問題があるか。私はものの考え方、見方だと思っている。そこがなんだか、変なのである」――フリーター、ニート、「自分探し」、テロとの戦い、少子化、靖国参拝、心の傷、男と女、生きがいの喪失等々、現代人の抱える様々な問題の根本が見えてくる。「バカの壁」を超える方法、考え方は自分の頭で生み出す。そのためのヒントが詰まった、『バカの壁』『死の壁』に続く、養老孟司の新潮新書第三弾。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
バカの壁、死の壁と続いてこれ。
何故か前2冊よりわかりやすく感じた。
なぜだ。なぜなんだ。
それでも難しい。一度読むだけでわかったような気になりたくないような、また読み返したくなる本。
毒舌でくすりとなるところもあり、とても好きだなあと思いました。
Posted by ブクログ
バカの壁、死の壁の続編、帯にこの「壁」を超えるのはあなた とある
相談をするときに、具体的な答えを期待する人がある。それはおかしい。自分のことは自分で決めるので、相談とは、根本的には「考え方」についての疑問である。他人に伝えることができるのは、「考え方」だけである。
人生とはそうした「些細な」体験の繰り返しである。歳をとれば、その「些細」が積もり積もったものになる。
バカの壁は超えられなくても、超バカな壁は超えることはできるのだろうか。
読んでいくうちに、著書は結構、極論が好きなのではというところが結構ありました。
気になったことは以下です。
・国民皆労働が常識になったのは戦争のせいではないかと思います。今は豊かになってから、ある程度の人数が働かないで済むようになったのです。
・働かないのは、「自分にあった仕事を探しているから」という理由を挙げる人がいちばん多いという。これがおかしい。二十歳そこらで自分なんかわかるはずがありません。中身は空っぽなのです。
・会社は全体として社会の中の穴を埋めているのです。その中で本気で働けば目の前に自分が埋めるべき穴は見つかるのです。
・そもそも仕事は世襲でもいいのです。世襲というものは一時期、悪の権化みたいに言われていました。封建的だとか何だかという批判です。
・医者の世界でも三代目なんてケースは珍しくありません。要するに、地盤、看板が必要な職業は世襲にならざるを得ない面があるのです。「先代が死んだからもう病院を閉めます。さようなら」では、地域が困ります。世襲ならば、設備などのハードの面をスムースに引き継げます。その代わり子供が幼いときから職業のことをたたき込むのです。もし子供がいないか出来が悪いければ、外から才能のあるやつを引き抜いて養子にすればいい。
・「秀吉の草履取り」、本気でやることの大切さを教えているものです。秀吉は、草履取りを本気でやた。初めから本気でやれば、あそこまで偉くなれるという話です。だから本気で仕事をしろと教えているのです。
・ナンバーワンよりオンリーワン。努力すれば夢はかなうという幻想。
・時を中心に考えれば、本当に大切なのは、先見性ではなくて普遍性なのです。その人が普遍性をもっていらいつか時が来る。その人に合った時代が来るのです。
・日本人の自分は、西洋人とは違います。西洋人の I ト 日本人の私は実は違うものなのです。
・頭とは、いいよりも丈夫なほうがいいことが多いのです。
・あなたの考えが100%正しいということはないだろう。せいぜい60%か、70%だろうと言っているのです。
・倫理とは個人の問題なのです。
・税金はがんで死にそうな人でも収入があれば、取られています。だから「血税」というのです。
・生物学的にいうと、女のほうが強い。強いということは、より現実に適応しているということです。つまり無駄なことを好まないということです。
・複雑すぎる機械は壊れやすい。だから女というものは、比較的シンプルな作りになっているのです。
・都市化ということは、根本的に子供を育てることに反するからです。
・子供には個性があるから大事にしましょうというタイプの教育は、戦後すぐには始まっていました。その個性を大事にすることが子供を大事にすることだと思ってしまう。だから、親は子供に教えない。教えるということはある意味では叩き込むことです。
・昔に比べると子供は大事にされているというのはウソです。それは甘やかしていることと大事にしていることを混同しているだけです。
・私には、戦争責任はありません。本人の記憶のないことについてあれこれいうのはおかしなことです。実感がないから、当時のことなんかわからない。私に責任がないならば、若い人に戦争瀬金があるはずありません。
・靖国神社に参拝するのは小泉首相の勝手です。憲法で「思想及び良心の自由」「信教の自由」は保障されているのです。ただし、政教分離なのですから、日本国総理大臣と署名して参拝するのだけはやめればいい。
・人間は金以外の動機で動くものなのに、ほとんどの人はそうではないと思っている。金とは単なる権利だということがわかっていないからです。
・原則を持つ、原則ができればどんな苦情にも答えられるようになります。
・本気の問題。きちんと正面からぶつかる経験をしておけばよかった。
・雑用のすゝめ。若いときにはいろんなことをやってみることを勧める。
目次
まえがき
1 若者の問題
2 自分の問題
3 テロの問題
4 男女の問題
5 子供の問題
6 戦争責任の問題
7 靖国の問題
8 金の問題
9 心の問題
10 人間関係の問題
11 システムの問題
12 本気の問題
あとがき
ISBN:9784106101496
出版社:新潮社
判型:新書
ページ数:192ページ
定価:760円(本体)
発売日:2006年01月20日
Posted by ブクログ
養老先生の考え方が書かれています。
下記記憶に残ったものを抜粋しています。
自分の好きな事を見つけようとするのは無理がある。社会で働くというのは、山を作るのではなく、空いている穴を埋める事だ。
I≠私
privacy(私情) とindividual(個人)
という全く別の言葉が
私
という漢字で表されている。
Posted by ブクログ
思考を固定化し、ラクをすると壁(『バカの壁』)の外が見えなくなる。
自分は変わらない、というのは、一見楽なこと(一元論)。でも、壁の向こう側は見えてこない。自分が変わることができれば、自分と違う立場のことは見えてくる。
自分の思い込みを捨てることが学びにつながる。
Posted by ブクログ
この人の本は正直さに惹かれる部分がある。嫌な感じもしない。文章が心に入るのは自分自身も似たような意識をどこかで持っているからか。戦争を経験している人の言葉は、大事にしたい。
Posted by ブクログ
ああなればこうなる理論が満映しているが、実際の世界はもっと複雑で、理論立て切ることはできない。
何にでも因果関係を求めるのはいかがなものかといったような考えは、今読んでいるドラグマグラに通じて面白い。
仕事は社会の穴を埋めるという考えはとても納得した。
Posted by ブクログ
著者の考え方が腑に落ちる。
・仕事とは社会に空いた穴であり、そのまま放っておくとみんなが転んで困るから、そこを埋めてみる。それが仕事というものであって、自分に合った穴が空いているはずだなんてことはない。
・社会システムすら「ああすればこうなる」式のいわゆる科学的な論理で割り切れるというふうにどこかで思ってしまう。
Posted by ブクログ
読書開始日:2021年12月6日
読書終了日:2021年12月22日
要約
①都市化する社会に伴い様々なものに意味づけする。自己にも意味を強要しオンリーワンを求められるが、そもそもがオンリーワンであり個性なのでそこに固執する必要は無い。
②紛争や戦争の原因は一元論者にある。一元論は気持ちよく分かった気になれるため堕落の一途を辿る。衣食整え余裕を持った復元論者を目指す。
③現代は他責追求社会。他に責任を追求しても所詮は他人なので届き切らず、精神コントロールができない。自責と水に流すことをうまく使いこなすべか。
Posted by ブクログ
この本は、東大名誉教授である著者の「壁シリーズ」である「バカの壁」「死の壁」の続編です。
著者の考え方が、丁寧に書かれており参考になりました。
ぜひぜひ読んでみて下さい。
Posted by ブクログ
最後の方に、プロとしての原則を持っているか、という話があり、大変共感した。様々な場面で他人に判断を仰がずに即時対応できるかどうかは、自分の中で考え抜いたかどうかによる。
Posted by ブクログ
いつもながらの語り口。読むひとに多くの気づきをもたらしてくれる。「本気の問題」が印象的。”こちらが本気でやれば自然に良い方向に行く”、”自分に原則があれば困らない”。
ホリエモン、山口周、島田紳助、みんな結局は同じことを違う切り口で言っている。もうほんとそれ。
Posted by ブクログ
仕事は社会に空いた穴(社会の側にある)。
自分に合ってなくて当たり前。
引き受けたらちゃんとやる。
やっていくうちに自分の考えが変わる。
自分自身が育っていく。
そう引き受けたらちゃんとやろう!
Posted by ブクログ
断捨離で出てきた本を今更というタイミングで読んだ。
もっと若いときに読んでいればよかったのかもしれない。
今ではこれといった感想がない。きっと私が大人になり過ぎてるせいだと思う。
Posted by ブクログ
バカの壁を読んでから読んだらもっと読みやすかったのかも。補足集を読んでいるような感覚だった。
いわゆる「思想が強い人」なのかと思っていたけど、適切な諦観がある大人だなと思った。ある程度を経験して、割り切れないあれこれのことを諦められるのが大人なのかもしれない。
Posted by ブクログ
バカの壁 を聞いている
途中で 超バカの壁 を
見つけて購入したので
先に読み終わってしまった
つい最近出版された
と言われれば
なんの違和感もなく
普通に読めると思う
普遍的なこと
書かれていると思った
自分に合った仕事 なんかない
仕事は社会に空いた穴
そこを埋めるのが仕事...とか
文中 小泉元首相 の名前が
何回も出てきますね
言いたいこと言ってくれている事
多いと思う反面
「...そう言う意味では
小泉純一郎首相も
伝統的な日本人だと言っていい..」
とか 異論ある部分もチラホラ
立派な解剖学の医師先生でも
その時代の 風潮 社会現象 には
影響されるのかも..と思った
勉強になる方が多いけど..
ところどころ なっとく出来ない
ところもあったけど
大部分は うなづける考え方だった
面白かった
Posted by ブクログ
まだあまり理解できていない部分も多い。
もう一度読み返したい。特に仕事に関する記述。
とにかく愚直に取り組むこと。
自分の見えている世界は狭いし正解じゃ無い。
まずは愚直にて目の前の仕事をやってそこから自分の考えを作っていくこと。
自分の責任で動いた時初めて大人になれた気がしたらしい。
面倒ごとから逃げずに真正面から見つめること。そこから反省して学ぶこと。
Posted by ブクログ
隙間時間に読む本が欲しくて、新書界の金字塔に手を伸ばした訳だが、「バカの壁」を飛ばして「超バカ」から入ったのは、若者、男女、子供、お金などテーマが具体的だから。
予想以上に、歯に衣着せぬもの言いで、スカッとする。「日本人ってこうだったよねー」(うんうん)という感じ。
また、お医者さまなので、男女の違いを染色体から論じたり、人と人との作用を「フェロモンの影響」と分析するあたりが面白く、説得力があった。(特にXY染色体との関連性については、私もぼんやりと疑っていたので、嬉しかった)
ただ、やっぱりお説教臭さもある 笑
あと、阪神淡路大震災による心の傷(トラウマ)に対して、「戦争と違って、自然災害は誰かのせいに出来ないから」って、それはちょっと単純に言い過ぎではないですか?と。先生のふるさとの横浜や鎌倉が、あれだけの局部的な被害で街の様相を変えてしまっても同じことが言えますか?と聞きたい。
このシリーズ、昭和生まれまでは、喧喧諤諤楽しめるけれど、Z世代ともなると、果たしてどこまで通じるやら?
養老先生は「イクメン」とかは、どう感じておられるのだろう・・・
Posted by ブクログ
本書の購入は2008年。一度読んだ形跡があるが、あまり覚えていなかったため再読した。
「バカの壁」とは「自意識の壁」、「主観の壁」、「思い込みの壁」ということであろう。現代文明は意識を肥大化させた。ゆえに、現代人は自意識が過剰だ。本書もそれを指摘している。
本書の「まえがき」が冴えている。
「相談をするときに、具体的な答えを期待する人がある。それはおかしい。自分のことは自分で決めるので、相談とは、根本的には『考え方』についての疑問である。他人に伝えることができるのは『考え方』だけである。」
「現代人はその『違い』を『些細な違い』だとみなしてしまう。そこから現代の不幸が始まるのである。それが仮に『些細な違い』なのだとしたら、『大きな違い』はどこから始まるのか。人生とはそうした『些細な』体験の繰り返しである。歳をとれば、その『些細』が積もり積もったものになる。」
養老孟司を絶対視してはいけない。本書でも一元論を否定している。相対化した方が物事が立体的に見えてくる。例えば日本と中国の関係について。あるいは、日本と韓国の関係について。
具体的なテーマを示しながら本書は相対化の大切さを述べている。
Posted by ブクログ
心に残ったワード
「自分に合った仕事」なんかない
仕事というのは社会に空いた穴で、そのまま放っておくとみんなが転んで困るから、そこを埋めてみる
自分に合った穴が空いてるはず、とかない
最近は穴を埋めるのではなく、地面の上に余計な山を作ることが仕事だと思っている人が多い
老人が「いつまでも生き生きと働く」ことがいいことのような風潮があるが、本当は老人の良い身の引き方、楽しい老後の過ごし方について考えたほうがいい
老人は生き生きしているよりは、イライラせずにニコニコしているほうがいい
極端な言い方をすれば、年をとっても働いていいのは、個人で働いている人だ
Posted by ブクログ
読者から寄せられる質問等に先生の考えで返している。
新しい知識が入るとかではなく自分がこのテーマで対談したらどうなるだろうと考えながら読んで楽しめた。
Posted by ブクログ
淡々としていて、冷静な文面。解剖学や医学、生物学という点から男女の違いについて書かれている部分は素人でも理解ができて自分にはない視点だったので面白いと思った。
Posted by ブクログ
自分がバカなのかだろうか、ところどころ解釈が難しい一文あり。ある種の壁を作り分かったつもりになってはいけない。特にスマホなど便利なものを使い始めてから、考えることが自然と面倒になり、頭を使わないことが多くなった気がする。著者の分析する賢い脳にならずとも良いが、頭を使っているなという感覚を忘れないように生きていきたい。そして人間のあるべきを追い続けたい。
Posted by ブクログ
「バカの壁」「死の壁」に続く3作目。
私個人で言うと、養老さんの本はこれで4冊目になります。
あとがきで著者本人が述べているように、この本は前2作と同じテーマを例題を変えて述べています。「あ、この話聞いたな」ということが何回かありましたが、それでも飽きないというか、考えさせられるなと感じてしまうところが著者の手腕なのだろうと感じました。
とある知り合いと話している際、「世間の犯罪は男性が多いんだ」ということが話題にのぼり、聞いた当初は(ええっ……そうなのかなぁ?)という感じだったのですが、この本を読んで驚嘆。彼女の言っていたことはある意味正しかったようです。
男性と女性についての話もそうですが、個人的には「イライラする匂い」のところが興味深く、もう少し調べてみたくなりました。
「楽になった」「安心した」と言ってくれる人がいたらうれしい、と著者は言っていますが、私にとっては「面白い」「もっと調べたいことができてくる」1冊でした。
Posted by ブクログ
現代で問題視されている問題
実は昔の方がひどかったのに、なぜか問題視されていない。
そんな疑問に触れた本
ステレオタイプの考えを脱却するのが大切だなと感じました。