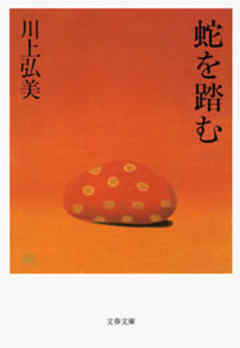あらすじ
藪の中で踏んでしまった蛇が女になり、わたしの部屋に棲みついた。夜うちに帰ると「あなたのお母さんよ」と料理を作り、ビールを冷やして待っている──「蛇を踏む」。うちの家族はよく消えるが、上の兄が縁組した家族はよく縮む──「消える」。背中が痒いと思ったら、夜が少しばかり食い込んでいるのだった──「惜夜記(あたらよき)」。神話の骨太な想像力とおとぎ話のあどけない官能性を持った川上弘美の魅力を、初期作ならではの濃さで堪能できる、極上の「うそばなし」3篇。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
⚫︎受け取ったメッセージ
「影」としての心との出会い
⚫︎あらすじ(本概要より転載)
ミドリ公園に行く途中の藪で、蛇を踏んでしまった。
蛇は柔らかく、踏んでも踏んでもきりがない感じだった。「踏まれたので仕方ありません」人間のかたちが現れ、人間の声がして、蛇は女になった。
部屋に戻ると、50歳くらいの見知らぬ女が座っている。「おかえり」と当たり前の声でいい、料理を作って待っていた。「あなた何ですか」という問いには、「あなたのお母さんよ」と言う……。
母性の眠りに魅かれつつも抵抗する、若い女性の自立と孤独を描いた、第115回芥川賞受賞作「蛇を踏む」。
⚫︎感想
ユングの「影」を想起した。積極的に生きてこなかった自分=影が蛇として表現されていると考えてみた。影としての心との出会い。蛇を踏んでしまった。その蛇が家に居着いて人間になったり蛇に戻ったりする。巻きつかれたり、職場までやってきたり、蛇の世界に誘われるが、拒んだり、心地よかったり、ザワザワしたり。影としての心が動き出して、蛇となっている…と捉えると、ヒワ子が違和感なく蛇を受け入れることも理解できる。無意識の自分なのだから。受け入れたり、争ったりするのは、自我と影だからであると考えられるのではないか。また、蛇が「あなたのお母さんよ」とヒワ子に言っていることも、ユングのグレートマザーを想起させる。
河合隼雄氏は昔話や神話の中に無意識の世界の広がりを研究された方だが、川上弘美さんの「蛇を踏む」は、「影」としての心との出会いを昔話風に物語ってくれているのではないかと思った。
Posted by ブクログ
蛇を踏む
著者:川上弘美
初出:1996年文学界三月号
1996年度上半期(第115回)芥川賞受賞作
本棚からあるものを探していると古い文藝春秋が出て来た。最近、あちこちで目にする、というよりすっかり大御所、重鎮になった川上弘美の芥川賞受賞作発表号だった。タイトルを見ても記憶にない。他にめぼしい記事もないので、きっと受賞作が読みたくて買ったに違いないのだろうが・・・読んでみても、全く記憶が甦らなかった。買ったはいいが、読み忘れて四半世紀以上たっていたのかも。
あの川上弘美先生は〝新人時代〟にこういう小説を書いていたのだ。といって、最近の小説もほとんど読んだことないけど。
主人公の若い女性は、女学校で理科の教師を4年し、辞めてしばらくして数珠店に入って働いていた。60歳過ぎの女性ニシ子が数珠を作り、8歳若い夫のコスガが配達などをし、主人公は店番をする。関東では一番と言われるニシ子の数珠づくり。彼女は元々京都の老舗数珠屋の奥さんで、そこで働いていたコスガと駆け落ちして今に至っている。
主人公がある朝、出勤途中の公園で蛇を踏んだ。「踏まれたらおしまいですね」と言った蛇は溶けて形を失い、やがて50歳ぐらいの女性になって歩き去った。その日、主人公が帰宅すると一人暮らしの部屋にその女性がいた。食事とビールが用意されている。誰だと聞くと、あなたの母親だと言う。母親は実家で健在。しかし、母親だとしか言わないし、主人公の幼少期のことも知っている。食事が済み、話が済むと天井に上がっていって蛇になって寝る。
そんな繰り返しの中、その蛇女性から「あなたも蛇の世界に来ない」と誘われる。意味不明だし、断り続けるが、彼女との生活は思ったほど苦痛ではないことも実感する。ある日、ニシ子も蛇と暮らしていることが分かる。その蛇はまもなく死ぬらしく、ニシ子は落胆。そして、調子が悪くなって店に姿を見せなくなる。コスガにきくと病気だという。
コスガとたまに納品に行くお寺で、住職から実は蛇と結婚をしていると聞かされる。いつも蕎麦を持って来てくれる女性だった。そして、その日、彼女は蛇っぽくなり、近づいてくる。主人公も、そして今は伏せっているニシ子も蛇と暮らしていることを知っている。
主人公は男とセックスをする時、目がつぶれないという。そして、事が進んで及びそうになると、相手の男が蛇になるという。
死ぬかもしれないと覚悟していたニシ子が戻ってきた。主人公は、同居する蛇女性から蛇の世界へと激しく勧誘される。耳の穴から体の中に入り込まれたり、液状になって体を侵されたり。思わずこのまま蛇の世界へ行こうかとも。少し心が揺らぐ。
選評を読むと、宮本輝と石原慎太郎の二人がこの作品の受賞に最後まで反対し、他の選考委員は評価している。石原慎太郎は、蛇が一体なんのメタファなのかさっぱり分からないと酷評し、こんな作品が選ばれる今日の文学界を嘆いている。しかし、この作品を読む限り、蛇がなんのメタファかなんて全く重要でない。それがテーマではなく、蛇を何に置き換えても人の生き様、そこでの薄弱さ、あるいは強さの表現に、感じ入ることができるそんな作品に思える。選考委員の一人、黒井千次は逆に「この種の小説にあっては、描かれる世界の意味や隠喩の形を探ることよりも、まず作品の中にするりとはいりこめるか否かが勝負」としている。まったく同感。