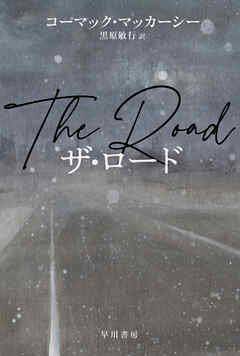あらすじ
空には暗雲がたれこめ、気温は下がりつづける。目前には、植物も死に絶え、降り積もる灰に覆われて廃墟と化した世界。そのなかを父と子は、南への道をたどる。掠奪や殺人をためらわない人間たちの手から逃れ、わずかに残った食物を探し、お互いのみを生きるよすがとして――。世界は本当に終わってしまったのか? 現代文学の巨匠が、荒れ果てた大陸を漂流する父子の旅路を描きあげた渾身の長篇。ピュリッツァー賞受賞作。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
ずっとドキドキしながら読んでいる
読むのを止められない、少年が生きているか?死なないでと思いながら読む
子持ちは読むのが辛い、ハッピーエンドを期待して読む
ハッピーエンドなんてありえるのか?全く想像もできないけど少年が死ぬのだけは耐えられない
今後存在しないものは今まで一度も存在しなかったものとどう違うのか
男に刺されそうになる少年をなんとか守り抜いた彼、大事にしているのは少年の生なのか、それとも自分の希望なのかどちらだろうかと思った
しかし最後まで読んでみて、そんなエゴの存在はわからなくなってしまった、自分より先にこどもが死ぬ、それが何よりも耐え難いのは分かりきったことだったなと思う
少年は何歳なのだろうか?
読んでいて自分たちを重ねて辛い、読むのをやめればよいのだがここまで読んでしまったのならハッピーエンドまで知りたいとの一心で読む、ピンチのとき彼らが死んでしまうことが受け入れなさすぎるので数ページ先で生きているのを一瞬確認してから読み進める、生きてくれと思う
誰に対してもオススメできる本。
ただ、私にとっては恐ろしい世界の描写が多すぎてもう一度読むぞという元気は今時点ではない。
Posted by ブクログ
初コーマック・マッカーシーは、世界的なベストセラー小説でピューリッツァ賞も受賞しているこの本から。
おそらく核戦争があった後のアメリカ大陸を歩いて旅する父と息子の物語。塵によって太陽光が遮られ気温が下がり、人間以外の生物もほぼ死に絶え、生き残った人々は、奪い合い殺し合い、死人を食らうようなことまでしつつ生きているディストピア。
父子も、体臭と汚れにまみれたボロボロの服を着て毛布や防水シートをまとい、ショッピングカートに生活品を乗せて移動しつつ、廃墟を漁り日々を凌ぐ。読んでいるだけで寒いし飢えるし喉が渇く。だが決して人の命や財産を奪うことはしない、生きていくために廃墟を漁ることはしても、人の気配があれば立ち入らない(防衛のためでもあるのだが)何度も飢え死にしそうになり、凍えても南へと歩みを止めない。
荒廃した情景の中で二人の会話が沁みる。静的で詩的で冷徹で少しだけ熱を持つ文章。
同じディストピアが舞台でも、キングとかマキャモンの小説や、マッドマックスや北斗の拳のような感情的だったり動的だったりする描写は極力排しているのが、かえって孤独と絶望感を際立たせる。
凄い小説、読んでるとこちらまで凍えてくる。本から現実の世界に意識が戻ってきたとき「この豊穣な現実を絶対守らないといけない」と心に誓った。
Posted by ブクログ
終末を迎えつつある世界でなんとしてでも息子を守ろうとする男が、最後まで父親として存在していたのが良かった。信じられるのはお互いだけ、という点が揺るがなかった。だから孤独で危険な旅も続けられたし読者としても安心できた。
父親のサバイバルスキルが高くて、色んな工夫を読んでいるだけで面白かった。読点がほとんどない、流れるような思考と会話の中に、記憶が混じってくるのも物語に没入できる理由なのかなと思う。
人が人を食うほど食べ物がない事態で、自分も痩せ細ってしまったのに少年の心は清らかで、他者を殺してまでは生きたくないという意志が強かった。その彼が無惨に殺されるようなことがなく保護者が現れ、いくらか救われた思いだ。
Posted by ブクログ
戦争か事故か天災か何かが起こった後の、人類の終末期を生きる父子の物語。
解説には近未来と書かれているが、未来的な道具立てがほとんどみられなかったので、例えば冷静時代に核のスイッチが押されたとか、そういう状況もありうるのではないかとか思いながら読んでいた。何であったとしても話にはあまり関係ない。
父子のひたすら南へと進む旅が、とにかく削ぎ落とされた文体によって淡々と表現される。
最後の父の死以外には起承転結に関わるできごとは起こらないが、ものすごい緊張感の中、まったく飽きずに読み進めることができた。
わずかに生き残った人間は、もはや人間としては生きていない。人類どころか、動物も植物もだめになっているので、備蓄食料や他の人間を食べ尽くしてしまえば最後の一人はもう生きる望みはないはずなのに、皆必死で生にしがみつこうとしている。
息子に偽りの希望を与え生き続けさせようとするのは父親の最後のわがままにすぎないので読んでいてつらい。
Posted by ブクログ
死んでいく世界の中、必死にお互いを支え合う父と子。読み終わり、涙が溢れてきた。二人の会話から伝わる状況や心境の変化。虚しさも痛みもひしひしと伝わってくる。生きる上でどこかで割り切らないといけないという父が下す正しさと、本当にそれで良かったのかと疑問を抱く少年の優しさ。お互いがそれぞれの学びとなり支えになる。父と同じように読んでいる自分も少年に暖かさを感じた。彼から優しさを分けてもらった気がした。
Posted by ブクログ
大厄災の後、ほとんどの動植物種・文明は絶滅し、灰色の厚い雲に覆われ、生き残る人類の大部分は人食い部族として存続している地獄の世界。
そんな地獄の中を、主人公の親子は、飢餓や凍死の危機をはじめとする様々な恐怖を経験しながら、倫理や理想を捨てずに進み続けようとする。
極限状態に追い込まれていく描写がとてもリアルで、読みながら何度も何度も「頑張れ!まだ死ぬな!」と応援してしまった。食糧にありつくたびに、自分がとても安堵した。
信仰を捨てず、こどもに無償の愛を注ぎ続ける父親が死んでしまうシーンはとても悲しかった。
少年が新たな夫婦に出会う、救いのあるラストでまだよかったが…いや、この世界には救いなどないか…。
父親がほんとに理想のパパすぎる。自分に息子ができたら、こんな父親になりたいと感じた。