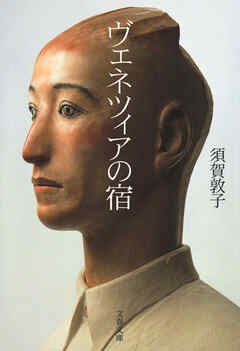あらすじ
ヴェネツィアのフェニーチェ劇場からオペラアリアが聴こえた夜に亡き父を思い出す表題作、フランスに留学した時に同室だったドイツ人の友人と30年ぶりに再会する「カティアが歩いた道」。人生の途上に現われて、また消えていった人々と織りなした様々なエピソードを美しい名文で綴る、どこか懐かしい物語12篇。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
目次
・ヴェネツィアの宿
・夏の終わり
・寄宿学校
・カラが咲く庭
・夜半のうた声
・大聖堂まで
・レーニ街の家
・白い方丈
・カティアが歩いた道
・旅のむこう
・アスフォデロの野をわたって
・オリエント・エクスプレス
須賀敦子は14歳の時「たしかに自分はふたりいる」「見ている自分と、それを思い出す自分と」と思ったのだそうだ。
若いころ彼女の文章を読んだとき、社会のしがらみから離れて自分の来し方を考えるような年になったら、こんな文章を書けるようになりたい、と思った。
しかし今、そんな年齢になってみれば、私にはそんな才能もなければ、振り返ってみれば転換点だったと思えるような経験もなかったのである。
そうか、14歳の時にはすでに見ていた景色が違ったのか。
その国に住んで暮らしていても、どこか旅人のようにしばられない心。
決して順調とばかりは言えなかったはずの日本での家庭の状況や、海外での苦労もあるはずなのに、振り回されることなく自分のペースで悩んだり行動したりする自由さに憧れた。
私が振り回されてばかりだったからかもしれないけれど。
そして全編を通して感じられる静謐。
ああ、そういう大人になりたかったのに。
それとは別に、結婚して初めて日本に帰国したとき、父親が新婚旅行として九州旅行をプレゼントしてくれたこと。
別府から阿蘇を抜け、熊本経由でフェリーに乗って長崎。
このルート、いいなあ。
行ってみたいなあ、私も。
Posted by ブクログ
須賀敦子さんの本としては2冊目。
1冊目の時はイタリアの地名に慣れなかったが、今回、
冒頭の章、「ヴェネツィアの宿」を読んだ時点で既に引き込まれた。
ヴェネツィアの波音、静かな夜、霧立ち込める雰囲気、そして何より夏の雰囲気、まるで自分がそこにいて外を歩く人たちの感想や足音を聞いているかのような感覚になった。
また、2日かけてフランス人の中30キロ歩いて大聖堂の中に入れないなど報われない話もおそらく人生の数年を「消費」してしまったであろう報われない環境も隔てなく書いていてよかった。あとがきでは、「うかうかと人生を費やしてしまう」ことを許さない人であったとあるが、模索して選んだ環境の先に時間を費やしてしまったことも描かれているように感じたし、それを変えようとしていたことも書かれていた。
その後の章からも、上記に被るが、須賀敦子が感じていたしていた2つの国の間でたゆたう孤独さ、変化や人目を恐れず環境を変えていくたくましさと模索感、しかしそれが実らない時の時間の流れ、など、自身に重ね合わせられるような描写もありつつ、
多くの人との一期一会的な別れ(最初に出会って別れた後も繋がっていようがいまいが問わない感じ)、夫や父との死別が少しずつ挟まり、須賀敦子の為人を感じることができた。
勇気をもらえるようでありながら(こちらが勝手にもらっただけだが)ただありのままの1人の生き方を見られたと思う。
「黒塗りのハイヤーに平気で乗るセンスと戦ってきた」という返答に色々とが籠っていた。
Posted by ブクログ
少女期や留学時代のことを振り返ったエッセイ集。
須賀敦子の本はおそらくこれで4冊目だと思う。
読み重ねていくと、だんだん深く沁みてくる文章。
戦直後のミッションスクールの寄宿学校の様子などは、何かもう、どこの世界の話だろうと思えてくる。
英語劇のために「Lord」という言葉が「正しく」発音できるまで執拗に練習を強いる修道女がいるかと思えば、アメリカから来たシスター・ダナムは「レクリエーション」の時間に野球を導入し、「ケイトノアタマー(woolen headの直訳)」と叫びながら、生徒よりも嬉々としてグラウンドを駆け回る。
小公女の世界のようでもあり、井上ひさしの育った孤児院のようでもあり…。
留学時代、学生寮で出会った韓国の留学生のキムさんや、ドイツから中学教師の職をなげうって来たカティアなどのエピソードも、それぞれに心に残る。
若いころ周囲の反対を押し切って筆者の母を娶ったはずなのに、いつのまにか家を出て他の女性と暮らしている父親のことも、この本にはたくさん出てくる。
愛憎半ばするだろうに、亡くなったあととなってはさまざまに思い出されるようだ。
「旅のむこう」は、不仲になっていた両親と、イタリアで結婚生活に入った後一時帰国していた筆者が国内旅行をした思い出を描いている。
読み進めて、昔大学入試の問題集に出ていた文章だと気づいた。
どんな家庭なのか、その後どうなるのかと思いながら読んだので記憶に残っていたのだろう。
頼りないようなお母さんが、時に筆者の背中を押しつつ、娘が遠くに行ってしまうのを寂しく思っている様子がほろりとする。
こんな終わり方だったんだ、と知ることができてよかった。
見ぬ世の人々のたたずまいの美しさが伝わってくるような気がした一冊だった。
Posted by ブクログ
家族、そしてさまざまな人たちとの出会いが著者の人生に大きく影響を与えたのだなあと感慨深かった。戦後間もない時代、その時代に留学を実行したことや結婚を目標としない女性の生き方を考えていたことに感動する。女性として憧れる生き方だ。また、文章の表現が丁寧で美しく、その土地の空の色や風、空気感、草花の色など自分も体験しているように感じ、読んでいて心地良かった。
Posted by ブクログ
洗礼者ヨハネは、苦行しながらキリストが世に出るのを待ちわびたというが、キリストのようにはではでしく弟子に囲まれるのでもなく、これといった逸話もないまま、ヘロデ王の逆鱗にふれて処刑され、孤独な生涯を終える。ヨハネは、生きることの成果ではなくて、そのプロセスだけに熱を燃やした人間という気がしないでもない。
待ちあぐねただけの聖者というのも悪くない。
大聖堂まで。フランスシャルトルの大聖堂の外、洗礼者ヨハネ像を見て。
オリエント・エクスプレス
憎いとも思っていた父との会話に心打たれる。
Posted by ブクログ
イタリア生活を書いた内田洋子さんのエッセイ集を読んだので、今度は須賀敦子さんのイタリア地名の付いたエッセイ集を読んでみた。
お二人とも素晴らしい文章力をお持ちだが、視点は全く逆である。
内田さんはご自分を透明化させて周りの人たちを小説のように描写する。 しかし、須賀さんは何処までいっても須賀さんご自身なのだ。
戦前からカトリックの学校に通い、戦後は同じ系列の修道院が経営する専門学校、それからまだ女性が大学へ行くことが珍しかった時代に大学へ進み、さらにフランス、イタリアに留学された。
確かに、裕福なご家庭に育たれており、高い学問を積んだり海外へ積極的に出たりということが出来る文化的背景のある方だったが、それでもまだまだ女性が大学まで行くことや留学まですることに偏見を持つ両親を説得して出国されたのだ。大学での文学や歴史の勉強の中で「どうしてもフランスやイタリアに行って見なければ分からない」という衝動にかられたからなのである。
戦前の兵庫から東京、戦後のフランス、イタリアとどこへ行ってもそこで出会う本や町や人が須賀敦子という人を形作ってきた。須賀さんの書くエッセイは須賀さん自身が主人公の小説のようだ。
戦後、修道院の経営する寄宿学校に入ったとき、中世のような時代遅れの訳のわからない規則縛られ、不自由な生活を送りながらも「戦争中に工場で働かされてばかりのころよりはずっといい」と、中世と現代、西洋と東洋、戦前と戦後が混在したような不思議な寄宿学校生活を好奇心を持って受け止めていた、そんな目のキラキラした少女。清貧と言う言葉が似合う。アニメ化して子供たちに見せたいな。
須賀さんが初めてパリに行かれたときの印象は安野光雅さんの挿絵入りで朗読したい。ホテルの窓からすぐそこに見えた、白く輝くノートルダム大聖堂がぽっかり宙に浮かんでいた。その「薔薇窓の円のなかには、白い石の繊細な枠組みにふちどられた幾何模様の花びらが、凍てついた花火のように、暗黒のテラスの部分を抱いたまま、しずかにきらめいている。」
その後のフランス中の学生が参加する年に一度の大巡礼の旅は映画で見たい。お弁当として、バケットを無造作にリュックに挿して歩く学生の姿。歩きながらの熱気溢れる学生たちの討論。農家の納屋に泊めてもらい、ハイジのように干草をベッドにして寝る。
病気だというのに家にちっとも帰って来ない父親を京大病院に訪ね、そこで父親の愛人と出くわしてしまったことを悩みながら母親に打ち明けるシーンは、そうだな朝ドラみたいかな。
須賀さんは14歳の時に自宅の窓から身を乗り出し、ミモザの薫りを嗅いで、「ワタシは今日のことを一生忘れないだろう」「確かに私は二人いる。見ている自分と、それを思い出す自分。」と思われたそうだ。その視点が須賀さんご自身の生涯を小説のように豊かなものとされたのだろうと思う。
Posted by ブクログ
初めて読む須賀敦子は、引き込まれるように読み終えた。
本書の解説を関川夏央が書いているが、その解説と、Wikipediaで調べた須賀敦子の生涯は、おおよそ下記のようであった。
■1929年生まれ。
■20代の終わりからイタリア在住。1961年にイタリア人と結婚するも、1967年に夫が急逝。
■1970年に父親が亡くなる。翌年1971年にご本人も帰国。大学の講師から教授まで務める。
■作家としてのデビューは、1990年、61歳の時。「ミラノ 霧の風景」がデビュー作。
■1998年没。
本書、「ヴェネツィアの宿」は、1993年の作品。
少女時代から、ヨーロッパ滞在中の出来事を綴った12編から成るエッセイ集。とても美しい文章。
特に最後の2編は、夫と父親の死を題材にしており、淡々とした中に哀しみが感じられる。死後20年以上を経てからの文章であり、逆に言えば、このような文章として仕上がるためには、20年以上が必要だったのだと思う。
Posted by ブクログ
イタリア語翻訳者の須賀敦子さんのエッセイ集。彼女が翻訳した本は読んだことがあったが、エッセイを読むのは初めて。
どれも心にしみて、とても良かった。でも妙に共感できたのは、私がヨーロッパに住んで似た人生を送っているからだろう。それにしても、彼女の感性はすごい。本書は、彼女がフランスやイタリアへの留学時代や結婚してからの生活のなかで出会った人々や、訪れた場所、日本でのミッションスクールで暮らしながら考えたことなどが綴られている。全く偉そうでないのに、教養がにじみ出る文章である。
イタリア人の夫に先立たれるところは、胸が痛んだ。ドイツ人の友人の話もとても良かったし、オリエント急行の話も素晴らしかった。
Posted by ブクログ
名文。
これは読む人を選ぶと思いますが、本好きなら一度は読んでほしい。
水のようにすらすらと読めて楽しいエッセーもいいけど、たまにはこういう文も読まないとダメになってしまう。
しっかりと意識して読まないと一つ一つの文が意味を持って入ってきません。でも、読めば読むほど、面白いし情景が心に迫る。
塩野七生や米原万里をおもわせます。
しかし、上記の二人にも通じるけど、時代から考えて外国に飛び出してそして一端の人となることのむずかしさ。その才智。憧れます。バックアップがあるとはいえ、やはり尋常ではないエネルギー。でもそれをひけらかさない。
すごいなぁ。
Posted by ブクログ
須賀さんの家族についてのエッセイが多いこの本。
若い頃、けっこう家族のことや留学のときの苦労の話が多く語られている。
年をとってから再び会った友人と1時間を共に過ごしたとき、あまり語らうことができなかったけど、友人のたたずまいを見ていい人生を送っていることが感じ取れたそう。
この話を読んで、今も昔も変わらないことというのはたくさんあるんだなと思った。
須賀敦子さんってけっこう遠い人なのかと思っていたが、少しだけ近く思えた。
Posted by ブクログ
須賀さんの文章に初めて触れた時
?と、疑問符が湧いた。
初めての味覚に戸惑う子どもに
なった様で、それは新鮮さを持って
何度も何度も口の中で須賀さんの言葉を転がすのだが、不思議とぴったりの
形容が浮かばない。
彼女の人生に触れれば、糸口が見つかるだろうか?
そんなわけで、私の須賀敦子探しの旅がこの本から始まった。
Posted by ブクログ
ずっと読んでいた本。借用本で一区切り。
ヴェネツィアの宿
夏の終わり
寄宿学校
カラが咲く庭
夜半のうた声
大聖堂まで
レーニ街の家
白い方丈
カディアが歩いた道
旅のむこう
アスファデロの野をわたって
オリエント・エクスプレス
イタリアに住んでいた頃のことと日本にいた時の話が交互に綴られている。何故か音が聴こえない風景ばかり思い浮かべて読んでしまう。ゆえに、何も考えず、静寂の中に浸りたいと思うとき、著者の本を手にとってしまう。著者は恵まれた環境の中で好きな勉強に没頭できる身分。なるほど、戦中戦後と外国へ女一人旅立てるのだから。エッセイストとして右に並ぶ人がいないと思うくらい。
Posted by ブクログ
「遠い朝の本達」と同様、著者の少女時代や父に対する反抗と愛情、母への想いなど日本や日本人に関する随筆が半分を占める。特にこの本は父の生き様や、著者が奔走の末になんとか修復にこぎつけた父母の関係がはっきりと描かれており、驚くことも多かった。いままでの彼女の文章からは、そのような家族のもめ事は感じ取れなかったからである。若き日の彼女は、密かに心痛めていた両親の関係にも、自身の内側の問題同様、真摯に向き合い行動してきたのだなぁ。著者の常に精神的に学問的に(?)向上し続けようとするストイックな姿勢と、それ故に日本でもヨーロッパでもがき苦しむ内面の遍歴をたどることができる。それがとてもうれしい。このような文章を残してくれた著者に感謝せずにいられない。特に日本の女性たちは彼女の文章を読んで勇気づけられることが多々あるのではないかと考えるのだが。
Posted by ブクログ
わたしにとって、特別な本です。
静かな、けれども着実にふみしめて歩いて行くような文体。
須賀さんは、本当に美しい言葉を話す人だったと
彼女と親しかった先生からうかがいました。
須賀さんのエッセイは
いまでも多くの人の心のなかに、たしかな音をたて、やわらかな足跡を残していく
そんな作品のような気がします。
Posted by ブクログ
イタリアと日本、両方の記憶が時代を超えてるつぼのように混ざり合い、往還するつくりの一冊。ほかの著作にくらべ少し湿っぽい雰囲気があるのは、家族の思い出にふれる筆のせいだろうか。まさにヴェネツィアにいるように、水の上にたゆたうイメージがある。
特に、確執を抱えながらも、父の一番の理解者だったとやはり思っていたであろう敦子さんが、オリエント・エクスプレスのコーヒーカップを手に父の死の床へと急ぐ終章と、その前に置かれた、さりげないくらい急いで筆を走らせたような夫との別れの予感をつづった章が、胸を打つ。
Posted by ブクログ
一貫して激しさとは無縁のような文章の須賀さん。でも伝わってくるものは熱い。涙が止まらなかった。
あこがれの存在というのでもない、これを読んで、あぁイタリアに行きたいなというのでもない、だけど一生読んでいたい本だ。
彼女の文章は、おそらく100年たっても心に深く
突き刺さっていくだろうなぁ。
その深さはその時々で違うだろうけれど。
100年後は私生きてないや。
Posted by ブクログ
つい先日イタリア旅行から帰って読んだ本
淡々とした筆致なのに妙に惹きこまれ、読み終えたとき何とも言えない不思議な感動があった
海外留学、ましてや移住する日本人なんてほんの一握りだった時代の空気感
生活もものの考え方も違う人々とこうして心を通わせることができたのは、人柄や語学力だけでなく、幼い頃から筆者の中にキリスト教が根付いていたからだろうか
私はたった数日のイタリア旅行に行っただけだけど、やや不安や心細さを感じつつも、その歴史や文化に圧倒され、街並みの美しさに惚れ惚れとしたことを思い出した。
日本の文化もそれはそれで素晴らしいと思ってるけど、西洋への憧れはいつの時代も変わらない。
遠い国で生きる人々の人生を垣間見たような話だった。
Posted by ブクログ
読書会で須賀敦子の存在を知り、手に取る。
自分もイタリアが好きで何度も訪問しているので、懐かしさもあり。
ただ、内容的には家族のこと、特に父との関係がテーマになることが多く、その家族史も興味深く、且つ心を動かされる。(「オリエント・エクスプレス」は涙を誘う)
時代は60年代~70年代のイタリアなので、時代背景の理解は必要かもしれない。
文章もとても読み易く、巧い。
以下抜粋~
・そのころ読んだ、サン=デグジュベリの文章が私を揺り動かした。「自分がカテドラルを建てる人間にならなければ、意味がない。できあがったカテドラルのなかに、ぬくぬくと自分の席を得ようとする人間になってはだめだ」
・たえず自分というものを、周囲に向かってはっきりと定義し、それを表現しつづけなければならない大陸と違って、暗黙の了解のなかで相手の領域を犯さない、他人を他人としてほうっておいてくれる英国人の生き方は気の休まるものだった。
・「建築成った伽藍内の堂守や貸椅子係の職に就こうと考えるような人間は、すでにその瞬間から敗北者であると。それに反して、何人にあれ、その胸中に建造すべき伽藍を抱いている者は、すでに勝利者なのである」(戦う操縦士:サン=テグジュペリ)
・「ヨーロッパにいることで、きっとあなたの中の日本は育ちつづけると思う。あなたが自分のカードをごまかさえしなければ」
Posted by ブクログ
いつの時代も知らないところや新天地に行くのは、震えるような勇気がいるものだ。
米女子来季出場権トップ合格の宮里藍ちゃんだって、「おとうさんの困難に立ち向かっていく後姿を見て」と、とてもえらかったけれど、前向きの勇気がどれだけ必要だったことかを思う。
このエッセイも当時(1950~60年代)としては珍しい家族の後押しがあれど、本人の「精神的に生きたい」という強い熱意と勇気がなければできなかった、ヨーロッパでの燃える向上心を記しているのだった。
「しばらくパリに滞在して、宗教とか、哲学とか、自分がそんなことにどうかかわるべきかを知りたい。今ここでゆっくりかんがえておかないと、うっかり人生がすぎてしまうようでこわくなったのよ」(カディアが歩いた道)
「うかうかと人生をついやす」ことは避けたい。肝に命じたいと思わされる。
家族小説(父母の思い出のエピソード)のようであり、教養小説(厳しい前向きの姿勢)でもあるエッセイ。「コルシア書店の仲間たち」同様美しい何度も読みたい文章である。
Posted by ブクログ
初めて読んだ須賀敦子。
著者の幼少期〜成人して留学、結婚した頃の、とりとめない回想と追憶が、上質な映画のように綴られていく。
にしても、この方、とんでもないお嬢さんであることが読み進めると分かってくる。
終戦から10年経たずにフランスへ私費留学というのもビックリだが、お父様が戦前にアメリカ、ヨーロッパへ贅沢三昧のグランドツアーをして、実家は神戸の実業家、麻布に別宅、田舎には武家時代のお屋敷と、語るネタは尽きない。
終戦直後に東京の聖心語学校(現在のインターナショナルスクールの前身)で日本語禁止、外人シスター監視の寮生活を送るというのもハイパー。
留学自体は貧乏で、と言われても留学すること自体がお大尽な行為だった時代だから、貧乏なんだかなんだか、よく分からない。
しかし、吉田健一や永井荷風といった、洋行セレブ文学者の系譜の最終コーナーを飾る本格派、という気がした。
Posted by ブクログ
某所読書会の課題図書.12の短編で構成されているが,イタリア,フランス,イギリスなどの街の描写が素晴らしい.どの国の人たちでもすぐに巻き込んでしまうキャラクターが,非常に心温まる経験のバックグラウンドになっているのだろう.言葉のギャップについてはあまり出てこなかったが,積極的な学び取る精神が,今より女性に対する目に見えないしがらみがあった時代でも,輝くような生き方をサポートしたのだと感じた.でも,かなり裕福で,一般人とはややかけ離れた生活基盤が随所に出てくるが,それをさらけ出すような雰囲気が見えないことに好感を持った.関川夏央の解説も的確なコメントが満載で素晴らしい.
Posted by ブクログ
1993年発表の須賀敦子の第3作。
文藝春秋の月刊誌『文學界』に、1992~93年に『古い地図帳』という通しの題名で連載されたものに手を加えた、12篇が収められている。
冒頭の『ヴェネツィアの宿』と最後の『オリエント・エクスプレス』では、著者が「父への反抗を自分の存在理由みたいにしてきた私」と語る父親について語り、『夜半のうた声』と『旅のむこう』では、わがままで強い父親にひきずりまわされる母親について、優しい視線で描いている。
『オリエント・エクスプレス』では、「あなたを待っておいでになって、と父を最後まで看とってくれたひとがいって、戦後すぐにイギリスで出版された、古ぼけた表紙の地図帳を手わたしてくれた。これを最後まで、見ておいででしたのよ。あいつが帰ってきたら、ヨーロッパの話をするんだとおっしゃって」と結んでおり、『文學界』の一年間の連載の大きなテーマが、両親(特に父親)と自分を記すことにあったことを窺わせる。
他の作品集同様、ほの哀しくも懐かしさを感じさせる作品集である。
(2008年2月了)
Posted by ブクログ
1929年生まれの著者がミラノでの生活から思い出した過去の日々。それはイタリア各地の旅行記であり、そして幼い日々の父と母の確執の思い出に繋がる。幼少期は関西の芦屋・御影が舞台になり、また母から聞き憧れていたという伯父が住んでいた青島(チンタオ)のエキゾチックな情景。私自身の過去とも重なり興味深く読むことができました。ペルージャ、ソレント、スコットランドのエジンバラなども登場し、旅行記といいながら、著者の精神史を思い起こさせる秀作だと思いました。
Posted by ブクログ
須賀敦子さんの作品を読むのは初めてです。先に読んだ池内紀さんの「文学フシギ帖」で紹介されていたので、興味を抱いて手に取ってみました。
著者のご家族・友人たちとの交流・ふれあいのエピソードを繊細で穏やかな筆で綴ったエッセイ集です。年代的には私が生まれたころですから、かれこれ50年ほど前、主な舞台は日本とヨーロッパです。
如何にもといった感じのその当時の風情を基調に、知的かつ行動的な著者の姿と感性が自然なタッチで描かれています。
Posted by ブクログ
一つ一つの話が本当に心にしみる.単なる随想を越えて,一つ一つが珠玉の小品というにふさわしい品格と完成度を持っている.今は失われてしまったものへの哀惜が常にその文章の底辺にあるのだが,それが生のかたちではなくて,浄化されて,澄んだ感情を通して絶妙のバランスで語られる. 名文としかよびようがない文章.
Posted by ブクログ
読書の胆力が足りない、私には、まだ。
母の苦しみ、父の身勝手さ、その辺りだけは惹かれるものの、イタリアの舞台にいまいちしっくり馴染めず。
いつかきっと、いつかもっと。
Posted by ブクログ
海外での暮らしぶりより、生い立ちをはじめとする、日本でのエピソードの方が心に留まった。
『白い万丈』は、どこか霧の向こうの話のような幻想的な空気感。
『寄宿学校』の、厳格でほとんど自由のない中で見える初々しさや青春世代のきらきらした感じは、懐かしいようでもあり頼もしくもあり。
彼女に対する父親の影響力はかなり大きそう。
日本を離れて、より父を意識することになったのかもしれない。
Posted by ブクログ
友人に薦められた一冊。
短編集になっているけれど、つながりがある。
タイトルがわかりやすいのだけれど、読んでいくとあぁだからこのタイトルとなるのが多い。
文章がとても読みやすかったのが最も印象に残ったこと。
繰り返し読むという友人の言葉を思い出す。
確かに、一度読んで終わりというよりは、読む度に新しい発見と琴線に触れる部分が出てくるだろうと思う。
また少し間をあけて再読したい。