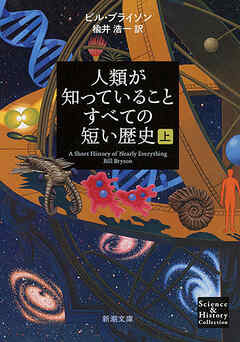あらすじ
こんな本が小学生時代にあれば……。宿題やテストのためだけに丸暗記した、あの用語や数字が、たっぷりのユーモアとともにいきいきと蘇る。ビッグバンの秘密から、あらゆる物質を形作る原子の成り立ち、地球の誕生、生命の発生、そして人類の登場まで――。科学を退屈から救い出した隠れた名著が待望の文庫化。137億年を1000ページで学ぶ、前代未聞の“宇宙史”、ここに登場。
...続きを読む感情タグBEST3
・「君は、神が事実を知っているとは思わないのか?」
「思うさ。神は事実を知っている。が、僕の目に映る事実はご存じない」
・生命は、化学的にはごく平凡な構造物だ。炭素と水素、酸素と窒素、少々のカルシウム、微量の元素。
その他ありふれたいくつかの元素を、ほんの少しずつ混ぜ合わせるとできあがる。
われわれを創る原子たちの非凡なところは、ただ一点、われわれを創っているというその事実にある。
それこそが、生命の奇跡だと言っていい。
・宇宙の果てには決して辿り着けない。まっすぐ外に向かって行っても、出発地点に戻ってきてしまう。
なぜなら、われわれの想像力が及ばないあり方で宇宙が曲がっているからだ。
・われわれは、何百万もある高度文明の中のたった一つにすぎないのかもしれない。
あいにく、宇宙空間がだだっ広いせいで、計算によるとこれらの高度文明は(あるとしたら)互いに200光年は隔たっている。
われわれが、ただ当てずっぽうに宇宙に飛び出した場合、惑星に到着、もしくはそばまで行ける確率はゼロに近い。
天体は貴重な存在なのだ。
・常に少量のエネルギーが無駄になっている。永久運動を行う装置という物はあり得ない。
どんなに効率の良い機械でも、必ずエネルギーの損失があり、やがては停止する。
エネルギーはゼロから創り出すことはできない。
温度を絶対零度まで引き下げることも出来ない。どうしても熱が残留するからだ。
・質量とエネルギーは、異なる形態をとった同じものである。
エネルギーは解放された物質で、物質は解放を待つエネルギーなのだ。
・空間と時間は絶対ではない。観測者と観測されるものの両方と相対的な関係にあり、
一方が高速で動くほど、その影響は顕著になる。
われわれは速く動くほど、外側にいる観測者に対して歪んだ存在になっていく。
・われわれ人間は短命だが、誰もが生まれ変わっている。われわれが死ぬと、原子は分解し、飛び去って、
どこかで新たな活動の場を見つけ出す。木の葉の一部や、他の人間や、一滴の露となる。
・地球上のどこへ行こうとも、たとえ、生命にとってこの上なく劣悪な環境に思える場所だとしても、
液体の水があり、何らかの化学エネルギーの源が存在する限り、生命が見つかる。
Posted by ブクログ
・宇宙は膨張していき、そのあと収縮していく。心臓のように膨張と収縮を繰り返す?
・隕石が地球に落ちるときは、前兆はなく一瞬でくる。
・地球の生物はあらゆる事から恩恵を受けている
・月は年間4cm遠ざかっており、20億年後には月は地球から遠くなりバランスが保てなくなる
・地中のマグマが大気を形成している
・太陽から数%近ずくと灼熱、離れると冷却して人類は住めない
・カンブリア爆発→生物の体制が一気に生まれた
・地球の歴史45億年。1日24時間に例えると人類の歴史は1分程度。恐竜は45分。
・生命の性質として絶滅は規則正しく発生する。複雑な生物ほど絶滅は早い。
・ダーウィンの進化論では、生物が進化している場合、中間形態が化石で残っていなく証明できない、新種が創造されるきっかけが説明できていない事はダーウィン本人も自覚のうえ、その点では根拠なしに進化論を伝えている
・進化論では人間は猿の子孫であると思われているが、この点は強調されていない。
・地球では気候は何度も変化しており、今の安定期は微妙な均衡のうえで成り立っている
・いまも氷河期のなかにいる。冬に雪が降ったり北極が氷で覆われていない時期もある。
・人類とチンパンジーは97%一緒
・いまの人類は偶然にできたもの。進化の頂点にいるわけではない。
・人類の祖先だけが霧がかかっていて謎である。
・我々生物は途方もない幸運のうえで生きていること
Posted by ブクログ
科学に興味がない人も是非読んで欲しい。著者が科学畑ではない人なので、知識がない人向けの分かりやすい説明になっている。そして、最初から最後まで好奇心を刺激される発見が満載だ。
Posted by ブクログ
科学技術史の集大成本。上巻は理科一類。宇宙の誕生から地球の生い立ちまでの歴史と物理化学地学系の技術史がない交ぜになって語られる。単行本の時は厚さ4.5センチあったらしい、大部の著作である。
Posted by ブクログ
今を生きている人は必読だと思います。自分と、生命と、宇宙の関係がそれなりに理解できると思いますよ。
難解な言葉や概念が出てきます。でも、科学と歴史の旅をする感じで、読み進めていくといいでしょう。
有名な科学者の人柄やスキャンダル的なことも適度に交えています。
科学者とは友達になりたくないですね。著名な作家もそうですが、どうも「普通」ではない。奇人、変人ですね。それがまた面白いのですが。
Posted by ブクログ
天文学も物理学も化学も地学も…とにかく色んなものがぎゅっと詰まった本。題の大きさ通りです。
フェルマーの最終定理からScience&history(新潮文庫)に惹かれたのですが、著者は違うもののやっぱり面白いです。(黄色のスピンも素敵です!)訳者もいいな〜と思う所もあり。(冗談をうまーく日本語的に訳している気がする)
私は何を専攻してるとか、むしろ文理とかもそんなの関係なく何でも面白い所は取り込みたいのでそれぞれおいしい所をかじるにはすごくいいと思います。難しいことは書いてないのでおすすめ。
Posted by ブクログ
人類が知っている知恵が短編集のような感じでまとめられた一冊。分野も宇宙論・量子論・地球物理学・進化論・生命科学と、他分野に別れているので飽きずに読み進められ非常に面白かった。さらに、筆者は文系の人間らしいので、かみ砕いて描かれており分かりやすかった。
宇宙論から始まり、量子論に移り、自然な感じで地球の話に移り、その流れから自然・生命・人間の進化等々の話。
科学の話を完全に理解できないにしても、科学者一人一人のエピソードや科学の概略は理解できるので、入門書や自分の興味を探す本としては非常に良い一冊だった。これを片手に、もっと難しい科学の世界に足を踏み入れるのもいいのかもしれない。
Posted by ブクログ
科学者による様々な法則や発見、そして科学者どうしのいがみ合いの歴史。帯にある「137億年→1000ページで!」どうりの本。上巻は、宇宙創世、地球の大きさ、恐竜発見、物理学、プレートテクトニクス、地震、火山、etc.
Posted by ブクログ
宇宙ってそんな一瞬でできるんだ!
星の位置を記憶できる人(エヴァンス)にもびっくり。すごいな、星読み特化型。
ハレー彗星の名前ぐらいは知っているが、経歴のすごさがエグいのも知らなければ、ハレー彗星の発見者ではなかったことにも驚いたw
船長、地図製作者、オックスフォードの幾何学教授、王立造幣局の会計監査官補佐、王室天文学者、深海用潜水鐘発明、天気図、平均余命表、地球の年齢と太陽までの距離計算、魚の鮮度を保つ方法って幅広すぎるw
最新とは言えないものの、近年までの地球の歴史を色々知れて面白かった。
たくさんの人々の試行錯誤や踏んだり蹴ったりの上に今があることがよくわかる。
名が残る人が功績者だとは限らないことは多々あるもんなんですね。
自分が世紀の発見をしたと思っていたものが実は1世紀も前に他の人が発見していたとか、どんな気持ちになるんだろう。
ズルした人の悪行もちゃんと残ってるのも面白いし、文才がなくて伝わらないのもウケる。
学者だからといって正しいとは限らないこともよくわかる。
結構最近にわかったことだったんだなぁと感じることもたくさんあった。
10の10乗表記、わかりやすくて好きだな。
ケタ覚えちゃえばいいけど、一般的な表記はいちいち数えなきゃ大きい数字がわからない。区切っても限界はあるし、なぜか区切り位置間違って表記されることもあるし…。
パーキンソンって暗殺計画で捕まってたのか…
キュリー夫人の「フランス人の尺度からしても過剰に不謹慎な不倫関係」ってどんななんだろう…相当だよなぁw
質量は変わらないけど、重さはどれだけ離れてるかによって変わってくるってのも相対性理論なのかな?音楽は変わらずかかっているけど、自分が離れれば聞こえなくなるのと同じだよな?
素粒子は難しくて全然入ってこん。まだまだ研究中だし、わからんのもやむなし。
Posted by ブクログ
学校でなんとなく習ったことを易しく詳しく教えてくれる。科学について知っているようで実は知らないことがわかり、勉強してきた身としても学ぶところが非常に多かった。科学の壮大さ、面白さを味わいたいなら教科書よりこの本を読んだ方がいいと思う。中学とかの段階で読みたかった。
Posted by ブクログ
相対性理論や量子力学が世に出てからまだ約一世紀で、そもそも我々がいる地球の年齢が46億年だとかその銀河系は137億年だと推定されてからまだそう長く経っていない。(それもあくまで仮説で覆るかもしれないが)プレートテクトニクス理論なんて若輩者もいいところだ。そうした人類の驚くべき発見や叡智を堪能できる本だ。こうした科学史の主役は物理学や天文学が多いが、上巻は地質学や化学が相応の位置を占めておりなかなか興味深い。
Posted by ブクログ
宝くじで一等当選する確率と、地球が滅亡する確率はどちらが高いだろう。
両方ともに遭遇せずに死ぬ確率の方がよっぽど高いことは間違いない。
氷河期、地軸反転、火山爆発、彗星衝突。過去46億年の中で、人類が滅亡するほどの自然現象に何度も見舞われてきたのが地球だが、偶然にもここ1万年ほどは安定しているようだ。
本書は地球滅亡陰謀論でもディザスター・ムービーの原著でもないが、どれも人が明らかにしてきた地球の歴史を語る上で無視できない事象だ。
宇宙創生、宇宙の大きさ、星の寿命、地球の大きさ、地球の年齢、恐竜の発見、元素の発見、大陸移動、彗星衝突、地軸反転、超巨大火山爆発。
語られるのは科学的詳細というよりはそれらの発見と人の物語であり、知ってる人から見れば新しい話でもないし、知らない人が読むには、話題の多さからか丁寧さに欠ける。
しかし、本書の全てを知っているような人も稀だろう。
"人類知識"の外観を眺めることで、次に読むべき一冊を見つけられるようになるかもしれない。
Posted by ブクログ
人類発生からの世界史的な話だろうかと思っていたら、宇宙の創生から始まるなんともスケールの大きな話であった。
様々な科学について、解き明かされていく様子が、テンポ良く記述されているので、なんとなく自分が知識人になったような気になるが、それは気のせいである。
ヒッグス粒子など、執筆当時はまだ未発見であるが今はもう存在が確認されているものなど、タイムリーな話も記載されているのもよい。
Posted by ブクログ
地球の歴史をぎゅぎゅっと短縮した本かと思いきや、いろいろな偉人伝をコンパクトにまとめてくれた印象。
そのおかげで、科学を全く知らなくても何とか読める。
科学者の人が一般向けに分かりやすく書いてくれたのかと思ってたけど、旅行作家として有名な専門外な人の本だったので、疑問に思うこと、興味がわくとなどはいわゆる私たち一般人に近い感覚。
途中興味のない章もあるけれど、飽きてきた頃に不遇の偉人伝が入ってくるので、そこはすらすらと読める。
さすが、地の文は読みやすかった
Posted by ブクログ
高校生の時分、生物学は20世紀の科学で、化学物理学は19世紀の内容を教えていると言われた。この本を読むと、そもそも最近になるまで人類は多くのことを知らないままだったのだと気づかされる。
登場人物が多くて一度では全ては把握しきれないだろう。それでも、ある程度自然科学の進化と体系について俯瞰図を与えてくれるような気がした。
著者のフランクな語り口も素敵。
Posted by ブクログ
宇宙、量子、地球、生物、人類の成り立ちなど、科学のエッセンスをまとめたような読み物。
科学でこんなことがわかるんだよ!逆に、こんな身近なこともまだわかってないんだよ!と、読みやすく知的好奇心を刺激する名著だと思います。
翻訳も読みやすくていいね!
Posted by ブクログ
宇宙がどうやって出来上がったか、地球は今どういう状態なのかについて、その謎に対して過去から様々な人々が挑戦されてきました。その歴史を通じて、その謎に出来るだけ迫ろうという意欲的な著書だと思います。
上巻は、宇宙のでき方から現在の姿まで、地球について(大きさや年齢など)、原子、地球の内部のこと、など興味深い内容になっています。それぞれに対して、どんな人がどんな研究を行って何が分かったのか、非常に具体的に分かり易く書かれており、飽きることなく通読出来ました。宇宙や地球、原子について、その研究を知ることが出来ます。
Posted by ブクログ
科学の本なのにまったく眠くならない。
宇宙の構造や地球の構造、現代物理学の成り立ちなど今まで不思議に思っていたことをユーモアを持って科学者達に焦点を合わせながら説明してくれた本。
この事象に関しては現在ここまでしかわかっていないということもはっきりしているのも興味深い。
今まで読んだこういった本の中では一番おもしろかった。
著者が読者の知りたいこと、どうでもいいこと、何が難しいのかを熟慮して構成を考えてくれたことがとてもよくわかる。
Posted by ブクログ
勉強になるけど固有名詞も多く、下巻を読み終わる頃には1割も覚えていないと思う。
相対性理論についてとハレー彗星は印象的だったのでかろうじて…
Posted by ブクログ
宇宙の謎と原子の謎に挑む人類の知的営為が、独特のユーモアと明快な文章で語られる、現代人の必読書。
全てはビッグバンから生じた素粒子から生まる。
素粒子は原子を形成し、超新星爆発によって生じた重い原子が集まって星を形成し、化学物質が何故か分裂して生命が誕生する。
生命は星屑からできているのだ。
それにしてもタイトルがあまりにひどい。
誰がこんなタイトルの本を手に取るものか!
原題は、A short history of nearly everything
これはシンプルで分かり易い。
Posted by ブクログ
原子のサイズを理解するために、原子の幅を1ミリと仮定してみる、そうすると一枚の紙の厚さがエンパアステートビルに相当する。その極めて極小の原子を大聖堂の大きさまで拡大してみる、すると原子核はハエほどの大きさにしかならないらしい。さらに原子核を回る電子については、太陽を回る惑星のイメージとは違い、形の無い雲の様相を呈しているんだとか(P271~)んー 難しい話だけど面白いこと間違いなし、おすすめの一冊。