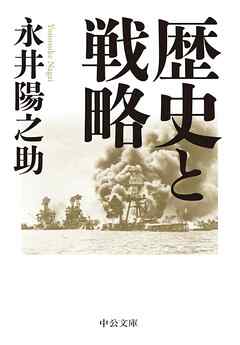あらすじ
戦略を研究し戦史を読むことは人間性を知ることにほかならない――。クラウゼヴィッツ『戦争論』を中核とした戦略論入門に始まり、山本五十六の真珠湾奇襲、チャーチルの情報戦、レーニンの革命とヒトラーの戦争など、〈愚行の葬列〉である戦史に「失敗の教訓」を探る。『現代と戦略』第二部「歴史と戦略」に自作解説インタビューを加えた新編集版。〈解説〉中本義彦
【目次】
戦略論入門――フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』を中心として
Ⅰ 奇 襲――「真珠湾」の意味するもの
Ⅱ 抑止と挑発――核脅威下の悪夢
Ⅲ 情報とタイミング――殺すより、騙すがよい
Ⅳ 戦争と革命――レーニンとヒトラー
Ⅴ 攻勢と防御――乃木将軍は愚将か
Ⅵ 目的と手段――戦史は「愚行の葬列」
インタビュー『現代と戦略』とクラウゼヴィッツ
解説 人間学としての戦略研究 中本義彦
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書『歴史と戦略』のオリジナルである単行本『現代と戦略』(文藝春秋、1985)は、永井陽之助氏が「文藝春秋」(1984年1月号から12月号まで)に連載したものを一冊の単行本にまとめたものである。
第一部「現代と戦略」・・・(米ソ冷戦末期の国際政治における)主として、日本の防衛論争や防衛戦略を巡る諸問題を扱う
第二部「歴史と戦略」・・・「戦史に学ぶ失敗の教訓」という意味で、歴史のケースに焦点を合わせる
本書は、単行本『現代と戦略』第二部を文庫化したものであり、出版社の宣伝文句は次のようである。雰囲気を感じ取れる。
<戦略を研究し戦史を読むことは人間性を知ることにほかならない――。
クラウゼヴィッツ『戦争論』を中核とした戦略論入門に始まり、山本五十六の真珠湾奇襲、チャーチルの情報戦、レーニンの革命とヒトラーの戦争など、〈愚行の葬列〉である戦史に「失敗の教訓」を探る。
『現代と戦略』第二部にインタビューを加えた再編集版。 解説・中本義彦
【目次】
戦略論入門――フォン・クラウゼヴィッツの『戦争論』を中心として
I 奇 襲――「真珠湾」の意味するもの
II 抑止と挑発――核脅威下の悪夢
III 情報とタイミング――殺すより、騙すがよい
IV 戦争と革命――レーニンとヒトラー
V 攻勢と防御――乃木将軍は愚将か
VI 目的と手段――戦史は「愚行の葬列」
インタビュー『現代と戦略』とクラウゼヴィッツ *単行本未収録 >
『新編現代と戦略』の「第Ⅰ章 防衛論争の座標軸」の冒頭から、政治的リアリスト・永井陽之助氏は、軍事的リアリスト・岡崎久彦氏の『戦略的思考とは何か』に対する批判を始める(概要)。
<私は、岡崎氏のように、客観的な戦略的環境なるものがモノのように実在していて、その情勢判断から日本の防衛戦略や兵力態勢などがほぼ一義的に定まるとは考えていない。たしかに安全保障問題は、不確かな、不測の事態にかかわるため、「相当な抽象的論理的思考」を必要とする。だが、現代の核時代の戦略論は、その本質上、「土地カン」のない虚構の議論とならざるを得ない必然性をもっている。
今日の安全保障論で直面する第二の困難性は、我々のような軍事問題の素人は、ハードなデータに直接のアクセスをもらえないことである。いったい何を根拠に戦略を論じたらいいのか、困惑を感じない人はいないであろう。
岡崎氏の著書を見ると、機密情報に接し得ない素人には安全保障問題などに口出しする資格はない、「土地カン」のある専門家を信頼するのが無難だという態度がほの見えるのは大へん遺憾である。本書、第Ⅺ章で指摘するように、外交や戦略に関するイギリス伝来の知的風土は、残念ながら岡崎氏の態度とは好対照をなしている。ロンドン大学の森嶋教授も強調していたように、イギリス指導階級特有のアマチュアリズムこそ、文民支配のコアにあるものである。ここにも岡崎氏がアングロサクソンの名で、イギリスとアメリカをいっしょくたに論じる例の悪いクセが出ている。
戦時中、日本の軍部や、国策研究に関わった御用学者たちが、「機密情報に接し得ない素人は黙っていろ」という態度で、日本の前途や戦況を憂える学生の疑問を封じたという。ところが、戦時中の、わが帝国陸海軍や外務省は、極秘情報(マジック)が連合国につつぬけであることさえ、疑ってもみなかったというマヌケぶりであった。今日、岡崎久彦部長統率のもと、外務省の活発な情報収集活動によって故アンドロポフ書記長・国葬での追悼演説序列をピタリと予測して(パパ)ブッシュ副大統領を驚かせた「24時間態勢」のことなど、私も敬意を表すに吝かでないが、広い教養とバランスの取れた判断能力の欠けた、プロぶる専門家の意見ほど、この種の問題で危険なものはない、というのが多年にわたる「自分の経験」から得た教訓である。
安全保障論議の第三の困難性は、核時代における防衛論は多くのパラドックスとディレンマを含むということである。この種の論議で、スッキリ割り切った意見は、俗耳に入りやすいが、そこに含まれる深刻なディレンマに感受性を欠く点で一種の傍観者の意見とみてほぼ間違いない。「平和主義者の明快さは、彼らが局外者の立場に身を置いているからである」という警句は、そのまま、いわゆる軍事的リアリストにも妥当する。
核時代の安全保障問題は少なくとも大別して三つの基本的なディレンマをもっている。
第一が、国家の「安全」確保(「同盟」関係の維持)と、「独立」達成(「自立」への願望)とのディレンマ
第二が、「福祉」か、「軍備」か、バターか大砲か、の手段の選択にかかわる優先順位の問題
第三が、「抑止」と「防衛」のもつディレンマ >
「国葬での追悼演説序列をピタリと予測」はユーモアと皮肉を込めたジョークのようにも聞こえるが、このような岡崎氏に対する批判が、通奏低音のように本書全体に響いている。上記の「三つの基本的なディレンマ」が現在でも重要な課題であることは、シロウトの私でも感じている。例えば、日米地位協定が示すように、日本は「同盟」「安全」を優先して「自立」「独立」を犠牲にしてきた。 さらに進化して、現在の日本はアメリカの戦争に参加する法律として戦争権限法を制定したので、アメリカとの「同盟」と日本の「安全」が何だか怪し気な状態になっているように思われる。
ここで参考に、永井氏がハーバード大学における共同研究で提示したという「日本の防衛論争の配置図」(座標軸)を紹介する。この配置図は、当時の混迷を極める世論、論壇、政界、官界の論点を整理し、真の争点がどこにあるかを明示する上で調法だったそうだ。A「政治的リアリスト」、B「軍事的リアリスト」、C「日本型ゴーリスト」、D「非武装中立論」である。
「同盟」「安全」
|
A | B
|
「福祉」ーーーーーーーーー「軍事」
|
D | C
|
「自立」「独立」
<ド・ゴール主義またはゴーリスム(Gaullisme)とは、ド・ゴールの思想と行動を基盤にしたフランスの政治イデオロギーのこと。イデオローグ達は「ゴーリスト」と呼ばれる。 ド・ゴール主義の最大の主張は外国の影響力(特に米英)から脱し、フランスの独自性を追求すること。ド・ゴール主義は思想上社会や経済にも言及し、政府が積極的に市場や経済に介入することを志向した広義の国家資本主義である。>(Wikipedia)
私は難しいことはわからないが、本書の岡崎批判を拾い読みするのが面白い。例えば、『歴史と戦略』の「第Ⅵ章 目的と手段――戦史は「愚行の葬列」」の「システム分析の功罪」における、岡崎氏らのシステム分析的思考に対する批判は痛快である。
<岡崎久彦氏が『中央公論』(1984年8月号)で私との対談(「何が戦略的リアリズムか」)で、「戦略でパリティというのは、およそ1と1.5の間だそうですよ。1と1.5で戦争しますと、どちらが勝つか全然分かんない運いい方が勝ったり、作戦のいい方が勝ったりする」と指摘し、練度とか士気とか稼働率とかの質的な要因も「全部勘定に入れて、1対1.5、つまりほぼ同等(ラフ・パリティ)という」と定義している。この種のものの考え方が、ランド研究所や、国防総省の戦略思考の典型といっていい。
この種の”合理的”思考に欠けていたところに日本軍の敗戦の一つの理由をみることに異論はないが、常識で考えても、ミスリーディングなものであることはわかる。
(略)
この種の思考の最大の欠陥は、敵があたかも「受け身のターゲット集合」であるかのように想定しないと計量化不可能になるため、相手側との反応と相互作用で力関係が決まるという自明のことを忘れがちになることである。外交、政治、戦争は、「恋愛」と同じで、相手方の反応と相互作用を考慮に入れずには成り立たない。クラウゼヴィッツ以来、今日でも変らぬ、目的と手段、士気、攻勢と守勢の弁証法など、戦争で最も大切な、計量できない、インタンジブルな要因が、コンピュータに入力できないという理由で排除される傾きが生じてしまうことである。
このような一種の「ワンマン・チェス・ゲーム」的な戦略思考は、敵も同じ戦略思想、兵器体系と手段の対称性を持つか、または持つと想定した時のみに成立する。>
『新編現代と戦略』に岡崎久彦氏の「永井陽之助氏への反論」が載っているが、あまり関心は持てない。
それはともかく、本書のエッセンスは、『歴史と戦略』の冒頭に収録された「戦略入門――クラウゼヴィッツの『戦争論』を中心として」の締め括りの”ことば”に集約されている。
<わが国の一部の戦略、軍事問題専門家のんかに、クラウゼヴィッツは時代おくれだという、それこそ時代おくれの謬見が、まかり通っているが、戦略を研究し、戦史を読むということは、人間性を知ることにほかならない。このことをクラウゼヴィッツとともに片時も忘れないでほしいと思う。>
永井氏の思想「戦略を研究し、戦史を読むということは、人間性を知ることである」は時代を超えた真理であると思う。人間性を大事にする永井氏は、『歴史と戦略』の「第Ⅴ章 攻勢と防御――乃木将軍は愚将か」の「「非対称紛争」の意味」で、胸にグッと迫るエピソードを語っている。
<私自身も小学生時代から口ずさんど「水師営の会見」の「庭に一本棗(なつめ)の木 弾丸あとも著しく・・・」で、浮かび上がる光景は、時代と場所をこえて人の心をうつ普遍的な、何ものかである降将ステッセル以下に帯剣を許し、アメリカ人が映画を撮ろうとしたのを乃木将軍は副官をして慇懃に断らしめた。この敵将への思い遣りは本物であり、外国特派員のすべてを感動させた。後年ステッセルは敗戦の責任を問われて、軍法が意義で死刑の宣告(1908年)を受けたが、乃木将軍が、元第三軍参謀津野田少佐に依頼し、英仏の新聞にステッセル将軍の武勇を宣伝させ、乃木将軍の名をもってステッセル将軍の善戦を賞讃する論文をも発表させた。それらの努力の甲斐があって、ステッセルは懲役10年減刑され、さらに健康を害しているゆえに、その刑も免除されたのである。私自身、ウォッシュバーンの著書ではじめて知ったのであるが、乃木将軍殉死の報がロシアに伝わるや、「モスクワ郊外のモンクより」という匿名の差出人で若干の香奠(こうでん)が送られてきたという。これは、まぎれもなくステッセル将軍からであった。こういう時代もあったのである。>
以上
********************
【参考】
かなり古い出版であるが、この本を知らないのは損ではないだろうか。収録されているE・ホッファー 「情熱的な精神状態」(永井陽之助訳)は貴重である。永井陽之助氏による解説も参考になる。
編集・解説 永井陽之助
『現代人の思想〈第16〉政治的人間』(平凡社、1968)
目次
解説 政治的人間 永井陽之助
Ⅰ 政治の極限にひそむもの
革命について H・アーレント 高坂正堯 訳
パルチザンの理論 C・シュミット 新田邦夫 訳
Ⅱ 秩序と人間
堕落論 坂口安吾
全体主義権力の限界 D・リースマン 永井陽之助 訳
情熱的な精神状態 E・ホッファー 永井陽之助 訳
肉体文学から肉体政治まで 丸山真男
Ⅲ 政治的成熟への道
職業としての政治 M・ウェーバー 脇 圭平 訳
権力と人間 H・D・ラスウェル 永井陽之助 訳
政治教育 M・オークショット 阿部四郎 訳
********************
Posted by ブクログ
現代社会はVUCA、すなわち不確実性の連続である。ビジネスでも私生活であっても、今この瞬間の事実こそ確実であれ、一年後、半年後、明日そして1秒後の事でさえ予期せぬ事態が訪れる可能性に日々怯えながら過ごしている。先日埼玉県で道路が陥没し、走行中の貨物車両が落下するという痛ましい事故が起こった。このレビューを書いている2週間ばかり経過した今もなお、運転手の発見には至らず、ご家族や関係者の方々の不安や悲しみは想像を絶する。何事もなく平和に過ごした日常が壊れるのは一瞬だ。一寸先は闇、こんな言葉が頭を過るが、正に何を信じて何を指針に前に進めば良いのか、判らなくなることばかりだ。私はITに携わる仕事だから、進化のスピードも変化の振り幅の大きさには多少の慣れがあるかもしれないが、それでも3年の計画を策定し、それ通りに進める事には、あまり力を割いても仕方ないと思っている。ITに関して言えば、AI分野で中国からDeepSeekが登場して、一気にその他の技術に良かれ悪かれインパクトを齎す様に、市場の明日は読み切れない。
こんな時に如何に未来を描いて追随するかを考える事もそれなりの価値があるが、寧ろ変化を自分で起こす事を考えた方が(勿論斬新なアイデアや技術化には相応の金と時間と何より超人的な発想力が必要なのだが)、気が楽だと思っている。自分以外に振り回される人生と、自分自身が牽引•作り出す人生。誰がどう見ても、自分の人生は自分が決めている方が健全なのは間違いない。そんな時に自分の考え方のベースが確立していないと、容易に元の振り回される人生に戻りかねない。だからこそ、ビジネスは勿論、自分自身、人生に於いても戦略は不可欠だ。
本書最後にビジネスマンが戦略本をよく読むという記載があったが、私もその1人なのかもしれない。だが「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」とビスマルクが言った様に、私は歴史を読むことのほうが多いし、好きである。今年は先の大戦終戦から80年という事もあり、本屋にも太平洋戦争や日露戦争など、過去に日本が経験してきた戦争に関する考察や分析本も多く見かける。同時に古くからある戦争関連の名著なども、目に触れる機会が増えた。戦略に関していうなら、クラウゼビッツの「戦争論」も数十年前の学生時代から何度となく読み返してきたが、何年かに一度、クラウゼビッツブームが来るから、読んだ方も多いであろう。本書は2016年出版された様ではあるが、それ以前の連載をベースに書かれているとの事で、若干時代背景の理解も必要になるが、非常にわかりやすく戦略、そして戦略に含まれる罠について描かれている。また中公文書の書籍としては、これまた私の人生に大きなインパクトを与え続ける「失敗の本質」や「組織の不条理」と並び、本書は名作であると感じる。一部そうした書籍の批判なども含まれるので、前述の作品を読んだり、バイブルにしている人にとっても、ぜひ一読をお勧めする。
何より描いた戦略が絵に描いた餅になる事など日常茶飯事だ。気が付いて、3年前に書いた中期戦略などを読み返すと、頭の中ではてなマークが手を繋いでダンスを踊っている様な状態。若しくは音楽のリズムに合わずに、テンポ遅れで足取りが覚束ない様な映像が思い浮かぶ。どこでズレてしまったのか、どこでキーを間違えたのか、それすらも判らないくらい、会場の雰囲気も、演奏する楽団もひっきりなしに変わっている状態を思い描いてしまう。原因を探るなら、そもそも変化が起こりやすい時代であることは言うまでもないが、指揮者や楽団、踊り手に予期せぬ摩擦が起こっている事が見えてくる。隣同士ぶつかり合い、一瞬の演奏のずれ、頭に浮かんだ別の意識などが邪魔して思った様に流れない瞬間が何処かにあった。ビジネスの世界でも、本書が扱う過去の戦争の事例に於いても、そうしたズレ=摩擦がその後の流れに与えた影響は殊の外大きい事が理解できる。またそれを、経験せずに生きた後世の人々が、偉そうに分析する、後知恵的なものを批判する。筆者である永井陽之助氏はその当時の状況と時代背景、他者との比較などあらゆる面から統合的な考察から得られた答えを描いている(その過程で失敗の本質への批判もあるが)。
クラウゼビッツの主張における重要な観点である「摩擦」を中心に、それを生み出す人間自体にフォーカスした内容は頷ける以上に、私の脳裏に深く刻み込まれた。また一つ私の中の名著の本棚に、新しい一冊が加わった。
Posted by ブクログ
オリジナルは1985年の出版。クラウゼヴィッツの「戦争論」を下敷きに、真珠湾の奇襲攻撃、核の下での抑止と挑発、情報戦、レーニンとヒトラーの比較、戦争の目的と手段等々について、記述している。
印象的な具体例をあげると、以下のようなものがあった。
【太平洋戦争】
太平洋戦争に至る経済制裁という名の非軍事的報復が、抑止力として作用するよりも、むしろ日本軍の奇襲攻撃を挑発した原因の一つとして、日米の文化の差として、E・ホールの説を引用しているのが興味深い。
太平洋戦争に至る日米関係は、英米のような「文脈度の低い文化」と日本の「文脈度の高い文化」との外交交渉であった。つまり欧米流の「これでもか、これでもか、もっと押せ」という交渉術が日本側を深く傷つける。そして日本側はその心の傷を顔に出し、言葉に怒りをあらわすことを最後の最後まで自制する。そして日本側が真に怒りの反応を呈するときは、時すでに遅く、もはやひきかえし不能地点を越えてしまっていることが多いという説は面白かった。
また、太平洋戦争の発端となった真珠湾攻撃について、「合理的なギャンブラー」としての山本元帥を捉えていることも同様に面白かった。
【ベトナム戦争】
アメリカのケネディがベトナムに介入していく意思決定についての解釈も面白かった。
それについては、さらに最後の対談で、著者は「要するに戦略的判断というのは天才のみがこれをよくなしえるというところがある。秀才ではダメなんです。ベトナム戦争の際、バンディやマクナマラと言った秀才たちが、その戦略的判断において取り返しのつかない失敗を犯したのは周知の事実です・・・(略)・・それは何故かといえば、戦争の指揮とか企業経営といったものは、科学ではなくて、アートなんです」という言葉は印象的であった。
また視点を変えて当時の日本の雰囲気を現わしている箇所があった。
「ベトナム戦争やインドシナでの内戦では、およそソ連や共産主義の嫌いな平均的日本人が、アメリカを非難し、解放戦線と称する側に同情と支援を惜しまなかったのは、この内戦が本質的に民族解放を目指すもので、共産主義革命を目指すものではないと信じていたが、ひとたび革命権力が確立されれば、旧政府関係者や協力者は殺され、共産主義政権の誕生というかたちで終結する・・・そのあいだリベラル、平和主義者なるものは、レーニン以来の民族統一戦線なるものに徹底的に利用される。そして旧政府の関係者の運命がいかなるものか、あとになって気がついても遅い。だがもっと罪深いのは、マスメディアを通じて、素朴な人々を騙す側に立つ知識人である・・・われわれ大学人も、アメリカの悲劇が分かるまでずいぶん時間が掛かったのである」
これ以外にも目から鱗といった箇所が次々と出て来る。
久々に面白い古典(?)に出会った感じがした。
Posted by ブクログ
第4章戦争と革命
ドイツは対内的には全体主義的ではなく自国民については甘やかしすぎであったとの見方。ソビエトこそが対内的に全体主義を徹底させた。一方でスターリンの対外政策は全体主義と言うよりもリアルポリティクスであるとの評価。
国民国家の成立以後、戦争は総力戦化。ナポレオンのような天才は再現性がないのでプロイセンは参謀本部をー発明ーする。フランスやオーストリアに勝利。クラウゼヴィッツの戦争論がそのテキスト。
レーニンは革命の正当化のため国内の敵を作り出し、対外戦争のための参謀本部の機能を対内抑圧革命のためのボルシェビキに負わせ、国内で革命の敵を徹底的に殲滅する。スターリンが権力を持つとレーニンがまだしも持っていた社会民主主義な要素は消え去り、その暴力が徹底される。
Posted by ブクログ
このところの新型コロナウイルスに関する政府の失策に対するヒントがあるのではないかと思って読んでみました。
ちょっとその事前の予想・期待とは違いましたが、8月と言う時期にぴったりな、太平洋戦争にまつわる日本の選択と失敗が描かれていて、非常に勉強になった。
太平洋戦争は、異なる文化間の戦いであることもこの書で描かれている。一方の行動の意図が、文化の異なる相手方に正しく伝わらないというのは悲劇。それは、今の時代もあって、国家間のチキンレースの様相を呈する事もある。
歴史を正しく学べば悲劇は避けられるのではないかと思うが、国家間の対立が起きているときは、その当事者は冷静さを失ってしまって、そんな事は無いんだろうな。
Posted by ブクログ
個人的には「失敗の本質」と双璧を成すと思う良書。
WWⅡにおけるヨーロッパでの戦いと太平洋での戦いを中心に各戦闘における特徴と共通点をあぶりだし、
それらがなぜ成功したのはもしくは長期的に見て敗北となったのかを考察している。
目次は
・奇襲
・抑止と挑発
・情報とタイミング
・戦争と革命
・攻勢と防御
・目的と手段
純軍事的な話も多く、はあ。。となって終わる部分も多いが
これは真理だと思う。
「戦略とは自己のもつ手段の限界に見あった次元に、政策目標の水準をさげる政治的英知である」
つまり、現実的にできなさそうにも関わらず
夢物語な目標を設定してしまうことが悲劇の始まりになる。
これはある意味、個人の生活にも言えるだろうし、
会社などの組織でもいえることだと思う。
大事なことはチャレンジと無謀を履き違えないことではないか。
Posted by ブクログ
歯切れが良くて面白い。といっても乱暴な簡略化をしているというわけでもない。
特に面白く思ったのは、クラウゼヴィッツ『戦争論』を読み込んで消化しきったレーニンが、そのエッセンスを国家間の戦いではなく、共産主義の階級闘争に応用したところ、その絶大なる効果のために20世紀後半に世界が苦しむことになったというくだり。
ナイーブな民衆や「自由主義者・進歩主義のインテリ」を、反論し難い正義感や倫理観の衣をまぶした暴力思想に感染させ、結果として世界の進歩を遅らせたレーニンの罪は重かろう。
現代でも、階級闘争は、環境保護運動に姿を変え、ナイーブな知識人や大衆を惑わし続けている。システムとして環境保護や反核を推し進めているきっかけを創り出した一握りの人々は、環境破壊防止ではなく、もっと利己的なあるいは独善的な欲望を隠しているに違いない。・・というと陰謀史観みたいだが・・。