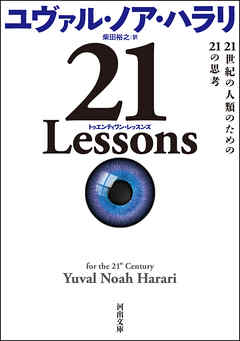あらすじ
私たちはどこにいるのか。そして、どう生きるべきか――。『サピエンス全史』『ホモ・デウス』で全世界に衝撃をあたえた新たなる知の巨人による、人類の「現在」を考えるための21の問い。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
現代のカントかなと思わせる程多岐にわたる論点を取り上げ、主張が展開されており、圧倒される。そこまで技術が発展するかなと感じる点もあるが、圧倒的な知識からの説明にただただ納得させられてしまう。同時に自分で考えないとダメだなあと反省させられる。今年一番の考えさせられた本。
Posted by ブクログ
いろんなトピックがあるのだか、
結局、こういうことに集約できるか。
取るに足らないはずの人間が力を持てたのは、
虚構を信じて団結できたから。
何か大きなことをなすには、周りに虚構を信じさせることが大事になる。
虚構を伝えてくるのは、
国であったり、企業であったり。
自分に問いかけたとして、果たしてそこに
本当の自分があるのか。
周りから信じ込まされた虚構なのではないか。
現在さらにバイオテクノロジーとデータによって、
個々人を理解した上で、それぞれに合わせた虚構さえ作りうる。
いったい何を信じたらいいのか。
と。
しっかりと自分で考える力をつけないといけない。
匿名
現在当たり前のように受けている恩恵が、今後急速に発展した結果悲惨なことにつながりかねないことを改めて実感した。無知が本当に危険なので、危機感を持つべきだと思った。
Posted by ブクログ
「現代の社会が抱える問題を学ぼう!」などと、肩肘張って読むことは、おすすめしない。この本は、著者のエッセイ的な文体で、21個のトピックに関して、ときに問いを投げ、ときに歴史の事実を紹介し、ときに著者の想いは垣間見える。そういった本である。本全体に散りばめられているエッセンスを、自ら結んでいくことで、より楽しめる本になっているだろう。
Posted by ブクログ
会社の読書会のテーマ本として取り上げた本。著書の他の本と異なり、テーマが多岐に渡り、一つ一つの章が基本的には独立して語られるエッセイのような形。なのである程度手に取りやすい。
ただし、他の本と同様、内容は彼の膨大な知識やそこから導き出される深い知恵に溢れており、学ぶことは非常に大きい。何よりも、さまざまなテーマを人類の歴史と
Posted by ブクログ
今の時代に目を向けた作品
改めてこれまでの著者の作品と同じ、一貫性のある姿勢(生化学的アルゴリズムなど)を持ちつつ、「物語」という観点に焦点を当てている
これを読んで自分は何をするのか、テーマが広範で難しい。
Posted by ブクログ
自分を価値ある何かに帰属させ、その中で役割と意味を与える物語。人はこれを信じてしまいがちらしい。
物語を疑うのが恐ろしいのは、その物語を前提に個人のアイデンティティや社会制度が築かれているから、とのこと。物語を否定すれば、今ある個人や社会も否定することになる。
たしかに、人権も物語に根拠をもつ、と言われると、物語を否定する恐ろしさがわかる。ここまでは同感。だけど著者のようにそれを受け入れ、瞑想によって心の真実を探ろうとは思えなかった。
僕なんかは、嘘でも人生に意味が欲しい、と思ってしまう。我ながら典型的なホモ・サピエンスなんだと思った。(笑)
Posted by ブクログ
今の捉え方について、納得感のある理論をもとに語られていた。問いかけの力がすごい。
虚構のおかげで進化したが、今は虚構のせいで狭苦しい世の中だと。自己•感情というものは、確固とした実態があるのではなく生化学アルゴリズムにすぎない。そんな中でどう生きるのか。
Posted by ブクログ
村上龍の「半島を出よ」を読んで、政治や経済や国際情勢や歴史に、興味と知識を持たないことは弱点だと気づいた。
とにかくなんでもいいから読みたくて、有名な本書を読んだ。
現代社会が抱える諸問題についてわかりやすく、面白く書いてある。
世界と未来に関して自分も何かしなくてはと思った。
もう一度読み直したい。
Posted by ブクログ
テクノロジー、宗教、戦争などの様々な切り口で、我々が無意識に(だが冷静に考えてみれば根拠なしに)抱いてしまっている思い込みや偏見を明らかにしてくれる。
世の中で起きている事柄について、多少なりとも見方が変わるような気付きをいくつか得られた。
Posted by ブクログ
単行本が出版された時に読んだのだが、途中で放り出したままになっていたのだが、サピエンス全史が文庫本化されたのを契機に、サピエンス全史、ホモデウス、21Lessonsと全て文庫で読み直しました。
21Lessonsはあまりにも取り扱う分野が広くてどれだけ理解したのかわからないのですが、サピエンス全史から通読したのでやっと征服した感を得ることができました。この21Lessonsの中で最後のLessonは「瞑想」なのですが、ユヴァル・ノア・ハラリは2000年にヴィパッサナー瞑想のレッスンを受けて、それ以降まいにち2時間の瞑想と毎年1か月から2か月の瞑想修行を続けているそうです。この瞑想の実践が提供してくれる集中力と明晰さがなければ「サピエンス全史」も「ホモ・デウス」も書けなかっただろうと振り返っています。
確かに情報をいくら与えられても、自分が考えていると思っていることの多くが虚構でありそれと現実を区別することがますます困難となっている現在、自分の集中力を研ぎ澄ます訓練なしには何事も明確な発言はできない。ハラリの主張はまさに明確であるのは、ユダヤ人だからではなく、瞑想の訓練をしているからなのだというのは驚きました。
いずれにしてもバイオテクノロジーと情報テクノロジーが進歩するにつれ、私たちの周りに様々なアルゴリズムが私たちをじっと見ているようになり、アルゴリズムが私たち以上に私たちを知るようになるのは時間の問題だと言えます。そのアルゴリズムに支配されずに自分自身を知るためには、努力が必要だということがわかりました。
Posted by ブクログ
いくつかの主題ごとに作者が設定したテーマをもとに考えを述べていく本書。最初に書かれている通り、その後読者がどう考えるのか、を期待して描かれている。
『サピエンス全史』では過去を、『ホモ・デウス』では未来を、本作では現在を描いている。
テクノロジー面の難題。テクノロジーが発展することにより、労働がAIに取って代わられるようになる。これはグローバリゼーションに伴い国際的な問題になりかねない。また、テクノロジーの発展が種の選別に繋がるかも知れず、それのキーワードとなるのは情報である。
労働に当てられていた時間を余暇などに当てられ、生活費などを気にしないで生きていける世の中になって欲しいと思ってしまう。が、実際には余暇を持てる人と労働者という形で越えることのできない壁ができてしまい、これが世代として脈々と連なってしまうのではないだろうか。
政治面での難題
世界はグローバルな実在的脅威を生み出すことによってテクノロジーが全てを変えてしまった。つまり、核戦争と気候変動と技術的破壊といった共通の脅威に対し協力して立ち向かわなければならないにもかかわらず、それが出来ていない。それは、危険が迫らない限り危機と思えない人間達だからである。という。今の現状として一つとして解決できそうな合意に達しているものがない以上、未来は暗いのかもしれない。移民の問題は、問題点が整理されて今まで他で見たり聞いていた議論が少しわかった気がした。
希望と絶望
テロを起こす人たちの意義を述べたのちに、それが起こる原因ともなった戦争や宗教について述べた章。最後の世俗主義については理解が深まった。世俗主義が覇権をとってほしいと思うが、一部の一神教の人たちには、一神教がゆえの寛容のなさがあるため、難しいことなのだろう。
真実
ホモ・サピエンスは虚構を作り出すことにより、他の動物たちよりも上位の存在になり得た。その過程で群れをなることとなり、その範囲内でのルールとして道徳などが生まれた。が、グローバルになりすぎた現代では、道徳の基準が昔のままで良いのだろうか。また、SFの示す世界観が今後の道標になるのであろうか。
最後の方や未来への展望で『ホモ・デウス』のようなアルゴリズムに支配されている我々というようなかんじでリンクしているのも良かった。
Posted by ブクログ
・自由民主主義や自由貿易は完璧な制度ではないが、最善の制度ではあるというのが21世紀の答えになっているが、果たして今後もそうだろうか。データ社会となり、頭のいいAIが理論上最適解を導ける社会が到来したとき、無知の人間に等しく投票させる自由民主主義は好ましいのか。最も納得感のある制度であることは間違いないが、正しい解を導けるかは分からない。
・チャンスを掴む人間というのはチャンスを掴む準備をしていた人間であり、何もしていない人間は、どんなに社会が機械化、AI化したとしても、棚ぼた的な成功はつかめない。今後の世の中というのは、より格差が生じる社会となる。
Posted by ブクログ
おもしろかった。
ニュースで気になっていたりしたとことについて、著者なりの整理をつけて解説してくれて、そうそう!そうなの!ってうなづいたり、もやもやしていた出来事への解説がすごく丁寧で気持ちが晴れた。
すごくありがたい。この本を読んだ人たちと話したい。
以下引用———————
ブレグジットに関してのリチャードドーキンス)
一般大衆は、判断に必要とされる経済学と政治学の予備知識を欠いていたからだ。「アインシュタインが代数学的な処理をきちんとこなしていたかどうかを全国的な投票を行なって決めたり、パイロットがどの滑走路に着陸するかを乗客に投票させたりするようなものだ(3)」 ところが是非はともかく、選挙や国民投票は、私たちがどう考えるかを問うものではない。どう感じるかを問うものなのだ。
今日すでに私たちは、誰一人よく理解していない巨大なデータ処理システム内部のごく小さなチップと化しつつある。-略- 山のようなメールに返信するのに忙し過ぎるから。
私たちがロボットを恐れるべきなのは、ロボットがおそらくつねに主人に従順で、けっして反抗しないからなのだ。
アルゴリズムは、あなたが女性だから、あるいはアフリカ系アメリカ人だから差別するのではなく、あなたがあなただから差別する。あなたが持っている、何か特定の点が、そのアルゴリズムには気に入らないのだ。それが何か、あなたにはわからないし、仮にわかったとしても、他の人々と団結して抗議することはできない。それと完全に同じ偏見に苦しんでいる人は誰もいないからだ。
政治家たちは自分には選択権があるという幻想を抱いているが、本当に重要な決定は、メニューの選択肢を決める経済の専門家や銀行家や実業家によって、ずっと以前にすでに下されている。二〇年ほどのうちに、政治家はAIが用意したメニューから選ぶようになっているかもしれない。
スイスにいるいとこと話すのは、かつてないほど簡単になったが、朝の食卓で配偶者と話すのは難しくなった。
今日の文化差別主義者は従来の人種差別主義者よりも寛容かもしれない。「他の人々」が私たちの文化を採用しさえすれば、対等の人間として受け容れる、というわけだ。その一方で、同化するようにという、はるかに強い圧力を「他の人々」にかける結果や、もし同化できなければ彼らに対して、はるかに厳しい批判を浴びせるという結果にもなりうる。
今日、主な経済的資産は、小麦畑や金鉱ではなく、油田でさえもなく、技術的な知識や組織の知識から成る。そして、知識は戦争ではどうしても征服できない。
苦しみに対する理解を深めさえすればいい。ある行動が自分あるいは他者に無用の苦しみを引き起こすことが理解できれば、その行動を自然と慎むようになる。
人間の決定のほとんどが、合理的な分析ではなく情動的な反応と経験則による近道に基づいており、私たちの情動や経験則は石器時代の暮らしに対処するのには向いていたかもしれないものの、シリコン時代には痛ましいほど不適切であることは、行動経済学者や進化心理学者によって証明済みだ。
権力はブラックホール
権力の中心にとどまれば、世界をはなはだしく歪んだ形でしか見られない。だが、思い切って周辺部に行けば、稀少な時間をあまりに多く浪費することになる。
瞑想の章
怒りとは何か、知りたいだろうか? それならば、腹が立っているときに体の中で起こって消えていく感覚をただ観察すればいい。
自分の苦しみの最も深い源泉は自分自身の心のパターンにあるということだった。何かを望み、それが実現しなかったとき、私の心は苦しみを生み出すことで反応する。苦しみは外の世界の客観的な状況ではない。それは、私自身の心によって生み出された精神的な反応だ。これを学ぶことが、さらなる苦しみを生み出すのをやめるための最初のステップとなる。
Posted by ブクログ
ー 人間は、事実や数値や方程式ではなく物語の形で物事を考える。 そして、その物語は単純であればあるほど良い。どんな人も集団も国家も、独自の物語や神話を持っている。だが二〇世紀には、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、モスクワのグローバルなエリート層が、過去をそっくり説明するとともに全世界の将来を予測するという触れ込みの、三つの壮大な物語を考え出した。 ファシズムの物語と、共産主義の物語と、自由主義の物語だ。
ファシズムの物語は、異なる国家間の闘争として歴史を説明し、他のあらゆる人間の集団を力ずくで征服する一つの集団によって支配される世界を思い描いた。 共産主義の物語は、異なる階級間の闘争として歴史を説明し、たとえ自由を犠牲にしても平等を確保する、中央集権化された社会制度によって、あらゆる集団が統一される世界を思い描いた。自由主義の物語は、自由と圧政との闘争として歴史を説明し 、あらゆる人が自由に平和的に協力し、たとえ平等はある程度犠牲にしても中央の統制を最小限にとどめる世界を思い描いた。 ー
単純化して言ってしまえば、人間は物語の中で生きている。物語りの単位は個人から始まり、家族、共同体、部族、民族、宗教、国家、人類、地球、宇宙、、、大小問わない。その物語りの中で生きている自分をその物語を通じてしか認識できないか、その物語りの外から認識できるか、その違いが重要。
物語りの外から世界を眺める事により、この世界の真実が見えてくる。その真実から、本来の我々のなすべき事を考えられるかどうか、その事によって、世界が救われるかどうかの明暗が分かれる。
それが、この21のLessonsの本質だと思う。
Posted by ブクログ
本作を読むにあたって前2作を改めて読み直したので、彼の作品を通しで5冊読んだことになる。
ホモ・サピエンスが覇権を握った理由の一つに虚構を信じる認知革命の影響があると言われるが、故にフェイクと真実を切り分けるのも苦手だったりする。
本作は、これまでの歴史を踏まえながら我々の思い込みを暴き、今をどう生きるか?を考えさせる一冊だ。
相対的にキリスト教文化圏にシンパシーを感じる反面、そのキリスト教の歴史を知る人はこの国には少ない。イスラム教やユダヤ教も同様に、変な思い込みが陰謀論を生み、フェイクニュースに騙される。
科学が暴いた真実によれば、人間の意識や心なんて崇高なものはなく、単なる電気アルゴリズムなのだそうだ。つまりは、バイオテクノロジーとIT革命によって人間の意識や心も完全にアルゴリズムと薬で支配できてしまいかねない…というのは暴論ではない。目の前を流れる大量の情報を捌くことばかりに意識を向けるのではなく、真実を観察して自分を持ち続けること、考える力を持ち続けることへの警鐘を鳴らしている。
Posted by ブクログ
Audibleにて聴了
ポスト・トルゥースの時代、社会情勢の変化に戸惑うことや無力感を感じることも多いなか、誰が何を見て、どのような意図で振る舞っているのかを理解する助けとなる書。
一章のテクノロジーについての話はなかなか入り込むことに苦労したが、三章以降は非常に興味深かった。
時間が経ったら、今度は読むことで理解を深めたい。
Posted by ブクログ
ハラリが21のトピックについて自分の考えを書いたもの。ほとんどが納得できるものである。特にイスラエル人だからか宗教についての考察が多いが、ユダヤ教をはじめとする一神教への批判が鋭い。宗教的にも国家的にも軽くなっている日本人には受け入れられやすいように思う。
しかし、気候温暖化、AIについての切迫感の強さは戦争よりも強いように思えた。
早く行動すべきというのが紙面から窺える。
個人的には人生には意味がないと繰り返し言っていることと瞑想を一つの解決方法としていることが面白かった。
人生に意味はないが、自分を観察して適切に動くためには、自分を知ることが必要ということ。
自分を知ることと世界へ行動を起こすことの繋がりはわかりにくい。
仏教的諦観からは地球が温暖化し、人間が絶滅しても何の問題もないような気がするが、人類として生き残る努力をするべきということか。
Posted by ブクログ
歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリによる
21 Lessons(21世紀の人類のための21の思考)
テクノロジーの難題、政治的難題をどう乗り越えるのか?21の考察は単純な答えで終わりはしない。その目的はさらなる思考を促し、現代の主要な議論のいくつかに読者が参加するのを助けることにある。
第一次トランプ政権誕生、イギリスのEU離脱があったのちに書かれた本書を第二次トランプ政権誕生のタイミングで読み進める。
一つ一つのトピックに深く考えさせられた。AIとバイオテクノロジー革命が社会はもとより私個人に難題を突きつけるそのときに、自由主義は信用を失いつつある。雇用は?自由は?平等は?
終盤の3トピック教育、意味、瞑想でレジリエンス(困難をしなやかに乗り越え回復する力)を示してくれている。
世の中の虚構の物語と現実を見分ける方法について、「もしこの世界や人生の意味や自分自身のアイデンティティについての真実を知りたければ、まずは苦しみに注意を向け、それが何かを調べるにかぎる。その答えは物語ではない。」
まさに、あなたが逃げている部分に目を向けなさい。そうしないと自分なんてわからないから。と言われている気がした。良書。
Posted by ブクログ
難しく、一度では理解出来ない部分もあったが、認識を改めたり、自分の中でより強く確信できたものもあった。
瞑想は自己流で毎日してるけど、ちゃんと師事してヴィパッサナー瞑想やってみたいな。
Posted by ブクログ
人類が気を付けるべきことや将来の可能性について考察した本。私たちの生活は、技術の進歩によってすぐに変わるかけではない。しかし。気づいた時には昔よりも進歩した社会になっているかもしれないことを思い知らされた。ホモ・デウスに比べると現実問題に焦点を当てているので、読みやすいものとなっていると感じた。
第5部に分かれているが、テクノロジーと政治面の課題は将来に繋がる問題、残り(欲望、真実、レジリエンス)はとりわけ現在解決できそうな具体的な問題について述べられている。
まず、目覚ましい発展を遂げているテクノロジーが生み出すアルゴリズムは、私たちの意思決定の判断をするかもしれない。すると、大量のデータ処理に長けたAIは私たちの雇用を奪っていく可能性がある。しかし、知能がアルゴリズムに取って変わられても、意識の所在についてはそうもいかない。未だ解明されてないことが多いからだ。データが生活を担うのならば、人類は五感を活かして、感覚を養うことが人生の目的になるのではないか。例えば、ユダヤ教正統派男性のように儀式や活動に深い意味を見出すことにあたる。
自由主義によって最も良い選択を求めるあまりにAIの決定に従う世界は、はたして自由と言えるのだろうか。少なくとも、データのありどころを掴む人が人を制すると思われる。
世界は様々なものが統一されようとしている。AIは私たちの生活と融合しようそしているし、文明は絶えず変化している。その文明もナショナリズムによって定着し、融合することでグローバル化が進歩する。
人類には、宗教や神が絶対とされる文化が存在する。現代では、それを振りかざすのではなく謙虚さを兼ね備えることが求められる。
情報が蔓延いている現代は、思っているよりも無知で正義が定まっておらず、嘘が入り混じる社会である。
このような世界で自分意思の支配権を維持したければ、自分のことを良く知るようにしておかなければならない。個人的な意見として、データが蔓延る時代はAIの処理の方が能力が高い。だから、柔軟性や誰にも譲れない価値基準を見つけることが大事なのだろう。
人間は行動に意味を持たせたいがために、矛盾した行動をとったり、不合理な決断をすることがある。本当の自分を理解するためには、瞑想によって自己を見つめることが必要である。
現代の重要テーマとして、テクノロジーの発展と倫理観をどのように扱うかについて自分の答えを持っておくべきである。そして、自分の謙虚さと真実を探せるようにしておくのだ。数ある情報を精査するために役立つのが瞑想である。
Posted by ブクログ
読書会で読むことにした本でなければ、途中で挫折していたかも(笑)
苦労しただけに読み終わった後のクリア感は半端ない。作者が結論を明確に(敢えて)しないので、それぞれの具体例が最終的にどこに帰結するのか忍耐力が必要。
読み終わった後に「虚構」=物語の位置付けを咀嚼し直して、メタ認知。ようやく視界が広がってこの本の全体像を把握した。
ホモ・サピエンスは物語(虚構)を作ることで力を得てきた。(これは「サピエンス全史で著者が解き明かしてきたことだ。いわゆる「認知革命」である)国家、宗教、イデオロギー、貨幣経済等を作ることで集団の力を発揮し、人々はその物語に陶酔すらした。大きい物語であればあるほど、それは力を持ち魅力的だ。
ハラリはその物語=「虚構」を否定しているわけではない。「虚構」を神話ではなく、「虚構」として捉える視点を持つことの重要性を説く。しかし、それは、難しいことでもある。
そのためには、時間と労力とお金をかけること。タダの情報より、お金を出して自分の欲しい情報を買うこと。(Yahooニュースより、新聞だ、と解釈した)私たちの情報はどんどん吸い上げられ、人間を凌駕するアルゴリズムが作り上げられる。アルゴリズムは進化するからだ。シンギュラリティは予想より早くもうまもなく到来するだろう。
テクノロジーの奴隷になるな、とハラリは警告する。アルゴリズムのままに誘導され、ベイシックインカムを与えられ「快適」な生活を送るのも下層に位置付けされたホモサピエンスの最終的な一つの生き方かもしれない。しかし、それは「人間」を捨てることと同義でもある。
「人間」とは何か。どれだけアルゴリズムが完璧な人間性に近づこうとも、人間とAIの違いは「意識」の有無だ。
かつてデカルトが言った。「我思う故に我あり」さすがデカルト!
私たちにはもう時間がない。ここでひと踏ん張りしなければならない。それが個人レベルであろうとも。
ハラリはそういう読者を求めている。
せめて読書会くらいで踏ん張ろうと思う。
Posted by ブクログ
オーディブルで拝聴。AIが自分の代わりに判断してくれるようになるし、世界は勝手に広がって自分の目の届かないところで何かが起きてるし、相変わらず宗教や国民性といった”常識”もある。でも考えることをやめないこと。知れば知るほど絶望するかもしれないし、滅入ることもあるかもしれないけど、考えること、知ろうとすることをあきらめないこと。
道徳的であるということは、知ろうとするということである。
Posted by ブクログ
この人が結局言いたいのは、現実に多く広がる虚構に騙されてはいけない。そのためには、まずは虚構を知ることであり、その上で自ら調べることである。
この人が大切にしたいことを1つ述べるなら、真実と言う言葉が1番あうと思う。真実とは一体何なのか?自分の心の中に出てきた疑問と向き合い続け、読者に最良の教えを伝えようとする姿勢がこの人から伝わってくる。だからこそ、世界的ベストセラーになるんだと思う。この人の新刊がでたら、また読みたいと思う。
Posted by ブクログ
コロナ禍のもと、初めてユヴァル・ノア・ハラリを知った。様々な知識人が発言したが、人文分野では最も信頼できる人だと思った。それで初めて著書を紐解くべく予約して6カ月、今度はウクライナ問題が勃発した。本書はウクライナを「予言」はしていない。けれども、「予見」はしていた。とても示唆に富む話が多かった。
21のissueのうち、「戦争」のみに絞って参考になった所をメモしたい。それだけでもかなりの量になると思う。
⚫︎過去数十年間は、人間の歴史上最も平和な時代だった。暴力行為は、初期の農耕社会では人間の死因の最大15%、20世紀には5%を占めていたのに対して、今日では1%に過ぎない。
←そうかもしれない、とは思っていたけど、そこまでだったんだ!
⚫︎1914年と2018年(←現在)では、世界大戦の危険性が高まっているという共通点がある。軍事費の増大、戦争挑発行為、危険な指導者。
違いもある。1914年では、戦争で勝利を収めれば経済が繁栄し、政治権力を伸ばせると思っていた。現在では、その反対。
⚫︎イスラエルが仇敵シリアの内戦に関与しなかったのは、ネタニヤフ首相の最大の政治的業績だろう。やろと思えば1週間以内にシリア首都ダマスカスを陥落させられただろうが、そこから得るものなどないと知っていたから。ガザを征服してハマス政権を倒すことは、なお易しいだろうが、ずっと思いとどまっている。
⚫︎21世紀に主要国が行った侵略で、唯一成功したのはロシアのクリミア征服(2014)だった。しかし、その後は良くなかった。ウクライナ東部で頑強な抵抗に遭う。総合的に言えば成功ではない。ロシアの威信は高まったが、同国に対する不信と敵意を募らせたし、経済的にも損失を招いている。ロシアのエリート層は、今のところ(2018年時点)、プーチンに冒険をエスカレートさせないように細心の注意を払ってきた。
←結局、プーチン独裁体制が完成してしまい、それが破裂したのか?
⚫︎ロシアは、80-90年代に西側諸国からの侵略(NATOの東ヨーロッパへの進出、セルビア、イラクに侵攻)から、自国の勢力圏を守るには、自らの軍事力に頼るしかないことをはっきり思い知らされた。最近のロシアの軍事的な動きは、その辺りに原因がある。
←だからNATOや米国も悪い「どっちもどっち」論があるが、間違っている。私はロシアに与しないが、ここでは展開しない。
⚫︎もちろん、ウクライナ、ジョージア、シリアでのロシアの軍事行動は、大胆な帝国主義的大攻勢の第一弾となる可能性はある。しかし、中国のような他の国が加わらなければ、新しい冷戦に持ち堪えられないし、本格的な世界大戦など戦えるはずがない。ロシアの人口は、1億5,000万人で、GDPは四兆ドルだ。人口とGDP両方で、アメリカ(3億2500万人、19兆ドル)やEU(5億人、21兆ドル)に遠く及ばない。アメリカとEUを合わせると、人口は5倍以上、GDPは10倍となる。さらに重大なのは、プーチンは共産主義に代わるイデオロギーも持ち合わせていない。
←これを見ても、長期的な展望で、ロシアが有利に戦争を終わらすことは無い。と私でさえ、思ってしまう。中国参戦すれば、また別の思考が必要ではあるが。
⚫︎21世紀の戦争で、勝利を収めるのがこれほど難しいのは何故か?
◯一つは、経済の性質の変化。
経済的資産が物だった頃は、勝って奪えばよかった。今は、資産は小麦畑や油田さえでもなく、技術的な知識や組織の知識からなる。イスラミックスステートは、イラクの銀行から五億ドルを掠奪し、石油販売で五億ドル稼いだが、中国・米国にとって、その額は微々たるものでしか無い。GDP20兆ドルの中国は、わずか10億ドルのために戦争は始めない。勝利を収めた中国は何千億ドルもの価値があるシリコンヴァレーの富を略奪できるのか?絶対できない。
◯戦争に勝利をすれば、自分に有利になるように交易制度を改変して莫大な利益を得ることは、まだ可能だろう。しかし、軍事テクノロジーの変化で、圧倒的な勝利は難しくなった。負けた側が報復的な核兵器を使う可能性はある(北朝鮮)。更にはサイバーテロで、むかしのように損害が少なくて利益が大きい事業は想定できなくなった(だから、クリミア征服は恐ろしい例、例外であることを願おう)。現代の核兵器やテクノロジーの戦争は、損害が多くて利益が小さい。相手をまるまる破壊すれば、利益の上がる帝国は築けない。
⚫︎しかし、このことは、平和が訪れることを保証はしない。人間の愚かさは、決して過小評価するべきではない。
◯例えば、1930年代、日本の将軍や提督、経済学者、ジャーナリストたちは、朝鮮半島と満州と中国沿岸部の支配権を失えば、日本は経済が停滞する運命にあるということで意見が一致した。だが、彼らは全員間違っていた。実は名高い日本経済の奇跡は、大陸に持っていた領土をすべて失った後に、ようやく始まったのだ。
◯人間の愚かさは、歴史を動かすきわめて重要な要因なのだが、過小評価されがちだ。
◯人間の愚かさの治療薬となりうるものの一つは謙虚さだろう。我が国の権益を、人類全体の権益よりも優先されるべきだという思い、に対する謙虚さである。そのためには、どうしたらいいだろう?
←かつて考古学者の佐原真は、人類史を一年で換算すれば、戦争を始めたのは大晦日の午後の遅いくらいだと言った。戦争は人間が始めた。しかも、つい最近始めた。だから戦争は人間が無くすことができる。だから私は古代の歴史に関心がある。
Posted by ブクログ
21世紀に起きる未来 人はどこからきて、どこにゆくのか?この壮大な問いかけをした知の巨人が21世紀の人類に語りかける未来。それは、急激に変わる世界で生きるためには、自分の心さえも組み立て直せるほどの柔軟性を持てという言葉でした。どうして、ハラリ氏はその結論に至ったのか?ぜひ、本書を読んで未来を考えてみてください。
Posted by ブクログ
我々は、多くの物語で構成された虚構の中で生きていて、虚構をさらに脅かすようなテクノロジーの出現に、崩れいく未来に直面していることを、気づかせてくれた。また、実感としても感じるようになった。
Posted by ブクログ
非常に内容が濃いこともあり、理解しきれない、読みきれない、読み飛ばしてうことがあった。
そのような中で印象に残った話題を記す。
・ITとバイオテクノロジー
両者が今後世界を大きく変えうることは他の本等で知ってはいた。本書ではこのフレーズが多く用いられていたこと、無用化の時代が来る可能性があると言及していたことが印象的だった。改めて、ITに関する知識を身につける必要性があると感じた。
・移民
移民に対し、賛成派と反対派に分かれて議論が起きていることはめよく目にしており、どちらの意見も正しいように思えるため、着地点はどこになるのかという疑問を私は持っていた。
本書では、受け入れる地元住民が移民に反対している場合、移民受け入れを政府が判断することは間違いであるという原則を示しており、参考になった。また、文化差別という概念が提示されており、非常に新鮮な者に思えた。
・瞑想
瞑想は良いと様々な媒体で言及されており、本書でも瞑想による効用の説明があった。今後、瞑想関係の本を読んだうえで、私の趣味のサウナで瞑想でもしてみようかな・・・
Posted by ブクログ
テクノロジーの支配、身近に感じる。スマホから逃げるのは今年の目標。お金や時間よりも意識を奪われることの怖さを理解。
世界にはたった一つの文明しかない、っていうのは、確かに!って感じ。ここ数百年で一気に世界の均質性が高まっている。
世俗主義の強さ、良さに共感。自らの陰の面を認めることによって進歩してきた。絶対は無い。宗教との違いであり、強さ。
この世は物語で出来ている。物語を信奉することによって人はこんなに他の動物よりも進歩してきた。確かにその通り。何をするにしろどんな物語なのかを意識せずにはいられない。でも実は物語なんてなく、ただ有機化学反応によって感情や意識が形作られており、ただそれだけ。怒りも喜びも悲しみもただの化学反応。
瞑想っていいのかなあ。。今年やりたいと思ってるんだけどなあ。。
SFとか過去の名小説とか観たり読んだりしてみようと思った。1984年とか、、
Posted by ブクログ
p75 〜私たちがどれほど努力したとしても、人類のかなりの割合が雇用市場から排除されるのなら、ポスト・ワーク社会やポスト・ワーク経済やポスト・ワーク政治のための新しいモデルを探求せざるをえないだろう。
p78 「仕事」と見なされる人間の活動の幅を拡げる〜。私たちは発想を変え、子供の養育はこの世でおそらく最も重要で大変な仕事であることに気づく必要があるのかもしれない。〜これらの仕事を誰が評価し、お金を払うか〜。けっきょくそれは最低所得保障と大差はなくなる。
p85 人間の幸せは客観的な境遇よりも期待にかかっている。ところが、期待は境遇に適応しがちで〜。
最低所得保障が本当に目標を達成するためには、〜何かしらの有意義な営みで補わなければならないだろう。
p86 ロボットとAIが人間を雇用市場から押しのけていくにつれ、ユダヤ教超正統派は〜将来のモデルと見なされるようになる可能性がある〜。すべての人の人生で、意味とコミュニティの探求が、仕事の探求の影を薄くさせるかもしれない〜。
p87 アルゴリズムに仕事を奪われることは、〜恩恵となる〜。〜それ以上に憂慮するべきこと〜人間からアルゴリズムへの権限の移行〜。
p95 b×c×d=ahh! すなわち、生物学的知識〜と演算能力〜とデータ〜の積は、人間をハッキングする能力〜に等しい。
p126 アルゴリズムが意識を持つことはない。
#意識の定義なくこのような断定は軽率ではないのか。