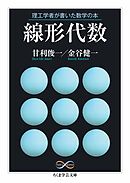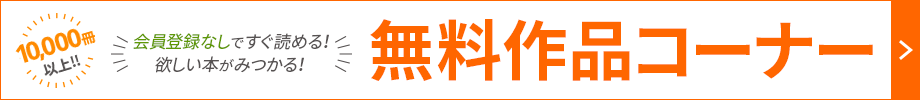脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす のユーザーレビュー
感情タグBEST3
Posted by ブクログ 2018年10月23日
神経回路の数理研究の専門家による、脳のメカニズムや人工知能に関する本。数式など完全に理解できたわけではないが、脳のメカニズムや理論、人工知能についての解説は詳しく役に立った。脳の数理的研究の第一人者であり、日本の研究体制についての意見にも説得力がある。
「生命は自己複製、すなわち自分と同じものを作...続きを読む
Posted by ブクログ 2016年06月12日
人工知能をこれ以上無いと思われる背景、ビッグバンに遡り、生物と脳の発展を振り返り、脳とは何かについて分かり易く解説、そして、ニューロコンピューティングを中心に、現在の第三次人工知能ブームに繋がる第一次人工知能ブームと第二次人工知能ブームそしてその間に横たわる冬の時代をご自身の研究と重ね合わせて丁重に...続きを読む
Posted by ブクログ 2018年07月07日
これは良書です。お薦めします。
脳の仕組み、人間の意識、人工知能の研究をそのコンセプト含めて、読みやすくまとめてくれています。
ディープラーニングの「ディープ」とはどういう事なのか、なぜ「ディープ」なのか、結果どういう事が起きたのか、今までモヤモヤしていた部分に対しても記載されていたので、個人的に...続きを読む
Posted by ブクログ 2017年02月19日
ちまたで人気の人工知能について日本の第一人者が極力平易な内容で論じてくれる一冊、良書。機械学習やディープラーニングがアプリケーションやプログラミングが中心にバズりまくってるけど、まずはバックグラウンドにあるカオスとか理論計算機科学とか、そのあたりを押さえとくといいんじゃないでしょうかね?(僕はアプリ...続きを読む
脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす の詳細情報
閲覧環境
- 【閲覧できる環境】
- ・ブックライブ for Windows PC(アプリ)
- ・ブックライブ for iOS(アプリ)
- ・ブックライブ for Android(アプリ)
- ・ブックライブ PLUS for Android(アプリ)
- ・ブラウザビューア
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。