無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
無料マンガ・ラノベなど、豊富なラインナップで100万冊以上配信中!
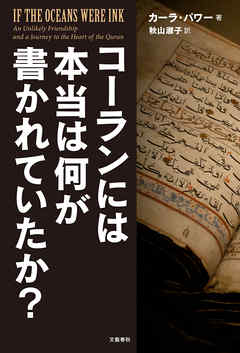
宗教への信仰を持たないアメリカ人女性ジャーナリストが、
友人のイスラム教の指導者とともに、コーランを実際に読む。
・女性はベールやヒジャーブで身体を覆い、肌を見せてはいけない。
・女性に教育を受けさせてはいけない。女性を打擲するのが夫の務めだ。
・ムハンマドが9歳の妻を娶っていたことは小児性愛の肯定だ。
・ジハードで死ぬと楽園の72人の乙女という報酬を約束されている。
コーランには、実はそんなことは一言も書かれていない!
子ども時代をイスラム圏で暮らし、今はジャーナリストとして「ニューズウィーク」や「タイム」などに多くの記事を寄稿しているカーラ・パワー。
彼女はある日、17年間のキャリアの中で、編集者から一度も「コーランについて書いてほしい」と言われたことがなかったと気がつく。
メディアが求めるのは、いつも「イスラム教から生まれた政治」であり、イスラム教そのものではない――。
そう感じた彼女は、かつてオックスフォード大学イスラム研究センターで同僚だったイスラム学者のアクラムとともに、1年間にわたってイスラム教の原点、コーランを読み解くことを決意する。
女性の権利、ジハード、小児性愛、夫の暴力、イエス・キリスト、そして死後の世界……。
コーランの真髄に触れる旅の中で、知られざるイスラム教本来の姿が明らかになる。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。
※アプリの閲覧環境は最新バージョンのものです。