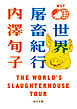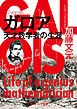ノンフィクション・ドキュメンタリー - KADOKAWA作品一覧
-
4.5ここ数年不振続きで開幕前はそれほど期待されていなかった阪神タイガースだが、ふたを開けてみれば巨人と首位を争う大躍進。チームの何が変わったのか。その秘密を元監督の岡田彰布が探る。
-
4.0「雪は天から送られた手紙である」の言葉で有名な中谷宇吉郎。世界で初めて人工雪の製作に成功した物理学の権威は、恩師・寺田寅彦の影響を受け、一般読者向けの随筆を数多く残している。科学的なものの見方とは、人間の愛情や道徳観から離れ、物質や法則をそのままの形で知ろうとすることとする「科学と人生」をはじめ、「科学と政治」「科学のいらない話」「寺田研究室の思い出」など、著者自選11編を収録。解説・永田和宏
-
3.0「空いた電車に乗るために採るべき方法はきわめて平凡で簡単である。それは空いた電車の来るまで、気永く待つという方法である」(「電車の混雑について」)。科学に興味をもつ一般読者向けに編まれた、『柿の種』と双璧をなす代表作。人間が発明し、創作した物のなかで「化物」は最も優れた傑作とする「化物の進化」をはじめ、「物理学と感覚」「科学上の骨董趣味と温故知新」「怪異考」ほか全13篇を収録。解説・全卓樹
-
3.0「科学は、自然に対する驚異の念と愛情の感じとから出発する」(「簪を挿した蛇」)。雪の結晶の研究や人工雪の製作で足跡を残した物理学者の中谷宇吉郎は、寺田寅彦と並ぶ名随筆家として知られている。身近な生活の中にあるさまざまな話題から、科学的な見方とはどのようなものかを説いた作品を厳選。代表作の「雪を作る話」「雪雑記」「ツンドラへの旅」「天地創造の話」「千里眼その他」「立春の卵」など17篇を収録。解説・佐倉統
-
4.5「記憶していた以上に凄い本だった。これは奇書中の奇書と言っていい」 解説の高野秀行氏も驚嘆! 前人未踏の養豚体験ルポルタージュ。 ロングセラーの名著『世界屠畜紀行』の著者による、もう一つの屠畜ルポの傑作。 生きものが肉になるまで、その全過程! 世界各地の屠畜現場を取材していく中で抱いた、どうしても「肉になる前」が知りたいという欲望。 養豚が盛んな千葉県旭市にひとりで家を借り、豚小屋を作り、品種の違う三匹の子豚を貰い名付け、約半年かけて育て上げ、屠畜し、食べる。 「畜産の基本は、動物をかわいがって育て、殺して食べる。これに尽きる」。 三匹との愛と葛藤と労働の日々に加え、現代の大規模畜産での豚の受精、出産から食卓にあがるまでの流れも併せて踏み込み、描いた前代未聞の養豚体験ルポルタージュ! ※本書は2012年に岩波書店から出た単行本を加筆修正し、文庫化したものです。 【目次】 はじめに なぜ私は自ら豚を飼い、屠畜し、食べるに至ったか 見切り発車 三種の豚 システム化された交配・人工授精 分娩の現場で いざ廃墟の住人に 豚舎建設 お迎え前夜 そして豚がやって来た 日々是養豚 脱 走 餌の話 豚の呪い 豚と疾病 増量と逡巡と やっぱり、おまえを、喰べよう。 屠畜場へ 何もかもがバラバラに 畜産は儲かるのか 三頭の味 震災が あとがき 文庫版あとがき 解説 高野秀行
-
4.0「科学の世界は国境の向うから文学の世界に話しかける」(「文学と科学の国境」)。日本の伝統文化への強い愛情を表した寺田寅彦。芭蕉連句を映画のモンタージュ構成や音楽の楽章に喩えるなど、ジャンルを越えて芸術の本質に迫る眼差しをもっていた。科学者としての生活の中に文学の世界を見出した「映画芸術」「連句雑俎」「科学と文学1」「科学と文学2」の4部構成。
-
5.0今の日本の臨終を巡る家族関係の在り方にどこか大きな間違いがあるのではないか。老衰死は全体の7.1%という現代で、臨終間際な患者の医療と介護の在り方、臨終に際しての家族の在り方を現役医師が説く。
-
3.8(目次) はじめに 酷暑下で展開される未曾有の「やりがい搾取」 第1章 10万人以上のボランティアをタダで使役 無償の根拠は何か なりふり構わぬ学生の動員 驚愕の「中高生枠」 薬剤師も無償で調達 高齢者は募集対象外? 1964年は夏季開催を強く否定、10月に行われた 19年ラグビーWCまでも無償ボランティアで 長野五輪のボランティア 第2章 史上空前の商業イベント 商業化は84年のロサンゼルス五輪から IOCと五輪貴族を支えるスポンサーシステム 一業種1社の原則を捨てた東京五輪 JOCの不明朗な体質 パブリックビューイングを開けない「スポンサーファースト」 第3章 ボランティアの定義と相容れない東京五輪 そもそも「タダ」という意味ではない 五輪運営費の内訳に対する疑念 巨額のスポンサー料をなぜ開示しないのか 第4章 東京五輪、搾取の構造 ボランティアがオリンピック貴族に貢ぐ構図 「やりがいPR」で再び炎上 さまざまな有償ボランティア 第5章 なぜやりがい搾取が報道されないのか 「全国紙全紙が五輪スポンサー」の異常 組織委の「核心利益」を追及できない メディアの東京五輪報道は原発プロパガンダと同根である 電通を批判できないメディア 第6章 問題を伝え続けること 5万人がリツイートしたタダボラ批判 批判ツイートが閲覧不能に 大学でのタダボラ反対講義で参加希望者がゼロに 君たちはどこにいるのか 終章 21世紀の「インパール作戦」である やりがいPRで再び炎上 外国人観光客の熱中症で病院はパニックに 無償ボランティアになるためにカネを払う? 「熱中症の患者がどのくらい出るか予想もできない」 おわりに
-
4.0自分のことを謙虚に受け止めることができれば、自分の足りないことや間違っていることに気が付くことができます。逆に謙虚さを失い、自分が成功したと思って満足してしまえば、それ以上の進歩はありません。成長を止めてしまうのは、結局、自分なのだと思います。私は様々な壁にぶつかり、もがきながらそれらを乗り越えて成長してきました。一生懸命に取り組んでいれば、その時々で進むべき道を示してくれる人との出会いがあると信じています。千葉ロッテマリーンズの選手たちも変わることを恐れず前に進んでいってほしいと願っています。(本文より) 第1章 引退の日 第2章 監督就任 第3章 王会長とギーエン監督の教え 第4章 壁の乗り越え方 第5章 メジャーから持ち帰ったこと 第6章 新生マリーンズの進む道
-
-高倉健が認めた刀匠・宮入小左衛門行平。左利きというハンデを克服し、人間国宝の父を次いで刀匠として生きる彼と、第一線の刀職者たちへの10年以上に及ぶ取材から、現代の刀作りにおける美、哲学、技を描く。 ※本書は、2016年10月22日に配信を開始した単行本「刀に生きる 刀工・宮入小左衛門行平と現代の刀職たち」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
4.1菅官房長官に質問をぶつけ続ける著者。演劇に夢中だった幼少期、矜持ある先輩記者たち、母との突然の別れ……。記者としての歩みをひもときながら、6月8日を境に劇的に変わった日々、記者としての思いを明かす。
-
4.3日本全土がフィーバーに沸いた中学生棋士・藤井聡太四段の登場と破竹の29連勝。中学生棋士はこれまで5人現れ、これまでその全員がトップ棋士として活躍した。早熟な才能はいかにして生まれるのか、その謎に迫る。
-
3.9大物政治家の金銭スキャンダルから芸能人のゲス不倫まで、幅広くスクープを連発する週刊文春編集部。 その取材の舞台裏を、編集長と辣腕デスクたちによる解説と、再現ドキュメントにより公開する。
-
3.8スマホ不正疑惑をなぜ未然に防ぐことができなかったのか。将棋ソフト、プロなき運営、見て見ぬふりをしてきた将棋ムラ…「憧れの職業どころか食えない職業になる日も近い」という将棋界の実情を現役棋士が明かす。
-
3.5ドキュメンタリー映画でも話題になった、山口組の顧問弁護士を長きにわたって務めてきた山之内幸夫。なぜ彼は山口組の弁護を請けることにしたのか。山口組を近くで見続けてきた男が語る、暴力と弁護。手記、独占出版。 第一章 山口組分裂の背景 第二章 代紋の重み 第三章 ヤクザの民事介入暴力と薬物 第四章 月額十万円の顧問弁護士 第五章 四代目山口組の船出、そして射殺 第六章 暴力団の運命 あとがき
-
3.0賠償金をめぐる地域コミュニティの分断、長い仮設住宅生活で崩壊する家族…。東日本大震災から5年、中越地震を取材した記者が、被災地における諸問題が福島で同様に繰り返され、深刻化している実態に警鐘を鳴らす。
-
4.0ギャンブル依存症は意志や根性ではどうにもならない、「治療すべき病気」である。この病気が引き金となった事件を知り、私たち日本人は学ばなくてはならない。この国が依存症大国から依存症対策国へと変わるために。
-
4.0混迷の中で建国され13年で崩壊した満洲国。一極集中の特異な社会、急拡大した満鉄、石原莞爾ら陸軍エリートの苦悩――成立と暴走の要因を「東大話法」で話題の著者が解明する。現代にも通ずる欺瞞の系譜が見える。
-
3.0発売1カ月半で使用者15人が死亡したハートショットなどますます劇薬化する危険ドラッグ。これほどまでの害毒がなぜ蔓延しつづけるのか? 製造元、売人、麻取等への取材から、身近に迫る闇の実態を明らかにする。
-
3.3花まるメソッドを公立小学校へ! 全国初の官民一体校創設がついに動き出す。「時代に取り残されないように学校も塾も変わる必要がある」と語る著者は一体どのようにこれまでの教育システムを変えていくのか?
-
4.4海軍で海上護衛総司令部参謀をつとめ、シーレーン(海上交通線)確保の最前線に立っていた著者がその戦略を綴った護衛戦の貴重な体験記。現代日本の防衛を考える上でも欠くことのできない記録である。
-
3.4人口5万人の九州の小さな町に、全国から100万人が訪れるすごい図書館がある。市民も観光客も満足するさまざまなアイデアの数々と、実現するまでの奮闘を仕掛け人自らが解説する。
-
4.3私達は身体ではなく「心」を進化させてきたのだ――。人類の起源を追い求め、約20万年のホモ・サピエンスの歴史を遡る。構想12年を経て映像化された壮大なドキュメンタリー番組が、待望の文庫化!!
-
3.8韓国の歴代大統領のほとんどが平穏な余生を過ごせていないという事実を知っているだろうか。収監、亡命のみならず殺害された者もいれば、自殺に追い込まれた者もいる。コリア・レポート編集長がその内実を明かす。
-
4.0「僕にとってコンビニは学校であり、接客が社会勉強でした」――どん底の幼年期を過ごした彼が、コンビニで働きはじめ、そしてサービス日本一の店舗に認められたその仕事術とは――。
-
-1984年から2014年まで高倉健を取材し親交していた編集者が、「高倉健」が人生の終い方を探し求めた30年間に向き合った。白洲次郎の「葬式無用 戒名不用」、江利チエミとの死別、酒井大阿闍梨の「契り」。高倉健が数々の別れを経験しながら、自らの死に方を見つけていった姿を描く。
-
5.0元総理大臣の著者が、2004年から10年かけて歩いた四国八十八カ所のお遍路について記す。著者のお遍路は7回にわたる「つなぎ遍路」で行われた。スタートは2004年7月のこと。この時は、のちに誤解とわかる「年金未納問題」で民主党党首を辞したことでお遍路に向かう時間ができたものだった。著書のお遍路は激動の10年のなかで行われている。民主党が政権交代を実現し、著者自身が総理大臣となり、大震災と原発事故に直面し、そして総理を辞し、民主党が下野するという10年。振り返ると、東京から四国に向かうとき、著者は苦境の中にいるときが多かった。そうした旅立ちの前に永田町で起きていたことを踏まえながら、歩きとおした1100km以上の記憶をつれづれに記していく。総理となった者は、なにを思って八十八カ所を周ったのか。
-
4.0チベットの小村に生まれたケツン氏。人類の叡智の伝統と、チベット仏教究極の教えの修行に励む彼を中国の侵攻が襲う。著者が師事した高僧の魂の旅と優しく偉大な文明の記憶を描く。『知恵の遥かな頂』を改題
-
3.7平成も終わり、安倍政権も終わった。しかし、忖度社会は続く。 ドキュメンタリーとは、抗いである。 タブーに抗い続ける監督のルポ&インタビュー! 平成という時代が終わり、安倍長期政権も終わった。 しかし、報道をはじめ、表現の自粛と萎縮は終わることなく続いている。この三十年で、その波は高く、強くなったのか、それとも……。 天皇、放送禁止歌、オウム、オカルト、小人プロレスetc。 撮影したいテーマはことごとくタブー視され、発表媒体が限られていく中でも、作品の力で“空気”を吹きはらってきたドキュメンタリー監督が、自粛と萎縮の正体を探る! 森監督作品のテーマを軸に、時代の表現者たちと「日本」を斬る!! 『放送禁止歌』×ピーター・バラカン(ラジオDJ、ブロードキャスター) 『ミゼットプロレス伝説』×日比野和雅(『バリバラ』初代プロデューサー) 『幻の「天皇ドキュメンタリー」』×松元ヒロ(お笑い芸人) 『A』『A2』×有田芳生(ジャーナリスト、参議院議員) 『未完の「北朝鮮ドキュメンタリー」』×若林盛亮(「よど号ハイジャック事件」実行犯) 『FAKE』×長野智子(ニュースキャスター) ※本書は2017年に小社より刊行した『FAKEな平成史』を改題の上、加筆修正したものです。 【目次】 文庫版まえがき まえがき 第一幕 疑似的民主主義国家ニッポン――『放送禁止歌』 第二幕 差別するぼくらニッポン人――ミゼットプロレス伝説 第三幕 自粛と萎縮に抗って――幻の『天皇ドキュメンタリー』 第四幕 組織は圧倒的に間違える――『A』『A2』 第五幕 平壌、かつての東京との交信――未完の『北朝鮮ドキュメンタリー』 第六幕 正しさこそが危機を生む――『FAKE』 あとがき 文庫版あとがき 解説
-
3.3近代市民精神の発見であると共に、寅彦随筆の転換ともなった「丸善と三越」をはじめ、「読書論」「人生論」「科学者とあたま」「科学に志す人へ」「わが中学時代の勉強法」「『徒然草』の鑑賞」等29篇収録。
-
3.0「結局自分に入用なものは、品物でも知識でも、自分で骨折って掘出すよりほかに途はない」(「錯覚数題」)。科学と文学をあざやかに融合させた寺田寅彦。随筆の名手が、晩年の昭和8年から10年までに発表した科学の新知識を提供する作品を収録する。表題作をはじめ、「錯覚数題」「夢判断」「三斜晶系」「震災日記より」「猫の穴掘り」「鷹を貰い損なった話」「鳶と油揚」等23篇。
-
3.7電車、銀座の街頭、デパートの食堂、花鳥草木など、生けるものの世界に俳諧を見出し、人生を見出して、科学と調和させた独自の随筆集。「春六題」「蓑蟲と蜘蛛」「疑問と空想」「凍雨と雨氷」他39篇収録。
-
4.3近代文学史の科学随筆の名手による短文集の傑作。「電車と風呂」「鼠と猫」「石油ラムプ」「流言蜚語」「珈琲哲学序説」他30篇。写生文を始めた頃から昭和八年まで、寅彦の鳥瞰図ともいうべき作品を収録。
-
4.0ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞作!(2016年度) 大宅賞受賞作家の上原善広が18年間をかけて聞き取りを続けた、まさにライフワークと言える作品。 18年以上の関係から紡がれる、ノンフィクションとしては異例の一人称文体。 「全身やり投げ男」。 1989年、当時の世界記録からたった6センチ足らずの87メートル60を投げ、その後はWGP(世界グランプリ)シリーズを日本人で初めて転戦し、総合2位となった不世出のアスリート・溝口和洋。 ■中学時代は将棋部。 ■高校のインターハイではアフロパーマで出場。 ■いつもタバコをふかし、酒も毎晩ボトル一本は軽い。 ■朝方まで女を抱いた後、日本選手権に出て優勝。 ■幻の世界新を投げたことがある。 ■陸上投擲界で初めて、全国テレビCMに出演。 ■根っからのマスコミ嫌いで、気に入らない新聞記者をグラウンドで見つけると追いまわして袋叩きにしたことがある。 無頼な伝説にも事欠かず、まさに陸上界のスターであった。 しかし、人気も体力も絶頂期にあり、来季のさらなる活躍を期待されていたにもかかわらず、90年からはパタッと国内外の試合に出なくなり、伝説だけが残った……。 その男の真実が、25年以上の歳月を経て、明らかとなる。 プロとは? アスリートとは? 天才と秀才の差とは? 日本人選手が海外選手に勝つための方法とは? 陸上界を貫き、競技を変えた漢を18年以上の歳月をかけて追った執念の取材!! 泥臭い一人の漢の生き様から、スポーツ界が、社会が、昭和と平成の歴史が彩られていく。 【目次】 プロローグ 第一章 発端 第二章 確立 第三章 挫折 第四章 復活 第五章 参戦 第六章 引退 エピローグ 著者あとがき 文庫版著者あとがき 解説
-
4.1自由なはずの現代社会で、発言がはばかられるのはなぜなのか。重苦しい空気から軽やかに飛び出した著者たち。会社や友人関係、家族など、さまざまなところを覆う同調圧力から自由になれるヒントが見つかる。
-
4.3国民国家の「エラー」にされた人々。 彼らから見た、移民大国・日本と世界の姿。 日本、中国、新疆ウイグル自治区、台湾をめぐった傑作ルポ!! いま、世界のルールは動揺している。「境界に置かれていた人々が、ルールの書き換えを強く要求する時代になったのだ。 我々は、彼らを知らなくてはならない――。 日本で生まれ育ったにもかかわらず無国籍者となった女子大生。 中国の軍閥高官の孫だったにもかかわらず夜都の住人を選んだ男。 移民、難民、無国籍者に、暮らしていた国が滅びた遺民、そして国家から切り捨てられた棄民など。 国民国家の「エラー」にされた人々の実態とは? 彼らの眼に移民大国・日本はどのように映っているのか? 日本、中国、新疆ウイグル自治区、台湾をめぐり、国と国の境界線に立つ人々、「境界の民」に迫った傑作ルポ!! <本書に登場する境界の民> ・日本で生まれ育った「無国籍者」。難民二世のベトナム人 ・日本人も信用できない四面楚歌。懊悩するウイグル人 ・夜都・上海に生きる軍閥の末裔。『文藝春秋』を愛読する中国人 ・日系企業・メディアを見限った漢奸の日本人と中国人 ・日本にも中国にも媚びない“ナショナル”を再構築する台湾人 ※本書は2015年2月に小社より刊行された単行本を加筆修正の上、文庫化したものです。
-
4.62011年3月、日本は「死の淵」に立った。福島県浜通りを襲った大津波は、福島第一原発の原子炉を暴走させた。日本が「三分割」されるという中で、使命感と郷土愛に貫かれて壮絶な闘いを展開した男たちがいた。
-
4.4「向いてないからやめます」。国政史上、前代未聞の理由で政界を去った元代議士・久野統一郎。竹下派、小渕派を経て「将来、大臣間違いなし」といわれたエリート2世議員である。しかし、本人は“政治家にはなりたくなかった”。不本意ながら政界に入ってしまった男がカネと選挙に翻弄され、奔走した10年間。政治とは? 政治家とは?そして有権者とは? その実態を大宅賞作家が赤裸々に描く必読の政治ドキュメント! カバー写真(C)FUJIO WADA/SEBUN PHOTO/amanaimages
-
4.2いま、日本は3組に1組が離婚する時代。離婚経験のある“男性”にのみ、その経緯や顛末を聞く、今までになかったルポルタージュ。“人間の全部”が露になる、すべての離婚者に贈る「ぼくたちの物語」。 【目次】 まえがきに代えて/離婚は「人間の全部」 第1章 “家族”を背負えないぼくたち Case #01 三浦隆司 夫になれない Case #02 竹田康彦 人は壊れる Case #03 橋本亮太 家族が得意じゃない Case #04 田中元基 「かわいそう」だから結婚した Case #05 吉村健一 父の条件 Case #06 花田啓司 ビルの気持ちがよくわかる 第2章 妻が浮気に走った理由 Case #07 木島慶 殿方たちのお気に召すまま Case #08 森岡賢太郎 完璧なあなた、勝ち組のわたし 第3章 こわれた伴侶 Case #09 河村仁×Case #10 渋井悟 頑張ってもしょうがない Case #11 北条耕平 おかしいのはどっちだ? 第4章 業と因果と応報と Case #12 滝田浩次 欲しいものだけ欲しい Case #13 片山孝介 離婚してよかった あとがき
-
4.0「1着賞金1億円、2着賞金2,000万円」最高峰のレースはわずか数センチの差に8,000万円もの違いが生まれる。競輪――人生の縮図とも言える昭和的な世界。15億円を稼いだトップ選手が今、初めて明かす。
-
-秘密部隊の青年たちは、 国家から二度死を宣告された。 封印を破り、レ兵士たちは語った!! マルレという秘密兵器があった。それは戦闘機でも潜水艇でもなく、ベニヤ板製の水上特攻艇。 マルレの特攻隊は秘密部隊ゆえに人知れず消えていった。 しかし、この特攻隊にはより大きな秘史がある! それは彼らが8月6日の原爆投下直後の広島に入り、真っ先に救援活動を行っていたこと。 結果、多くの隊員が被曝したこと、そして被爆者として戦後に苦しんでいたこと、である。 被爆地に真っ先に駆けつけて被爆者を助けた秘密部隊の特攻兵たちは、 復員後に自らの身体に発症した原爆症と戦い、被曝という事実を認定しようとしない国と戦い、 周囲の被爆者差別と戦った。 特攻と原爆によって、二度も死を国に告げられた彼らは、「戦後」を戦い続けたのだ。 秘密部隊ゆえにマルレは戦果を秘され、彼らの部隊が原爆投下直後の広島を救援に奔走した行為は忘れられ、 その隊員たちが被爆者として戦い続けた歴史は消えようとしている。 「彼らの証言は、語らずに逝った戦友たちへ捧げる鎮魂であり、いかに戦争が悲惨で愚かで空しいかを訴える警鐘であり、戦争のない平和な世界を祈念する遺言である」 もう、この国で人命を消耗品にしてはならない。 ■「俺は戦争に行きたくない! 軍隊に入隊したくない!」 ■「一艇を以て一鑑を屠る、それが諸君の任務である」 ■「みんな今年いっぱいの命だと覚悟して精進してくれ」 ■「私たちには玉砕は許されませんでした」 ■「俺が原爆症だと知れ渡ったら、子供たちが何されるかわからん」 ※本書は2015年7月に弊社より刊行した単行本『原爆と戦った特攻兵 8・6広島、陸軍秘密部隊レの救援作戦』を 改題の上、加筆修正したものです。
-
4.3こうして今日も、世界で肉は作られる。 「見てきました、“動物が肉になるまで”」 世にも稀なイラストルポルタージュ!! 「食べるために動物を殺すことを可哀相と思ったり、屠畜に従事する人を残酷と感じるのは、日本だけなの? 他の国は違うなら、彼らと私たちでは何がどう違うの?」 アメリカ、インド、エジプト、チェコ、モンゴル、バリ、韓国、東京、沖縄。 世界の屠畜現場を徹底取材!! いつも「肉」を食べているのに、なぜか考えない「肉になるまで」の営み。そこはとても面白い世界だった。 「間違いなくオンリーワンの本」佐野眞一氏(解説より) 【目次】 まえがき 第一章 韓国 第二章 バリ島 第三章 エジプト 第四章 イスラム世界 第五章 チェコ 第六章 モンゴル 第七章 韓国の犬肉 第八章 豚の屠畜 東京・芝浦屠場 第九章 沖縄 第十章 豚の内臓・頭 東京・芝浦屠場 第一一章 革鞣し 東京・墨田 第一二章 動物の立場から 第一三章 牛の屠畜 東京・芝浦屠場 第一四章 牛の内臓・頭 東京・芝浦屠場 第一五章 インド 第一六章 アメリカ 終章 屠畜紀行その後 あとがき 文庫版あとがき 主要参考文献一覧 解説 佐野眞一
-
4.5台湾で、その命日が「正義と勇気の日」に制定された日本人がいた――。日本と台湾の絆を表す「英雄」が歩んだ苦難と感動の物語。史上初の「日台」同時発売ノンフィクション! 1895年、ひとりの若者が台湾を目指して故郷・熊本をあとにした。台湾の治安維持と発展に尽くすためである。やがて台湾女性と家庭を築いた彼は、のちに「英雄」と呼ばれる男の子をもうけた。しかし、戦後の台湾の悲劇は、一家を動乱に巻き込んでいく。日本と台湾の“絆”を表わす「5代120年」にわたる壮大な一族の物語――。 「私には大和魂の血が流れている」「台湾人、万歳!」。台湾最大の悲劇となった1947年の「二二八事件」で、そう叫んで、永遠の眠りについた英雄がいた。坂井徳章弁護士(台湾名・湯徳章)である。父親は日本人、母親は台湾人で、生まれながらにして日本と台湾の“絆”を表わす人物である。父を早くに亡くした徳章は、貧困の中、辛酸を舐めながら勉学に励み、ついに当時の最難関国家試験である高等文官司法科と行政科の試験に両方合格する。 帝都・東京から故郷・台南へ帰り、台湾人の人権確立のために活動する中、徳章は国民党政府の「二二八事件」弾圧から台南市民を救うために奔走する。自らの身を犠牲にしながら、多くの市民を助けた徳章は、50年後に忽然と“復活”する。苦難の道を歩んだ台湾と、なぜ今も台湾人が日本と日本人をこれほど愛してくれているのか、その根源を解き明かした感動の歴史ノンフィクション――。
-
3.610年前は男性依頼者が1割だったのに対し、現在では4割超が男性依頼者へと変わっている。時代や社会の変化とともに、依頼内容や調査方法にも変化が。獲物は絶対に逃がさない、探偵の調査実録。
-
4.52013年10月、2人の老人が死んだ。 1人は大正8年生まれの94歳、もう1人はふたつ下の92歳だった。2人は互いに会ったこともなければ、お互いを意識したこともない。まったく別々の人生を歩み、まったく知らないままに同じ時期に亡くなった。 太平洋戦争(大東亜戦争)時、“輸送船の墓場”と称され、10万を超える日本兵が犠牲になったとされる「バシー海峡」。2人に共通するのは、この台湾とフィリピンの間にあるバシー海峡に「強い思いを持っていたこと」だけである。1人は、バシー海峡で弟を喪ったアンパンマンの作者・やなせたかし。もう1人は、炎熱のバシー海峡を12日間も漂流して、奇跡の生還を遂げた中嶋秀次である。 やなせは心の奥底に哀しみと寂しさを抱えながら、晩年に「アンパンマン」という、子供たちに勇気と希望を与え続けるヒーローを生み出した。一方、中嶋は死んだ戦友の鎮魂のために戦後の人生を捧げ、長い歳月の末に、バシー海峡が見渡せる丘に「潮音寺」という寺院を建立する。 膨大な数の若者が戦争の最前線に立ち、そして死んでいった。2人が生きた若き日々は、「生きること」自体を拒まれ、多くの同世代の人間が無念の思いを呑み込んで死んでいった時代だった。 異国の土となり、蒼い海原の底に沈んでいった大正生まれの男たちは、実に200万人にものぼる。隣り合わせの「生」と「死」の狭間で揺れ、最後まで自己犠牲を貫いた若者たち。「アンパンマン」に込められた想いと、彼らが「生きた時代」とはどのようなものだったのか。 “世紀のヒーロー”アンパンマンとは、いったい「誰」なのですか――? 今、明かされる、「慟哭の海峡」をめぐる真実の物語。
-
4.42011年3月11日、一人の新聞記者が死んだ。福島民友新聞記者、熊田由貴生、享年24。福島県南相馬市で津波の最前線で取材をしていた熊田記者は、自分の命と引きかえに地元の人間の命を救った。その死は、仲間に衝撃を与えた。それは、ほかの記者たちも同じように津波を撮るべく海に向かい、そして、生命の危機に陥っていたからである。なかには目の前で津波に呑まれる人を救うことができなかった記者もいた。熊田記者の「死」は、生き残った記者たちに哀しみと傷痕を残した。取材の最前線でなぜ記者は、死んだのか。そして、その死は、なぜ仲間たちに負い目とトラウマを残したのか。非常用発電機のトラブルで新聞が発行できない崖っ淵に立たされ、さらには放射能汚染で支局も販売店も避難を余儀なくされた福島民友新聞を舞台に繰り広げられた新聞人たちの壮絶な闘い。「命」とは何か、「新聞」とは何か、を問う魂が震えるノンフィクション――。
-
4.0タイガース「苦難の時代」を文献資料に基づいて再現する。しかし「記録集」にはしない。あくまで「物語」として主人公を置き、彼らを中心にして記述しよう。その主人公とは村山実、江夏豊、田淵幸一の三人だ――。 序章 「二人のエース」と二度の優勝 1959-1964 第一部 「伊予タヌキ」の知略 1965-1968 第一章 平和台の雨に泣く――1965年 第二章 奪三振記録での村山と長嶋――1966年 第三章 村山の苦闘、江夏の快投――1967年 第四章 江夏の江夏による江夏のための年――1968年 第二部 燃えつきた「炎のエース」 1969-1973 第五章 「クマさん」後藤の悲喜劇――1969年 第六章 苦悩の兼任監督――1970年 第七章 伝説の九連続三振――1971年 第八章 二人の監督――1972年 第三部 追放された「黄金バッテリー」 1973-1978 第九章 あと一勝に泣く――1973年 第一〇章 冷戦――1974年 第一一章 黄金バッテリーの終わり――1975年 第一二章 孤立する田淵――1976年 第一三章 崩壊する吉田体制――1977年 第一四章 どん底――1978年 終章 優勝までの七年
-
3.0沖縄、フィリピン、タイ。米軍基地の町でネオンに当たり続ける女。黄金町の盛衰を見た外国人娼婦。国策に翻弄されたからゆきさんとじゃぱゆきさん。世界最古の職業・娼婦たちは裏日本史の体現者である!
-
3.0瀬古利彦、サッカー日本代表、遠藤純男、ファイティング原田、新日鉄釜石、明徳義塾……。さまざまな競技から歴史に残る名勝負を選りすぐり、勝敗を分けた「あの一瞬」に至るまでの心の奇跡を描きだす。 ※本書は二〇一〇年七月に新潮社より刊行された単行本『あの一瞬 アスリートはなぜ「奇跡」を起こすのか』を一部改題し、加筆・修正したものが底本です。
-
3.5コミュニケーションに慎重になる人が増えている。社会的な交わりの中で、お互いに上手に距離を取ることができれば、悩みの多くは解消する。相手ごとにふさわしい距離感を見極め、ときに間を取ることが大切だが、適切な距離感を図ることは、歳をとって社会経験を重ねても難しいもの。 距離感に悩むのは、距離が近すぎるか、遠すぎるかのどちらかだ。人間関係をうまく構築しようと意識するあまり、ストレスが溜まる。「距離の取り方」は、心の持ちようを変えることで、技として学ぶことができる。間合いの取り方が分かれば、ぐっと生きるのが楽になり、人間関係も劇的に豊かに。疲れないために、上手に距離を取る、齋藤流メソッドを公開!
-
4.0環境問題、アニマルウェルフェア、人権・労働問題、フェアトレード、商品・サービスの持続可能性、利益の公正な分配、フードロス。食文化、生産者、自分自信を守るために知っておくべきエシカルの基準を提示する!
-
5.0浄瑠璃や歌舞伎にはじまり、1910年の映画化以降、何度も何度も作られ続ける『忠臣蔵』。実は時代によってその描かれかたは変化している。忠臣蔵の歴史を読み解けば、日本映像の歴史と、作品に投影された世相が見えてくる。物語の見所、監督、俳優、名作ほか、これ一冊で『忠臣蔵』のすべてがわかる! 【目次】 はじめに 第一章 「忠臣蔵」概論 A 6つの見せ場/B 三大キャラクター/C 愛された理由/D 作り手側の事情 第二章 忠臣蔵は世につれ 1 江戸時代=庶民たちの反逆 2 国家のために利用される「忠君」 3 「義士」から「浪士」へ~『赤穂浪士』 4 GHQの禁令と戦後の「忠臣蔵」~『赤穂城』 5 東映の「赤穂浪士」 6 大河ドラマ『赤穂浪士』 7 悪役を主役に!~『元禄太平記』 8 悩める大石~『峠の群像』 9 ドロドロの人間模様~『元禄繚乱』 10 TBS三部作 11 「決算! 忠臣蔵」 第三章 キャラクター名鑑 A 四十七士/B 脱落者/C スターのための脇役/D 吉良方のスターたち/E 女性たち 第四章 オールスター忠臣蔵の系譜 A 戦前編/B 東映三部作/C 松竹、大映、東宝の動向/D その後の二本/E テレビの動向 第五章 外伝の魅力 A 外伝名作五選/B 後日談 おわりに 参考文献 索引
-
4.3(章立て) はじめに 第一章 会見に出席できなくなった 第二章 取材手法を問い直す 第三章 日本学術会議問題と軍事研究 第四章 フェイクとファクトの境界線 第五章 ジェンダーという視点 第六章 ウィシュマさんの死が私たちに問いかける 第七章 風穴を開ける人たち おわりに
-
5.0(章立て) はじめに 第一章 愛国は多層的だ 第二章 戦前の愛国 ――上からの愛国は命さえも軽んじられる 第三章 元兵士たちの愛国 ――ナショナリズムの拒絶と新しい表現 第四章 定まらない愛国 ――島は巨大な墓である 第五章 戦後の転機 その1――尖閣諸島問題 第六章 戦後の転機 その2――3.11 第七章 天皇が示した愛国 第八章 沖縄の人々 おわりに
-
3.7密室政治の極致、元号選定。 繰り広げられるマスコミのスクープ合戦に、政治利用をたくらむ政治家、そして熱狂する国民。 しかし、実は昭和も平成も令和も、たった一人の人間と一つの家が支えていた! そもそも、誰が考え、誰が頼み、誰が決めていて、そもそも制度は誰が創り上げ、そして担ってきたのか? 安倍改元の真相はもとより、元号制度の黒衣を追った衝撃スクープ!! 実は、現在の元号は明治以降のわずかな歴史で創られた「新しい伝統」に過ぎない。 大日本帝国時代の遺制である元号は、いかにして、民主主義国家・日本の戦後にも埋め込まれてきたのか。 令和改元ブームの狂騒の裏で、制度を下支えてきた真の黒衣に初めて迫る。 元号制度の根幹は、砂上の楼閣と化していた――。 知られざる実態を、7年半に及ぶ取材によって新聞記者が白日のもとにさらす。渾身のルポ! 【目次】 序 章 特命官僚 第一章 考案者捜索――誰が考えているのか? 第二章 極秘の元号研究官――誰が頼んでいるのか? 第三章 二代目研究官――誰が引き継いだのか? 第四章 安倍改元の真相――誰が決めたのか? 第五章 近代国家と元号――誰が創り上げたのか? 第六章 戦後社会と元号――誰が広めたのか? 第七章 漢籍の名門一家――誰が担ってきたのか? 終 章 脱「伝統」の選定を あとがき 主要参考文献一覧
-
4.1トイレを見れば、丸わかり。 都市と農村、カーストとイノベーション…… ありそうでなかった、「トイレから見た国家」。 海外特派員が地べたから徹底取材!! インドはトイレなき経済成長だった!? 携帯電話の契約件数は12億件以上。 トイレのない生活を送っている人は、約6億人。 経済データという「上から」ではなく、トイレ事情という「下から」経済大国に特派員が迫る。 モディ政権の看板政策(トイレ建設)は忖度の産物? マニュアル・スカベンジャーだった女性がカーストを否定しない理由とは? 差別される清掃労働者を救うためにベンチャーが作ったあるモノとは? ありそうでなかった、トイレから国家を斬るルポルタージュ! トイレを求めてインド全土をかけめぐる! ■家にトイレはないけれど、携帯電話ならある ■トイレに行くのも命がけ ■盗水と盗電で生きる人たち ■「乾式トイレ」の過酷さはブラック企業を超える ■「差別」ではなく「区別」と強弁する僧 ■アジア最大のスラムの実情 etc. 【目次】 はじめに 第一章 「史上最大のトイレ作戦」――看板政策の実像と虚像 第二章 トイレなき日常生活――農村部と経済格差 第三章 人口爆発とトイレ――成長する都市の光と影 第四章 トイレとカースト――清掃を担う人たち 第五章 トイレというビジネス――地べたからのイノベーション 終章 コロナとトイレ――清掃労働者の苦渋 おわりに 主要参考文献一覧
-
3.3「芸人は商品だ。よく磨いて高く売れ!」 温かかった“ファミリー”は、なぜ“ブラック企業”と指弾された!? “伝説の広報”にして組織を知り尽くした男が初告白!! 吉本興業はどこへ向かうのか――? “闇営業問題”が世間を騒がせ、「吉本興業VS芸人」の事態にまで発展した令和元年。 “芸人ファースト”を標榜するファミリーの崩壊はいつ始まったのか? 35年勤めた“伝説の広報”が芸人の秘蔵エピソードを交えながら組織を徹底的に解剖する。 笑いの世界を愛するすべての読者に贈る「私家版」吉本興業史! 第一章 “ファミリー”の崩壊 第二章 吉本創業と躍進の歴史 第三章 戦時をくぐり抜けて 第四章 大衆に笑いを提供する使命 第五章 笑える百年企業の未来
-
-国家のアイデンティティを誇示するシンボルマーク「国旗」とテーマソング「国歌」。そして人類の肉体的・精神的な高みを謳歌するスポーツ。日本で唯一の「国歌」研究者が、豊富な事例を繙きつつ、両者の愛憎の歴史に迫る。 【ある試合が、本当の戦争に発展した!! 日本で唯一の「国歌」研究者が「スポーツと愛国心」を徹底解説!】 ◆日本のある行動が、世界のスポーツファンから称賛を浴びた理由とは? ◆オリンピックはいつから国別対抗戦になった? 考案者クーベルタンの目的は「競争」ではなかった!
-
4.1(目次) はじめに ~このまま汚れた海でいいのだろうか 第一章 世界の海はプラスチックごみだらけ 第二章 プラスチックは地球の異物 第三章 マイクロプラスチックを生き物が食べる 第四章 わたしたち一人ひとりの力は小さいのか?
-
3.0表の歴史には絶対に出なかった、知られざる裏芸能史! 花電車芸とは、女性器を使って芸をすることである。 花電車(装飾された路面電車)は客を乗せないことから、男を乗せない芸者がそう呼ばれるようになった。 戦後の色街や花街の摘発によって職を失った芸妓たち。彼女たちはストリップ劇場に流れ、芸を披露してきたのだ。 しかし、日本で花電車芸を披露する者は、いまや十指にも満たない。 テレビで映される芸ではない。伝統芸能として称賛され、国から保護される芸でもない。 だが、世の片隅で人々の心をとらえ続けてきた庶民の芸である。 女性器を使って、バナナを切る、ラッパを吹く、吹き矢を飛ばす、火を噴く、花を活ける、台車を引く、コインを一枚一枚出していく等々。 前代未聞の芸が脈々と伝えられていた。 いつ始まった?秘技はどう受け継がれてきたのか? 色街を取材し続けたルポライターが秘史を探る! 正史では触れられない、庶民の芸の歴史と芸人の姿。 ■「私のお股から火を噴いてみせましょう」 ■両国は見世物小屋で栄えていた ■「コインを一枚一枚、アソコから出していくんですよ」 ■親子二代のストリッパーになる ■ストリップは新宿で産声を上げ、浅草で隆盛を迎えた 人は生きていくうえで、闇を必要とする。かつてはその闇がストリップ劇場であり、見世物小屋であったのだ。 【目次】 まえがき 第一章 生ける伝説、ファイヤーヨーコ 第二章 花電車芸、その起源を探る 第三章 異端の芸人たちは極みに至る 第四章 ストリッパーたちは見た 第五章 花街、その興亡をたどる あとがき 主要参考文献
-
4.0時代劇は『水戸黄門』『遠山の金さん』だけじゃない! 「勧善懲悪モノは一部に過ぎない」「異世界ファンタジーのように楽しむ」「専門用語は調べなくてよい」……知識ゼロからでも楽しめる、時代劇の教科書。
-
3.3第一章 少年時代 1 ガロアとその家族 2 リセでの生活 第二章 数学との出会い 1 数学者ガロア誕生 2 ルジャンドル『幾何学原論』 3 数学への渇望 第三章 数学史的背景 1 エコール・ポリテクニーク 2 西洋数学の流れ 3 方程式を解く 第四章 デビューと挫折 1 〈数学者ガロア〉デビュー 2 二つの不幸 3 エコール・ノルマル入学 第五章 一八三〇年 ――革命と放校 1 七月革命 2 革命の傍らで 3 放校 第六章 一八三一年 ――獄舎の中で 1 三度目の論文 2 「ルイ・フィリップに乾杯!」 3 獄舎の中で 4 ガロアの黙示録 第七章 一八三二年 1 恋愛事件 2 決闘 あとがき、文庫版あとがき (本書は2010年に中公新書より刊行された『ガロア 天才数学者の生涯』を加筆修正のうえ、文庫化したものです)
-
-保守にあって改憲に反対した宮澤喜一や後藤田正晴、野中広務。「九条の会」呼びかけ人、澤地久枝・井上ひさし。『官僚たちの夏』の主人公・風越信吾のモデル、異色官僚・佐橋滋。少年兵として戦争を体験した城山三郎や「憲法を変えるなどもってのほか」と主張した宮崎駿監督、三國連太郎、美輪明宏、吉永小百合といった文化人、そしてアフガニスタンで井戸を掘りつづける医師・中村哲。 彼らがどう人生を生き、そして憲法を護りたいのか。著者だからこそ知り得たエピソードとともに紹介(本書は、光文社刊の単行本『この人たちの日本国憲法』に、新たに澤地久枝氏と井上ひさし氏の2章を増補した角川新書版です)。 [もくじ] 第1章 「九条の会」の孤塁を守る澤地久枝 第2章 井上ひさしは憲法をやさしくおもしろく語った 第3章 宮澤喜一の『新・護憲宣言』 第4章 「戦争で得たものは憲法だけだ」と呟いた城山三郎 第5章 “異色官僚”佐橋滋の非武装論 第6章 派兵反対に職を賭した後藤田正晴 第7章 野中広務の日本への遺言 第8章 徴兵を忌避しようとした三國連太郎 第9章 美輪明宏の「戦争は野暮の骨頂」 第10章 「憲法を変えるなどもってのほか」の宮崎駿 第11章 吉永小百合の平和への祈りと行動 第12章 アフガンを歩く日本国憲法、中村哲
-
-脳梗塞で声と聴覚を失った元医師が、フェイスブックでその苦しみをリアルに綴ると、またたくまに35万「いいね!」を獲得。絶望の淵にいた青年は多くの人とのネット上のコミュニケーションに生きがいを見出していく ※本書は2015年6月27日に配信を開始した単行本「僕の声は届かない。でも僕は君と話がしたい。」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-2016年2月、”ヘルメットおじさん”でメディアに登場した著者は、かつてのファンに衝撃を与えた。 いったい何があったのか? 違法薬物との関係は? 現役時代は絶対的なセットアッパーとして活躍した。 「なめとんのか、この野郎!」 強気のピッチングに球場が沸く。 オールスターにも2回選出されるなどファンからの信頼も厚く、両リーグで優勝。日本一にも貢献した。 「野球を面白いと感じたことはない」という厳しいプロの世界で、愚直に投球に向き合った。 栄光、悲哀、けが、クスリ、メジャーリーグへの挑戦、引退後の逮捕、そして――。 波瀾の半生をありのままに語り、新たな一歩を踏み出す。 ※本書は、2016年9月28日に配信を開始した単行本「再生」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
3.5私たちが受け取る情報の汚染度は、ますます増している。ネットで多くの情報に触れる人ほど、被害を受ける可能性が高くなっているのだ。情報社会の危険性を浮き彫りにし、「情報汚染の時代」を生き抜く術を伝える書。
-
4.0「ほめる技術」の需要は高まる一方。人との接し方がデリケートになり、人間関係に起因するトラブルが増え、「人を傷つけない」だけでなく、「人を励ます」言葉が求められる現代。人を上手にほめるには、「なぜ相手をほめたいか?」「相手は自分にとってどういう存在か?」を意識し、ほめる語彙を増やすこと。技を身につければ、人間関係も自然に良好に。
-
3.6そこは、外国人、高齢者をネトウヨが襲う「空間」と化していた。 団地は、この国の“未来”である。テロ後のパリ郊外も取材した、地べたからの最前線ルポ!! 団地はこの国の課題最先端「空間」となっていた。 団地。そこは、かつて「夢と希望の地」だった。 しかし、いまは都会の限界集落と化している。高齢者と外国人労働者が居住者の大半を占め、さらにそこへ“非居住者”のネトウヨはじめ排外主義者が群がる。 排外主義的なナショナリズムに世代間の軋轢、都市のスラム化、そして外国人居住者との共存共栄……。 厳しい現実に負けずに、“一緒に生き続けること”を実践している各団地の取り組みを、私たちは“日本の未来”に出来るのか? 外国人実習生や排外主義者の問題を追い続ける著者が、日本各地に加えてテロ直後のパリ郊外も取材し、日本に問う。 ■団地は差別と偏見の触覚だ ■孤独死に国籍は関係ない ■九〇を超える国籍の人が住むパリの団地 ■「人種間というよりは、世代間のギャップなんですよ」 ■きっかけはほとんど“ごみ問題” ■日系人は合法的労働者供給源だった ■ヘイトスピーチを昇華する ※本書は2019年3月の小社より刊行した単行本を加筆修正したものです。 目次 まえがき――団地は「世界」そのものだった 第一章 都会の限界集落――孤独死と闘う 第二章 コンクリートの箱――興亡をたどる 第三章 排外主義の最前線――ヘイトへ抵抗する 第四章 パリ、移民たちの郊外――レッテルを塗りつぶす 第五章 残留孤児の街――歴史の中に立つ 第六章 「日本人」の境界――差別と分断に屈しない あとがき 新書版あとがき 参考文献一覧
-
5.0(章タイトル) はじめに 第一章 「朝日新聞」が隠すベトナム人留学生の違法就労 第二章 「便利で安価な暮らし」を支える彼らの素顔 第三章 「日本語学校」を覆う深い闇 第四章 「日本語教師」というブラック労働 第五章 「留学生で町おこし」という幻想 第六章 ベトナム「留学ブーム」の正体 第七章 幸せの国からやってきた不幸な若者たち 第八章 誰がブータン人留学生を殺したのか 第九章 政官財の利権と移民クライシス おわりに
-
5.0若田部昌澄が日銀副総裁就任直前に再評価、日本の新聞・出版が崩壊の危機に瀕する今、再び注目される技術革新によるメディアと人間の変貌の物語。 「日本人にかくも壮大かつ重厚なノンフィクションが書けるのかと驚嘆した。(中略)。市場経済の変化がメディアとジャーナリズムを否応なく変えていく半世紀余りをトップ経営者から現場記者まで、国際的、複眼的、重層的に描き出す」 (若田部昌澄 早稲田大学政治経済学部教授・当時 週刊ダイヤモンド 2017年9月30日号) プロローグ 第1章 潰れかかった通信社 第2章 取引所とコンピュータ 第3章 黄金郷へ 第4章 国士 第5章 筆剣一如 第6章 同盟解体 第7章 強者連合 第8章 独裁と密告 第9章 退場する将軍 第10章 漂う通貨 第11章 ロイター・モニター 第12章 裏切られた革命 ※本書の続編『勝負の分かれ目(下)』には、電子書籍版特典として著者がこれからのメディアの在り方について記した「そして『2050年のメディア』へ」を収録しています。
-
3.0躁うつ病や統合失調症はもとより、いまや「発達障害」も一般名称化した。もはや「心の病」は特殊ではない風潮の一方、医療現場では何が変わり、何が変わらず、何が起こっているのか。最前線を走り続ける現役医師が、精神医療「内部」の諸問題、精神医療と「外部」事象との問題、精神医療と心理社会的な問題との関連を批評・露呈させる。 第1章 医療の中の精神科 第2章 流行の病 第3章 精神病院の風景 第4章 精神鑑定のウソ 第5章 カウンセリングと精神分析 第6章 ヒステリーと神経症 第7章 精神療法のワナ 第8章 精神疾患の治療法 第9章 特異な精神症状
-
3.3縁日から屋台が消える。 暴走する暴排条例。反社でないのに排除されている――。 テキヤ経験者の研究者が祭りを支える人々の実態を取材・調査! テキヤ社会と裏社会の隠語集も掲載。 ソースせんべい、わた菓子、ヨーヨー釣りなど、 薄利の品を祭りで売る、縁日を支える人たちはどのように商売をし、どう生活しているのか? 世話人(出店を取り仕切る幹部)を務めた男に帳元(親分)の娘、2人のテキヤのオーラルヒストリーを通じ、戦後から現在までの縁日の裏面史が明らかとなる! ■ヤクザとテキヤは祀神が違う ■酉の市の熊手の商売は助け合い ■昔は刑事さんもお客さん ■祭りの混雑をさばくのも世話人の仕事 ■テキヤ稼業は闇市から始まった ■テキヤの葬式じゃあ、ちらしちゃダメ ■前金も契約書もない、ご縁による商売 【テキヤ隠語使用例】 ・バイはマブテン、サンタクヨロクした(商売は上首尾で沢山儲かった) ・アニコウからタイガリくっちまった(兄貴からひどく怒られた) ・ヒンはヤリモカマラん(銭は一文も無い) ・今日はジンがナイスクだった(今日は人出が少なかった) ・スイがバレないうちにハヤバにゴイしょうぜ(雨が降って来ないうちに早く帰ろう) ・あいつにヤクマチ切られちゃったよ(あいつに悪口言われた) 【目次】 まえがき 序章 テキヤ稼業とはなにか 第一部 テキヤの世界 第一章 テキヤ稼業の実態――元世話人の回想 第二章 戦後縁日史――帳元の娘の回想 第三章 彼らはどこから来て、どこに行くのか 第二部 テキヤ社会と裏社会の隠語 はじめに テキヤ用語一覧 概説/数字/テキヤ用語使用例 あ~わ行 裏社会用語一覧 あ~や行 あとがき 参考・引用文献
-
-欲望渦巻く街、新宿二丁目。変わり続けるこの街とともに人生を歩んできた6人の物語。今、この街と人が語りえるものとは何か。気鋭のノンフィクション作家による渾身作。 Episode 01長谷川博史 (特定非営利活動法人「日本HIV陽性者ネットワーク・ジャンププラス」理事) 「私が死んだら、この街に骨を撒いて」 Episode 02 村上ひろし (元「バディ」編集長) 「出会い」が希薄化しつつある街に Episode 03 一ノ瀬文香 (タレント・「香まり」オーナー) この街とともに生きていく Episode 04 コンチママ (「白い部屋」オーナー) 今後は普通の街になる Episode 05 りっちゃん (「クイン」オーナー) 心の憂さの捨てどころ Episode 06 山縣真矢 (特定非営利活動法人「東京レインボープライド」顧問兼理事) 「プライド」のある街 Episode 07 変わりゆく街、変わらぬ街
-
3.92011年3月11日、地震発生の数時間後に最初の災害対応サービスが立ち上がり、数日のうちにいくつものプロジェクトが本格始動していった。これらを可能にしたGoogleのスピード、組織力、柔軟性などその源は何だったのか? 最前線で活動するITジャーナリスト2人が克明にレポート!
-
5.0「本当に目から鱗が落ちまくり。このイラン観は唯一無二だ」高野秀行氏、熱烈推薦・解説 国民は脱法行為のプロばかり!? 強権体制下の庶民の生存戦略を、長年イランの一般社会で暮らしてきた著者が赤裸々に明かす! イスラムへの無関心、棄教・改宗が進んでいる? 国民の関心はいかに国から逃げるか!? イスラム体制による、独裁的な権威主義国家として知られるイラン。しかし、その実態に関する報道は、日本では極めて少ない。 イスラム共和国支持者=敬虔なムスリムといえるのか? 棄教者は本当にいないのか? 反体制派の国家ビジョンとは? 違法・タブーとされる麻薬や酒に留まらず、イスラム体制下の欺瞞を暴きつつ、庶民のリアルな生存戦略と広大な地下世界を描く類書なき一冊。 ■イスラム宣伝局の職員はイスラム・ヤクザだった ■イスラム法学者たちはアヘンの上客 ■「隠れキリシタン」「神秘主義者」として生きる人々 ■古代ペルシアを取り戻せ!――胎動する反イスラム主義 ■美容整形ブームの裏には低い自己肯定感がある 小さな独裁者たちが「大きな独裁者」を生み出す ■親日感情に隠された本音「尊敬されたい!」 ■メンツ(アーベルー)がすべて、「知らない」と言えない人々 ■おしゃべりこそマナー、しゃべらないのは失礼 ■おらが村こそイラン一! 強すぎる愛郷心 ■イラン人は個人崇拝と訣別できるか 【目次】 はじめに 第一章 ベールというカラクリ 第二章 イスラム体制下で進む「イスラム疲れ」 第三章 終わりなきタブーとの闘い 第四章 イラン人の目から見る革命、世界、そして日本 第五章 イラン人の頭の中 第六章 イランは「独裁の無限ループ」から抜け出せるか おわりに 解説 高野秀行
-
-1985年3月、イラク軍はテヘラン空爆を開始。在留邦人を救い出したのは、日本ではなくトルコの救援機だった。国家が真に守るべきものとは何か。日本の「自衛」問題の本質に迫る緊迫のノンフィクション。
-
3.0その肉声から社会の深淵をのぞく。 6人の日比ハーフたちのインタビューを通じて、 国際結婚の内情、家族の肖像を描き出す出色ルポ。 『全裸監督』原作者、最新作! 第一章 キットカットの少女 第二章 モリンガ姉妹 第三章 孤独を友にする青年 第四章 雨を待つ女 第五章 微笑のボクサー 終章 六人のそれから…そして 「八〇年代、アジア各国から日本に働きにやってくる女性たちは、 ジャパゆきさんと呼ばれその多くが劣悪な環境で働かされた。 日本人男性とのあいだに生まれた日比ハーフたちの多くは、 貧困やネグレクトと無縁ではなかった。日本の男たちを虜にしてきた フィリピン人女性とのあいだに生まれた日比ハーフたちは、 どんな生き方をしているのだろう。」(本文より) 本橋信宏が新たなタブーに挑む!!
-
3.0昭和の剣豪小説家たちのバイブルとなった名著、待望の復刊! 「大家」上泉和泉守・柳生但馬守、次点の「名人」塚原卜伝、第三の「上手」小野忠明・宮本武蔵……。剣・槍・長刀にいたるまで、武術名人の話が次々に登場。達人が伝授した秘訣で素人が勝負に勝つなど、驚くべき逸話も満載。幅広い歴史書を元に、いまも語り継がれる剣豪・武術家伝説がどのように作られたのか、一覧できる貴重な資料。巻末に登場人物の索引付き。
-
-「殺し以外のことはすべて警察で面倒をみる」威勢のいい掛け声で始まった潜入捜査。茶髪にした刑事は偽名を名乗って暴力団幹部に接触。潜入に成功して拳銃の密売情報を入手したが、警察組織に裏切られる。警察の不可侵部分に迫る衝撃の証言。
-
4.0エロ、暴力、心の傷、ホラー、ゾーニング、変態、炎上、#MeToo、身体、無意識…… 「欲望」をテーマにこの世界を読み解けば、未来の絶望と希望が見えてくる――。 「現代人は、かつての、つまり二〇世紀までの人間から、何か深いレベルでの変化を遂げつつあるのではないか、というのが本書の仮説なのです。」―「序」より 【目次】 序 第1章 傷つきという快楽 第2章 あらゆる人間は変態である 第3章 普通のセックスって何ですか? 第4章 失われた身体を求めて 終 章 魂の強さということ 文庫判増補
-
4.0第50回大宅壮一ノンフィクション賞、第5回城山三郎賞をダブル受賞した傑作ルポの完全版。 2019年香港デモと八九六四の連関を描く新章を収録! 「“その事件”を、口にしてはいけない」 現代中国最大のタブー、天安門事件に迫る! 1989年6月4日。変革の夢は戦車の前に砕け散った。 毎年、6月4日前後の中国では治安警備が従来以上に強化され、スマホ決済の送金ですら「六四」「八九.六四」元の金額指定が不可能になるほどだ。 あの時、中国全土で数百万人の若者が民主化の声をあげていた。 世界史に刻まれた運動に携わっていた者、傍観していた者、そして生まれてもいなかった現代の若者は、いま「八九六四」をどう見るのか? そして、事件は2019年の香港デモにどう影響したのか? 歴史は繰り返されるのか? 中国、香港、台湾、そして日本。60名以上を取材し、世界史に刻まれた事件を抉る大型ルポ。 語り継ぐことを許されない歴史は忘れ去られる。これは、天安門の最後の記録といえるだろう。 ●“現代中国”で民主化に目覚めた者たち ●タイに亡命し、逼塞する民主化活動家 ●香港の本土(独立)派、民主派、親中派リーダー ●未だ諦めぬ、当時の有名リーダー ●社会の成功者として“現実”を選んだ者、未だ地べたから“希望”を描く者 etc. ※本書は2018年5月に小社より刊行された単行本を改題の上、修正し、新章を加筆したものです。 【目次】 序章 君は八九六四を知っているか? 第一章 ふたつの北京 第二章 僕らの反抗と挫折 第三章 持たざる者たち 第四章 生真面目な抵抗者 第五章 「天安門の都」の変質 第六章 馬上、少年過ぐ 終章 未来への夢が終わった先に あとがき 新章 〇七二一 香港動乱 主要参考文献
-
4.0黒船来航直後、幕末の江戸を大地震が襲った。安政5年、これにコレラが追い打ちをかける。3日で死ぬといわれたコレラ。それを操るとされた悪狐を倒すため、強い霊力を持つ御神犬や御札を求め、さらには京から神社を勧請。無礼講の祝祭に走った。当時の人々がどのようにコレラと闘ったのか、東海の村に残る記録から再現。民衆の迷信と笑えない。新型コロナ騒動を彷彿とさせる、おかしくもたくましい庶民たちの姿を活写する。
-
3.7なぜ、強国なのか!? 情報(インテリジェンス)大国なのか!? 世界の鍵となる国を第一人者が徹底解説する。 「全世界に同情されながら死に絶えるよりも、全世界を敵に回しても生き残る」 これがイスラエルの国是だ。 世界の政治・経済エリートへ大きな影響力を有す情報(インテリジェンス)大国。 中東と世界情勢を分析するには避けては通れない国だが、その実態はあまりにも知られていない。 「イスラエルは通常の国民国家ではない」と喝破する第一人者が、イスラエル人の愛国心、さらにそれを支える神理解を読み解く! 「本書で私(佐藤)は、イスラエルとユダヤ人から学んだ事柄を記した。 イスラエル人の愛国心、さらにそれを支える神理解から、日本国家と日本人が生き残るための知恵を学ぶことが、私が本書を著した目的である」 ※本書は2015年2月にミルトスより刊行された『イスラエルとユダヤ人に関するノート』を改題の上、加筆修正したものです。
-
-囲碁界に「悪女」と呼ばれ、普及に人生をかけるインストラクターがいる。政界、経済界、アーティストら各界の囲碁を愛する人々の笑いあり涙ありの素敵な交遊録! ※本書は2017年11月17日に配信を開始した単行本「囲碁と悪女」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-32歳の熱心な仏教女子が、仏教の神髄ともいえる「さとり」について、6名の賢僧に学んだ珠玉の対話集。インターネット寺院・彼岸寺で連載した「ひらけ! さとり!」をもとに書籍化。 第1章:「つながり」をたのしんで生きること(藤田一照さん・曹洞宗国際センター所長) 第2章:夢であると気づいた上で夢を生きること(横田南嶺さん・臨済宗円覚寺派管長) 第3章:「いま」という安らぎの中に生きること(小池龍之介さん・月読寺住職) 第4章:自分をまるごと受けいれて生きること――泥仏人生(堀澤祖門さん・三千院門主) 第5章:死では終わらない物語を生きること(釈徹宗さん・如来寺住職、相愛大学教授) 第6章:「ほんとうのいのち」に従って生きること(大峯顯さん・専立寺前住職、大阪大学名誉教授) ※本書は、2016年11月18日に配信を開始した単行本「教えて、お坊さん! 「さとり」ってなんですか」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-地球に滅ぼす規模の大爆発を繰り返す太陽、毎年少しずつ地球に近づく月、宇宙人がいる確率……などなど、知っているようで知らない宇宙の姿を太陽研究の第一人者が楽しく紹介。想像を軽々と超えるおどろきの世界へ! ※本書は、2016年1月23日に配信を開始した単行本「とんでもなくおもしろい宇宙」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
3.0政治・経済・事件の裏側からマスメディアの真の姿まで、テレビでは口に出せない日本の真相をえぐり出す。「辛坊治郎メールマガジン」(2015年10月~2016年8月)の内容を加筆した、大好評シリーズ第3弾!
-
4.0著者は大学を出て活字の仕事を望みながら女子の就職先がなく放送という現場で時間に追われるうちに、 両親との距離が開き、四つ年上で中学のときに東京へ行ってしまった兄と話す機会も失われた。 家族のことをあまりに知らなかったことに気付いて、つながる方法を模索し、三人に手紙を書くことを思いついた。 それが『家族という病』の最後に掲載している手紙であり、 『家族という病』を書くことは、著者が家族とつながるための方法だったのである。 さらに、著者は自分の母の死んだ年令に近づきつつあり、自分はどこへ行くのかとしきりに考えていた。 それを知るためには、どうやって自分という生命がこの世に来たのかを知りたいといつしか思うようになっていた。 そんな矢先、夏を過ごしていた軽井沢の山荘で、母親の遺品が何箱かあることに気付く。 恐る恐る開けてみると、著者が子供の頃書いた日記などにまじって、たくさんの手紙らしきものが見つかった。 何気なくその一枚を手にして著者は驚く。 それは、結婚前に母が父に送った手紙だった。 それを読むと、二人共再婚で、二年間百通近い手紙のやり取りをして結婚に至ったらしい。 母は生地の上越、父は今の中国の旅順と海をはさんで結婚まで、一度もあったことがなかったのだ。 読み進むうちに、著者の知らない事実が明らかになり、想像もできない情熱的な母を発見することになった。 著者が母親の強い意志のもとに生まれたことも。
-
4.0安全神話を守るため安全を度外視する逆説。管理・監視の自己目的化。そして分割・民営化の先駆へ。「東京電力」その排除の本質を社会的・歴史的に抉り出す“現代の古典”。名門企業は、自壊した!!
-
5.02014年にデビュー30周年を迎えたTM NETWORK。そのアニバーサリーイヤーに向けて進み出そうとした2013年3月26日、16時27分。木根尚登のケータイはある1通のメールを受信した。メールの送信者は宇都宮隆。そのメールは“事実”だけを伝えていた…。2013年7月のさいたまスーパーアリーナ公演から、アルバム『QUIT30』を引っ提げて展開した“QUIT30”ツアーまで。TM NETWORKの舞台裏をメンバーの木根尚登が綴る「電気じかけ」シリーズ第6弾!
-
4.334歳を迎えた遅咲きの天才・遠藤保仁が今なお代表で活躍できる秘密とは。アスリート然としないキャラクターや関係者が驚くメンタルコントロールなど、多くのテーマに満ちた遠藤を読み解く渾身ノンフィクション!
-
4.5SNSで大人気のはまだFamilyストーリー。たくさん喧嘩してたくさん泣いて恋の辛さを教えてくれたけど、それ以上にたくさん笑ってたくさん愛されて恋の温かさを教えてくれた初めての彼は、いま私の家族です。
-
5.0アデュカヌマブの崩壊から、レカネマブ執念の承認まで。両者の死命を分けたのは2012年から始まったフェーズ2の設計にあった──。当事者たちの証言によって壮大な物語が完結。 物語は青森のりんご農家から始まる。陽子が、りんごの実ではなく、葉をもいで帰ってきたとき、一族のものたちはささやきあった。 「まきがきた」 遺伝性アルツハイマー病の突然変異解明からわかっていく病気のメカニズム。 遺伝子の特定からトランスジェニック・マウスの開発。ワクチン療法から抗体薬へ――。 患者、医者、研究者、幾多のドラマで綴る、治療法解明までの人類の長い道。 解説・青木薫 <文庫書き下ろし新章 目次> 新章その1 オーロラの街で 青森の一族同様、その北極圏の街で、代々アルツハイマー病に苦しむ一族がいた。その地を訪ねたスウェーデンの遺伝学者が全ての始まりとなる。 新章その2 アデュカヌマブ崩れ アデュカヌマブはFDAで「迅速承認」というトラックをつかって承認される。が、承認直後から批判が噴出、議会調査も始まり、壮大な崩壊劇が始まる。 新章その3 運命のフェーズ2 2012年から始まったアデュカヌマブとレカネマブのフェーズ2の治験には実は大きな違いがあった。その年、エーザイにインド出身の統計学者が入社をしていた。 新章その4 ショーダウン ついに「アルツハイマー病研究運命の日」が来る。「レカネマブ」フェーズ3治験結果。内藤晴夫はその日、携帯電話を枕元に置き眠りについた。米国からの報せはいかに? 新章その5 みたび青森で 連綿と続く遺伝性アルツハイマー病の苦しみ。レカネマブは希望の光となるか? 他 プロローグ「まきがくる」からエピローグ「今は希望がある」まで
-
-日本最年少市長(当時)を襲った身に覚えのない浄水プラント収賄疑惑。なぜ何ら証拠も出てこないのに、二審では逆転有罪判決が下されたのか? 藤井浩人美濃加茂市長とともに検察の闇と闘った弁護士の記録 ※本書は2017年12月8日に配信を開始した単行本「青年市長は“司法の闇”と闘った 美濃加茂市長事件における驚愕の展開」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-名人四連覇など囲碁界の頂点を極めた依田紀基。頂点を極める才能を開花させた環境とは? そして私生活でも極めた贅沢。やがて頂点から遠ざかり、家庭も崩壊していく破天荒な人生を、著者自らが書き記す。 ※本書は2017年11月10日に配信を開始した単行本「どん底名人」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-中島飛行機という小さな飛行機会社のエースとして、「九七式」「隼」「疾風」などの戦闘機を開発した天才技師・小山悌。終戦間際は「富嶽」と呼ばれる極秘計画に取り組んでいた。小山が富嶽に込めた願いとは? 本書には、紙版に収録されていた図版の一部が収録されておりません。予めご了承ください。 ※本書は2017年7月28日に配信を開始した単行本「銀翼のアルチザン 中島飛行機技師長・小山悌物語」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-日本は朝鮮半島から離れられない―― 激動の歴史の中で起きたさまざまな事件を追うと、 現代の絡み合った両国関係の背景が浮かび上がってきた。 35年に渡って韓国に暮らす著者は、終始、かの地に刻まれた「日本の足跡」が気になっていた。 韓国併合、敗戦と引き揚げ、国交正常化、南北対立―― 激動の歴史の中で、日本は朝鮮半島へ押しかけ、押しかけられ、引き込まれ、そして深入りしてきたのだ。 そしてわれわれは今、韓国・北朝鮮との付き合い方に悩まされている。 少し時間をさかのぼれば、その理由が見えてくる。 ※本書は2017年6月23日に配信を開始した単行本「隣国への足跡 ソウル在住35年 日本人記者が追った日韓歴史事件簿」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-一点一点の作品が世界を切り拓いてきた分野、マンガ。 それは、正解のない時代に心(ヴァーチャル)と市場(リアル)、二つの世界を開拓し続けてきた業界とも言える。 その“運営者”たる編集者の「頭の中身」を、ベストセラー編集者にしてマンガ原作者である著者が探る。 競う・編む・拓くの三部で構成。 「少年ジャンプ」『火の丸相撲』『僕のヒーローアカデミア』 「少年マガジン」『リアルカウント』『風夏』 「少年チャンピオン」『弱虫ペダル』 「ヤングアニマル」『自殺島』『KAPPEI』 「ヤングキングアワーズ」『蒼き鋼のアルペジオ』 「モーニング」『GIANT KILLING』 などを立ち上げたベストセラー編集者たち。 これら少年誌、青年誌、月刊誌に加え、女性向けの「ハーレクインコミックス」からボーンデジタルの「コミックシーモア」まで。 電子書籍雑誌「AiR」の仕掛け人であった著者だからこそできた、各ジャンルの若手からベテランまでを押さえた、類書なきインタビュー集! ※取材対象者の所属名は取材時のものである ※本書は2017年3月27日に配信を開始した単行本「“天才”を売る 心と市場をつかまえるマンガ編集者」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
-東南アジア「最後のフロンティア」、ミャンマー。 その実権を握る者は、いったいどういう人物なのか? 民主化、市場開放の行方は?? ミャンマー、ノーベル平和賞受賞者のアウンサンスーチーが実権を握る新政権が誕生した国。長きにわたる軍事政権からの転換により、 民主化だけでなく、東南アジア「最後のフロンティア」として経済の伸張にも目が注がれている。 軍事政権の度重なる弾圧に耐え続けたアウンサンスーチーの人気は、もはや宗教的な崇拝に近い。だが、外交関係者からは「頑固」との声も漏れる。 その力量は、まだベールに包まれている。 日本、英国、ミャンマーで彼女の知人や友人を訪ね、知られざる素顔に迫り、四半世紀に及ぶ国軍との「権力闘争」の行方を占う!! 一人の女性は、偶像(アイドル)を経て国家の頂点に立った。 新たな独裁者か、偉大な改革者か!? 元駐ミャンマー大使も称賛するジャーナリストの取材力で迫る!! 【目次】 序章 英雄か、独裁者か 第一章 闘争の幕開け 第二章 日本軍が育てた英雄 第三章 英国とミャンマーの狭間で 第四章 NLD結党秘話 第五章 自宅軟禁 第六章 解放 終章 最後の闘い あとがき ※本書は2017年2月2日に配信を開始した単行本「ミャンマー権力闘争 アウンサンスーチー、新政権の攻防」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)
-
4.0千葉ロッテマリーンズの捕手として16年間プレー。弱小だったチームを日本一に導き、WBCでは世界一の原動力となった。彼のモットーは「常識を疑う」こと。型にはまらない考え方こそが成功へつながるという。 ※本書は、2015年3月9日に配信を開始した単行本「非常識のすすめ」をレーベル変更した作品です。(内容に変更はありませんのでご注意ください)