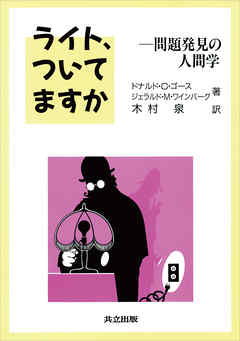あらすじ
この楽しい本を訳して出すことは、著者の一人から1冊もらって以来の夢だった。一見冗談だらけに見えるけれども、実はひどく思い当たることばかり書いてある。訳者は世慣れない方で、ここに書いてあるようなことでしょっちゅう失敗をする。この本を訳したいと思い続け、深読みを繰り返したお陰で、近ごろ少し失敗が少なくなったような気がしている。本の副題にあるように、問題発見についての本である。学校では問題を解くことを教わる。だが問題は、解くより発見する方がずっとむずかしく、ずっと面白い。実人生で本当にものをいうのはそこなのだ。実務に就いておられる人生経験豊かな読者には、特によろこんでいただけるのではないかと思う。だが訳者としては身辺の若者たちにこそ、だましてでも読んでもらいたいと思っている。この本に書いてあるようなことが身についていないばかりにあたら才能を空費している若者が、実に多い。訳者自身も、学生時代からこういうことを知っていたら後悔がずっと少なかったろうに、と思っている。いや、訳者風情がごちゃごちゃいう必要なんかないだろう。ちょっと開けてみれば、そんな必要はないことがご納得いただけると思う。この本に訳者序はいらない。ただ一言この場を借りて、「だまされたと思って開けてみてください、きっとお得ですよ」とだけ申し上げておきたい。
<訳者前口上>より
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
問題を定義してから答えを見つけなくてはならない。ただ、問題が完全に定義しきれるわけではない。解いても問題は生まれる。
無意識に除外している事物を考慮しなくてはならない
本当に解きたい問題か?自分に起因した問題ではないか?解いてほしいと考えている人はいるのか?
Posted by ブクログ
■印象に残った言葉
「もし人々の頭の中のライトがついているなら、ちょっと思い出させてやる方がごちゃごちゃいうより有効なのだ。」
有効であるかどうかは頭の中のライトのレベルを見極める精度が必要なので自身の頭に依拠するところがあるなあと思う…
■実体験と照らし合わせ
就職、転職、結婚、最終的になぜ生きるのかというところまで考える
第五部に関しては個人的に一番考えさせられる話であった。
今まで自責自責、自己責任と考えて生きていたがある意味思考停止であったことに気付かされた、
■感想
この本を読んで心底面白いと感じた気持ちは本物なのでそれが全てかなと。
Posted by ブクログ
問題をどう扱うか。問題とどう付き合い、うまくやるか。そのエッセンスがいくつも入っている。
問題と向き合う私 を俯瞰的に見て、それをさらに俯瞰的に見る存在の視点から、問題と当事者との関係について、よりベターな関係を築くことができる、稀有な本。
また、問題の本質に近づくシンプルな方法は、それについて素朴で適切な質問をする、ということではないか。本書の中にもそれに近いことが書いてある。
以下、印象に残ったこと。←は私の補足。
・解法を問題の定義と取り違えるな。ことにその解法が自分の解法であるときには注意
←例えば、自分の得意なツールが万能、と思っているときなど。
・正しい問題定義が得られたという確信は決して得られない。だがその確信を得ようとする努力は、決してやめてはいけない。
←なぜなら、その努力によって確信に近づくから。
Posted by ブクログ
思っていたより軽い読み味の本だった。
『問題とは、望まれた事柄と認識された事柄の間の相違である』はなるほどと思ったし
タイトルの文言に関するところも納得はした。
ただ文章自体は訳されているせいなのか平易なのに読みづらかった。