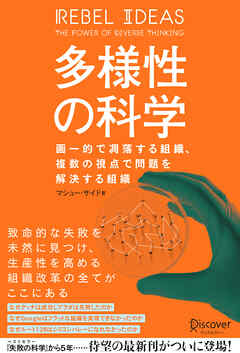あらすじ
なぜ一部の組織や社会はほかに比べて革新的なのか?
経済をさらに大きく繁栄させるには、多様性をどう生かせばいいのか?
致命的な失敗を未然に見つけ、生産性を高める組織改革の全てがここにある
シリーズ10万部突破! (2023/3 ディスカヴァー・トゥエンティワン調べ)
◆なぜCIAは9.11を防げなかったのか?
→第1章 画一的集団の「死角」 へ
◆なぜ一流の登山家たちがエベレストで遭難したのか?
→第3章 不均衡なコミュニケーション へ
◆白人至上主義の男が間違いに気づけたきっかけとは?
→第5章 エコーチェンバー現象 へ
【目次】
第1章 画一的集団の「死角」
第2章 クローン対反逆者
第3章 不均衡なコミュニケーション
第4章 イノベーション
第5章 エコーチェンバー現象
第6章 平均値の落とし穴
第7章 大局を見る
【推薦の声】
これほど面白く、一気に読めるビジネス書は他にない。
多様性を取り入れた組織だけが成功する。
自分の周囲では何を変えるべきか、誰もが考えさせられる一冊だ
――アビームコンサルティング株式会社 代表取締役社長 鴨居達哉
素晴らしい! 知識の共有は複雑化していく世界で生き残る最善の方法だ
――エコノミスト
よくぞ、ここまでまとめてくれた! 多様性が組織の知性を高めることが証明されている
――タイムズ
知性と展望に満ちた、魅力的な読み物だ!
――ジェームズ・ダイソン(ダイソン創業者・発明者)
【読者からも絶賛の声、続々!】
「小説でも読んでいるかのようにワクワクと読み進められる」
「まるでドキュメンタリー番組を見ているかのような読後感」
(弊社に寄せられた「お客様の声」より抜粋)
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
多様性がある集団は複雑な問題の解決という点において、そうでない集団と比較し優秀であるという話。
多様性のある集団において大切なこと、または多様性を阻害することを1つ1つポイントを挙げて説明している。ヒエラルキー、エコーチェンバー現象がそれにあたる。
過去にあった事件、事故を経時的に説明しながら、合間にそれに関する解説や科学的なエビデンスを示しながら進むため、決して飽きることなくヒリヒリしながら内容がすんなり理解できる。
自分としては、知性のない?人間は同一化していくという点と、エコーチェンバー現象が刺さった。
自分は、人の話を聞くとすぐその意見と同化してしまうクセがある。自分というものがないのかな、と自分で情けなく思う所だ。
またエコーチェンバー現象は今のネット社会の問題点である。アルゴリズムによる関連動画や関連商品、関連情報に囲まれて、自分自身も息苦しさのような閉塞感を感じていた所だったので、何ともリアリティーを感じる点だった。ネット社会では無意識に自分にとって好ましい情報しか入らなくなってしまう。この状況は、もうとにかく自分がいろんな分野やいろんな方向からの意見を意識的に収集していくしかないのかな。
これからの自分の実生活につながると感じた点は、3点。まずは耳の痛い反対意見(反逆者の意見)もじっくり聞くこと。2つ目はヒエラルキーや閉塞感を生み出してしまうような人間関係にならないようにすること。3つ目は多様性のある集団の一員になれるように、自分自身、エキスパートとしての価値観を磨くこと。
総じて学びの多い本だった。どんな人にもおすすめでき、読み返したいと思える良書。
Posted by ブクログ
ためになった!
個々の天才を作るよりコミュニケーションを活かしたネットワーキングで集団脳を作る、そのためにはいろんな意見や考えを尊重する民主主義が重要だと理解した。
Posted by ブクログ
多様性とは何なのか。我々の直感はあてにならない。多様性を真に理解したいなら必ず読むべき。
画一的な集団。これが集団的な知性として考えると低くなる。
多様な人を入れると最初は相互理解に手間取る。一方、画一的な集団では見られない、発想も得られる。
しかし、多様性があれば良いという訳ではない。求められるドメインに対しては多様。かつそのドメインに合致しない人をあえて入れる必要はない。とは言えこの判断は難しい。なぜならば、画一的な集団に属していれば、ドメインを狭く定義しかねないからだ。
不均等なコミュニケーション。これはその集団にヒエラルキーがある場合だ。階級が下のものは発言しなくなる。軍隊的な統制が必要な場面は確かに多い。しかし、不測の事態。特に階級が上の者。決定者に知識や情報が十分に集まらない場合。最悪は死等の悲劇となる。状況が生存に関わらないのであれば、延々と続く。そんな組織や集団もゴロゴロしているのであろう。
イノベーションは無視されやすい。実は解決方法は意外に提示されている。イノベーションがイノベーション足り得るのは、誰もその良さに気が付かないから。気づきが重要なのである。しかし、ヒエラルキーがある場合と同様なことになる。また、ビジネス上の成功者であれは、その価値基準から外れているものの有用性に気づくはずもない。
イノベーションは同時多発的に起こる。一人の天才が生む訳では無い。過去の積み重ねが気付きを与える。エジソンが凄いのはたまたま気付くのが早かった。たくさんの試行錯誤を誰よりも多くやったから。現に周りには相当の競合他社が実際にはいたのだ。
エコーチャンバーとフイルターバブル。これはちょっとした違いがある。しかし、そこで起こることには雲泥の差がある。フイルターバブルは関係ないことがほぼ入らない。エコーチャンバーにはある集団の声が増幅される。しかし、たまに反対意見も入ってくる。その時にその反対意見に対し、過激な闘争心を燃やして対抗してしまう。これにより、悪意が増し対立が増してしまう。
ダイエットや食事療法。ここに平均値を持ってくるとよろしくない。やせるはずのことが真逆になる可能性がある。ある食物に対する身体の反応。そこには差がある。あるダイエット法がある。それはある人には血糖値を安定させる。一方、別の人だと血糖値スパイクを生じさせる。平均をとり、それに合わせるは危険ですらある。また、ダイエット本に正解はなく、別の語り口の本がどんどんでてくる。書籍の中で語られることの多くが真逆の効果を出していればそうなる。
日常で多様性を取り込むには3つのことが重要だ。
・無意識のバイアスを取り除く。気づく
・影の理事会、若い人の意見を取り入れる
・与える姿勢、テイカーではなくギバーになる
自分の方法論がうまくいく理由。それはある種の偏りがあるからではないのか。その集団の逆を提示する。それだけで改善した気になれる。そこに留意した思考や行動が必要だ。